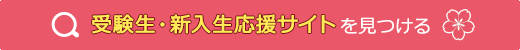- HOME
- 受験生の方へ
- 学生座談会
- (2024年開催)自分に合った勉強の仕方と今しかない高校生活
- 受験期のタイムスケジュール
「高校生×大学生座談会」(2024年開催)
自分に合った勉強の仕方と今しかない高校生活
受験期のタイムスケジュール
加藤さん:
高校3年の受験勉強中の休日のタイムスケジュールを教えていただきたいです。
太田さん(司会):
私は朝型で、朝に勉強時間を寄せて、夕方からはのんびりしていました。5時頃に起きて、9時半に開く図書館に行く前に家で1時間半ぐらい勉強し、図書館では昼食を挟みながら16~17時には切り上げていました。1日の勉強時間は6~7時間、多い日で8時間ぐらいです。
吉澤さん:
平日は、朝に補習の日がありました。その日は7時頃に家を出て、学校で授業が始まる前に1時間ぐらい勉強し、授業が終わったら塾に行って17時~22時ぐらいまで勉強していました。
休日は、塾が開いている9時~22時頃まで勉強をしていました。その間、ご飯を食べに出たり、人と話している時間はあります。家ではだらだらして全然勉強ができなかったので、なるべく塾に行って勉強をするよう意識して、「家では勉強しない」と割り切っていました。
橋本さん:
休日は、塾が開いている10時~22時まで極力長くいて時間を確保するようにしていました。ただ、怠惰な受験生だったので、1ヵ月間ぐらいまったく勉強していない時期もありました。10時~22時までいることが大事ではなくて、自分が継続できる時間でしっかり勉強したほうがいいと思います。
石田さん:
僕は塾に通っていません。休日は市のコミュニティセンターに行き、部屋を9時~21時まで一人で借り、昼食や休憩の時間を抜くと1日10時間ぐらい勉強していました。家では疲れてすぐ寝てしまうことが多かったので、たっぷり時間がある日は集中できる家の外で勉強していました。
佐藤さん:
私も塾には通わず、公民館に行って勉強していました。朝が弱く、休日はリズムが乱れがちでしたが、朝8時までには起きるように頑張っていました。
橋本さん:
私は私立文系で、「Study plus」というアプリで記録していた受験期の総勉強時間を調べると1503時間でした。365日で割ると1日約4時間です。滑り止めにかけるのは1日4時間程度、高校2年の7月から1500時間勉強すれば大丈夫だと思います。
太田さん(司会):
私も「Study plus」を使っていました。勉強時間を記録するのはおすすめです。
小林さん:
高校2年は平日忙しいと思いますが、どのようなスケジュールで勉強をしていましたか。
太田さん(司会):
部活がしっかりあったときは、朝は6時半頃に学校に着き、誰もいない教室で1時間半ぐらい自習していました。夜は部活が19時頃に終わり、塾に通っていなかったので20時頃に家に着いていました。夜はほとんど勉強していなかったと思います。やるとしても、次の日の小テストの暗記物を30分頑張るくらいです。
吉澤さん:
僕は部活が終わるのが18時半頃で、19時半頃には塾に行き、3時間ぐらい勉強していました。朝は学校で1時間でも勉強できたらいいなと思ってはいましたが、なかなか起きられませんでした。
橋本さん:
弓道部は総体があるため引退は高校3年の7月で、それまで塾以外ではまったく勉強していなくて、すごく後悔しています。高校3年の5月頃に部活を引退した人との2ヵ月の差は大きく、あとから追い付けませんでした。
石田さん:
僕は柔道部で、高校2年の12月までやっていました。部活があった日は疲れてしまって勉強できないので、早ければ20時台には寝て、4~5時に起きられた場合は勉強をしていました。起きられなければ「仕方がない」と割り切り、もし溜まっていたら週末にまとめてやる、と部活がある時期はやっていました。
太田さん(司会):
朝早く家を出るには家族の協力も必要です。簡単にできるわけではありませんが、できるなら疲れていない朝に勉強をできたらベストだと思います。ただ、疲れていて無理に勉強するよりは、早く寝て次の日の集中力を上げるのもいいのではないでしょうか。
通学時間の使い方
原口さん:
皆さんの通学時間の使い方をお聞きしたいです。
佐藤さん:
私は自転車通学で、本を読んだりはできません。ただ、学校で勉強した帰りには「この単語ってこういう意味だよな」「こういう流れだったよな」と思い出していて、定着に役立ちました。自転車通学の人は、安全に気を付けながらやってみてもいいかもしれません。
吉澤さん:
僕は45分ぐらいバスに乗って通学していたことがありました。その間に英単語や日本史・世界史の暗記などをやったり、スマホを見たり、眠ったりと気分次第でした。
石田さん:
僕は高校2年までは電車とバスで通っていました。その間に何をするかは特に決めず、眠っているか、小テストなどがある日は勉強をしていました。部活終わりで同じ方向の友達と帰るときは勉強していません。3年になってからは親に送ってもらっていて、睡眠時間に充てていました。
太田さん(司会):
私は家から最寄り駅までは自転車で、学校までは20分電車に乗り通っていました。その20分で英単語や古文単語の小テストの勉強をしていました。運良く座れたら勉強しやすいですが、立っていてもできます。部活帰りは眠るときもありました。「友達と帰るときは勉強しない」というお話がありましたが、せっかく一緒に帰れる日は友達と話す時間にするのも大事だと思います。
受験期の息抜き方法
野口さん:
皆さんは、勉強の息抜きとしてどんなことをしていましたか。
橋本さん:
私は国語がすごく好きで、現代文や小論文、古典などすべてが息抜きになっていました。受験が近づいてきた頃はご飯の時間だけが息抜きに。ただ、その時間も英単語帳や歴史を赤シートで隠しながら見ているときもありました。
太田さん(司会):
「息抜き科目」は私もありました。理系なのですが、数学に疲れたら地理を見ていました。それ以外の息抜きは、マンガや動画を見ることです。だらだらしないように、スクリーンタイムをかけたり、タイマーを設定して時間を切ってやっていました。
また、部活をやっていたときの息抜きは、机に突っ伏して15分間眠ることです。部活で疲れて、眠いままやっていると寝落ちしてしまうこともあります。それならと、タイマーをかけたスマホを膝の上に置いて15分間眠っていました。いい感じに眠気が取れておすすめです。スマホのアラームをバイブにすれば図書館でも使えます。
石田さん:
地理が息抜きになっていました。僕は理系で、東京大学の場合は共通テストがかなり圧縮されて、地理は数点分しかありません。その分、息抜きの時間になっていました。
勉強以外の息抜きは、楽器や運動です。すぐ近くに人が全然いない公園があり、「勉強が嫌だな」と思ったらすぐに行っていました。
吉澤さん:
僕は勉強が嫌で、人と話すのが息抜きでした。塾では疲れてきたときにチューターの人やスタッフの人と話したり、学校では休み時間に友達と話したり。受験が近づくほど、いい息抜きになっていました。
佐藤さん:
私は本を読むのが好きなのですが、『ビギナーズ・クラシックス』というシリーズがおすすめの息抜きです。『太平記』や『源氏物語』などの古典の現代語訳と原文と解説がコンパクトにまとまっていて、物語を楽しみながら自然と勉強になります。