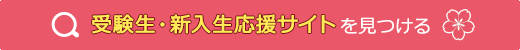- HOME
- 受験生の方へ
- 学生座談会
- (2024年開催)自分に合った勉強の仕方と今しかない高校生活
- 暗記科目を始めるタイミング
「高校生×大学生座談会」(2024年開催)
自分に合った勉強の仕方と今しかない高校生活
暗記科目を始めるタイミング
原口さん:
理科基礎や世界史を取っているのですが、暗記科目は始めるのが早すぎると忘れてしまいそうで、遅すぎても間に合わなそうで不安です。皆さんはどうしていましたか。
佐藤さん:
理科基礎は焦る必要のない科目だと思います。3年から少しずつ覚え始め、共通テスト対策問題集をやり始めたのは共通テストの3ヵ月ぐらい前でした。ただ、地歴科目は二次試験でも使いますし、特に東京大学では論述の配点が重いので、2年の今頃から少しずつ教科書の内容を覚えていったほうが後々楽になると思います。私は「どうせ忘れてしまうし」と後回しにして3年で苦しんだタイプです。3年になってから始めても、最初のほうにやったことはどんどん忘れていくので、何度も覚えることを前提に地歴科目は早めに始めておくことをおすすめします。
吉澤さん:
僕は東京大学を受けて落ちてしまったのですが、落ちた身からアドバイスすると、東京大学は社会科目を二つやる必要があり大きな負担になります。僕は社会科目に手が回らず点を取れなかったので、早いうちから始めておくと後でだいぶ楽になると思います。社会科目の内容は絶対忘れるので、何度も繰り返すことが大事です。
理科基礎は学校の授業でやっていたぐらいで、本格的に自分で勉強し始めたのは共通テストの2~3ヵ月前でした。
数学の勉強の仕方
原口さん:
僕は数学がすごく苦手で、高校1年の基礎からやり直したいくらいです。教科書の問題集として『青チャート』など選択肢がいろいろあり、量も多すぎて何から手を付ければいいのか分かりません。どのように勉強をしていけばいいのか、教えていただきたいです。

『青チャート』
吉澤さん:
僕も数学は苦手で、入試も数学が足を引っ張りました。その中で主に使っていたのは『フォーカスゴールド』です。『青チャート』と同様の網羅系の参考書で、まず解法を覚えようとしました。「こういう問題だったら、こういう解法」というパターンがあるので、問題を見て「自分だったらこう解く」という方針を頭の中で考えてから、解答を読み解法をひたすら覚える、というやり方です。それと並行して、学校で配られた参考書などで問題演習をしながら、ちゃんと身に付いているか試していました。

『フォーカスゴールド』
佐藤さん:
私が主に使っていたのは学校で配布された『フォーカスゴールド』です。基礎を固めるためなら、問題数が多い網羅系の参考書がおすすめです。特に『フォーカスゴールド』なら「ステップアップ」、『青チャート』なら「エクササイズ」という項目の終わりにあるまとめ部分の問題です。本編をやるより少ない問題数で、かつ大事なところが抜粋されています。他には『1対1対応の演習』という問題集を使っていました。これは量が少なくてやりやすいのですが、抜けが出やすいので注意が必要です。
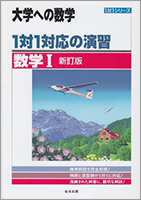
『1対1対応の演習』
太田さん(司会):
学校では『青チャート』が配られました。私は理系でありながら数学は苦手で、長期休みなどにコンパス2~3の難易度が低めの問題を1周やっていました。もし基礎が分からない状態であれば、レベルの高いものは捨て、コンパス1~2だけに絞ってもいいと思います。基礎的なものだけを思い切って選んでやり遂げると、基礎固めになります。
野口さん:
僕は数学が好きで『黒チャート』などをやっているのですが、皆さんの中で「やっていて楽しかった」と思えるような数学の参考書があれば教えていただきたいです。
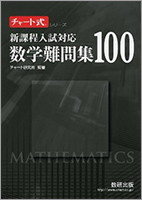
『黒チャート』
石田さん:
僕は過去問演習が楽しかったです。『青チャート』や教科書傍用問題集などで基礎を固めたら、すぐに過去問に移っていました。自分が間違えた問題の解答を出している会社のものをすべて読み、良いところだけを集めてノートにまとめ、自分専用の参考書にしていました。そして入試前に間違えた問題の詳しい解説や自分が書いた解説を読んだりしていました。
佐藤さん:
私は、数学は早めに過去問演習に入っていました。他の教科は基礎を固めてから最後に過去問をやるのですが、数学の過去問はどの大学で出てもおかしくないので早めにやりました。特に数A分野が好きで、数A分野だけの参考書をやっていたときは楽しかったです。
吉澤さん:
ぜひおすすめしたい参考書があります。それは青木純二先生の『数学の真髄』です。教科書には出てこないような数学の本質的な部分の「命題とは何か」「同値変形はそもそも何をしているのか」などが詳しく説明されていて、本質を理解していると記述問題を解くときなども表現に気を配るようになりました。「ここは同値変形でいいのか」などを考えるのは、数学が好きな人には面白いと思います。

青木純二先生の
『数学の真髄』
原口さん:
皆さんは数学の教科書をどのように使っていたかもお聞きしたいです。
吉澤さん:
教科書はほとんど使っていません。授業で新しい単元を習うときに教科書を見ていたくらいで、一通り終わったあとは問題集を使っていました。復習をする際も、『フォーカスゴールド』の冒頭のまとめページを見ていました。
石田さん:
教科書は主に授業で使っていました。その授業は問題演習というより、問題を解く前の定理や公式の証明のために教科書が使われていました。演習は自分で買った参考書の問題をやっていました。
太田さん(司会):
教科書は授業で使うだけでした。ただ、定理の導出などが最も丁寧に書かれているので、それが分からなくなったときは教科書を読んでいました。根本から原理をしっかり理解して基礎を固めたい場合は、教科書を読むのがいいと思います。
大学生がおすすめする参考書
太田さん(司会):
せっかくですので、数学に限らず、おすすめの参考書を紹介していきましょう。
吉澤さん:
1冊目は『ヨコから見る世界史』で、時代ごとにまとまっています。多くの教科書や参考書は地域や時代がばらばらですが、この本は時代に基づいてまとまっています。「この時期に中国は何をやっていた」「ヨーロッパのほうでは何をやっていた」「アジアは何をやっていた」ということが同じ章に収録されています。同時代にどこで何があったのか、ヨーロッパと中国のつながりなどが書かれていて面白かったです。
2冊目も世界史で、『荒巻の新世界史の見取り図』は豆知識が盛りだくさんです。上中下3巻で内容が多く、理解の手助けになります。休憩気分で読める参考書なのでぜひ使ってみてほしいです。
3冊目は『日本史の論点』です。教科書では少ししか触れていない内容も詳しく説明されているので、日本史の理解が深まります。
ためになった参考書
世界史

『ヨコから見る世界史』
世界史

『荒巻の新世界史の見取り図』
日本史

『日本史の論点』
橋本さん:
1冊目は英文法の『全解説 頻出英文法・語法問題1000』です。この1冊をやっておけば、文法問題や単語問題の漏れがなくなると思います。入試は2~3点の差で合否が決まるので、漏れをなくすことは大事です。
2冊目は『漢文早覚え速答法』です。漢文をあまり勉強をしていなかったのですが、この参考書を1週間くらい勉強して共通テストに臨みました。正答率が高かったのでおすすめしたいです。
3冊目は『史料をよむ』です。私立文系では史料問題が出るようになってきています。『山川一問一答』などを仕上げていくと思いますが、長文の史料問題などが出たときに出題形式に慣れていない、もしくは単純に史料を知らない状態だと解きづらいので、『史料をよむ』で仕上げておくことをおすすめします。
ためになった参考書
英 語

『全解説 頻出英文法・語法問題1000』
漢 文
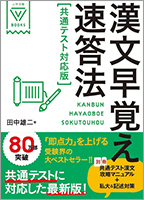
『漢文早覚え速答法』
日本史

『史料をよむ』
日本史

『山川一問一答』
佐藤さん:
1・2冊目は記述対策の問題集『得点奪取』シリーズの古文と漢文です。高校生3年生になるタイミングで、この問題集をやってから過去問演習に入りました。共通テストなどのマークシートと論述問題では解答のポイントが違うので、過去問演習に入る前におすすめです。
3冊目は私立向けですが、『スーパー講義 英文法・語法正誤問題』という正誤問題の問題集です。よく出る正誤問題がたくさん入っていて、解いていく中で「この文法事項あったな!」とインプットにもなります。後半には特殊な問題もあり、私立併願で受ける人におすすめです。
4・5冊目は過去問集で、『東大古典問題集』『東大数学問題集』です。特に東京大学志望の人におすすめです。解説が本当に詳しくて、理系志望でも古典はぜひやってみてもらいたいです。
ためになった参考書
古 文

『得点奪取』
漢 文
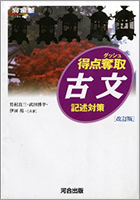
『得点奪取』
英 語

『スーパー講義
英文法・語法正誤問題』
古 典

『東大古典問題集』
数 学

『東大数学問題集』
石田さん:
1冊目は『古文攻略マストアイテム76』です。古文単語をひと通り覚えたあとでも文章が読めず、つまずいたときに使いました。どういう世界だったかを中心に解説してくれるので、単語を学んだあとにやると文章が読みやすくなり、古典が親しみやすくなります。
2冊目は数学の『ランダム演習』で、高校2年の夏から冬にかけて使っていました。共通テスト対策になるのですが、50ページ程度で150問ぐらいと量が少なく、早めに1周終わらせることができます。『青チャート』でいう「N進法の問題」のような題名が付いていなくて、ランダムに問題が並んでいます。「この分野のこの題名だからこの解き方」で覚えていて、実はしっかり理解していないということを洗い出せます。付録には解法がすぐに浮かぶように、問題の指針が書かれています。問題を解いたあとに指針を確認するだけでも、共通テスト対策として仕上がると思います。
3冊目は英作文の参考書『英作文基本300選』で、英作文で頻出する大事な表現だけが300個収録され、1文1文が短くて覚えやすいです。この作者は「丸覚え厳禁主義」で、まず英語に訳しやすい日本語にしてからその日本語を英訳するという解き方で、英作文を鍛えたい人におすすめです。
最後は『基礎問題精講』シリーズの理科で、高校2年で使っていました。共通テストから国公立大学までをカバーできると思うので、共通テストを固めたい人におすすめです。
ためになった参考書
古 文
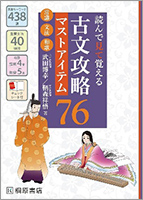
『古文攻略マストアイテム76』
数 学
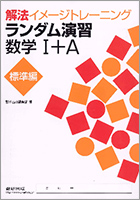
『ランダム演習』
英 語

『英作文基本300選』
理 科

『基礎問題精講』シリーズ
太田さん(司会):
私が紹介したいのは、『出口式 現代文 新レベル別問題集』という現代文の問題集です。高校2年まで現代文をフィーリングで解いていて、得点が安定しませんでした。この本の「超基礎編」に現代文の解き方や掟が載っていて、忠実に従って解いていくと現代文が論理的な科目になり、根拠を持って答えられるようになりました。現代文が苦手な人、得点が安定しない人におすすめです。
ためになった参考書
現代文

『出口式 現代文 新レベル別問題集』
受験には英検何級が必要か
加藤さん:
大学入試において、英検は何級まで取っておくといいでしょうか。
橋本さん:
準1級を高校3年の春に取り、早稲田大学と慶應義塾大学、上智大学の受験で使いました。また、明治大学の国際日本学部では、準1級保有で英語試験が免除になります。スコアによっては加点式のところもあるので、滑り止めを受けるときは調べてみてください。上智大学では、英語試験免除やスコア換算がされるので、英検で高いスコアを取るほど有利です。早稲田大学の商学部に関しては、私が通っていた塾の分析によると準1級を持っていると70点有利になるそうです。
石田さん:
僕は高校3年の6月に準1級を取りました。高校として全員が英検を受ける方針で、2年で2級、3年で準1級を受けました。
佐藤さん:
実力試しのために高校1年の冬に2級を取り、それ以降は受けていません。私は併願で早稲田大学の文化構想学部を受けたのですが、準1級でないと使えませんでした。
吉澤さん:
僕は高校2年の2月に準1級を取りました。周りが取り始めて焦っていたこともあり、具体的な目的はなく「取っておけば何かに使えるかな」という感覚です。
太田さん(司会):
私は2級を取りましたが、受験では使っていません。力試しで英語の勉強をするなら2級でもいいとは思いますが、入試のためなら準1級がいいと思います。