特集記事
「1・17 阪神・淡路大震災(1995)」
~あれから30年、次の世代に記憶を伝えるために~
スペシャルメッセージ
次の世代に阪神・淡路大震災の記憶を伝えるために-震災資料の持つ意味-

奥村 弘 先生
神戸大学理事・副学長
大規模地震災害時の記憶の特徴はなんだろうか。100名を超える方の被災体験をお聞きしてきて、地震災害の特色は、大災害という共通性と、被災地での体験の多様性が共存しているところにあると私は考えている。大災害のニュース等の映像は、被害の激しい場所を切り取って報道するため、すべてが失われるよう見えることも多い。しかし、実際には、被災のあり方は多様で、その中で人々は生をつないでいった。
大震災から30年が経ち、神戸でも震災を知らない世代が社会を支えるようになった。この世代にとって記憶を継承することは、震災を歴史として学ぶ上に成り立つ。体験者の聞き取り、震災に関わる資料(震災資料)や映像の読解、研究者の著作の学習や、小説や映画等の検討、記憶を継承していく道筋はひとつではない。その中で、私は共通性と多様性を継承していく上で、震災資料は特別な意味を持つと考えている。それは「もの」であるが、人々の記憶の塊である。その意味を読み解く中で、私たちは、その時代に生きた人々と対話し、その生をしっかり捉えることができるのであり、そのことは、今後も続く大災害の中で、一人一人を大切にした対応の基礎となるからである。
特別寄稿Ⅰ
心の底から「たすけあおう」と思った経験
全国大学生協連 専務理事 中森 一朗
(1995年1月当時:全国大学生協連学生理事を任期終了し、同年3月より京都大学生協就職予定)

中森 一朗
全国大学生協連 専務理事
「O大学店舗は完全倒壊」「K大学生協・○○理事の死亡を確認」・・・当時の現地対策本部報告からの抜粋である。
私の任務は報告を作成し、大学生協連を通じて全国の会員生協に発信することだった。
あの日は東京にいた。テレビをつけたら聞き慣れた地名が倒壊したビルや高速道路の様子とともに映っていた。現地情報を待ち焦がれていたときに、「関西に明るい」という理由で現地赴任の要請を受けた。全く躊躇はなかった。西宮北口から現地対策本部のある上ヶ原までは瓦礫の中を歩いた。途中避難所の小学校で子どもたちがサッカーをしているのを見て、ほっとしたことを覚えている。
当時は回線事情も悪くなかなか現地報告が送れなかった。「絶対に送る」と決め何度も接続を試みた。東京からは全国の会員生協に発信してくれた。すると、使命感に燃えた全国の生協職員が神戸に集まってきた。まもなく生協職員となる私が、懸命な支援活動を続ける彼らから学ぶことは本当に多かった。
2月には全国の大学生が芦屋の宿舎に結集し、その後被災者支援に奔走した。「ボランティア元年」である。3月には住居をなくした大学生のための仮設寮建設が始まった。ログハウスを活用した仮設寮建設は手作業であり、「僕、ここに住むんです」と作業に参加した被災学生を拍手で迎えた。結局3月末まで現地対策本部の活動に従事した。復旧した居酒屋で開催された送別会で大泣きした。
私は直接地震を体験していないし、被災の実情を目の当たりにした経験も多くない。けれども、現地の方々と寝食を共にし、自分にできることを真摯に行い続けた。その時の心の底からの「たすけあい」の経験は、間違いなく現在の自分を形作っている。
特別寄稿Ⅱ
震災30年の節目に思う、能登半島復旧への道
全国大学生協連 学生委員 久野 耕大

久野 耕大
全国大学生協連 学生委員
2025年は阪神・淡路大震災から30年の節目となり、復興の道のりを振り返る中で、私たちが直面する新たな課題にも目を向ける年です。昨年、奥能登(主に輪島市)を訪れた際、地震被害の爪痕が未だに深く残る現状を目の当たりにしました。多くの住宅が放置され、避難所や仮設住宅での生活が続いている方々が多いことからも、復旧作業の遅れが実感されます。特にインフラの復旧が最優先とされている中、道路や水道の修復が進まない限り、住宅の復旧もままならない現状があります。
しかし、訪問活動を通じて得た最大の収穫は、現地の方々との対話から見える希望の光です。25組の現地の方々と直接お会いし、支援が現地の方々にとってどれほど励みになるのかを実感しました。被害状況を写真に収める際にも、地元の方々から快諾を得られたことは、自らの現状を広く知ってほしいという切実な思いの表れでしょう。
阪神・淡路大震災から30年経った今、私たちは過去の教訓を活かし、能登半島の復旧支援にも全力で取り組むべき時です。時間と全国からの継続的な支援が必要とされる中で、私たち一人ひとりの小さな行動が、大きな力となることを改めて認識しました。能登の地が再び活気を取り戻す日を目指し、さらなる支援の輪を広げていきましょう。
「1・17」の記憶を風化させないために ~学生のみなさんより~
丸山 和栞さん(京都大学文学部1回生、生協学生委員会・京大銭湯サークル所属)

丸山 和栞さん
震災が変える運命と行動
30年前に近畿地方を襲った阪神淡路大震災。私の母は前日まで神戸におり、神戸の海運会社に就職を決めていました。夜が明けると思い出深い町が変わり果てた様子で広がり、内定も取り消されたそうです。そのような母の話を聴き、陳腐ですが日常の大切さと変わってしまったものは二度と戻ってこないことを実感しました。私自身、まだ大きな災害を経験したことはありませんが、実家では防災グッズを常備したり、地域の避難訓練に参加したりしていました。震災を防ぐことはできませんが、誰かを悲しませずに済むよう備えたいと思っています。
(2025.01.17.)
体験談
特集記事
JUON NETWORK 総会・記念イベント
JUON設立のきっかけとなった阪神・淡路大震災と大学生協
阪神・淡路大震災から30年の節目の年、2025年6月21日、大学生協ともつながる「JUON NETWORK総会・記念イベント」がハイブリッドで開催されました。第1部の「過去:阪神淡路大震災からJUONの設立」について当時の大学生協関係者からの発信を中心に取材しました。
80名参加(うち現地64名)
本特集の概要
JUON NETWORKホームページには、「JUON(樹恩) NETWORK は、設立の母体である大学生協が過疎地域に住む人々と出会い、 “「まち」と「むら」の架け橋になりたい。”との思いを抱いたことから誕生しました。」との記載があります。また、本イベントの案内にも「阪神淡路大震災の際の大学生協の仮設学生寮建設が設立の大きなきっかけとなっています。」とあります。その原点を見つめ直し、当時、中心的に被災地で役割を発揮された大学生協関係者の声(特別寄稿)と現在の学生の視点での感想などをお届けします。
まず小林正美さんの動画が放映されました。震災の翌日に現地入りされてからの様子を、想いのこもったご自身の言葉でわかりやすく伝えていただきました。当時を知らない参加者からは、「感動で涙が出てきた。この想いを未来へつないでいきたい」との声も寄せられていました。
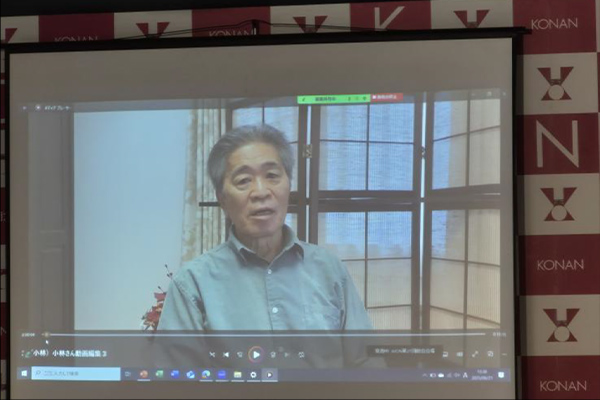
「翌日、神戸に飛んで」 小林正美(こばやし・まさみ)さん
(JUON副会長・元全国大学生協連常務理事(震災発生当時))
次に「徳島から被災地に思いをはせて」と題して、田中剛さん(JUON四国地域世話人)より、JUON設立のきっかけの一つになった阪神・淡路大震災の際の大学生協による仮設学生寮の建設につながるお話をいただきました。

「徳島から被災地に思いをはせて」田中剛(たなか・つよし)さん(JUON四国地域世話人)
そして、第一部<過去>のパートは、石井真弘さん(元大学生協神戸事業連合専務理事(震災発生当時))の報告へと想いが受け継がれました。石井さんが、何度も丁寧に繰り返して述べられていた以下の言葉に、エッセンスが集約されていると強く感じました。
「小林正美さんと藤原利廣さんの2人は、“井戸を掘った人”として忘れない!」。この言葉は、多くの参加者の心にも響いたことでしょう。
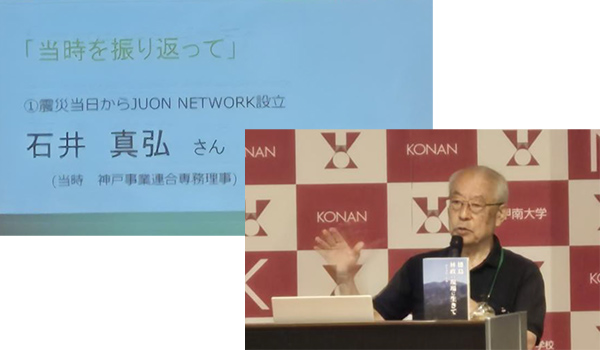
「当時を振り返って」 石井真弘(いしい・まさひろ)さん
(元大学生協神戸事業連合専務理事(震災発生当時)
交流会・懇談会では参加者どうしが、対話し学び合えたことで、たくさんの“忘れない”が、未来(次世代)につながった素晴らしい企画でした。
特別寄稿Ⅰ
阪神淡路大震災から30年 そしてこれから
小林正美(こばやし・まさみ)さん
JUON副会長・元全国大学生協連常務理事(震災発生当時)
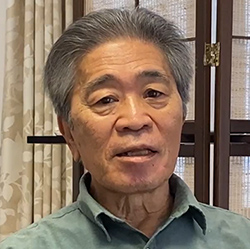
小林正美さん
阪神淡路大震災から30年が経過しました。20世紀未曾有の災禍でした。
被災者である現地の人達の頑張りと、全国からの善意と、ボランティアなどの支援が寄せられ、奇跡の復興が成し遂げられました。
大学生協としても、現地に対策本部を設置し、避難所への2,500名に及ぶ学生を中心としたボランティアの活躍、240室の仮設学生寮の設置と運営などを短期間に展開し、被災された方や学生の支えとなる活動を継続することができました。
それらの活動を通して、人間はこんなに優しく、素晴らしいものか、と励まされ、加えて学んだこともたくさんありました。
その一つに、ボランティア活動もその他の支援活動も、現場主義が大切だと言う事があります。震災などの現場を見て、聞いて、感じて、発信する。これこそが力になります。
自分は遠く離れた安全な場所に居て、間接情報で判断していては、駄目です。適格性 緊急性にそぐわず、それだけでは後追い型で、決して問題解決型にはならないと思います。
能登の震災にも言え、政府や然るべき人は、もっと現地に入るべきです。震災ではないですが、ウクライナやパレスチナのガザで起きている戦争も、責任有る当事者、国の代表が、自分が下した判断の結果、戦地で何が起きているのか?現場感覚で判断出来れば、無意味な戦争も止められると思います。
天災も人災も、今何が起きているのか?その現場の事実から、全てスタートする事、このことを今後の震災の際でも第一にしてもらいたいと思います。
特別寄稿Ⅱ
つながるチカラ
寺尾善喜(てらお・よしき)さん
JUON理事・元神戸商科大学生協専務理事(震災発生当時)

寺尾善喜さん
阪神淡路大震災より30年の節目にあたり、学生のつながりのチカラ、地域とのつながりのチカラについて、自身の経験・想いを伝えたいです。
すごい!その一:学生がボランティア活動に参加するチカラ!
大学生協が設定した学生ボランティアセンターには1,200人を超える学生が参加し、そのボランティアコーディネイトも学生がやりました。参加した学生の自発性と、その学生の思いを後押しした大学生協の行動があってのことです。ボランティア活動への参加を通じてみるみる成長する学生の生きるチカラは、人と人がつながる中で発揮されると思います。大学生協はこれからも学生のつながりを後押ししてほしいです。
すごい!その二:学生と地域がつながる連携のチカラ!
大学生協の提起から始まった「仮設学生寮」、その一つに間伐材を活かしたログハウス型仮設寮があり、地域からの材料提供、組み立てへの学生ボランティア参加で、まさに生協とボランティアと地域の連帯で形にできた偉業であり、そのつながりがJUON設立のきっかけともなりました。そのことを忘れることなく、学生と地域のつながりをJUON NETWORKはこれからも後押しし続けてほしいです。
本企画に参加して
当時の方々からお話を聞いて
小谷晃輝(おだに・こうき)さん
全国大学生活協同組合連合会 2025年度 執行役員全国学生委員・広報担当

小谷晃輝さん
「震災当時、街中を歩いているときに、倒壊したアパートの前で呆然としている二人の学生を見た。大学生協連が戦後50年間、学生組合員の力で成り立ってきた中で、目の前の学生に対して何もできないままで良いのか。何もできないのであれば、大学生協の存在価値はないのではないか。」
震災発生時に大学生協連常務理事を務めていた小林さんが今回の記念イベントの中で話されていた内容です。こう感じた後、小林さんは行動に移し、文字通り東奔西走の結果として仮設学生寮建設につながったそうです。
他にも仮設学生寮として使用されたログハウスの製作やそれが提供された経緯、当時のみなさんが行動に移した際のエピソードを聞いていると、人と人のつながりや共感から協同に移すというものに対して大きな価値と魅力を感じました。そして、共通の想いを重ね合わせながら行動した時の力強さも感じました。
私たちが所属しているのは、一人では実現が難しいことも同じ願いを持った人と手を取り合いながら一緒に形作っていく組織です。形作るものが大きなものである必要は全くありませんが、日常的に形作っているものに気付くことが簡単でないこともまた事実です。私たちの役割は、日常に溢れる価値や魅力にスポットを当て続け、拡げていくことであると思っています。
参加した現役学生の感想
過去を知り、未来に繋げる
藤井優月(ふじい・ゆつき)さん
富山県立大学4年生・全国大学生協連関西北陸ブロック2025年度学生事務局
災害というものが、大学生の「よりよい生活と平和」をどれほど脅かすものなのか、今回のお話から強く感じることができました。それと同時に、自分が今どれほど幸せで安定した生活を送れているのかを改めて実感しました。
過去から学ぶことももちろん大切ですが、その学びを単なる知識として終わらせるのではなく、いつか「よりよい生活と平和」が脅かされている人が現れる前に自分に何ができるのかを今から考え行動に移していくことこそが、過去と現在、そして未来をつなげることにつながるのではないかと感じました。


