Essay 心に残るコメントカードを書く
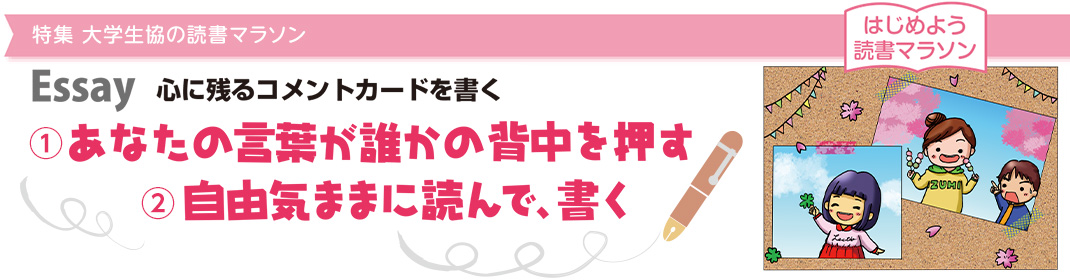
あなたの言葉が誰かの背中を押す
早川 凌矢
小田亮/ちくま新書 購入はこちら > 名前を知っている人は多いでしょう。高校の倫理(公共)を学習したことがある人は、構造主義の哲学者という理解でしょうか。ところが、これには誤りと不十分な点があります。誤りは、レヴィ=ストロースが哲学者ではなく「文化人類学」の道を歩んだこと。そして不十分な点は、どうして「構造」を解き明かしたかったのか、その先に何を目指していたのか。真相は、「人間というものを理解するためにはたった一つの社会だけを考察するのでは不十分だという自覚」(13頁)という言葉に隠されています。ぜひ、その謎を紐解いてみてください。
『弱者の居場所がない社会』
阿部彩/講談社現代新書 購入はこちら > 本書は「社会的排除」という概念を用いながら弱者の生きる世界を考察するものです。社会的排除とは、簡単にいえば、衣服や寝具という生活に必要な物質の不足だけではなく、そうした資源不足をきっかけに社会への参加ができなくなることを指します。今の日本社会は、異性愛にもとづく「近代家族」が理想的とされた時代に構築された制度を色濃く残しています。逆に言えば、理想から外れる人々はとことん周辺化されるということです。書籍内には、著者が出会ったホームレスとのエピソードが記されています。かれらにとっての生きる場所とはどこだったのか。
阿部彩/講談社現代新書 購入はこちら > 本書は「社会的排除」という概念を用いながら弱者の生きる世界を考察するものです。社会的排除とは、簡単にいえば、衣服や寝具という生活に必要な物質の不足だけではなく、そうした資源不足をきっかけに社会への参加ができなくなることを指します。今の日本社会は、異性愛にもとづく「近代家族」が理想的とされた時代に構築された制度を色濃く残しています。逆に言えば、理想から外れる人々はとことん周辺化されるということです。書籍内には、著者が出会ったホームレスとのエピソードが記されています。かれらにとっての生きる場所とはどこだったのか。
私は、本が大嫌いでした。中学2年生のとき、担任の先生は「本をたくさん読んだ方がいい」とアドバイスをくれました。それでも、私には「本を読むことの意味」が分かりませんでした。
読書嫌いを克服したきっかけは、意外にも、予備校時代の「現代文」の授業でした。担当の講師には、小手先の解法テクニックではなく、きちんと本文の内容を理解するための指導をしていただきました。
そして、多くの本文を読み重ねていくうちに、問題演習の意味を超えて、何か人生において大切なことを学ぶことができている気がしました。今ではすっかり本の虫です。前置きが長くなりましたが、私はこのエッセイを書かせていただくにあたり、まずは私の本との出会いを紹介しました。
さて、本題に戻りましょう。日々の読書のなかで、コメントカードを書くことは、一体どのような意味をもつのでしょうか。私は、「みえない輪を広げること」だと考えています。
たしかに、コメントカードを書くことで、自分が本を読んだときの感情を言語化して、記録することができます。私も、コメントカードを書き始めた当初は、同じように考えていました。でも、それが目的であれば、自分のパソコンにメモを残すなど、他にもいろいろな方法があると思います。
大学生協の書籍販売コーナーでは、学生が提出したコメントカードを書籍のそばに掲示してくれています。当然、生協には多くの人が訪れるわけですから、自分の書いたコメントカードが他人の目に留まることもあります。実際に、私が書いたコメントを読んで書籍を購入したと報告してくれた知人がいました。
そのときに私は、コメントカードを書くことの意味がわかりました。自分の書いた言葉は、誰かに読まれたことで、もっと大きな意味が付与されたのだと。自分のコメントをきっかけに、その本を読んでくれたことは、素直に嬉しかったです。その知人と本の内容を語り合うきっかけにもなりました。
でも、それと同時に、自分が書くコメントに対する責任感も芽生えました。もし私が異なる表現をしていたら、知人はその本を購入して読むことはなかったのかもしれない、と思いました。つまり、私のコメントが、誰かの読書の機会を創りだす一方で、その機会を奪ってしまう可能性もあるのです。読書愛好家の一人である私にとって、それだけは避けたいです。
それ以降、私はコメントカードの存在を、書評でもなければ、ただの感想文でもない、他者と私をつなぐ媒介項として考えています。コミュニケーションの手段だから、書くときには、十分に書籍の内容を理解したうえで、たくさんのことを考えてしたためます。余談にはなりますが、コメントカードや読書マラソンを通じて、限られた紙幅に遺したいことを表現する能力も培うことができているような気がします。
反対に、私も、誰かがしたためてくれたコメントカードを読みます。現在所属している名古屋大学では、コメントカードと本のセットを、書籍コーナーのひとつの場所に集めて展示してくださっています。また、この『読書のいずみ』でも読書マラソンで入賞された方のコメントなどを読むことができます。
気になっている本や、すでに読んだことがある本について書かれているコメントは、積極的に読みます。そして、自分の感想と、コメントを対照させることで、顔もわからない誰かとの対話を試みます。
その作業は、孤独でありながら、確かにコメントをしたためてくれた他者がいるコミュニケーションなのです。
そうしたやり取りをしたうえで、自分は新しいコメントカードを書く。そして、またどこに住んでいるのかもわからない誰かが、コメントを読んでくれることで、みえない輪が日本中に広がります。
私はいま、大学院で調査や論文の執筆に精進しています。研究に向き合うなかで気がついたことがあります。それは、論文であれ、本であれ、そこに書かれていることは、著者が人生をかけて取り組んできた「生のあゆみ」である、ということです。
私たち読者は、かれらの「魂の軌跡」に敬意をもって、本と向き合わなければなりません。読まなくてよい本なんて、一冊もありません。だったら、読んでみようか迷っている人の背中をそっと優しく押すことができる、あたたかいコメントカードを、みなさんも書いてみませんか。そして、直接会えなくとも、そのコメントを通じて、つながり合えることを楽しみにしています。
読書嫌いを克服したきっかけは、意外にも、予備校時代の「現代文」の授業でした。担当の講師には、小手先の解法テクニックではなく、きちんと本文の内容を理解するための指導をしていただきました。
そして、多くの本文を読み重ねていくうちに、問題演習の意味を超えて、何か人生において大切なことを学ぶことができている気がしました。今ではすっかり本の虫です。前置きが長くなりましたが、私はこのエッセイを書かせていただくにあたり、まずは私の本との出会いを紹介しました。
さて、本題に戻りましょう。日々の読書のなかで、コメントカードを書くことは、一体どのような意味をもつのでしょうか。私は、「みえない輪を広げること」だと考えています。
たしかに、コメントカードを書くことで、自分が本を読んだときの感情を言語化して、記録することができます。私も、コメントカードを書き始めた当初は、同じように考えていました。でも、それが目的であれば、自分のパソコンにメモを残すなど、他にもいろいろな方法があると思います。
大学生協の書籍販売コーナーでは、学生が提出したコメントカードを書籍のそばに掲示してくれています。当然、生協には多くの人が訪れるわけですから、自分の書いたコメントカードが他人の目に留まることもあります。実際に、私が書いたコメントを読んで書籍を購入したと報告してくれた知人がいました。
そのときに私は、コメントカードを書くことの意味がわかりました。自分の書いた言葉は、誰かに読まれたことで、もっと大きな意味が付与されたのだと。自分のコメントをきっかけに、その本を読んでくれたことは、素直に嬉しかったです。その知人と本の内容を語り合うきっかけにもなりました。
でも、それと同時に、自分が書くコメントに対する責任感も芽生えました。もし私が異なる表現をしていたら、知人はその本を購入して読むことはなかったのかもしれない、と思いました。つまり、私のコメントが、誰かの読書の機会を創りだす一方で、その機会を奪ってしまう可能性もあるのです。読書愛好家の一人である私にとって、それだけは避けたいです。
それ以降、私はコメントカードの存在を、書評でもなければ、ただの感想文でもない、他者と私をつなぐ媒介項として考えています。コミュニケーションの手段だから、書くときには、十分に書籍の内容を理解したうえで、たくさんのことを考えてしたためます。余談にはなりますが、コメントカードや読書マラソンを通じて、限られた紙幅に遺したいことを表現する能力も培うことができているような気がします。
反対に、私も、誰かがしたためてくれたコメントカードを読みます。現在所属している名古屋大学では、コメントカードと本のセットを、書籍コーナーのひとつの場所に集めて展示してくださっています。また、この『読書のいずみ』でも読書マラソンで入賞された方のコメントなどを読むことができます。
気になっている本や、すでに読んだことがある本について書かれているコメントは、積極的に読みます。そして、自分の感想と、コメントを対照させることで、顔もわからない誰かとの対話を試みます。
その作業は、孤独でありながら、確かにコメントをしたためてくれた他者がいるコミュニケーションなのです。
そうしたやり取りをしたうえで、自分は新しいコメントカードを書く。そして、またどこに住んでいるのかもわからない誰かが、コメントを読んでくれることで、みえない輪が日本中に広がります。
私はいま、大学院で調査や論文の執筆に精進しています。研究に向き合うなかで気がついたことがあります。それは、論文であれ、本であれ、そこに書かれていることは、著者が人生をかけて取り組んできた「生のあゆみ」である、ということです。
私たち読者は、かれらの「魂の軌跡」に敬意をもって、本と向き合わなければなりません。読まなくてよい本なんて、一冊もありません。だったら、読んでみようか迷っている人の背中をそっと優しく押すことができる、あたたかいコメントカードを、みなさんも書いてみませんか。そして、直接会えなくとも、そのコメントを通じて、つながり合えることを楽しみにしています。
P r o f i l e
早川 凌矢(はやかわ・りょうや)名古屋大学、博士前期課程1年生(2025年3月現在)。旅が大好きな地理学徒。町民として、推し活も欠かさない。ライブ遠征を口実に日本各地で旗を立てる日々。2023年度開催 第19回全国読書マラソン・コメント大賞 ノンフィクション部門 金賞受賞。
自由気ままに読んで、書く
鹿子嶋奎太
『バッタを倒しにアフリカへ』
前野ウルド浩太郎/光文社新書 購入はこちら > この男、バッタが好きすぎるあまりにバッタアレルギーになってしまった! それでも、彼は恋するバッタに会うためにアフリカまで飛び立つ。
しかし、そこはアフリカ。時間通りに人は来ない、暑い、そもそもバッタがいない、などなど困難の連続!そして彼は「神の罰」と呼ばれるバッタの大群と対峙することになる……。
ファーブルに憧れた若き研究者の熱き冒険の記録がここに!
エッセイを書こうと思ったら、下手くそな評論が出来上がった。前野ウルド浩太郎/光文社新書 購入はこちら > この男、バッタが好きすぎるあまりにバッタアレルギーになってしまった! それでも、彼は恋するバッタに会うためにアフリカまで飛び立つ。
しかし、そこはアフリカ。時間通りに人は来ない、暑い、そもそもバッタがいない、などなど困難の連続!そして彼は「神の罰」と呼ばれるバッタの大群と対峙することになる……。
ファーブルに憧れた若き研究者の熱き冒険の記録がここに!
今回ありがたいことにエッセイを書く機会をいただいた。こんな私でいいのだろうか、非常に不安である。メールを返信するときですら、「メール 返信 例文」と検索している私で本当にいいのだろうか。そんな私だが、意外と真面目である。依頼をいただいたからには期待に応えるように精一杯書こうと決めた。そして、長い時間をかけエッセイらしきものを書きあげた。が、それはエッセイとは到底呼ぶことができない、硬い表現ばかりの読みにくい長文であった。そして、冒頭の一文に戻るわけである。書いていく途中で自信を無くし、自分の思いを省きに省いたのがダメだった。エッセイなのに自分の考え、思いを書かないでどうする! とんだあほである。AIに書かせたほうがよっぽどいいエッセイを書くのではないかと思う。しかし! まだ人間はAIに負けるわけにはいかない。人間には人間の意地というのがあるのだ。ということで、現在白紙から書き直している。エッセイver2.0である。このエッセイには2つの目的が存在する。まずコメントカードの良さについて述べること、そしてAIよりも突拍子のない文章を書きシンギュラリティを阻止すること、の2つである。以降、硬い文章が途中見え隠れするかもしれないが、それは始めに書いたエッセイver1.0の残骸である。どうか寛大な心で受け入れていただきたい。
まず皆さんはコメントカードをご存知だろうか。大学生協の書店に行くと見かける、大学生が書いた感想コメントである。私はこれが好きだ。というのも、私は本をタイトルや表紙、帯で決めるタイプであるからだ。帯に「書店員オススメ!」と書いてあったら必ず手にとる。「○○大賞受賞や○○絶賛!」などの文言でも手に取ってしまう。書店や出版社の思うつぼである。でもよい、たいがい良い作品と出会えるからだ。このコメントカードもそうである。同世代が書いているということもあり自分に刺さるものが多い。本当に同世代が書いたのか!?と思うほど、上手な言葉づかいで書かれているものもあり魅力的である。そういうコメントを読むと、そのコメントとは対照的な自分の幼稚な文章が恥ずかしくなる。
では、そんな私がなぜコメントカードを書き始めたか? 単純である。いいコメントを書くと図書カードが貰えると聞いたからだ。自分のコメントがその月のナイスコメントなるものに選ばれた場合、図書カードが貰えるというではないか。これはやるしかないだろう。本を読みたいが本を買うにもお金が必要だ。図書カードがもらえたなら、幾分か足しになるだろうと思った。図書館で借りるのもいいが、やはり好きな本は買いたいという思いがある。ならもっとバイトしろ!と言われそうだが全くその通りである。異論はない。そういった不純な動機から私はコメントカードを書き出した。
しかし、書いてみるとこれが意外と面白い。本の感想を書くって読書感想文的な感じでしょ~と想像される方が多いと思う。安心していただきたい。コメントは宿題でもなければ、コンクールでもない。自分の感想を自由に書けばいいのだ。あらすじを大量に書き「おもしろかった、すごかった、びっくりした」の三種の神器を使い読書感想文を書いていた私でも書けたのだ。自分が読んで感じたこと、作品の好きなところ、印象に残っている言葉、何でもいい。本を読んだ感想を、自分の心に素直にしたがって自由気ままに綴ってみてほしい。そういったコメントは不思議と惹かれるものだ。そして書いてみると、感想を文字にすることが案外面白いことに気づくだろう。本を読んだ時の感想を文字にすると、モヤっとしていた自分の想いの輪郭が見えてくる。無理に体裁を整えなくていい。飾り気ない言葉ほど心を打つこともあるだろうから。
同じ本を読んでも、同じ感想を持つ人はいないというのが読書の面白いところだ。どこに共感したか、感動したか、衝撃をうけたか、読者によって多種多様の感想が生まれる。自分と歳の近い人が何を読んでどう感じたのか、コメントから知ることは刺激的で面白いものだ。コメントでは、様々なジャンルの本の感想が紹介されている。どのコメントも素晴らしく興味を引くものばかりだ。
あなたも好きな本について書いてほしい。「何故か?」って、私が読みたいからだ、気になるからだ、完全に自己都合である。ダラダラと文章を書きすぎたため、書ける文字も限られてきた。最後に、私が一番伝えたいことを書いて終わりとする。「みんな! 本を読んだ時の感想をコメントとして残そう!! 楽しいよ!」以上である。
P r o f i l e
鹿子嶋奎太(かごしま・けいた)静岡大学4年生。最近は「カレーライスのご飯の位置は左右どちらか」というくだらない話題で友人と盛り上がる。ちなみに、ご飯は右派。2023年度開催 第19回全国読書マラソン・コメント大賞 文芸部門金賞受賞。
特集「大学生協の読書マラソン」記事一覧


