いずみ委員 文芸誌を語る
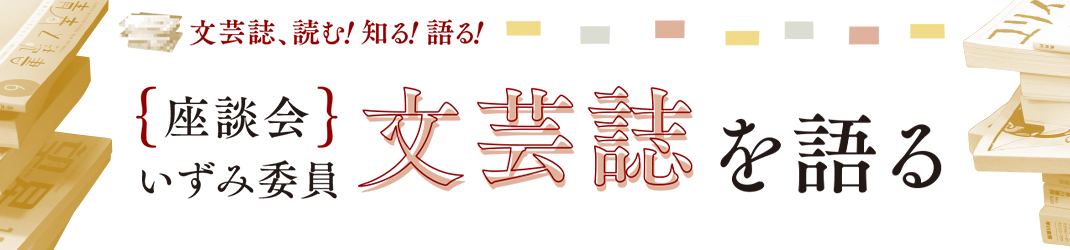
齊藤ゆずか・中川倫太郎・山原和葉
日ごろから読書を愛するメンバーたちが、それぞれの視点から文芸誌の魅力とその可能性を語ります。日常の読書体験から見えてくる文芸誌の奥深さとは?
1. 文芸誌って何?
4. 作家と本が生まれる場所
1.文芸誌って何?
山原
こんにちは。いずみ委員の山原和葉です。普段は本屋さんで単行本や、文庫本の新刊をひたすら見ては、面白そうな作品を読んでいます。
中川
同じくいずみ委員の中川倫太郎です。僕は文庫派で、手軽に持ち運べるところが好きです。この前もお尻のポケットに文庫本を1冊だけ入れて散歩していました。
齊藤
同じくいずみ委員の齊藤ゆずかです。私は本がある空間が好きで、本屋さんを巡ったり、部屋の中を本でいっぱいにするのが目標です。
山原
今回の座談会はテーマが「文芸誌」ということですが、そもそものきっかけは、181号の『読書のいずみ』で、『スピン/spin』(河出書房新社)の編集長である尾形さんに取材させていただいたことでしたよね。「文芸誌とはなんぞや?」と思っている大学生が多いと思います。私も『スピン/spin』を見るまで「文芸誌って何?」という感じだったので。まずは「文芸誌」について軽く教えてください。
齊藤
いろいろな出版社やアートグループが出していて、小説や、エッセイ、詩、短歌など、1冊の雑誌にいろいろな方が寄稿しています。連載も読み切りもあって、そういうあらゆる文芸要素が詰まっている、主に月刊・季刊の文芸の雑誌だと私は認識しています。中川さんはどうですか。
中川
狭い意味だと、『群像』(講談社)や『文學界』(文藝春秋)などの、硬派ないわゆる文芸誌。もう少し広くとらえると、独立して作っている文芸誌・ZINEや詩や批評も入っている『ユリイカ』(青土社)、あとは『現代詩手帖』(思潮社)。僕が推したいのは『悲劇喜劇』(早川書房)ですね。早川書房はSFが有名ですが、もともと創業者の早川清さんが演劇青年だったんです。だからこれは早川書房肝いりの雑誌と言っても過言ではないと思います。
山原
すごい。文芸誌って思っていた以上に大量にあるのですね。私は今まで文芸誌を読んでいなくて、今回この企画をするということで、『スピン/spin』を初めて買ってみました。いろいろな作家さんが寄稿して集めたものではアンソロジーがありますが、それとも少し雰囲気が違う感じがしました。『スピン/spin』だったら、短歌が入っていたり、小説があったり、段組みも作品によっていろいろで、さらに紙へのこだわりについても書かれていて、普通の単行本や文庫本ではできないことをやっているなと感じました。
2.様々な種類の文芸誌、その魅力

山原
お二人のおすすめの文芸誌を紹介してください。
齊藤
文芸誌の魅力は、ある意味「型」があることだと思います。文芸誌ごとにキャラクターがあって、そこにいろいろな作家さんがドアをノックして入ってくるようなイメージ。文芸誌という家の中にいろいろな人が出たり入ったりするのを、自分が窓から覗いているような感覚になれて、文芸誌の作り手の意志みたいなものが見えてくるというのが私は面白いところだと思います。
中川
僕は、リアルタイムで車が行き交う交差点みたいな感じだと思います。例えばこれ(『文藝』(河出書房新社))は文芸賞発表の受賞作が載っています。そういうリアルタイムで追っていけるところ。あとは、文芸誌に書かれているバージョンと実際の単行本とでは、改稿されているところもある。そういうライブ感が面白いと思います。
山原
私は『GOAT』(小学館)がおすすめです。510円(税込)で、素敵な作家さんの作品が大量に自分の手元にやってくるというのが、初めて買った時は衝撃でした。
齊藤
作家さんに注目する読み方は、作家さんを推している感覚になれる気がして面白いなと思います。2025年6月号の『文學界』は金原ひとみさんの特集が組まれています。私は最近金原さんにハマり始めたので読んでみたのですが、金原さんの新作『YABUNONAKA ―ヤブノナカ―』(文藝春秋)についていろいろな人が寄稿していたり、アイドルの方との対談が掲載されていたり、金原さんに様々な作家さんが悩み相談をするというコーナーもあります。
山原
私は一穂ミチさんや凪良ゆうさんが大好きで、これ(『オール讀物 2025年5・6月号』(文藝春秋))は二人の作品が揃って掲載されていたから迷わず買いました。たくさんの作品が詰まっていて、希望がめちゃくちゃ湧いてくる。文芸誌って、楽しいですね。
齊藤
『悲劇喜劇』のことを聞いてみたいですね。これはどういう雑誌ですか。
中川
演劇の雑誌で、例えばこれ(『悲劇喜劇 2023年1月号』(早川書房))は、20世紀と21世紀を代表する世界的な演出家のピーター・ブルックが亡くなった時に、その追悼号でいろいろな有名人がピーター・ブルックにまつわる話を書いています。あとは毎回戯曲が2本ぐらい載っています。あまり戯曲を読む機会はないじゃないですか。実際本を買おうとすると結構高いですし。でもこういう戯曲雑誌や詩の雑誌は、文字数を値段で割ったらめちゃくちゃコストパフォーマンスがいいと思います。
山原
学生ならではの、読みたい本はたくさんあるのにお金は足りないという悩みに素晴らしく寄り添ってくれるものですね。
3.文芸誌ならではの「読むこと」の楽しみ方

中川
さっき、文芸誌のライブ感が好きと言いましたが、『スピン/spin』は特に面白いです。11号に中村文則さんの連載で「彼の左手は蛇」という小説が載っているのですが、3号までは、おそらく小説を期日までに書けなくて、代わりにエッセイを書いているんです。普段は作家の表情を見ることはできないけど、すみませんと言っている中村さんが見える気がして。
齊藤
連載ならではの面白さですよね。逆に連載であるということが、文芸誌を読まない人には、毎月読まないから置いていかれてしまうと感じるかもしれません。私も初めて『スピン/spin』の11号を買った時に、その不安がありました。でも、ある作品を、連載だと気づかないで読んだら、それはそれで面白かったんですよ。前後があるから繋がらないのですが、切っているところが絶妙だからか、1つの短編としてすごく面白く読めました。たまたま読んだ作品が面白いなと思ったら、前後の号を読んでみればいいし、すごく自由な読書ができると思いましたね。
山原
確かに、単行本や文庫本を買ってきて、真ん中から読もうとはならないですよね。真ん中から読むって、意図的ではなくやろうとしたら、文芸誌しかないかもしれない。
中川
好きな作家の作品を読んで、次のページに別の作家の作品が載っていて、意外とそちらが良かったという経験があります。
山原
新たな出会いがあるかもしれませんね。
齊藤
(『スピン/spin』11号を見ながら)この短歌とイラストもいいですよね。岡野大嗣さんの短歌と、安福望さんのイラスト。歌集を1冊買うのはハードルが高いと感じる人がまだ多いと思うのですが、こういう風に短歌に触れられるのもすごく素敵。
山原
雰囲気がガラッと変わって「おっ!」となりますよね。
齊藤
掲載の順番にも意図があるのかも。
山原
作り手の意図がめちゃくちゃ詰まっているなというのは、ぱらぱらと見ただけでも感じるので、この順番にはいろいろ意図があるのでしょうね。
齊藤
文学作品に限らず、連載の「絶版本書店」や、名久井直子さん(装丁家)の本作りの話など、他の本ではなかなか読めないものが入っているのもいいなと思います。
中川
僕は佇まいオタクなので、『スピン/spin』の目次の紙は、本文とは違う紙が使われていて、いいなと思いました。
山原
この目次の紙、いいですね。模様が入っている。
中川
それで1冊330円税込みは凄すぎる。
山原
値段を知らずにレジに持っていって、330円と言われて、何か別のバーコードを読み取られてしまったのかなと驚きました。この価格で本を届けるなんて、相当な気概がないと絶対できない。
齊藤
「日常に『読書』の『栞』を」という、『スピン/spin』の人たちの思いが、そういう全てに表れている。触り心地が楽しめるし、手軽に手に取れるところもそうだし。
4.作家と本が生まれる場所
中川
文芸誌に載った作品が、文学賞を受賞することもありますよね。
齊藤
文芸誌から生まれる作家さんがいるというのも、めちゃくちゃドラマがあって面白いなと思いますね。これ(『すばる2023年11月号』(集英社))は、すばる文学賞の発表号ですね。
中川
そうです。これには大田ステファニー歓人さんの『みどりいせき』が掲載されています。
齊藤
作品を選考した人の感想も読めるので、それも面白いなと思います。
中川
文芸誌は、作家が生まれる場所でもあるということですね。
齊藤
作家が生まれる場所でもあるし、単行本が生まれる場所でもある。その連載がいつか1冊の本になる。
中川
文芸誌に載っているのに単行本にならない作品もありますね。村上春樹の最新作『街とその不確かな壁』(新潮社)。元々デビュー第2作とかで、当時「街と、不確かな壁」というタイトルで掲載されたのですが、その小説をご本人がどうしても気に入らなかったらしくて。全集への掲載も断られたそうです。だから実際に掲載は見送られたとか。それをリライトした結果がその最新作。
山原
そこでしか読めなかった完全にまぼろしの作品になったということですね。今我々の手元にあるいくつかは、すごく貴重な何かになるかもしれない。手放せないですね。
5.作家ではない人たちが作る文芸誌
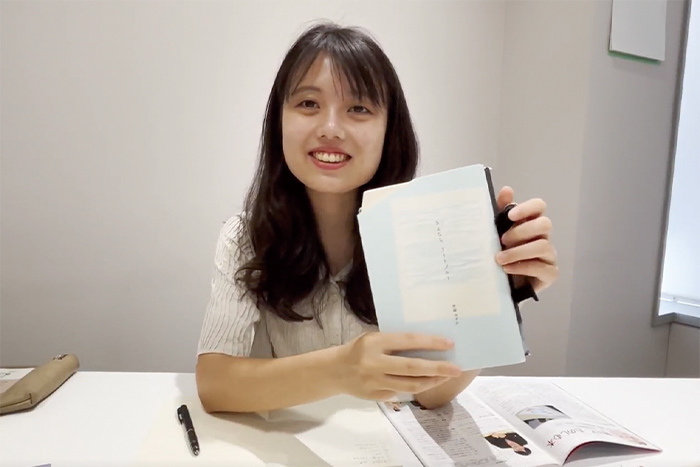
中川
ちなみにこれは『おてあげ』(困ってる人文編集者の会)という雑誌で、書店員さんや、編集者の人が寄稿した本の周りの困りごとが掲載されています。だから蟹が手を挙げておてあげ、というちょっとかわいいデザインの表紙。最近はこういう新しいムーブメントも生まれている。あと……齊藤さん、これは何ですか?
齊藤
私が大学で作っている文芸誌『木天蓼』で“またたび”と読みます。大学の同期と作っているのですが、その言い出しっぺの子が猫好きで、本を作りたいという話になった時に、タイトルを考えていたら、この“またたび”というワードが出てきたんです。漢字にすると格好いいのでは? ということで、漢字にしたのですが、誰も読めない(笑)。これは同じ学部の人たちに呼びかけて作ったもので、小説もあるし、エッセイ、短歌や詩もあります。書いたことがないけれど書いてみたい人や、ずっと書いてきたけど、発表する場がないなと思っている人に、文芸サークルに入るよりももっと気軽な感じで、書くことに携わってもらいたいという思いがあって始まった。実際にやってみると、こんなに面白いものが読めるんだと、受け取った自分が嬉しくなるような原稿もあります。書いた後の感想交流会では、作成にあたっての悩み事の相談や、もっと良くするための話をします。書くこと・読むことで繋がれる輪ができたのが、よかったなと思っています。
中川
昔はもっと大学から始まる文芸誌がありましたよね。これは『三田文學』(三田文学会)という雑誌ですが、『三田文學』の「三田」は、慶應義塾大学本部キャンパスの「三田」です。「いろいろな作家が広い分野で、慶應義塾の出身者に限らず、数多くの逸材を世に送り出してきました」と書かれています。このように大学から動きが始まるということがあるから、もしかしたらこの『木天蓼』も……。
山原
いつか成長して、『三田文學』のようになるかもしれない!
齊藤
私が文芸誌を初めて作ったのは、実は高校生の時に遡ります。タイトルは『海棠』。花海棠という植物からとっています。私は出身が北海道で、北海道立文学館という施設が高校の近くにあって、そこで自分の高校の大先輩たちがかつて文芸誌を作っていたということを知ったんです。それを見た時に私も作ってみたいと思い、制作しました。
山原
文学的な活動をしてみたいなという時に、最初に手を出しやすいものとして文芸誌という存在があるからこそ、新たな書きたい人が出てきやすいのかなと思いました。
齊藤
初めて書いた時は、自分の作品だけで1冊本ができるような、そんな分厚さにはなかなかならないけど、みんなの間に挟まると意外といい感じになりました。順番もいろいろ考えるんですよ。この人から始まってほしいなとか、最後はこの人がいいなとか。そういうのも楽しかったですね。最近は文フリ(文学フリマ)やZINEフェスなどで、多くの人が本を作るということに目が向いているので、そういうものと文芸誌は親和性が高いと思います。
中川
昔は大学から始まっていたムーブメントが、形は変われど文フリのように、いろいろな仲間と組み合って同人誌を作るという活動が広まってきている。そういう風に火は燃え続けているんだな……。
あ! (一冊の文芸誌を手に取り)『文芸誌アパート』と書かれていますね。しかも一番表が見覚えのある名前だ。これは何ですか?
齊藤
ありがとうございます(笑)。私が関わっている文芸誌です。4人の作家が集まって作りました。それぞれ別の話を書いて、しかもそれぞれ独立した本の形をしています。ちょっと特殊な製本方法をしていて、凸凹の凸の形のようなホチキスを使って、紐を通して4冊本を組み合わせる。裁断の形も違うので、前から見てもそれぞれが見えます。この作品は『文芸誌アパート』と言いまして、それぞれの作家の個性とか、その物語性そのままに、でもゆるく同居している感じ。さっき私、文芸誌のことを家と表現しましたよね。
山原
文芸誌と言ったら、いわゆる雑誌の形をどうしても考えてしまいますが、そういう文芸誌もあっていいですよね。さっきの家の話と絡めると、むしろそういう形にすることで、文芸誌の本質がより視覚的に目に見えて分かりやすくなっているなと思います。
6.初めての文芸誌、どれにする?
中川
最初に読むなら、どういう文芸誌がいいでしょうか。詩について読むなら、この『現代詩手帖』という詩の雑誌がおすすめです。1月号は毎回「現代日本詩集2000」が掲載されていて、その年のいろいろな作家の詩を総なめにできる。だから、あまり詩ってよくわからないなという人には、ぜひこの『現代詩手帖』の1月号、何年のものでもいいですけど、古本屋さんや本屋さんに行って見てみて、いいなと思ったら買ってみてください。
齊藤
他の文芸誌でも1月号は、今年を俯瞰するとか、去年を総括する内容が多いですよね。
山原
『本屋大賞』(本の雑誌社)は年に一回しか出なくて、その前の年の12月からその年の11月までの間に出た本の中で、書店員さんがこれを推したいという作品が詰まっていて、最新の面白い本がたくさん載っています。これは私のイチ押しです。
齊藤
『本の雑誌』(本の雑誌社)って、『読書のいずみ』とテンションが似ているなと思います。作家さんの読書のことにフィーチャーしている。『読書のいずみ』を読んでくれている方だったら、『本の雑誌』は入り口としていいと思いますし、本格的な文芸誌にチャレンジしようという場合は、好きな出版社のものがいいと思います。本を読んでいると、自分の好きな本がよく同じ出版社から出ているなと気づくことがあると思います。デザインが好きとかなんでもいいのですが、作り手のカラーが凝縮されている文芸誌に手を伸ばす理由としては、いいのではないかなと思います。
中川
『本の雑誌』はWEB版もありますよね。確か『文學界』も『文藝』も電子書籍化していたと思います。
山原
『GOAT』もこれからオーディオブックを進めたり、電子版も同時に出してテキストを提供しているものもあるようです。このような取り組みは、やはり新しい文芸誌ならではだなと思いました。
中川
これからも文芸誌は変わっていくんだなあ。
山原
変わっていきつつ、根幹はきちんとある。
中川
文芸誌を見習って、我々『読書のいずみ』もこれから変化しながら、大事なところは変えないで。頑張りましょう。
(収録日:2025年6月7日)


