文芸誌年表

1874-1911
| 1874 (明治7) |
『明六雑誌』 | 明治初の雑誌。文学論も掲載された。 |
|---|---|---|
| 1885 | 『我楽多文庫』 | 山田美妙、尾崎紅葉ら硯友社のメンバーで回覧され、のちに販売される。同人誌のルーツ。 |
| 1888 | 『都の花』 | 初の商業文芸雑誌。美妙、紅葉のほか幸田露伴、樋口一葉ら寄稿。この年から数年間で多くの文芸誌が創刊された。 |
| 1891 | 『早稲田文学』 | 坪内逍遥が創刊。評論や文学界の動向も記した。 |
| 1893 | 『文學界』 | 島崎藤村、北村透谷らが創刊。樋口一葉「たけくらべ」が連載された。 |
| 1895 | 『太陽』 『文芸倶楽部』 |
博文館が20種以上の雑誌を統合した。 |
| 1896 | 『新小説』 | 夏目漱石「草枕」、田山花袋「蒲団」などを掲載。泉鏡花、永井荷風も執筆。 |
| 『新声』 | 『新潮』の前身。 | |
| 1897 | 『ホトトギス』 | 松山の新聞記者が正岡子規の俳句を広めたいと創刊。夏目漱石「吾輩は猫である」が掲載された。 |
| 1899 | 『中央公論』 | 漱石や森鷗外の作品を起用。現在も続く雑誌。 |
| 1900 | 『明星』 | 与謝野鉄幹が創刊。与謝野晶子や上田敏、石川啄木、北原白秋らが活躍。 |
| 1904 | 『新潮』 | 日露戦争中で、創刊号には戦時色が強く出ている。「国木田独歩追悼号」が注目された。 |
| 1905 | 『火鞭』 | 社会主義文学運動の拠点となる。 |
| 1908 | 『アララギ』 | 伊藤左千夫らが創刊した短歌誌。 |
| 1909 | 『スバル』 | 石川啄木らが『明星』廃刊後につくった。誌名の決定にもかかわった森鷗外「雁」などを掲載した。 |
| 1910 | 『白樺』 | 武者小路実篤、志賀直哉、有島武郎らが参加し、ロダンやゴッホ、セザンヌなどの絵も掲載した。 |
| 『三田文学』 | 慶應義塾大学文科の機関誌。永井荷風を発行人とし森鷗外、上田敏も参加。 | |
| (第二次) 『新思潮』 |
小山内薫、谷崎潤一郎らによる。 | |
| 1911 | 『青鞜』 | 平塚らいてうや伊藤野枝を中心に女性の書き手が集まり、女性解放運動を展開した。 |
1912-1933
| 1912 (大正元) |
『奇蹟』 | 舟木重雄らが創刊。ロシア文学の翻訳紹介もした。 |
|---|---|---|
| 『近代思想』 | 大杉栄らが創刊。労働文学の先駆け。 | |
| 『聖盃』 | 早稲田大学、東京大学、外国語学校や美術学校などの外国語に堪能な学生が集まり、海外文学を紹介。 | |
| 1913 | 『生活と芸術』 | 読売新聞記者・詩人の土岐哀果が創刊。ここに集まった歌人が「生活派」と呼ばれる。 |
| 1914 | 『国民文学』 | 当初は田山花袋、徳田秋聲らが寄稿したが、翌年から短歌雑誌となる。 |
| 1915 | 『ARS』 | 誌名はラテン語で「芸術」という意味。北原白秋が創刊、森鷗外、上田敏が顧問となった。堀口大學、高村光太郎、室生犀星、萩原朔太郎らが参加。 |
| 1918 | 『赤い鳥』 |
鈴木三重吉が童話・童謡を掲載する児童文学雑誌として創刊。芥川龍之介や小川未明らの作品を掲載した。 |
| 1919 | 『改造』 | 志賀直哉の「暗夜行路」や宮本百合子の作品などを掲載。『中央公論』とともに文壇の二大雑誌と評された。 |
| 1920 | 『新青年』 | 青年向けの文芸誌で、探偵小説が人気となった。原稿募集を行い、横溝正史や江戸川乱歩が入選した。 |
| 1921 | 『種蒔く人』 | プロレタリア文学運動の発端となる。 |
| 1923 | 『文藝春秋』 | 菊池寛が創刊。川端康成や横光利一が寄稿、直木三十五による文壇ゴシップ記事が話題に。 |
| 1924 | 『文芸時代』 | 横光利一、川端康成らが創刊。執筆メンバーは「新感覚派」と呼ばれた。 |
| 1928 (昭和3) |
『戦旗』 | プロレタリア文学を掲載し、18回の発売禁止処分を受けながら発行した。 |
| 『女人芸術』 | 女性解放のための婦人総合誌として出発し、林芙美子が登場した。 | |
| 1930 | 『作品』 | 井伏鱒二、小林秀雄らが創刊号で「仲間」として紹介されている。 |
| 『オール讀物』 | 『文藝春秋』の臨時増刊号としてスタート。翌年から月刊化される。 | |
| 1932 | 『コギト』 | 大阪高校出身者らが創刊。「古典を愛する」とうたい、詩と評論を掲載。 |
| 1933 | 『四季』 | 堀辰雄が創刊。創刊号には横光利一、川端康成らが寄稿した。 |
| 『文藝』 | 改造社が創刊し、1944年に河出書房にうつる。戦時中も発刊が続いた唯一の文芸誌。 | |
| 『文學界』 | 小林秀雄らが創刊。1949年に文藝春秋に発行が引き継がれる。 |
1935-2008
| 1935 | 『文藝春秋』が「芥川賞」「直木賞」制定を発表 | |
|---|---|---|
| 1939 | 出版統制が強まる | |
| 1943 |
|
|
| 1944 | 『日本文学者』 | 出版統制と紙不足のため、80以上の同人誌が統合して生まれた。 |
| 1945 | 10月、『文藝春秋』『新潮』『早稲田文学』など | 戦争が終わり、文芸誌の復刊が始まった。 |
| 『新生』 | 戦前から活躍していた作家が復活する場となった。 | |
| 1946 | 『中央公論』『改造』『三田文学』など復刊 | |
| 『近代文学』 | 小田切秀雄ら評論家による同人雑誌。 | |
| 『群像』 | ||
| 1947 | 『小説新潮』 | |
| 1968 | 『小説セブン』 『小説エース』 『小説宝石』 |
純文学と大衆小説の間にある「中間小説」の文芸誌が急増。 |
| 1969 | 『早稲田文学』10年ぶりに講談社から復刊 | |
| 1970 | 『思潮』 | |
| 『すばる』 |
 季刊誌として創刊された。
|
|
| 1974 | 『野性時代』 | |
| 1976 | 『文藝春秋』9月号、史上初の100万部を達成。 | |
| 1985 | 『新潮45』 | 日記・伝記を中心としたノンフィクション誌。 |
| 1987 | 『小説すばる』 | 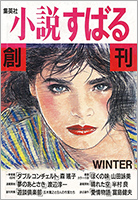 |
| 1988 | 『新潮』千号記念号 『群像』五百号記念号 『ホトトギス』千百号記念祝賀会 | |
| 1993 (平成4) |
『小説王』 | |
| 1995 | 『小説トリッパー』 | 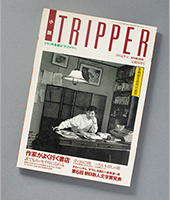 |
| 1999 | 『KADOKAWAミステリ』 | |
| 2003 | 『小説 野性時代』 | |
| 2004 | 『きらら』 | |
| 2008 | 『真夜中』 | 文芸だけでなく写真・絵・デザインも掲載し、「人間の想像力、表現力のすばらしさと自由、現実に抗う力、そして自分と自分をとりまく世界を変えようとする意志」をテーマとした。 |
2013-2025
| 2013 | 『MONKEY』 | 2008年に創刊した『モンキービジネス』を新装。柴田元幸が責任編集を務める。 |
|---|---|---|
| 2014 | 『小説 野性時代』全面リニューアル | 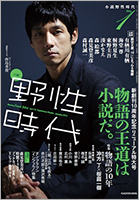 |
| 2019 (令和元) |
『文藝』リニューアル |
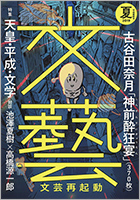 ここから現在まで、文芸誌のリニューアル・復刊・創刊が相次ぐ。文芸誌が再び話題を集めるようになった。
|
| 2020 | 『小説現代』リニューアル復刊 | 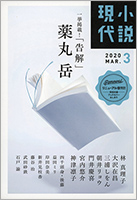 |
| 『群像』リニューアル | ||
| 2021 | 『小説新潮』リニューアル | |
| 2022 | 『スピン/spin』 |  |
| 2024 | 『文學界』リニューアル | 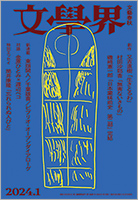 |
| 『GOAT』 | 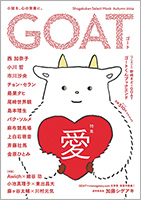 |
|
| 『小説すばる』リニューアル | 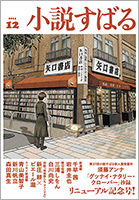 |
|
| 2025 | 『文芸ブルータス』復刊 | |
文芸誌の歴史は明治時代までさかのぼることができる。作家が創刊する同人誌的性格の強いものから、出版社が発行するものまで、様々な文芸誌がつくられてきた。誰もが知る古典の名作も、もとは文芸誌で掲載されていたとわかり、いま手元にある文芸誌の中から、百年後も読み継がれる作品が出てくるかもしれない、とわくわくする。編集する人の思いが込められたタイトルの並びを見ているだけでも、文芸の世界の豊かさを、文芸誌が担ってきた部分は大きいと思える。
作成:齊藤ゆずか
参考にした本やウェブサイト
石崎等ほか編『日本近代文学年表』(鼎書房、 2017年) 小田切進編『日本近代文学年表』(小学館、1993年) 杉本邦子『明治の文芸雑誌 その軌跡を辿る』(明治書院、1999年) 長谷川泉編『近代文学雑誌事典』(至文堂、1966年) 講談社・集英社・小学館・KADOKAWA・文藝春秋・新潮社・河出書房新社・朝日新聞出版・リトルモアの各社サイト(2025年7月30日閲覧) 好書好日(2025年7月30日閲覧)
特集「文芸誌、読む! 知る! 語る」記事一覧


