座・対談
「『人生は一度きり』にしないために小説がある」道尾 秀介さん(小説家)
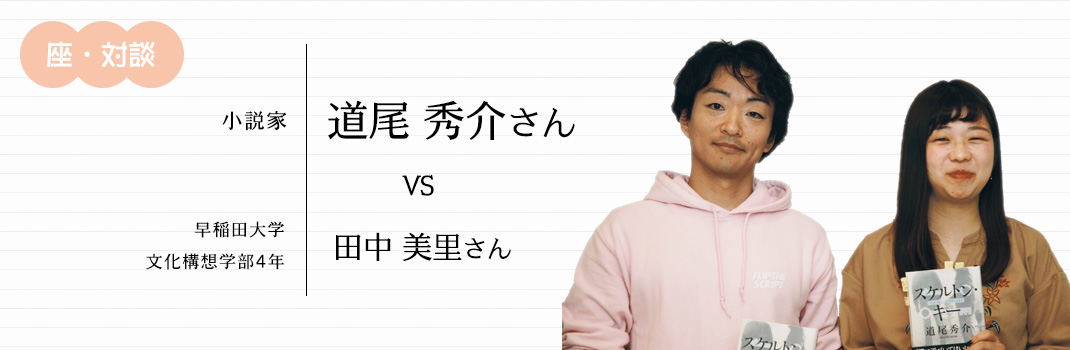
「人生は一度きり」にしないために小説がある
道尾 秀介さん プロフィール 著書紹介 サイン本プレゼント
1.サイコパスを描く
田中7月に発売された『スケルトン・キー』(角川書店)を読ませていただきました。道尾さんらしさがありながらも今までとは少し違った作風だなと感じました。サイコパスが題材の小説ということで、普通の人間には理解が難しいのかなと読む前は思っていたのですが、一人称で書かれていたので主人公と同じ目線で読むことができました。
道尾さんが今回サイコパスを書こうと思ったのには、何かきっかけがあったのですか。
道尾
サイコパスはずっと書きたいテーマだったんです。レクター博士シリーズやロバートブロックの『サイコ』などが、もともと大好きだったので。ただ、世の中にすでにあるものを僕がもう一度作っても意味がない。そこで一人称を考えました。でも普通の一人称にもしたくなかったので、ある工夫をつけ加えました。今まで見たり読んだりしたことのない作品が書きたかったんです。
田中
『スケルトン・キー』は、本の「帯」から始まった小説だと聞きました。帯の内容が決まってから、どのような感じで書いていったのですか。
道尾
「道尾秀介最新作」として書店に並んでいたときに、どんな帯だったら買いたくなるのかなと思って、内容を全く考えていないうちから、帯を先に作ってみてくださいと編集者にお願いしたんです。それで悩みに悩んで作ってくれたんですね。そうして出来上がったものを見たら、「なるほど不穏な雰囲気のものが読みたいんだな」「ほほう人がけっこう死ぬ小説なんだな」等、道尾秀介の最新作としてどんなものが読みたいのかが、すごくわかる帯だったんですね。もちろん物語の内容がそこに書かれているわけではないし、実際に発売するときには別の帯になるわけだけど、読みたがっている方向性がよくわかりました。それでその帯をスプリングボードにして書くとなったときに、「サイコパスを書くのは今じゃないか」と思い、あの主人公が生まれたんです。ちょうどサイコパスの研究が世界中でどんどん盛んになっていて、中野信子さんの『サイコパス』(文春新書)などを読んでいたところでもあったので、色々なタイミングが合ったんですね。
それで実際に書き始めたのですが、サイコパスを一人称で書くというのは、思ったよりも難しかった。
田中
具体的には、どのようなところが難しいと感じられましたか。
道尾
一人称の小説は、もともと違和感と臨場感のバランスがすごく難しいんです。臨場感たっぷりで違和感がないと、読みやすいけれど引っかかるところがなくて、あまり面白くない。ですから一人称の小説を書くときには、いつもそのバランスに気を付けています。でも今回はサイコパスの心理描写なので、違和感の部分がどうしても際立ってきてしまって。それを「読みやすいけど不思議。理解しきれないけど読み進めてしまう」というレベルまで持って行くのが難しかったですね。だから前半は何度も書き直しました。後半はもう、「ここだ」というバランスがはっきりと掴めたので、文体を自由に操れるようになって、筆の進みも急激に速くなってくれました。
田中
サイコパスの人物を書き進めていく中で、道尾さん自身、サイコパスに共感することはできましたか。
道尾
共感とは違うんですが、書き続けているうちに、その人が考えそうなことが少しずつ分かってきます。サイコパスに限らず、女性や老人など、自分が人生で一度も経験したことがない人を主人公にしたときも同じで、少しずつ人格を自分の肌に染み込ませる。とくに今回の主人公については人格に関する科学的事実も重要だったので、大量の関連書籍を読んで理論武装してから執筆に入りました。
田中
『ラットマン』(光文社文庫)や『シャドウ』(創元推理文庫)も精神疾患や脳科学がテーマになっていますよね。今回サイコパスについて調べる中で、特に面白いと思ったことはありますか。
道尾
面白かったのは、「サイコパスは遺伝するのかしないのか」という論争です。科学的には「遺伝する」で結論付けられていますが、それが矯正可能なのかどうかが興味深かった。他にも「心拍数が低い」「発汗しにくい」など、サイコパスが共通して持っている身体的特徴なども、調べるほど面白いですね。
2.比喩表現
田中『スケルトン・キー』は「ボウフラがわく」「カメとカマキリ」「半透明なセロハンテープのような目」など、比喩表現が独特だなという印象を受けました。『スケルトン・キー』に限らず比喩表現が独特なのが道尾さんらしさなのかなと個人的に思っているのですが、比喩表現はどうやって紡いでいるのですか。
 道尾
道尾面白いことに、その主人公でしばらく書き進めていくと、比喩は自然と出てくるんです。前に書いた『スタフ』(文藝春秋)という作品は、初めて女性を主人公にした長編小説だったのですが、そのときすごく感じたのが「今までこんな比喩出てこなかったな」というような表現が自然に出てきたことでした。時間が過ぎていくのを「ネックレスの鎖が指の間からするすると落ちていく」と表現したのですが、男性主人公だったらこの表現は絶対に出て来ない。こうした体験は作家として非常に嬉しかったですね。『スケルトン・キー』はサイコパスが主人公なので、比喩に容赦がないというか、出てくる表現がとても無機的なんです。自分の身体の中に「ボウフラがわく」というのは、普通だったらあまり想像したくないけど、それを容赦なく想像できてしまうところに、恐怖の感情が欠如している感じが出ている。他にも、「半透明なセロハンテープのような目」というのはよく考えると不自然な表現なんですが、本人にはそう見えているからスッと言葉になってしまう。ちょうど先日、伊坂幸太郎さんが、僕の小説の中で『スケルトン・キー』が一番好きで、特に比喩が好きだと言ってくれたんですよ。今回あるシーンで主人公が被害者を見下ろして、死んでいくその人の目が、あるとき「二つの水たまりになった」と表現しているんですが、これもサイコパスならではですね。目の前に自分が殺した人間がいるのに、あまりに冷静なんです。こういうのは普通の殺人者では出てこない比喩です。
ちなみに「カマキリとカメ」という比喩は、実はちょっとしたいたずらなんです。『向日葵の咲かない夏』(新潮文庫)で、主人公が母親と父親のことをカマキリとカメに喩えているんですよ。今思えば『向日葵の咲かない夏』も、サイコパスの一人称だったともいえる。だから実は『向日葵の咲かない夏』と『スケルトン・キー』には大きな共通点があったなと。「カマキリとカメ」のいたずらは、それを思いつく前に入れていたので、共通点に気づいてから自分でも面白いなと思いました。たぶん、どこかでは分かっていたんでしょうね。
田中
道尾さんの作品は、特に『月と蟹』(文春文庫)など比喩表現や描写がすごくリアルで、読んでいると情景が目の前に浮かんできます。他の作品でもそうなんですが、自分が経験したことがないことを読者に想像させるくらいにリアルに書くというのは、登場人物になりきっているからこそできることなんでしょうか。
道尾
なりきるというのも一つの技術だし、読者に「読んでいる」のではなく「見ている」かのように思わせるのも技術の部分です。僕がわりとこだわっているのが、ページを開いたときのビジュアルなんです。どこで改行するかとか、ぱっと開いたときにどのくらい文字が目に入ってくるかとか、余白がどのくらいあるのかとか。ページをめくっている感じをなくすというか。逆に、文字を追う目の動きを、わざと止めさせる場所も要所要所に入れています。あんまりスルスルめくってしまうと細部への集中力が薄れてしまうので、読者をその世界から逃がさないように、視線が止まる箇所をわざと作っています。
田中
そこまで計算されているんですね。内容のネタバレになってしまうので詳しくは言えませんが、今回も仕掛けに気づいたときにはすごいなと感動しました。
道尾
仕掛けって、作中で明らかにされたとき、初めて読者が仕掛けの存在に気づかないといけないんですよ。その調節は難しいです。
田中
すごく作りこまれているのですね。ちなみに『スケルトン・キー』で「カマキリとカメ」という表現や、『ラットマン』の「カマキリの中にハリガネムシが寄生する」など、比喩に虫や動物、植物が登場するのが印象的でした。比喩表現に動物や虫などのモチーフを使うのは何故ですか。
道尾
虫や植物がもともと好きだからというのがあります。それから、カメやカマキリ、向日葵などの虫や植物は、知らない人はいないから、確実に伝えられるというのもあります。子どものころから知っているものを喩えに使われると、ドキッとするので、そういう効果も狙っています。たとえば「バッタみたいにずるい目をした男」と書くと、すごくその顔が頭に浮かびますよね。それを喩えを使わずに「まぶたの角度が云々」「しわが何本あって云々」と書くと、大変だし伝わらない。それを伝えるために比喩があるんです。
3.書くことへのこだわり
田中『スケルトン・キー』もそうですが、道尾さんの小説には、普通の家族ではなくて何かわけのある家族を描いた「家族って何なんだろう」と考えさせられるものが多いと感じます。そこに何か特別な理由や意図のようなものはあるのでしょうか。
道尾
安定しているものを書くのは面白くないんです。不安定なものはぐらぐら揺れているから、たとえば途中まで書いた原稿の続きを翌日書こうとすると、見ていない間に傾きが勝手に変わっていたりする。それを追いかけて書いていくと、文字だけで構成された作品のはずなのに、動いてくれるんです。最初から美しく完成されたものを書くと、デッサンモデルのように、ずっと相手が止まっている。僕は西洋画よりも日本の浮世絵が好きで、西洋画は、印象派は別ですが基本的に写実的で、たとえば「午後3時の木」を描く場合にはそれ以外の何物でもないものを描く。でも浮世絵は基本的に写生をしないから、スケッチをして、後は部屋で想像しながら仕上げていく。そこで作品の中に独特の息遣いが生まれるんです。小説も、動いている人の息遣いが何より重要。そうすると、家族を書くときに不安定なものにしたくなるんです。自分で動かすというより、勝手に動いてしまうのが面白いんですよね。一つの能動体を描くことになるので。それに、物語は基本的に不幸から始まるんです。幸福からはあまり物語って生まれないんですよね。歌の歌詞も、別れとか不幸とかから物語が生まれていることが多いですよね。だから、歪んだ家族を書くというのもあるかもしれないです。
田中
『カササギたちの四季』(光文社文庫)や『透明カメレオン』(角川文庫)の「誰かを守るためにつく嘘」など、「嘘」について考えさせられる作品が多いと個人的には思っているのですが、道尾さんは「嘘」というものをどのようにとらえているのでしょうか。
道尾
「嘘」も、犯罪者がつくような悪い嘘を書くときもあるし、人を守るための嘘を書くときもあります。僕の中では「嘘=物語」というイメージがあります。悪い物語もあれば、人のためになる良い物語もある。誰かのためにつく嘘のような、所謂「ホワイト・ライ」を書いているときには、嘘をついているというよりも物語をプレゼントしているというようなイメージを持っています。とはいえ、誰かを物語に巻き込むというのは、本を一冊プレゼントするようなこととは違うので、嘘をつく当人たちも全力でやらないといけない。するとそこに「物語を必死にプレゼントしようとしている人たちの物語」が生まれてくれる。その入れ子構造は、とても書き甲斐があります。小説を入れ子構造にしたときには、一番内側の大きさをしっかりと維持している限り、全体の物語が大きくなってくれます。だから、最終的にすごく大きなものが出来上がってくれるんです。
田中
『シャドウ』、『ラットマン』、そして『龍神の雨』(新潮文庫)など、道尾さんの作品では登場人物が生涯忘れ得ないほどの仕打ちを受ける場面が出てくることが結構あるように感じたのですが、何か理由のようなものがあったりするのでしょうか。私は初めて読んだ道尾さんの小説が『カササギたちの四季』で、その次に読んだのが『龍神の雨』だったのですが、当時高校生だったこともあって結構衝撃でした。
道尾
僕は「これは書かない」というのは、やりたくないんです。実人生で、人は殺されることもあれば巨大な不幸に見舞われることもある。たとえば昔話だったら「いじわるじいさんがいました」でいいけど、大人向けの小説なので、いかにしてじいさんがいじわるになったのかを書かないといけない。野球小説をプレイヤー無しで書けないのと同じで、人生と地続きのものを書くには表と裏を全部書かなければいけない。そのために「こういうシーンが必要」と思ったら躊躇はしないようにしています。読者が嫌悪感を抱くものを取り入れるのはリスキーなんですが、そこでためらったら、そもそも書く意味がない。ただし、物語を盛り上げる目的でそうした要素を取り入れるといった、安易なことは絶対にしません。これは作家としての矜持です。

田中
作品の中で登場人物の名前などをイニシャルや「□□□」などで表記されていることがありますが、そこにはどのような意図があるのでしょうか。またイニシャルなどの表記を使う基準などはありますか。
道尾
たとえば『向日葵の咲かない夏』には「Sくん」が出てきます。あれをSにしたのは、彼に関しては誰の顔も連想してほしくなかったからです。だからといって知り合いにいないような突飛な名前を付けるのも記号的になってしまって物語の雰囲気にそぐわなかったので、イニシャルにしました。
田中
『貘の檻』(新潮文庫)の村の名前をイニシャルにしたのも、どこにも存在しない村にしたいという意図があったのですか。
道尾
地名の場合はビジュアル的なミステリアス感が好きというのもありますね。
田中
人名と地名ではけっこう違うんですね。『貘の檻』や『水の柩』(講談社文庫)など、農村部が舞台の小説では、実際に調査に行かれて農村部の描写や歴史などを書かれているのでしょうか。読んでいてとてもリアリティを感じました。
道尾
地方を舞台に書くときには、そのものズバリではなくてもモデルになっている場所があることが多いです。『月と蟹』は葉山・鎌倉周辺。実在するお寺なども出てくるので、この場合は特定されていますね。『水の柩』では奥秩父をモデルにして取材しました。いつも1〜2泊してその土地を歩き回って、身体に空気をしみこませてから書いています。奥秩父は、もちろん実際には見えないけど、水の底に村が沈んでいるんですよ。その水を眺めていたら風が吹いて、そこにあった細い螺旋状の階段の柵が不思議な音で鳴り始めたんです。そういうことも、小説に入れ込んだりしています。だからこそ、レッグワークは重要だし、楽しいんですよね。
田中
実際にその場所まで足を運んでイメージを膨らませてから書かれているのですね。
道尾
ただ、見た物をあまり忠実に描写すると紀行文のようになってしまうので、想像の方がそれ以上になるように、いつも気をつけています。このバランスも、小説にはとても大事ですね。
P r o f i l e
.jpg)
1975年生まれ。2004年『背の眼』(幻冬舎)で第5回ホラーサスペンス大賞特別賞を受賞し、デビュー。05年に上梓された『向日葵の咲かない夏』(新潮社)が08年に文庫化され100万部を超えるベストセラーに。07年『シャドウ』(東京創元社)で第7回本格ミステリ大賞、09年『カラスの親指』(講談社)で第62回日本推理作家協会賞、10年『龍神の雨』(新潮社)で第12回大藪春彦賞、『光媒の花』(集英社)で第23回山本周五郎賞を受賞。11年、史上初となる5回連続候補を経て『月と蟹』(文藝春秋)で第144回直木賞を受賞。他に『鬼の跫音』『球体の蛇』『透明カメレオン』(以上、角川文庫)、『スタフ』(文藝春秋)、『サーモン・キャッチャー the Novel』(光文社)、『満月の泥枕』(毎日新聞出版)、『風神の手』(朝日新聞出版)など著作多数。最新刊は『スケルトン・キー』(角川書店)。


