わが大学の先生と語る
「生命と世界の多様性に人間を映す」安達 潤(北海道大学)

生命と世界の多様性に人間を映す インタビュー
▼ Profile
1. “何でも屋"を貫く軸に読書あり
2. 見えている世界は、唯一の真実なのか
3. サポートの秘訣は、発想の転換
4. 正解を探すよりも、自分を観察してみよう
P r o f i l e
.jpg)
1960年生まれ、兵庫県出身。
北海道大学大学院教育学研究院 特殊教育・臨床心理学教室 教授。
1992年北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程 単位取得退学。
1992 年より社会福祉法人旭川荘旭川療育センター児童院 療育主任、2002年より北海道教育大学旭川校臨床発達専攻 特別支援教育分野 准教授、2009年より同大学同専攻同分野 教授を経て、2015年より現職。専門は認知心理学・臨床心理学・特別支援教育。
■著書・論文
主な著書に『発達障害の臨床的理解と支援 第3巻 学齢期の理解と支援』(編著 金子書房)、『発達障害の臨床心理学』(共著 東京大学出版会)、『発達障害支援の現状と未来図』(共著 中央法規出版)、『発達科学ハンドブック 7 災害・危機と人間』(共著 新曜社)、論文に「アイトラッカーを用いた高機能広汎性発達障害者における会話の同調傾向の知覚に関する実験的検討」『児童青年精神医学とその近接領域』53(5),561-576,2012 など。
 徳永 陽子
徳永 陽子
(理学院DC 3) 沼崎 麻子
沼崎 麻子
(理学院DC 3)
1.“何でも屋"を貫く軸に読書あり
徳永自己紹介もかねて、安達先生のご専門についてお聞かせください。
安達
専門はいろいろなんですよ。特殊教育・臨床心理学の看板を掲げつつ、臨床支援(発達障害児者の具体的支援を考える)、認知心理学(発達障害児者の体験世界を実験的に把握する)、実態調査(発達障害の当事者や家族が求める支援を確かめる)、地域支援システムの構築(地域の支援力が上がる仕組みを作る)などをやっています。
沼崎
ご自身の研究の軸となるものを一言で表すなら、どんな言葉が当てはまりますか。
安達
「人間は自然の一部」という捉え方かな。学生時代に何度も読んだ本に、稲垣足穂の『一千一秒物語』というのがあります。“歩いていたら街角で流星にぶつかってポンッと跳ね飛ばされて、気が付いたら家にいた"というようなショートショートが詰まっています。この本全体が醸し出しているのは「宇宙に翻弄される人間」だと感じます。宇宙、すなわちもっともっと広い存在と比べて、人の営みってすごくちっぽけで、人間では制御しえない何かに人間は翻弄されていると。
僕自身もおそらく人間なので、人間ということにやはり関心があるのだけれど、それ以上にもっと他のいろいろな人間以外の視点から見る、ということに関心があったのかなと思うのですよね。
2.見えている世界は、唯一の真実なのか
徳永他にも、学生時代に読まれた本がありましたらお聞かせください。
.jpg) 安達
安達ユクスキュルの『生物から見た世界』という本があります。彼は生物学者なんですが、「環世界」という概念を提唱しています。簡単に言うと、まず主体としての生命体があり、生命体が外界を知覚し、それに対して働きかけ、またそれを知覚するという循環を表しているんです。特に僕が面白いなと思ったのは、どうやって生命を維持しているか、生きているかによって、その生命体に現れてくる世界の様相が違うという話なんです。例えば、コウモリは我々が聞こえない声を発し、その反射音で障害物をよけて動いている。我々人間が感知できないものを感知しているわけです。要するに、我々が見ている世界というのは、唯一無二の「ホントの世界」ではないということですね。
私たちが感受し、見ている世界というのが絶対ではないし、同じ人間同士でも、もしかしたらそれぞれ見ている世界は違うかもしれない。
例えば、自閉症の人ってとても感覚の鋭いところがあって、蛍光灯の点滅が見える人がいるんですね。光がちらちらした状態が続くため、かなり日常生活が大変になります。そのため、彼らは自分にとって落ちつける光というのは何だろうかと探したりしているんです。また、僕が昔かかわっていた子どもさんで、「雨が痛い」ので雨の日に外出できない小学生がいました。雨が体に当たる感覚や雨の音を痛覚として感じとっていたようです。
適応の形態やその世界の切り取り方みたいなものは、人間それぞれや動物、生命体によっても違う。それを教えてくれたのがユクスキュルなんです。
3.サポートの秘訣は、発想の転換
沼崎実際に当事者さんに見えているそれぞれの世界というものに触れるということは、どういうふうに感じますか。
安達
僕が思うのは、自分が見ている世界以外、他の誰かが見ている世界は絶対分からないということです。分からないから多分コミュニケーションするんだと思うんです。
徳永
例えば家族や周囲の人に当事者さんがいる場合、どういうふうに接したら良いのかと悩んだりすると思うのですが。
安達
まずひとつは、障害という言葉の概念を変えることからですね。「発達障害」という言葉は、定型発達と呼ばれる大多数の人たちがつくり上げている社会文化のなかでネガティブインパクトを与えると思われます。そこにカテゴライズされることは、大多数の人が作りあげた文化にうまく乗っていけない存在に位置づけられることだからです。また、「障害」となると自分のネガティブなところに目が向いてしまって、あれもこれもだめだ、できないという考えも出てきてしまうんです。なので、それをどう解除するかが大事だと思います。
機能障害(個体内の障害関連因子)があっても、うまく環境と関わりあえる状態となるような「ニッチ」は必ずあるし、それを見つけるには、自分の得意なことや好きなことが手掛かりになるはずなんですよ。
他に重要なのは、良い悪いといった価値観に左右されるのではなく、「自分が楽でいられる」というという感覚。「こんな状態や環境なら私は安心できる」とか、「こういうふうにしてもらえると私は快適だよ」とか、そういうことだと思うんですね。例えば学校の先生に、「明日持ってくるものはこれこれだよ」と口で言われるよりもメモでもらった方が楽だと感じたら、楽になった分、その人の潜在能力が発揮できるということになると思います。
沼崎
逆に「楽ばかりしていないでもっと頑張るべきだ、努力すべきだ」という意見も出てくると思うのですが。
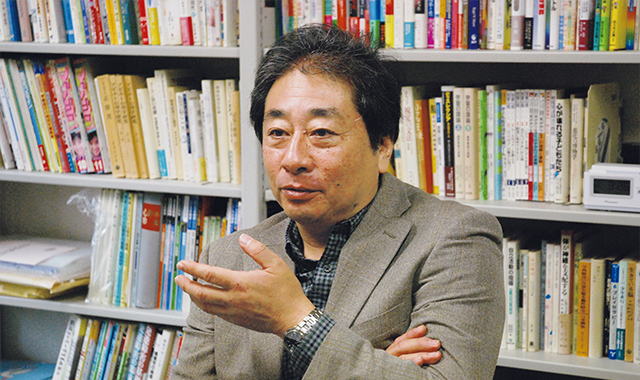 安達
安達そうですね。人間は自らが収まりきらない世界を作ってしまったと思うんです。だから、我慢が当たり前だとなる。でも我慢することでその人の力が削がれるのなら、我慢第一よりも、ちゃんと力を発揮できた方がいいと思うんです。これは認知心理学の話になるのですが、人の情報処理活動に関わる「リソース」(処理資源)という概念があるんです。例えば、人間の持っているリソースを100だとしたら、車の免許を取りたての頃はほぼ80くらいのリソースを運転に使うんです。その時期に車内で友達がしゃべりかけてくると、会話に30のリソースを求められるので安全な運転に必要なリソースを充当できず、「ちょっと黙って!」となる。でも慣れてくると必要なリソース量が少なくなるので、運転しながら話もできますよね。
だから人に応じた合理的な配慮の提供というのが必要なんです。これは障害者権利条約の中で提唱されている概念で、障害者差別解消法でも義務化されています。つまり、その人が快適な、過ごしやすい環境を提供することが大切で、それが配慮なんです。困難性を示している人たちが生きやすくなる世界を作っていくために重要な考え方であり方法ですね。
4.正解を探すよりも、自分を観察してみよう
沼崎読者の方の中にも、自分にも発達障害があるかもしれないと思っている方がいらっしゃるかと思います。そう思った場合、次に何をすればよいのでしょうか。
安達
今は発達障害の情報が広がっているから、自分もそうかもしれないと思ったらいろいろ調べることができますね。それはそれでOKだと思う。でもそこには「正解を求めてしまう」という問題もあります。当事者さんにも周囲の人にも言えることですが、人それぞれが持つ特徴を、発達障害だと決めてしまうということがあります。答えが見つからない状態というのはリソースを使うんですよ。だから自然な傾向として、シンプルな解を求めてリソースを使わないようにする。これが正解なら全部解決、と決めつける発想にスーッと引かれてしまうんです。「この壺を買うとあなたは幸せになれますよ」と同じことですね。
徳永
きっと楽なんだと思います。
安達
そうそう、楽なの。それはリソースを消費しなくて済むということだから。可能ならいったん思考停止してリフレッシュして、もう一度状況把握をすることが大事です。「自分がどういう状況なら楽なのか」「どういう自分なら安心できるのだろう」「どんなふうに関わってもらえるといいのかな」に目を向けてもらえればと思います。同じような困り方をしている人が少数派だったり、一般的には、視点を切り替えることは難しかったりするから、簡単ではないかもしれませんが。
沼崎
既に発達障害の診断を受けている方にお伝えしたいことはありますか。
安達
今の話と共通しますが、まずは「自分自身を観察する」ということが大切だと思います。「こんな状況だと楽だな」とか、自分を活かせる場面や条件とか、「自分はこういう時に不調になってしまう」というのが分かっていると、ちょっと困難を回避できる場面もあるかもしれない。「自分のこれとこれが発達障害の特徴と重なっている」と考えることがあっても、それはそれでいいと思います。でも、ちょっと抽象的な言い方をすると、それよりも「自分はどんなふうに世界と関わったり、世界を見ているのかな」「どんな世界なら過ごしやすいのかな」ということを考えてみるといいのではないかなと思います。
それは合理的配慮の発見にもつながりますから。一応、法律上では、当事者がちゃんと自分で言わなければ合理的配慮を提供してもらえないんです。だから、「こんな場面だと自分はこんなことができる」ということを把握しておくことがとても大切なんですね。
徳永
最後に、読者の方へのメッセージをお願いいたします。
安達
読書においては、知識を得ようとするのではなく、雑読をしてその背景にある“世界の捉え方"を感じてもらえればと思います。例えば、ユクスキュルはこう考えていた、という知識を覚えてもしょうがない。それよりも、“生命体は環境の一部かつ主体としてそこに存在している、しかもそれぞれ見ている世界はまったく違う。その相対的視点をグッと広げて、我々人間も自然環境の一部に過ぎない"といった感じ方を得ることが大切だと思います。それは別に科学書だけでなく、文学作品でも同じかなと思いますね。
徳永・沼崎
ありがとうございました。
(収録日:2018年10月10日)
対談を終えて
「良いとか悪いとかという価値観ではなく、『自分が楽でいられる』という感覚は、その人の潜在能力が発揮できる状態」という安達先生の言葉がとても印象的でした。ともすれば私達は、楽な状態を否定的に捉え、自分で自分を追い込んでしまうことがあります。しかし、それを「潜在能力が発揮できる状態」と考えるだけで生きていくことが少し楽になるんだ、と感銘を受けました。多くの人に知ってもらいたい言葉です。
(徳永陽子)
ネットや日常にはびこる、発達障害への偏見や誤解。心無い言葉たちに先生ならどう向き合うのか、という思いを抱きながらお話を伺いました。自分も周りも楽だと思えるあり方、自分ができることに目を向けること。世界は絶対的なものではなく、お互いの世界を知ろうとすることで、心は近づくことができる。対談後の胸に光が差す感覚は忘れられません。今回の対談が、発達障害や世界のみかたが変わるきっかけとなれば嬉しいです。
(沼崎麻子)
コラム
▼用語解説▼一人で抱えるより、コミュニケーションを
▼支える人も楽をしていい
用語解説
○発達障害先天的な脳機能の偏りに起因する行動・心理・感覚の特性によって社会や環境への不適応が生じ、日常生活が困難となる状態。ASD(自閉スペクトラム症)は社会的コミュニケーションの困難と興味の限局・反復行動・感覚問題、ADHD(注意欠如多動症)は不注意や多動性・衝動性、LD(限局性学習症)は読み書きや計算などの困難を特徴とします。
○当事者
本稿では、発達障害の診断を受けた人、発達障害を持つ可能性が高い人のことを指します。
○障害者権利条約
障害者の人権や基本的自由を保障し、障害を理由とする差別禁止や合理的配慮の提供を求めています。本稿では「障害(disability)は機能障害(impairment)と社会的障壁の相互作用の結果である」という条約の定義を踏まえ、「障害」と表記します。
○障害者差別解消法
行政や民間事業者による、障害を理由とする差別を禁止する法律です。障害者から配慮要請があった場合に、負担になりすぎない範囲で支援や配慮を行うか、難しい場合はそれに近い配慮を行う「合理的配慮」を提供する義務も定めています。
一人で抱えるより、コミュニケーションを
沼崎ドラマや映画では、発達障害者を「天才的な能力を持った人」と描くことが多いですね。そのため、「発達障害者=天才」という一般的なイメージに苦しんでいる当事者も多くいらっしゃいます。
安達
良かれと思って「天才」のイメージで描いているのかもしれないけど、無責任だなとも感じます。
沼崎
「自分には得意なことが何もないのに」と感じる、という当事者さんの話も聞いたことがあります。
安達
発達障害の人たちに限らず、人間、誰しも落ち込んだときはそう考えてしまうんじゃないかな。そういう時は、ひとりで考えこまずに、他の見方をとってみるのが大事かなと思いますね。あと、ネットの情報に頼りすぎず、やはりリアルな情報に接するのが大切かな。人によるけれど、例えば当事者会に参加すれば、メンバーとわりと波長が合ったり、テーマや話の展開にのりやすかったりして、リアルな情報を得ることもできます。当事者であるかどうかを問わず、お互いもっとコミュニケーションしあうことが大切かな。
支える人も楽をしていい
安達僕の仕事歴は重症心身障害児施設の職員から始まっているのですが、当時、重篤な障害像を示している息子さんと一緒に暮らしているお母さまがおられて、ずっとその生活が続くと時々休息が必要になるんですね。そういった時は、レスパイトケアというかたちで、当事者さんに一時的に施設を使っていただき、その間、ご家族の方には息抜きをしてもらうんです。そういったサポートを使いながら、それぞれの生活を組み立てていくことが当たり前である、という価値観が求められると思いますね。
沼崎
支える人も楽をしていいという。
安達
そうそう、楽をしていいというか、そうだと思う。その人が持っている力を発揮していくために、少し自由に選択できるとみんないいなと思う。そういう意味では、障害と関わる人にとっても、仕事だけではなく余暇が大事になってくるなとは思いますね。
▲ Profile
1. “何でも屋"を貫く軸に読書あり
2. 見えている世界は、唯一の真実なのか
3. サポートの秘訣は、発想の転換
4. 正解を探すよりも、自分を観察してみよう


