いずみ委員・スタッフの 読書日記 157号
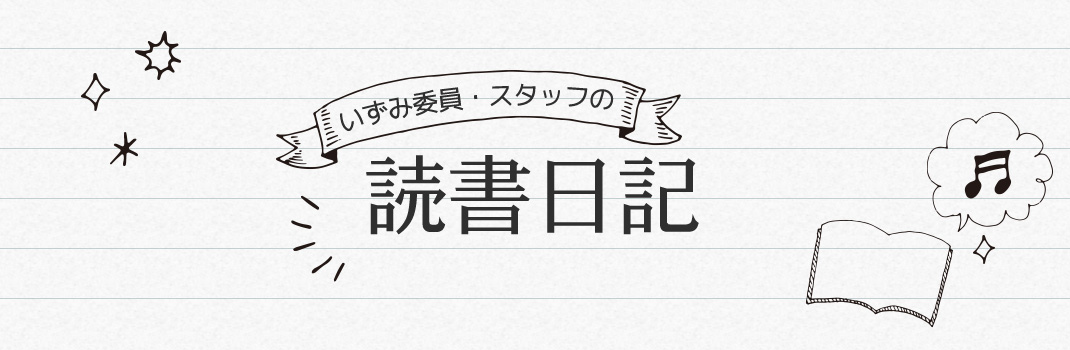
レギュラー企画『読書のいずみ』委員・スタッフの読書エッセイ。本と過ごす日々を綴ります。
山形大学3年 片山凜夏
5月下旬
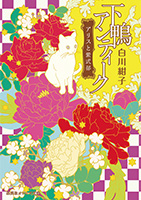 何か読みたくて本棚を眺めた。手に取ったのは『下鴨アンティーク アリスと紫式部』(白川紺子/集英社オレンジ文庫)だ。表紙に惹かれて購入したまま積読になっていたもの。毎回、私の心に刺さる表紙で刊行されているのは本屋さんで見て知っていた。ついに私が1巻を読まないうちに、そのシリーズは完結したらしい。
何か読みたくて本棚を眺めた。手に取ったのは『下鴨アンティーク アリスと紫式部』(白川紺子/集英社オレンジ文庫)だ。表紙に惹かれて購入したまま積読になっていたもの。毎回、私の心に刺さる表紙で刊行されているのは本屋さんで見て知っていた。ついに私が1巻を読まないうちに、そのシリーズは完結したらしい。祖母の遺した着物の柄や、その着物にまつわる想いの謎を解いていく連続短編集だ。着物の模様や種類の名称が難しい。でもどんどん読み進めてしまう。慧ちゃんが素敵だなとも思う。慧ちゃんと鹿乃の関係がどうなっていくのかも気になるし、可愛い表紙の本たちを並べたくて、きっと2巻も買ってしまうだろう。
6月中旬
 「最果タヒ」という名前も作品のタイトルもすごくいいなと思う。友達が薦めてくれたので読んでみることにしたのは、『死んでしまう系のぼくらに』(最果タヒ/リトル・モア)だ。表紙も目次もすごい。詩集だから空いている時間にちょっとずつ読むつもりが、どんどん読んでしまう。お気に入りは「恋文」だ。「一生大切にする」と言われたときの「一生」は私の一生であってほしい。そうじゃないと私もきっと永遠にゆるさない。もんもんとそんなことを考えてしまった。以前読んだ『グッドモーニング』(最果タヒ/新潮文庫nex)よりも読みやすく、誰かに薦めたくて仕方がない。
「最果タヒ」という名前も作品のタイトルもすごくいいなと思う。友達が薦めてくれたので読んでみることにしたのは、『死んでしまう系のぼくらに』(最果タヒ/リトル・モア)だ。表紙も目次もすごい。詩集だから空いている時間にちょっとずつ読むつもりが、どんどん読んでしまう。お気に入りは「恋文」だ。「一生大切にする」と言われたときの「一生」は私の一生であってほしい。そうじゃないと私もきっと永遠にゆるさない。もんもんとそんなことを考えてしまった。以前読んだ『グッドモーニング』(最果タヒ/新潮文庫nex)よりも読みやすく、誰かに薦めたくて仕方がない。
10月下旬
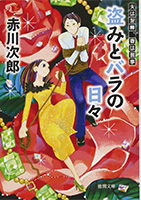 どうしても小説が読みたい。論文を読まないと、と思いつつ、やはり小説が読みたかった。あのシリーズがいい。まだ読んでないのがあったはず。『夫は泥棒、妻は刑事⑭ 盗みとバラの日々』(赤川次郎/徳間文庫)を読み始める。何巻からでも読めるこのシリーズはこれで6冊目。少し抜けたところのある明るい刑事の真弓と、泥棒である淳一の掛け合いがとても好きだ。いつも冷静で機転の利く淳一は、やっぱりかっこよくて、無意識にルパンを思い起こさせる。
どうしても小説が読みたい。論文を読まないと、と思いつつ、やはり小説が読みたかった。あのシリーズがいい。まだ読んでないのがあったはず。『夫は泥棒、妻は刑事⑭ 盗みとバラの日々』(赤川次郎/徳間文庫)を読み始める。何巻からでも読めるこのシリーズはこれで6冊目。少し抜けたところのある明るい刑事の真弓と、泥棒である淳一の掛け合いがとても好きだ。いつも冷静で機転の利く淳一は、やっぱりかっこよくて、無意識にルパンを思い起こさせる。会話が多くて読みやすいと思うのだけれど、あの人は小説を読まないから薦めても読んではくれないだろう、と考えながら『夫は泥棒、妻は刑事⑱ 泥棒たちの黙示録』(赤川次郎/徳間文庫)も表紙を開いてしまった。
愛媛大学2回 河本捷太
9月X日
 本屋にふらっと寄った時に見つけた一冊の本。平積みされていたのでどうやら話題の本らしい。名前は『友だち幻想 人と人の〈つながり〉を考える』(菅野仁/ちくまプリマー新書)。タイトルにある「幻想」の文字が妙に気になって購入した。
本屋にふらっと寄った時に見つけた一冊の本。平積みされていたのでどうやら話題の本らしい。名前は『友だち幻想 人と人の〈つながり〉を考える』(菅野仁/ちくまプリマー新書)。タイトルにある「幻想」の文字が妙に気になって購入した。この本を簡単に説明するとしたら、人間関係の悩みを解決してくれる本。タイトルにある「幻想」とは自分を100パーセント受け入れてくれる友達は幻想であり、だからこそ他者に過剰な期待をするのはやめて、他者は他者であることを意識した上での信頼関係を作らなければならないということだ。なるほど、たしかにそうだ。そう思うことで人間関係ずいぶん楽になる気がする。他にも納得するようなことばかりだし、サクサク読めるから是非いろんな人にこの本を読んでほしい。さっそく明日この本を友達に勧めてみよう。
10月Y日
最近はまっている番組がある。NHK Eテレで放送されている「100分de名著」だ。一冊の本あるいは一人の作家を100分で解説する番組だ。先日、テキストのバックナンバーを買ってみた。『100分de名著 メアリー・シェリー フランケンシュタイン』(NHK出版)だ。「フランケンシュタイン」に登場する怪物は、実はただの殺人鬼ではなく非常に人間的だった。怪物は博士に見放され孤独となり、愛を求めた。なぜ殺人を犯すのか、本当の怪物は誰なのか。そんなことが解説されていた。
文学の面白さはそれが書かれた歴史的背景や作家の思想などが物語に深みを出しているところだ。しかし、時に難解なことがあるが、この「100分de名著」のテキストは理解を容易にしてくれる。そういえば、録画しているのがあったんだった。これから観ることにしよう。
11月Z日
 今日は履修している倫理学の授業の参考文献に指定されていた、『死刑 その哲学的考察』(萱野稔人/ちくま新書)を読み終えた。今度、授業でプレゼンをしなければならないのだ。そのテーマは「死刑制度の賛否」。死刑制度のことなんて真剣に考えたこともなかったから、これをいい機会に本気で考えてみよう。とはいうものの、難しくて一筋縄ではいかない。
今日は履修している倫理学の授業の参考文献に指定されていた、『死刑 その哲学的考察』(萱野稔人/ちくま新書)を読み終えた。今度、授業でプレゼンをしなければならないのだ。そのテーマは「死刑制度の賛否」。死刑制度のことなんて真剣に考えたこともなかったから、これをいい機会に本気で考えてみよう。とはいうものの、難しくて一筋縄ではいかない。この本は死刑について制度、道徳、政治哲学の見地から考察している。死刑廃止国が多い国際的潮流の中、ただ賛成・反対ではなく、なぜ賛成・反対なのかをはっきりさせることはかなり大事なことだと思う。この本にはその根拠となる事例や考え方が数多くあり、考える手助けとなった。
やっと読み終わったところだが、プレゼン用のパワーポイントを作らないといけない。もうひと踏ん張りするか。

.jpg) 山形大学3年
山形大学3年.jpg) 愛媛大学2回
愛媛大学2回.jpg) 東北学院大学4年
東北学院大学4年.jpg) 広島大学M1
広島大学M1
