座・対談「自分の中の”面白い”を出力する」小説家 河野 裕 P2
河野 裕さん プロフィール 著書紹介サイン本プレゼント
4.幸福な出会い

私は文学作品をあまり読まないので、文学の入り口とライトノベルの入り口というのは結構遠いところにあるような気がするのですが、河野さんは両方読まれますよね。
河野
読む本ってなんとなく選んでいるんですよね。もともと小学生のころは漫画が好きだったんですよ。でも小学校高学年のころ、小説と漫画を一冊の価格で比較したとき、同じ値段で小説のほうが長く楽しめるなと思って、小説を読み始めました。純文学は無料で読む機会が多かったので手に取りやすかった、ということもあるかもしれません。まあ、好奇心があればいろいろな本に手を伸ばすと思うのですが、たまたま、ライトノベルでも純文学でも好きな作家がいたので、わりと自然に両方を読んでいましたね。
杉田
私は読書の入り口は児童書でしたが、図書館のティーンズ向けコーナーに足を延ばしたら、そこにライトノベルが共存していたり、学校で友達に薦められたりということもあって、自然にライトノベルにハマっていきました。
河野
私もライトノベルを読み始めたのは、友達の影響ですね。結局、入り口で好きな作家に出会えたらそこにのめりこんでいくものだと思います。いろいろな出会いがありますが、純文学にもライトノベルにも私は幸福な出会い方をしたのでしょう。
杉田
幸福な出会いというのは、私の場合は小説というジャンルに対して普段感じていることです。最初に小説が好きだということを児童書で感じて以来それがずっと続いているし、これまで何度も小説が面白いということを再発見する機会があって、漫画も読むしアニメも見るけど、やっぱり小説が好きだなと思います。
河野
そういうことなんですよね。私の小説の入り口にはミヒャエル・エンデの『モモ』があるんですよ。『モモ』がたまたま純文学とライトノベルの両方の性格を持っていると思います。なので、『モモ』、それから『二分間の冒険』、この二冊で私が好きな小説のベースが出来上がっています。ともにわりと幅の広い作品だったので、ライトノベルにも純文学にも違和感なく行けたのだと思いますね。
杉田
私は大学にはいってから『モモ』を読んだのですが、児童書だと思って読んだらそうではないのですね。
河野
『モモ』は年代で読み方が変わります。小難しく読もうとしたらそう読めてしまう話ですが、小学生で読んだら純粋ないい児童書ですよ。ああいう小説はいいですよね。大人が真面目に語っている感じがね。子どもに合わせていないですよね。表現はもちろん子どもに合わせているんですけど、やっていること自体がね。経済学を比喩として児童書に置き換えているのか、児童書に付随するものとして経済学があるのか、ということが何歳で読んでもわからないんですよね。どちらがミヒャエル・エンデの本領なのかはわかりませんが、そこが一番ミヒャエル・エンデの誠実さを感じます。これがエンデの素の価値観なんだなと。
5.理想の型
杉田河野さんの作品には、結構、音楽とか映画のタイトルが出てきますね。
河野
ちょくちょく出てきますね。それから食べ物の名前もよく出てきますね。
杉田
とても美味しそうに出てきます。しばらくシュークリームが食べたくなったり。

河野
そうですか。シュークリームもよく出ますね。私はわりと商品名を平然と出してしまうんです。やはりイメージが強いので。スニッカーズのイメージを「スニッカーズ」以外の言葉では語れませんよね。言葉で伝えようとしたらたぶん五行くらいは書かなくてはいけないので、それなら数文字で済む「スニッカーズ」でいいじゃないか、と思うんです。ですので、止められない限り商品名は気にせずに出していますね。
わたしのなかでは、「夕日」と書くことと「スニッカーズ」と書くことってほとんど一緒なんですよ。「夕日」という言葉が持つイメージって結構複雑じゃないですか。綺麗な面もあれば哀しみを感じさせる面もある。同じように「スニッカーズ」とか「コアラのマーチ」とか「クリームソーダ」とか、単語自体がいろいろな要素を持っていて、イメージと合えばそのまま使います。作品タイトルもそれに近いものがあります。
最近の本ではスピッツの曲名を出していますが、そこでは主人公が話したいことがちょうどスピッツとマッチしていたんですよね。だからスピッツしかないな、と。そんな感じです。
杉田
河野さんの文章を読んでいると綺麗だなと感じるところがあるんですけど、具体的に理想に適う一行とか、綺麗な文章を書く指針はありますか。
河野
いくつかありますね。『ベイビー、グッドモーニング』の短編でも書いていますが、『草枕』の冒頭はとにかく綺麗です。あれは純粋に理想に近いですね。
それから、秋山瑞人さんの『猫の地球儀』というライトノベル作品。このなかに「海だ。」という一行があるんですよ。この二文字と句点に、ストーリーが全部圧縮されているんですね。惑星にいる猫が宇宙船をつくって地球に戻ろうとする話なんですけど、最後に「海だ。」という一行があって、この物語がこの最後の一行のためにあると言っていいくらい綺麗にその二文字が決まっている。それは二文字だけどただの二文字じゃない。それまでの十万文字ありきの二文字なんです。それが私の理想に近い型です。
これは、その小説における「海」という単語の意味をずっと煮詰めたら「海だ。」だけで名文になるという例示で、小説をずっと書いていくと同じ単語の意味をどんどん肉付けして厚くすることができる理想の書き方ですね。
杉田
〈北野坂〉でも雨坂さんの小説について似た文章がありましたよね。
河野
そう。そこは私のなかの大きなテーマなので。
杉田
先ほどの「夕日」と「キットカット」の話がつながった気がします。
河野
夕日とキットカットは世間のもつイメージの利用方法なんですよ。いまの「海だ。」は作者が自ら作品のなかで単語を作り上げていくので、微妙に違うところがあるんですね。
杉田
でも、上乗せされているのかなと思います。たとえば、〈サクラダ〉に出てきたパンケーキとかビー玉はもともとイメージがあると思うんですけど、読んだあとでまた新しい意味がこれに加えられて食べたくなるし、道端で見かけたら拾ってしまいそうになるので……。
河野
そうです。そういうことをしたいんですよ。
杉田
『猫の地球儀』もまた読んでみたいです。
河野
イラストは〈サクラダ〉とおなじ椎名優さんです。あれはすばらしい小説ですよ。
6.ジャンルにこだわらない
杉田どの作品にも超常現象、超能力とか幽霊という要素は共通してありますが、そういう要素が共通しているのは、河野さんにとって読者に届けたいものがその辺りと関係しているのかなと思ったのですが、いかがですか。
河野
まぁ、そうですね。私の作品で扱っているテーマは、完全に超常現象的な要素を抜いて書くと凄く生々しくなるんですよね。そうすると限定的な物語にしかならず、現実のなかで超特殊な環境に育った思考の話になるんです。超常現象は何もかもが比喩の一種みたいなもので、現実に超常現象を絡めることによって、現実を比喩に置き換えているつもりなんです。比喩を用いることで、現実から離した分それぞれの読者が自分に寄せやすくなるんですね。そういうことができるので、超常現象って便利だなと思います。真面目にシリアスな人間関係の話を書くと、やはりどこまでいっても他人事の話になると思っているんですよ。たとえば過酷な環境のなかで育った人の話の場合は、「哀しい」という感情が先に立つと思うんですよね。それを能力で再現することによって、もう少し引いた目から、この人は善なのか悪なのか、ある程度倫理的な観点から話ができるのかなと思うので、超常現象をたくさん入れるようにしていますね。
杉田
そういう狙いがあったのですね。もうひとつお聞きしたいのですが、他紙のインタビューで、ご自身の作品について「ジャンルを意識して書いているわけではない」と話されていますが、それでも読んでいるとミステリー仕立てのような側面が感じられるのですが。
河野
面白いプロットってどう作ってもミステリーに近くなるんですよね。プロットを無視した面白い小説もあるんですけども、ストーリー・ラインで見せようとしたら丁寧に伏線を張って、ポイントポイントで驚きを作って、とやっていくとどんなジャンルであってもミステリーっぽいプロットの仕上がりになるのかもしれません。ミステリーにしようと思っているわけでもないんですけどね。
杉田
「かつくら」のインタビューで「いつか真剣にミステリージャンルに取り組んでみたい」と書いてあったのですが、〈北野坂〉はミステリーじゃないのですか。
河野
〈北野坂〉はあまりミステリーのつもりはないですね。私のなかではその小説が持っている柱の部分が何なのかということなので。佐々波と雨坂の関係性や編集者と作家のプロ意識というところが柱で、ミステリーの要素はその肉付けでしかない。私のなかでジャンルは何かと尋ねられたら、「人間関係ものです」というのが正しい答えなので、〈北野坂〉はミステリーではないんですね。
逆に『最良の嘘』は柱がミステリーです。プロットの骨格を楽しんでもらいたいというのが作品のテーマなので、人間関係はその肉付けでしかない。『最良の嘘』だけが私のなかで唯一ミステリーとして書いた小説です。ということで、結局作者レベルでのジャンルの意識って、どこを中心に作者が考えているかだと思います。
杉田
探偵の出てこない推理小説は結構存在しますが、河野さんの作品のように探偵が出てくるのに推理小説ではない話は、凄く面白いなと思います。
河野
〈北野坂〉でいうと、別に探偵行為をしているわけではないのでね。探偵役は雨坂ですが、かといって佐々波が探偵のつもりもないです。探偵という言葉は好きなので、ミステリーとして読んでいただいてもいいんですけど。
杉田
私も読んでいて、やはり探偵は雨坂だなと思いました。
河野
佐々波は走っている役ですよね。本格探偵もの・名探偵ものと私立探偵もの・ハードボイルドものって明確にプロットが違うと思うんです。佐々波はどちらかというと私立探偵というかハードボイルド系なので、走り回って情報を獲得してゴールにたどり着くランナー的な人ですよね。名探偵は頭の中で物事を解決すると思うので。私はハードボイルド系ってミステリーではない気がするんですね。ミステリーをどう定義するかが難しいのですが。
最初に、「面白い」という感覚を細分化することに意味があるのかという話をしました。ジャンルを無視して書きたいというのはその辺にもつながる話で、結局私が面白いと思うものは素直に出力できていたらそれで良いと思う。そのようなわけで、私のなかでは探偵が出てきてもミステリーじゃない小説はありうるんです。
杉田
最後に、大学生へメッセージをいただけないでしょうか。
河野
小説って面白いですよ。学生時代に読んだ小説は、特に心に残りやすいと思うんです。大学生の皆さんはもうすぐ社会人になりますよね。社会人になると本との付き合い方がまた変わって、本の読み方さえ効率を求めるようになるので、目的と手段が逆転しているんじゃないかなと思うことがあるんですね。大学時代は本当にいい本を楽しめる環境にいるので、今を大事に読書に励んでもらえたらと思います。
杉田
今日はいろいろなお話を聞かせていただき、ありがとうございました。
(収録日:2017年6月28日)
サイン本プレゼント
 河野 裕さんのお話はいかがでしたか?
河野 裕さんのお話はいかがでしたか?河野さんの著書『少年と少女と正しさを巡る物語 サクラダリセット7』(角川文庫)と『最良の嘘の最後のひと言』(創元推理文庫)のサイン本をセットで5名の方にプレゼントします。下記のアンケートフォームから感想と必要事項をご記入の上、ご応募ください。
プレゼントは2017年10月31日までに応募していただいた方が応募対象者となります。
当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
対談を終えて
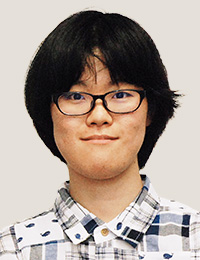 ずっとずっと大好きで、お話ししてみたいと思っていたので、対談が叶って嬉しかったです。執筆方法についてのお話が特に印象深く、「その一行がどうして重要だと感じるのかを掘り下げて続きを構築する」というのは、河野さんの作品から受ける「まるごと差しだされている」という印象と重なりました。対談後、理想として挙げていただいた『猫の地球儀』を再読。河野さんの作品から感じることの多くを、このお話からも感じました。切なくて、温かい。
ずっとずっと大好きで、お話ししてみたいと思っていたので、対談が叶って嬉しかったです。執筆方法についてのお話が特に印象深く、「その一行がどうして重要だと感じるのかを掘り下げて続きを構築する」というのは、河野さんの作品から受ける「まるごと差しだされている」という印象と重なりました。対談後、理想として挙げていただいた『猫の地球儀』を再読。河野さんの作品から感じることの多くを、このお話からも感じました。切なくて、温かい。杉田 佳凜
P r o f i l e

1984年徳島県出身。グループSNE所属。
2009年に『サクラダリセット CAT, GHOST and REVOLUTION SUNDAY』(角川スニーカー文庫)でデビュー。『いなくなれ、群青』で、2015年大学読書人大賞を受賞。その他の著書に、『ベイビー、グッドモーニング』、<つれづれ、北野坂探偵舎>シリーズ(以上、角川文庫)、『いなくなれ、群青』を含む、<階段島>シリーズ(新潮文庫nex)、『最良の嘘の最後のひと言』(創元推理文庫)など多数。
コラム
▼至福のひととき▼メディアミックス
▼ゆくゆくは
▼世界でたったひとつの物語
至福のひととき
杉田152号の特集のテーマが「時間」なのですが、河野さんにとっての至福の時間はどんなときですか。
河野
間違いなく、執筆が順調に進んでいるときですね。それ以外にはないです。書けないストレスを書くことで解消するということの繰り返しですからね。
杉田
ほかの趣味で気分転換をすることはないのですか
河野
気分転換にならないですね。書けない時にほかのことをしていること自体ストレスなので。
杉田
はぁ。
河野
書けるまで苦しみながら、だらけていることしかできないですね。そうしながら、たまに凄く書ける日があるんですよ。無意識にタイピングをしているくらい調子のいいときがあるので、そのときが一番気持ちいいですね。そのほかの至福の時間は、美味しいものを食べるとき。それから、漠然とほしいものがあるとき、腕時計とか。それをひと月くらい、寝る前30分程度検索して、好みに合うものを探すのも至福の時間です。ひとつのものを長い時間をかけて探すのは好きですね。
杉田
そうすると、作品を書き上げたらひと息つかずに次の作品に取り掛かってしまうのですか。
河野
いえ、だらだらしますよ。疲れるので。だらだらと楽しくない毎日を過ごしますね。そして書き始めたら楽しくない毎日があり、たまに書ける日だけ楽しい。
杉田
書けないこと自体を楽しんでいたりするのですか。
河野
締め切りがないと、楽しいと思います。あと、生活費が保証されていれば楽しいと思います。考えている時間は楽しいんですよ。順調に書けるだけじゃなくて、ずっとひっかかっていたところの答えが出た時は楽しいですしね。それは3日に1回くらい、わりと頻繁にありますよ。
メディアミックス
杉田〈サクラダ〉は小説として書かれて、その後、アニメ、実写映画と二種類の漫画になりました。別の媒体になると聞いたとき、どう思われましたか。
河野
正直、メディアミックスの話は出ては消え、ということを繰り返していたので、入り口では「またそういう話があがっているんだな」という感じでした。だから、それほど心が動くこともなく、形になったところで「今回は公開まで行ったな」というくらいで、そんなに深い感慨というものはないですね。ただ、多くのスタッフさんたちがこの作品にかかわってくださるのでとても光栄ですし、なんて幸せな環境にいるんだろうと思います。
杉田
表現の部分で、メディアミックスによって小説よりも補われる面、また逆に弱くなるのではないかという不安を感じた面はありましたか。
河野
もちろん媒体によって全然物がちがうので、変わるのは当然だと思いますし、やるなら原作を気にせずにもう徹底的に変えてもらっていいんですよ。いろいろと葛藤はありますが、私の作品なのでいいものにしたいという思いがあるのと同時に、メディアミックスでは私はメインスタッフではないので、メインスタッフにとって納得のいく作品になればいいのではないでしょうか。
ゆくゆくは
杉田河野さんは大学卒業後、最初から小説を書くお仕事をされていますが、そもそもそれを仕事にしようと思ったのはなぜですか。
河野
ほかのことはしたくなかったからでしょうね。凄くお金があれば商業出版にもこだわらなかったと思います。書くだけ書いて、本は出しても出さなくてもいい。でも、感想はほしいな。本当に納得がいく小説が書けたときは、読者の反応にはあまり興味がないんですよね。これは自分とってはいい話だなというものが書ければ、あとは世界中にどれだけ私と気の合う人がいるのか、というだけの問題なので。凄く苦しんで頑張って書いたら、多少の反応は気になるのかな。『ベイビー、グッドモーニング』、とくに二本目の「ジョニー・トーカーの『僕が死ぬ本』」は本当に評価はなくてもいいです。100%私の趣味で書いているので。
将来的にはそんなにたくさん本を書かなくてもいい作家になりたいですね。年に一冊を出していれば生活できる作家になって、その一冊を作りこむのが夢の生活ですね。
世界でたったひとつの物語
杉田<サクラダ>の角川文庫版が出た時に、全巻購入者が応募できる懸賞の賞品が凄くうらやましいなと思ったのですが、これは河野さんのアイディアですか。
河野
これは私です。なにかプレゼントをつけよう、ということでね。まず「<サクラダ> の続きを書くことはあり得ますか」と尋ねられまして、続きを書くことはできるのですが、7巻で終わっている話なので先は公開する気持ちはないので、そのようにお答えしました。ただシリーズから切り離してたった一人にプレゼントする企画であれば、続きを書くこと自体は楽しめると思ったので、それはやろうと。ちなみに、いま4割くらい書いて止まっています(苦笑)。
杉田
読者からのリクエストで物語を書くのではなく、<サクラダ>の続きをその人だけに読ませるというコンセプトなんですね。
河野
そうですね。7巻のその後のエピソードの書き下ろしです。7巻を書いた時点で、そこに続くプロットがある程度浮かんでいたんですよ。本として書く気はないのですが、無意識に続きを考えてしまうので。なので、それを小説にして、お渡しします。
杉田
少しだけプロットを明かすことはできますか。
河野
7巻の続きと〈サクラダ〉の裏設定まで見せた短編という構想が私のなかにあります。なぜ咲良田に能力があるのか、とか、その辺のエピソードに入っていくプロローグ。その続きはありませんが……。
杉田
すごく気になります。
河野
当選者に連絡をして読ませてもらうしかないでしょうかね。ただ、読んでもそんなにすっきりしないですよ。今後こんな話が始まるんだ、みたいな、導入で終わるので。読めないもやもや感が好きなんですよ、私。あるとわかっているものが手に入らない、ということにすごく憧れるので、それをやりたくてこの企画にしました。
杉田
じゃ、当たらなかった人にとっても?
河野
もやもやしてもらえたら楽しいんじゃないかな。
杉田
いつかはどこかの短編集に収録されることがあるのでしょうか。
河野
それは編集者と意地の張り合いですね(笑)。
河野 裕さん プロフィール 著書紹介サイン本プレゼント


