わが大学の先生と語る
「文学で他者に出会う」小倉 孝誠(慶應義塾大学)
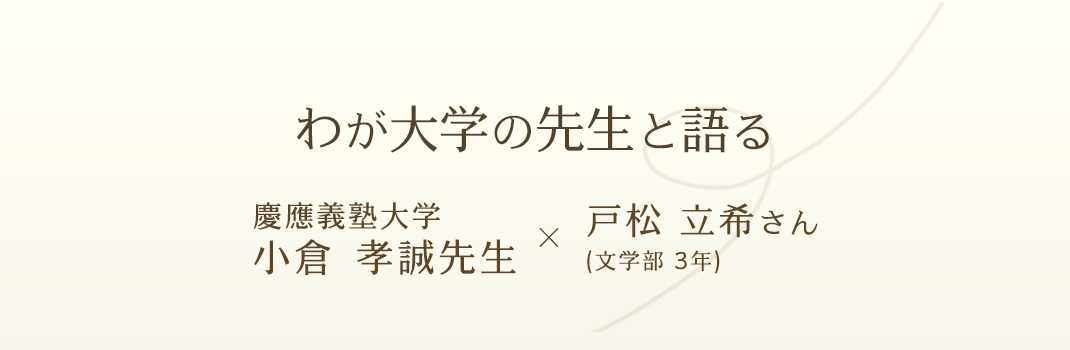
文学で他者に出会う インタビュー

1956年生まれ、青森県出身。
慶應義塾大学文学部教授。
1988年、東京大学文学部助手。1989年、東京都立大学人文学部助教授。2003年、慶應義塾大学文学部教授、現在に至る。2011年日本翻訳出版文化賞、2018年福澤賞。専攻はフランスの文学と文化史。
■主な著書・共訳書
著書に『愛の情景』(中央公論新社、2011年)、『革命と反動の図像学』(白水社、2014年)、『写真家ナダール』(中央公論新社、2016年)、『ゾラと近代フランス』(白水社、2017年)、『逸脱の文化史』(慶應義塾大学出版会、2019年)など。翻訳にアラン・コルバンほか監修『身体の歴史』全3巻(監訳、藤原書店、2010年、日本翻訳出版文化賞)、フローベール『紋切型辞典』(岩波文庫、2000年)、ユゴー『死刑囚最後の日』(光文社古典新訳文庫、2018年)などがある。
1.フランス文学に触れたきっかけ
戸松
小倉先生は具体的にどのようなテーマで研究をされているのですか。
小倉
18世紀後半から20世紀半ばまでのフランス文学と文化史です。例えば、これまで研究してきたのは、よくフランス文学の舞台になるパリについて。それから非常に関心があるのは「人間の身体」や「病理や病」というテーマです。そういったテーマについて今まで本を書いたりしてきました。
戸松
「人間の身体」と「フランス文学」の2つの分野はあまり関係なさそうにも聞こえますが……。
小倉
身体というのは文学だけでなく哲学や社会学なども含む幅広いテーマなのです。例えば、哲学は身体について深く論じてきたものですし、社会学や人類学も「どうやって人間は自分の体を認識しているか」ということについて問題提起をしています。文学も同様に人間の身体や顔を描いてきたので、なかなか面白いテーマです。
戸松
先生が近代のフランス文学と文化史を研究しようと思ったきっかけは何ですか。
小倉
面白いもので小説というのは、詩や演劇に比べると当時の社会や風俗を映し出しやすく、同時代の社会や物の考え方と非常に関係が深いんです。そうすると物語の中で何が起こっているかということだけでなく「そもそもなぜこういうものが書かれたのか?」ということに疑問を持つようになります。それから私の専門は19世紀フランスの小説ですが、この時代は人類学や社会学という学問がまだなかったので、文学がすべてを代弁していたのです。そういったことから、単に小説や特定の作家だけでなく、文学に映し出されている文化や社会がどういうものなのか、さかのぼっていきたくなったのです。
戸松
フランス文学に興味を抱いたきっかけはなんですか。
小倉
直接的なきっかけとしては、中学生の時に読んだスタンダールの『赤と黒』ですね。これは主人公が貧しい階級の野心的な青年で、社会の階段をかけあがっていこうとして最後は挫折するという小説です。最初は何気なく読んでいたのですが、文学ってこういう世界なのかと圧倒されてハマりました。スタンダールの研究者にはなりませんでしたが、私の衝撃的な読書体験といえばそれです。実は大学に入ってからはロシア文学にもハマったことがあるのです。ドストエフスキーとかトルストイとかの19世紀ロシア文学は圧倒的な深みと広さがある世界ですよね。
2.文学の中にある恋愛

戸松
先生が授業の中で「フランス文学における恋愛」について取り上げている理由は何ですか。
小倉
理由は色々ありますが、ひとつは恋愛が文学の中で非常に普遍的なテーマだからです。日本でも『万葉集』の時代からずっと大きなテーマでした。恋愛というのは、色々な意味で人間の感情や人生観、世界観すべてを巻き込む出来事なので、文学のテーマになりやすいのです。もうひとつは、何となく恋愛は学生にとって身近な話題のひとつだろうし、人間を成長させる大事な要素だと思うからです。自分と全く違う人間と深くかかわらないと恋愛はできないですよね。相手に言ったり言われたりすることで自分がどういう人間なのか振り返る機会でもあると思います。恋愛は他者と関わる究極的な形のひとつとも言えますね。
戸松
授業で「文学の中ではラブレターを書くシーンがよく描かれる」というお話をされていましたが、今ではあまり手紙を書く機会がないように、恋愛の形も時代とともに変化していくものですか。
小倉
そうだと思います。その時代と今の時代とでいちばん変わったのは、色々な意味で「待てなくなっている」ということだと思います。紙の手紙は届くまでに何日もかかりますが、スマホの場合は瞬時に返事が来るのが一般的になっていますよね。時間の節約にはなりますが、その分だけ自分の内面や心情をゆっくり考える時間がなくなっているのかもしれません。例えば昔のドラマや映画では待ち合わせのすれ違いというものがありましたが、今はスマホがあるのですぐに「どこにいるの?」と聞けてしまうので、こんなことは起こらないですよね。
戸松
また、手紙というのはひとつひとつの文をちゃんと考えて書くので言葉の重みを感じますよね。
小倉
もちろん手書きなので、字に書き手の個性が出ますよね。筆跡学という学問もあるくらいです。字がきれいだと、なんとなくその人の性格までしのばれるところがあるように思えてきます。僕は今の学生とは親子以上に年齢が違うので、きっと恋愛観も大分違うと思いますよ。
戸松
確かに色々な時代の恋愛小説を読んでいると、3,40年違うだけでも恋愛のスタイルが大分異なるなと思います。
小倉
それが国も違って100,200年違うとなれば、本当に異質の世界ですよね。そうなると単に恋愛小説というよりは、人間観や世界観全体にも関わってきます。そういうものを知るのにも、文学や哲学はある意味で役に立つのかなと。
戸松
確かに小説を読んでいる時に「なんで主人公はここでこういう気持ちになっているんだろう?」と考えたりします。
小倉
それはまさに文学を読むことの醍醐味のひとつです。そこで自分と違う何か(他者)に出会うことができるので読み応えがあるのです。自分と同じ世界だけに囲まれていても人間は成長しないですからね。学問においても同じことをやっていた方が楽ですが、自分が予期していなかったことを聴いたり読んだりしないと、研究者としても進歩しないです。
戸松
だから先生もフランス文学以外にも色々な作品に触れているんですね。
小倉
私が主に研究しているゾラやバルザックなんか、現代の我々からすれば古典的な作家ですが、彼らが生きていた時代では文字通り時代の最先端の作家だったわけです。それを考えると、現在のフランスや他のヨーロッパ諸国でどんな作家が何を書いているかを知ることも重要です。当然、生活様式も登場人物も考え方も、19世紀とは全く違いますが、文学研究者として感性を磨く、あるいは保つためには、そこを知ることが大事ですね。
戸松
先生は授業の中で石田衣良さんなどの現代の作家さんも紹介されていたので驚きました。
小倉
生きている場所も生活様式も違いますが、文学の良いところは「石田衣良もバルザックも、200年も違う時代の人だけど同じようなことを考えたり悩んだりしていたんだ」と思えるところです。だから昔の作品が、今でも読者の心を掴んでいるんだと思います。
3.「実際に感じる」ということ
戸松
先生が学生だった時に何か夢中になったことはありますか。
小倉
趣味があって何かに打ち込むということはなかったのですが、フランス留学中に、美術館を訪れたり、貧乏学生なりに旅行したりしていたのは印象に残っていますね。その中で「美術、文化、建築は実際に自分の目で見てみないとわからない」というのは改めて感じました。例えば、フランス料理だって料理のうんちくだけ聞いても、実際に食べてみないとどんな味かわからないですよね。建築や美術もそれと同じです。実際に思いがけない美術館にふらりと入って、全く予期しなかったものを発見した時は圧倒的に感動しますよね。それは言葉で聞くより実際に見て聴いて感じる、理屈抜きの深い感動を得られるということです。この時、人間は「一体この感動はどこから来るのだろう? 誰がこれを作ったのだろう?」と思って知りたくなります。なので、自分が知らない未知のことに出会うのは、学生時代は特に大事だと思います。色々なものを読んだり見たりするのも大事ですし、自分の世界とは全く異質な人間と出会うことも良いことです。留学は勉強以外にも自分と違うものに出会えるという意味ではとても良いことだと思いますね。
戸松
先生の学生時代は家族や友達とも連絡が頻繁にとれないこともあって、留学もかなり密なものになったのでしょうか。
小倉
確かに手紙くらいしか連絡手段がなかったので、良い意味で「雑音が無い留学生活」だったなとは思います。必要な情報が入ってこないので、自分の好きなように行動していました。今は情報のツールがたくさんあるので、ありとあらゆる情報が入ってきますよね。でも、情報と知識は違います。よく「情報が不足している」という言い方がされますが、ものを考えるのに必要なのは情報だけではないのです。限られた情報の中で「考える」ことも大事なことだと思います。
戸松
先生がフランス留学した時に1番に得られたことは何だと思いますか。
小倉
日本でフランス語の本を読んだりするのは、それはそれで良いけれど、これだけでは今のフランス人がどういう生活をしていて、何を考えているかについては全く分からないんですよ。特に、文学って生身の人間が出て来るものなので、卑近なレベルで「何を愛し、どんなところに住んでいて、何を食べているのか」ということも文学と社会を理解するためには大事です。こういうのは実際に行ってみて初めてわかることですよね。「フランス人はこういう時にこう反応するものだ」ということも、留学してフランス人と接触している中でなんとなくわかっていきました。
戸松
では、最後に先生が研究を通して今の学生に一番伝えたいことは何ですか。
小倉
大学にいる間に色々な意味でひとつのことに打ち込むことは、ものすごく大事だと思います。何か興味を持てることや熱中できるものをひとつ見つけると、そこから次々と興味の対象が広がっていきます。逆に何の興味もなく漫然と生きていると、「調べてみたい」とか「知りたい」とかいう気持ちが出てこないので広がっていきません。自分が何を知りたいのか、何を学んでみたいのかを自分で見つけるのが一番良いと思います。教師はあくまでそのお手伝いをするだけです。実現できているかわかりませんが、授業では学生自身の知的好奇心を刺激したいと思っています。
戸松
私は今までフランス文学に触れたことがなかったのですが、先生の授業を受けて一度手にとってみようかなと思うようになりました。
小倉
そう思ってくれると、教師としてはやりがいがありますね。
戸松
本日はありがとうございました。
対談を終えて
私はフランス文学の専攻ではないのですが、小倉先生の授業は本当に面白くていつかお話してみたいなぁと思っていたので、今回このような機会をいただけて嬉しかったです。先生へのインタビューを通して、読書が私たちにもたらしてくれるものの大きさが改めて分かった気がします。また、自分が興味を抱く対象をたったひとつでも持っていることで、「学ぶ」ことに対して楽しさを見出せるのではないかと思いました。
コラム
▼文学と歴史▼映画「ラマン(愛人)」から見えること
▼文学とジェンダー
文学と歴史
小倉
「都市・身体・病理・ジェンダー」という話をしましたが、文学と歴史学の関係についても、とても興味を持っています。特にヨーロッパでは「歴史・記憶・忘却」の観点で見てみると、自分の国や国民にとって都合が悪いことにはフタをしているようにも見られます。フランスの場合は、第二次世界大戦中のドイツとの関係です。長い間「多くのフランス人はドイツ軍に抵抗してきた」とフランスでは考えられてきましたが、実際はドイツに協力したフランス人もたくさんいたようです。これは「フランスはドイツに抵抗し、最後は勝利した」というイメージを作り上げようとしたために表に出てきませんでした。ドイツ軍に協力してアウシュビッツに多くの仲間を送り込んだフランス人もいたのだという歴史にはフタをされてしまったのですね。ただ、1980年代頃からそこを見直そうという流れが出てきて、文学にも波及してきているため、そのような戦争やユダヤ人の問題を提示する文学作品も多いです。昔から文学と歴史は大きな問題なのですが、今は歴史学との関係で掘り下げられてきています。その点は学生時代から興味をもっていたので、もっと掘り下げてみたいなと思っています。
映画「ラマン(愛人)」から見えること
戸松
以前先生からお借りしたデュラスの『ラマン』は衝撃的でした。華僑の青年とフランス人少女の恋物語ですが、あのような愛の形もあるんだなぁと。
小倉
あの作品は舞台が1930年ごろのベトナムで、まだフランスの植民地だった頃の物語です。植民者と植民地被支配者の角逐という政治的な問題も絡まっています。当時の植民地の様子、フランス人と華僑の人が恋愛をするのはどういうことなのか、などが描かれていますよね。「ラマン」は作家自身の自伝要素が強いと言われています。もちろんノンフィクションではなく小説ですが、フランス人のデュラスがベトナムで育ったことは事実です。
戸松
あの作品の面白いところは、1人の少女が青年と恋に落ちたことによって、「大人の女性」に成長していくというところかなと思います。
小倉
たしかにそういう視点でしょうね。恋愛が1人の少女を成長させるという要素はあると思います。我々男性の偏見かもしれませんが、文学作品を読んでいると特に女性の方が恋愛から得る影響は大きいと感じますね。ただ女性の研究者からしてみたら「小倉先生、それはちょっと違いますよ」と思われてしまうかもしれませんが。
文学とジェンダー
小倉
実は文学とジェンダーの問題は非常に結びつきやすいものなのです。例えば文学に女性が出てきて、その身体描写を誰が書いているかというと圧倒的に男性が多かったのです。男の作家が「彼女は清楚で美しかった」というふうに描きます。そして読者が男性の場合、男性作家の書いたものを何げなく普通に読んでいるけど、女性が読むと「あれ?こういうのはあり得ない」と思うような話がたくさん出て来るそうですよ。だから男が書く女の身体というのは、女性が読むか男性が読むかで印象が全然違う、それがジェンダーバイアスというものですね。ジェンダー研究というのは日本でもそうですが、女性の研究者が多いです。男性の作家や研究者はしばしば、人間一般の名において語り、論じると思っています。でも女性にとっては、それは人間一般の名において語られたことではなくて、男の視点から語られてきたことであるというのが基本的なジェンダーの認識なのです。その意味では、ジェンダー研究が女性の領域になっているのは当然のこととも言えます。
戸松
確かに男性だとなかなかそういうことを疑わないですよね。先生が授業でおっしゃっていた中で面白いなと思ったのが「悲劇に終わる恋愛小説ではヒロインがだいたい最後に死んでしまうし、主人公の男は死なない」というものです。たしかに、日本で大ヒットした映画『世界の中心で愛を叫ぶ』でも主人公と結ばれるはずだった女の子が白血病で死ぬというラストを迎えますよね。
小倉
伝統的に文学の中では女性が死ぬシーンが多く見られます。今は女性の作家も多いですが、19世紀から20世紀はじめくらいまでは作家は圧倒的に男性が多かったので、男性の作家が恋愛小説の中で女性を殺してきたのです。現代の女性作家が書く恋愛小説の中でそんなに女性が死んでいるかといったら、そうではないでしょうし、『世界の中心で愛を叫ぶ』も著者は男性ですよね。昔の悲劇を今の若い女性が読んだら「いや、今どきの女性は恋愛なんかで死なないよ」と思うかもしれませんが。その点については授業に出ている女子学生の意見を聞いてみたいところです。


