いずみスタッフの 読書日記 166号
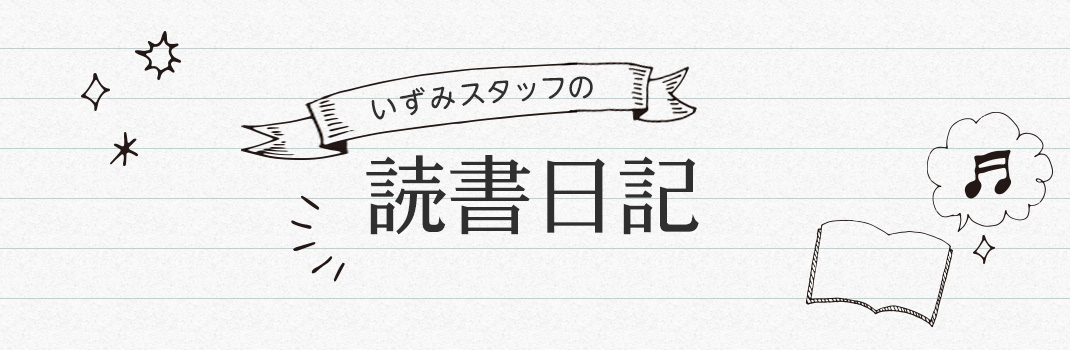
レギュラー企画『読書のいずみ』読者スタッフの読書エッセイ。本と過ごす日々を綴ります。
東京経済大学2年 内田 充俊
12月

下手な人ほど、ゴテゴテと飾り立てる。ファッションも文章も壊滅的な我が身を振り返るに、自信の無さが過剰な装飾に駆り立てるのだろう。
例えばファッションなら腰からチェーンをジャラジャラとぶら下げて、孔雀のように派手な色の服を重ねる。文章なら比喩や形容詞、擬音語のオンパレードで形容過剰となる。
その「過剰」の精神の対極が、短歌だ。五・七・五・七・七の三十一文字のなかに想いをぎゅっと詰め込むのだから。まるでダイヤモンドの周りを研磨して輝きを放つが如く、無駄が削ぎ落とされて凝縮された言葉たちは白黒印刷なのに輝いて見える。
12月に読んだ本は、そんな短歌カテゴリから2冊。穂村弘『求愛瞳孔反射』(河出文庫)と、穂村弘『本当は違うんだ日記』(集英社文庫)。前者は「恋をしているある瞬間、僕たちの瞳は不思議な輝きを放つ」というエピグラムからはじめる、恋愛をテーマとした短歌集。後者は短歌作家、穂村さんの視点から日常を切り取ったエッセイ集。ふだん言葉を彫琢している詩人の視点は、ナイフのように鋭い。
1月
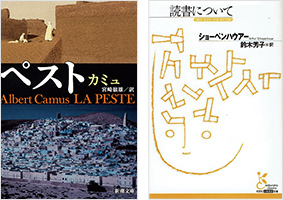
苺パフェと乾パンの賞味期限の長さは10年以上違うように、本の賞味期限も一様ではない。けれど確かにいつか「おわり」があるという点で共通点がある。
読まれなくなった本は絶版になり、断裁され、失われていく。平成20年には年間2億冊が廃棄処分されたという。
そんな中で、50年100年の時の試練を経ても読まれ続けている、不死鳥のような本を、我々は古典と呼ぶ。
1月に読んだ本はそんな古典の中から2冊。カミュ『ペスト』(宮崎嶺雄=訳、新潮文庫)とショーペンハウアー『読書について』(鈴木芳子=訳、光文社古典新訳文庫)。前者は14世紀の感染症を描写した文学として、コロナ禍を類比的に捉える視点を提供してくれる。後者は乱読を諫める読書論だ。
ところで村上春樹『ノルウェイの森』(講談社文庫)にて、知的な東大生の永沢さんは「俺は出版されて50年が経った本しか読まない。はずれの本を読んで貴重な時間を無駄にしたくないからな」と嘯く。今回紹介した2冊も「貴重な時間を無駄にしない」こと請け合いだ。
京都大学大学院M1 畠中 美雨
元旦 こたつを夢見る下宿先で
 今年は帰省せずに年を越した。新年一冊目に読んだのは伊藤計劃さんの『虐殺器官』(ハヤカワ文庫JA)。シェパード大尉を主人公に据えた近未来のSF小説。スリル満点の書き出しから章の終わりで一息つき、すぐに次へ次へと読み進む。国家間や個人の思惑の駆け引きなどスリリングな展開を軸に、章を追うごとに規模が大きくなり新たな思惑が浮き彫りになる展開に手がとまらない。そのスケールとは逆に、自我の境界線や罪の意識など非常に繊細なテーマも軸のひとつ。巻末での円城さんとの対談も読み応えがあり大満足。戦争をビジネスと捉える世界線と、何かとニーズや課題をほじくり返しては解決策を提供していく現代を重ねて、どうかこれがいつまでも「SF世界」の物語であるようにと思う。
今年は帰省せずに年を越した。新年一冊目に読んだのは伊藤計劃さんの『虐殺器官』(ハヤカワ文庫JA)。シェパード大尉を主人公に据えた近未来のSF小説。スリル満点の書き出しから章の終わりで一息つき、すぐに次へ次へと読み進む。国家間や個人の思惑の駆け引きなどスリリングな展開を軸に、章を追うごとに規模が大きくなり新たな思惑が浮き彫りになる展開に手がとまらない。そのスケールとは逆に、自我の境界線や罪の意識など非常に繊細なテーマも軸のひとつ。巻末での円城さんとの対談も読み応えがあり大満足。戦争をビジネスと捉える世界線と、何かとニーズや課題をほじくり返しては解決策を提供していく現代を重ねて、どうかこれがいつまでも「SF世界」の物語であるようにと思う。なお初夢がこの世界観を投影したかなりグロテスクなものになることを、この時はまだ知らなかった……。
1月中旬 片方だけ手袋を外しながら
 運転免許を更新する際の待ち時間に、昨年末から読んでいたフランクリンの『フランクリン自伝』(中公クラシックス)を読み終わる。「自伝」とあるように著者自身が書いた一冊。一介の印刷工(しかもその仕事ですら彼本人が望んだ仕事ではない!)から、初代郵政長官になり、独立宣言を草案するその人生はまさに劇的。その他にも新聞発行、図書館設立、稲妻の発見など至る分野で功績を残しているのに本人の語り口調はいたって淡々。相当に頭が切れ、弁がたつひとだったのだなというのが文章からよくわかるが、それもこの本に書いていたように、日々の目標を定め毎日チェックするといった地道な努力によるところがあるのだろう。よし私も! と意気込むも、無事免許を更新できほっとしたまま1日が終わる。
運転免許を更新する際の待ち時間に、昨年末から読んでいたフランクリンの『フランクリン自伝』(中公クラシックス)を読み終わる。「自伝」とあるように著者自身が書いた一冊。一介の印刷工(しかもその仕事ですら彼本人が望んだ仕事ではない!)から、初代郵政長官になり、独立宣言を草案するその人生はまさに劇的。その他にも新聞発行、図書館設立、稲妻の発見など至る分野で功績を残しているのに本人の語り口調はいたって淡々。相当に頭が切れ、弁がたつひとだったのだなというのが文章からよくわかるが、それもこの本に書いていたように、日々の目標を定め毎日チェックするといった地道な努力によるところがあるのだろう。よし私も! と意気込むも、無事免許を更新できほっとしたまま1日が終わる。
1月下旬 冬の寒さに驚く日々
 大晦日特番「村上春樹ラヂオ」を聞いたあと、私最新刊読んでない! と気づいて早数週間。やっと村上春樹さんの『一人称単数』(文藝春秋)を手に取る。一作目の「石のまくらに」が一番のお気に入り。
大晦日特番「村上春樹ラヂオ」を聞いたあと、私最新刊読んでない! と気づいて早数週間。やっと村上春樹さんの『一人称単数』(文藝春秋)を手に取る。一作目の「石のまくらに」が一番のお気に入り。言葉、偶然性、名前。ここではない不確かな、それでいて日常の一幕を語り手一人の一人称で描いている。作者自身が歳をとることや時間が流れていくことを受け止めている印象を受けた。エッセイに近い気もしたので、長編や世界観に物怖じしてしまう人にもすすめたい一冊。

 東京経済大学2年
東京経済大学2年 京都大学大学院M1
京都大学大学院M1 京都大学3回生
京都大学3回生 お茶の水女子大学2年
お茶の水女子大学2年
