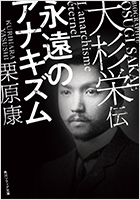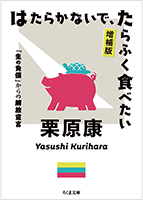いずみスタッフの 読書日記 167号
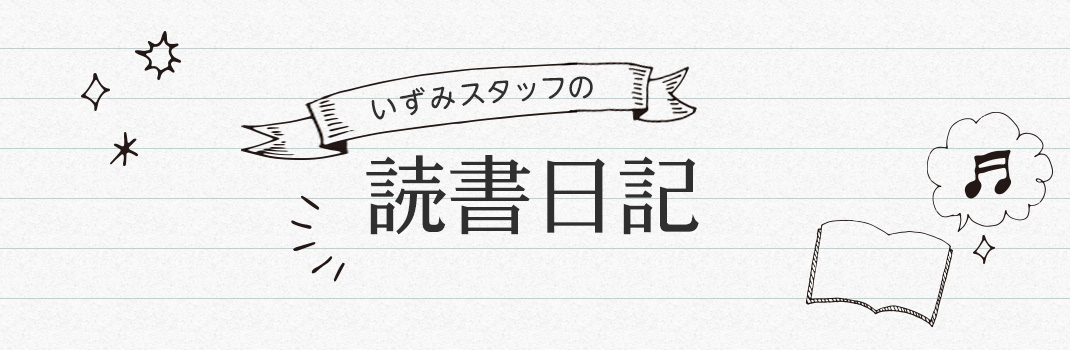
レギュラー企画『読書のいずみ』読者スタッフの読書エッセイ。本と過ごす日々を綴ります。
広島大学4年 倉本 敬司
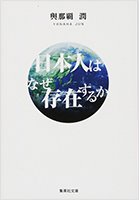 外国書講読の授業でナショナリズムに関する本を読んでいる。ナショナリズムというと、右翼やヘイトスピーチを想像してしまうかもしれないが、もう少し広い意味で、近代国家の成立やいわゆる民族問題を扱う分野だ。領域横断的な内容で、一義的な定義が難しく、なかなか掴めないと感じているが、とても興味深い。日本で言えば、沖縄問題や中国や韓国との領土問題に深く関連している。この授業の関係で読み返した本が『日本人はなぜ存在するか』(與那覇 潤/集英社文庫)だ。平易な文章だが、とても読み応えがあるし、ブックリストが付いているのが○(マル)。
外国書講読の授業でナショナリズムに関する本を読んでいる。ナショナリズムというと、右翼やヘイトスピーチを想像してしまうかもしれないが、もう少し広い意味で、近代国家の成立やいわゆる民族問題を扱う分野だ。領域横断的な内容で、一義的な定義が難しく、なかなか掴めないと感じているが、とても興味深い。日本で言えば、沖縄問題や中国や韓国との領土問題に深く関連している。この授業の関係で読み返した本が『日本人はなぜ存在するか』(與那覇 潤/集英社文庫)だ。平易な文章だが、とても読み応えがあるし、ブックリストが付いているのが○(マル)。
 それから、『幸福と人生の意味の哲学』(山口 尚/トランスビュー)は、イチオシだ。本屋に行くと「〇〇すれば〜」とか「成功する人は△△」のような「自己啓発」本に溢れている。それが目に入ると、先の尖ったもので胸のあたりをプスッと突かれるように感じる。「生きていることはとてつもなく理不尽だ」「努力至上主義なんかクソ食らえ」と思っているが、プライドが高すぎて頑張ることからも逃れられない、中島敦や中島義道を密かに愛読していたりする、つまるところ「困った人」にはオススメ。幸福がいかにままならないものかをひとつひとつ丁寧に、徒らに理屈っぽくもなく論証していく。注釈がきちんとついているのも良い。努力すれば幸せになれる(=努力しないのならば幸せになれない)と言われるよりも、(ある意味で)努力なんかしても幸せになれないと言ってくれる方が、よほど誠実だろう。幸福について語っている本は数あるが、初めて得心がいったのでぜひ紹介したかった。
それから、『幸福と人生の意味の哲学』(山口 尚/トランスビュー)は、イチオシだ。本屋に行くと「〇〇すれば〜」とか「成功する人は△△」のような「自己啓発」本に溢れている。それが目に入ると、先の尖ったもので胸のあたりをプスッと突かれるように感じる。「生きていることはとてつもなく理不尽だ」「努力至上主義なんかクソ食らえ」と思っているが、プライドが高すぎて頑張ることからも逃れられない、中島敦や中島義道を密かに愛読していたりする、つまるところ「困った人」にはオススメ。幸福がいかにままならないものかをひとつひとつ丁寧に、徒らに理屈っぽくもなく論証していく。注釈がきちんとついているのも良い。努力すれば幸せになれる(=努力しないのならば幸せになれない)と言われるよりも、(ある意味で)努力なんかしても幸せになれないと言ってくれる方が、よほど誠実だろう。幸福について語っている本は数あるが、初めて得心がいったのでぜひ紹介したかった。
京都大学4回生 徳岡 柚月
4月上旬
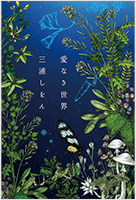 図書館を散歩していると、三浦しをんさんの『愛なき世界』(中央公論新社)に目が止まった。植物の研究者のお話だとどこかで目にして以来、読みたいなと思っていたんだった。ちょうど研究室生活がはじまったばかりの今、うれしい出会い。躍る心で読み始める。
図書館を散歩していると、三浦しをんさんの『愛なき世界』(中央公論新社)に目が止まった。植物の研究者のお話だとどこかで目にして以来、読みたいなと思っていたんだった。ちょうど研究室生活がはじまったばかりの今、うれしい出会い。躍る心で読み始める。読了。『愛なき世界』というタイトルは、一見冷たい不穏なものに感じるけれど、その実、この物語は愛に溢れていた。植物には体温はないし、愛も存在しないけれど、植物を取り巻く世界は、温かい、というか一部灼熱の地域もある。本村さんのように、わたしも研究対象に愛を注ぎ、深く知っていきたいなと思う。三浦さんの明るくて優しい世界の見方に、今回も元気をもらった。
4月中旬
 町田そのこさんの『52ヘルツのクジラたち』(中央公論新社)。本屋さんで見かけたときに、表紙に一目惚れし、家にお連れした。福田利之さんの、眺めてるだけで、物語の世界へ入り込んでしまうような装画。
町田そのこさんの『52ヘルツのクジラたち』(中央公論新社)。本屋さんで見かけたときに、表紙に一目惚れし、家にお連れした。福田利之さんの、眺めてるだけで、物語の世界へ入り込んでしまうような装画。童話の中の不思議な植物みたいなものでできたクジラと、その口から発せられる52の文字。そう、タイトルにもある、この「52」という数字がとても気になる。表紙を満足いくまで堪能したところで、「52」の謎を胸に抱きつつ、ページをめくっていく。
読了。長い間海に潜っていたかのような感覚。虐待やトランスジェンダーなど、さまざまな問題をかかえた人がいて、同じ虐待に苦しんでいる人でも、状況や、心情、選ぶ行動は違っていて。頻繁に流れるニュースを見て、少しはわかっているような気になっていたけれど、受け入れるのが、深く考えるのが怖くて、心を背けていたことの多さに、改めて気づかされた。本当をいうと、少し遠い世界での出来事のように感じていた。でも、これまでも、気づけなかっただけで、わたしも「声なき声」を発する人とすれ違っていたのかもしれない。それに、今も、わたしのまわりにいるのかもしれない。ひととひとが関わり合う中ではどうしてもうまくいかないこともあって、ありふれているからニュースにはならないけど、でも痛い。これぐらいの痛みはみんな味わっているんだからと、心の内に閉じ込めてしまう。そういうことだってある。自分のことでいっぱいいっぱいになるのではなく、もっとまわりに目を向けたい。せめて、近くにある「声なき声」には気づけるように。耳をすませよう。

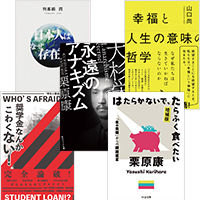 広島大学4年
広島大学4年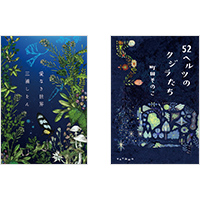 京都大学4回生
京都大学4回生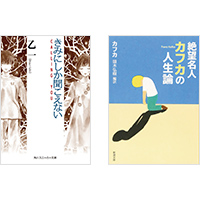 京都大学大学院M2
京都大学大学院M2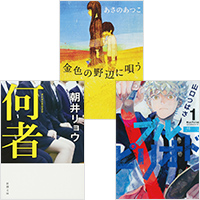 お茶の水女子大学大学院M2
お茶の水女子大学大学院M2