いずみスタッフの 読書日記 169号 P2
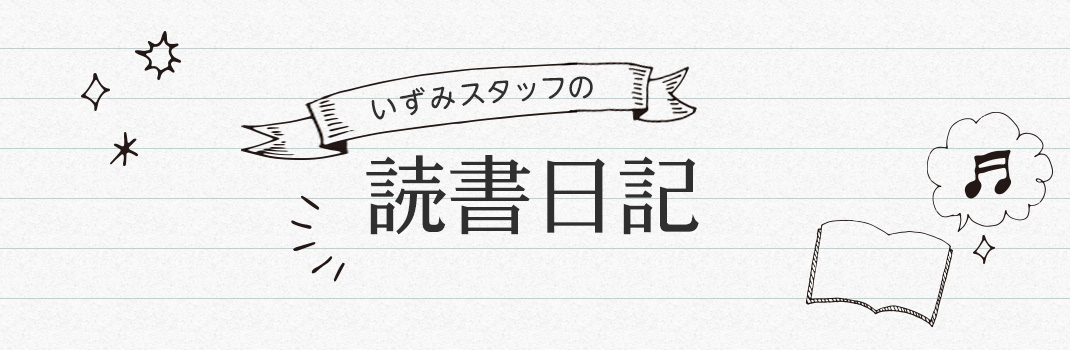
レギュラー企画『読書のいずみ』読者スタッフの読書エッセイ。本と過ごす日々を綴ります。
京都大学2回生 齊藤 ゆずか
8月
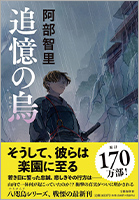 大好きなシリーズの最新刊が書店に並んだので、急いで買いに行った。『追憶の烏』(阿部智里/文藝春秋)は八咫烏シリーズの本編8巻目。3年前、部活の先輩に勧められて読み始めたのだが、ミステリと和風ファンタジーが混ざり合ったこのシリーズは、巻を追うごとに面白くなっていく。美しい文体に緻密な伏線、そうだったのかと驚くこと連続の展開で、読み始めると文字通り止まらなくなる。これから読むであろう未来のファンのために詳しくは書かないが、前作『楽園の烏』の伏線回収ともいえる今作は中盤に衝撃の出来事があり、思わず声を上げてしまった。このシリーズは私が母に勧め、母がさらに祖母に勧めたため三世代で読んでいる。早く内容について語り合いたいので、実家に持ち帰らねば。読み終えてすぐに帰省用のスーツケースに入れた。
大好きなシリーズの最新刊が書店に並んだので、急いで買いに行った。『追憶の烏』(阿部智里/文藝春秋)は八咫烏シリーズの本編8巻目。3年前、部活の先輩に勧められて読み始めたのだが、ミステリと和風ファンタジーが混ざり合ったこのシリーズは、巻を追うごとに面白くなっていく。美しい文体に緻密な伏線、そうだったのかと驚くこと連続の展開で、読み始めると文字通り止まらなくなる。これから読むであろう未来のファンのために詳しくは書かないが、前作『楽園の烏』の伏線回収ともいえる今作は中盤に衝撃の出来事があり、思わず声を上げてしまった。このシリーズは私が母に勧め、母がさらに祖母に勧めたため三世代で読んでいる。早く内容について語り合いたいので、実家に持ち帰らねば。読み終えてすぐに帰省用のスーツケースに入れた。
9月
 去年買って積読になっていた、『父の詫び状』(向田邦子/文春文庫)に手を伸ばす。向田邦子のエッセイは、読んでいて心地よい感覚になる。この本では子どものころの話が多く、戦前の日本という、わたしの経験からは程遠い時代の家の中が描かれているのだが、どうしてだろう、お櫃のご飯が立てる湯気、着物姿の母に酔っぱらった父という、向田の子ども時代がありありと目の前に浮かび上がる。本当は自分もその時代に生きていたのではないかと思うくらいに懐かしい。読み進めていくと、アイスクリーム売りのアルバイトにしろ、飲み屋で落とし物をした話にしろ、人と人とのふれあいの多い時代だったのだなと思う。品がありながらも素直な生き方にあこがれる。わたしもエッセイを書こうと決めた。
去年買って積読になっていた、『父の詫び状』(向田邦子/文春文庫)に手を伸ばす。向田邦子のエッセイは、読んでいて心地よい感覚になる。この本では子どものころの話が多く、戦前の日本という、わたしの経験からは程遠い時代の家の中が描かれているのだが、どうしてだろう、お櫃のご飯が立てる湯気、着物姿の母に酔っぱらった父という、向田の子ども時代がありありと目の前に浮かび上がる。本当は自分もその時代に生きていたのではないかと思うくらいに懐かしい。読み進めていくと、アイスクリーム売りのアルバイトにしろ、飲み屋で落とし物をした話にしろ、人と人とのふれあいの多い時代だったのだなと思う。品がありながらも素直な生き方にあこがれる。わたしもエッセイを書こうと決めた。
10月
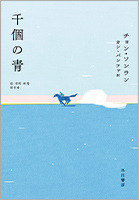 大学の近くに商店街があり、その中に小さな映画館がある。1階には本が並べられていて、今までは映画の待ち時間にひと眺めするくらいだったが、初めてそこでゆっくり本を選んだ。大きな書店とはまた違った雰囲気があり、違う選ばれ方をした本が表紙を見せている。表紙に惹かれて購入したのは『千個の青』(チョン・ソンラン/早川書房)。かつてないスピードで競馬を行うために登場したロボット騎手。思考や感情をもつことはなかったはずだが、別の部品が紛れてできたコリーは馬のトゥデイと心を交わそうとする。人らしく生きることへのあきらめすら漂う未来の世界で、それを超えていこうとする人々が描かれる。ロボットが人間に代わるだろうとはよく言われるが、数十年後の世界を、本を片手に想像した。
大学の近くに商店街があり、その中に小さな映画館がある。1階には本が並べられていて、今までは映画の待ち時間にひと眺めするくらいだったが、初めてそこでゆっくり本を選んだ。大きな書店とはまた違った雰囲気があり、違う選ばれ方をした本が表紙を見せている。表紙に惹かれて購入したのは『千個の青』(チョン・ソンラン/早川書房)。かつてないスピードで競馬を行うために登場したロボット騎手。思考や感情をもつことはなかったはずだが、別の部品が紛れてできたコリーは馬のトゥデイと心を交わそうとする。人らしく生きることへのあきらめすら漂う未来の世界で、それを超えていこうとする人々が描かれる。ロボットが人間に代わるだろうとはよく言われるが、数十年後の世界を、本を片手に想像した。
名古屋大学大学院 瀬野 日向子
10月7日
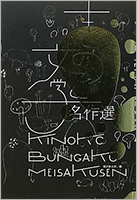 秋になり、修士論文の提出日が近づいてきた。終わりの見えない作業に頭を抱えながらも、少しでもよい結果を残すべく、日々実験に追われている。
秋になり、修士論文の提出日が近づいてきた。終わりの見えない作業に頭を抱えながらも、少しでもよい結果を残すべく、日々実験に追われている。秋といえばきのこ。読書ときのこが大好きな私にとって、秋は「読書の秋」も「きのこの秋」も楽しめる最も幸せな季節なのだ。しかし外に飛び出してきのこを探したくても、今年はその時間がとれそうにない。
せめてきのこを近くに感じたい、と『きのこ文学名作選』(飯沢耕太郎=編/港の人)を手に取った。この本には、きのこ文学研究家である編者の飯沢さんが選んだ、きのこが出てくる小説や詩が十六篇収録されている。作者の中には、泉鏡花や宮沢賢治など、名前を知っている作家も大勢いて驚いた。
もう一つ驚くのは、デザインの美しさ。なんとこの本、作品ごとに紙の種類、フォント、挿絵の有無などがどれも大きく異なるのだ。パラパラとページをめくって眺めているだけでも楽しい。中には本を回転させながら読む箇所や、ページに穴が空いている箇所もある。どこか怪しさ、不思議さを感じるデザインは、きのこの森に迷い込んでしまうような、そんな印象を受ける。
食用のきのこだけでなく毒きのこも多数登場しており、収録作品を全て読むと、それだけで豊富な種類のきのことの出会いを楽しめる。今年はこの本の中できのこ狩りを満喫しようと思う。
10月19日
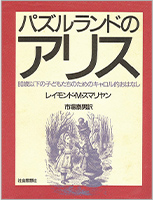 実験の疲れからか、なんだか頭がぼんやりする。思い切り頭を使ってリフレッシュがしたい、と思い選んだのは『パズルランドのアリスー80歳以下の子どもたちのためのキャロル的おはなし』(レイモンド・M・スマリヤン〈市場泰男=訳〉/社会思想社)だ。
実験の疲れからか、なんだか頭がぼんやりする。思い切り頭を使ってリフレッシュがしたい、と思い選んだのは『パズルランドのアリスー80歳以下の子どもたちのためのキャロル的おはなし』(レイモンド・M・スマリヤン〈市場泰男=訳〉/社会思想社)だ。この本は不思議の国のアリスと鏡の国のアリスをベースにした物語形式になっている。ハンプティ・ダンプティやハートの女王など、アリスの世界でおなじみのどこかおかしな登場人物たちによって、論理パズルが次々と出題される。その数およそ90問。その問題の多さに戸惑う人もいるかもしれない。でも大丈夫。簡単な数の計算から、複数人の証言をもとに犯人を推理するものまで、多種多様なタイプの問題があるので、最後まで飽きずに取り組むことができる。
問題は本の後半にいくにつれて難しくなっていく。何とか巻末の解答に頼らずに読破したい!と試行錯誤すること数日。解けば解くほど思考がクリアになっていくような、不思議な感覚を味わうことができた。楽しくてクセになりそうだ。
この本の他にも、著者の論理パズルの本は数多く出版されているらしい。時間を見つけて少しずつ挑戦していきたい。
前のページへ

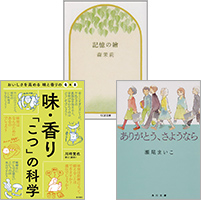 お茶の水女子大学大学院
お茶の水女子大学大学院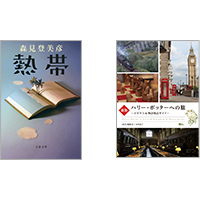 京都大学4回生
京都大学4回生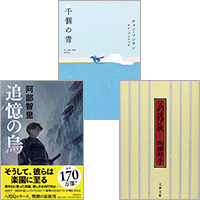 京都大学2回生
京都大学2回生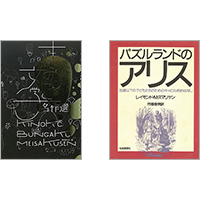 名古屋大学大学院
名古屋大学大学院
