講演録
「大学のゆくえ 本のゆくえ 〜長く広い歴史のなかで文系知の未来を見通す〜」東京大学教授・ハーバード大学客員教授 吉見俊哉先生
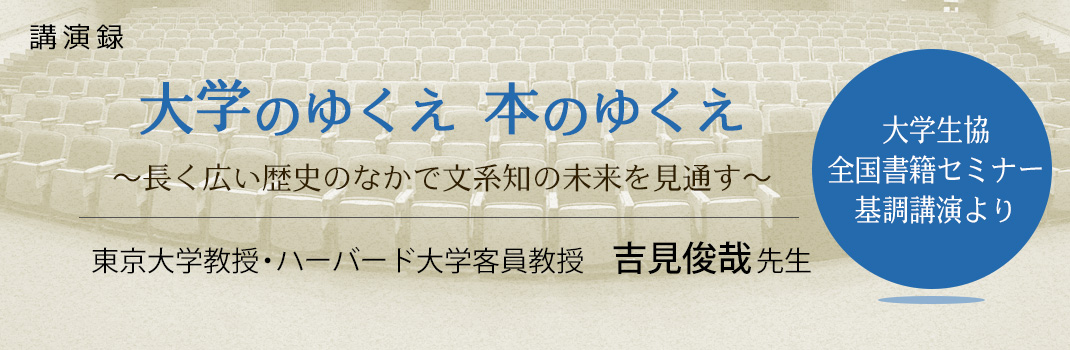
▼ Profile
1. 「文系学部の廃止」報道の虚実
2. 大学の現在
3. 大学の死、大学の再生
4. 出版の爆発 出版の危機
5. 「文系」は、役に立つ
6. 大学のゆくえ 本のゆくえ— 脱甲殻類社会への指針
P r o f i l e
吉見 俊哉 (よしみ・しゅんや)一九五七年、東京都生まれ。東京大学大学院情報学環教授。同大学副学長、大学総合教育研究センター長などを歴任。社会学、都市論、メディア論、文化研究を主な専門としつつ、日本におけるカルチュラル・スタディーズの発展で中心的な役割を果たす。著書に、『都市のドラマトゥルギー』『博覧会の政治学』『親米と反米』『ポスト戦後社会』『万博と戦後日本』『夢の原子力』『「文系学部廃止」の衝撃』など。
2017年7月28日、セシオン杉並(東京都杉並区)にて大学生協全国書籍セミナーが開催されました。基調講演は東京大学教授の吉見俊哉先生。先生の著書『「文系学部廃止」の衝撃』『大予言』(集英社新書)をベースに、いま大学が置かれている状況、そしてそれが出版、本の問題とどう絡んでいるのかというお話をしていただきました。全国の大学生協で書籍部門を担当する職員に向けた講演ですが、『izumi』読者のみなさんも大学と出版を取り巻く状況を知るいい機会です。ご一読ください。
1.「文系学部の廃止」報道の虚実

2年ほど前に「国立26大学文系改廃へ」、あるいは「国立大文系見直しへ」と多くの新聞で大きく見出しが出ました。この最初の報道が出たのは2015年5月28日です。産経新聞が「人文系学部・大学院、規模縮小へ転換」という見出しで報道を出しました。そして6月8日、教員養成系や人文社会系の学部や大学院の廃止や転換に取り組むことを求める通知が文部科学省から出された。朝日新聞は「社会に必要とされる人材を育てられていなければ廃止や分科の転換にとりくむ検討を求めた」、さらに毎日新聞、東京新聞、日本経済新聞、読売新聞もそれに続いてどんどん報道がエスカレートしていきます。この流れを受けて8月23日には日本学術会議が、9月9日には経団連までが反対声明を出していきました。いわば文部科学省は袋叩きにあうことになるわけです。
文部科学省が6月8日に出した通知には、教員養成系学部大学院、人文社会系学部大学院については「18歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国立大学としての役割等を踏まえた組織の見直し計画を策定し、組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組む」という文章があります。この最後の「組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組む」という部分だけを抜きとれば報道が全然間違いだったということは言えません。しかし、実はまったく同じ内容の文書が1年前にも出されていました。2014年8月4日にそれが伝えられた時にはほとんどのメディアは反応していません。ところが2015年6月8日にまったく同じものが出た時には大騒ぎになったわけですね。
なにが違ったのかというと、政治状況です。2015年の夏というのは思い出していただければ分かるように、安倍政権が安保関連法案の強行採決をして、国会前をデモが取り囲んでいたときです。そして新国立競技場をめぐる色々な問題があり、当時の下村文部科学大臣は日の丸・君が代の要請発言がありました。どうも安倍政権を叩くネタをマスコミは一生懸命探していたんですね。そこにこの文部科学省の通知が出たものですから、マスコミがこれを大きく取り上げて叩いていった。日本中がそれに乗っかったということになります。
実は、ここで出されたような問題は2000年代初頭つまり国立大学が法人化する前から言われ続けてきたことです。
例えば2001年6月に文部科学省が出している「国立大学構造改革の方針」ではすでに教員養成系大学等の規模縮小とか、単科大学の統合とか、そういうある種の社会的な需要の中で国立大学のあり方を見直さなければいけないということが明確に出されていました。その中にみなさんご承知のように国立大学の法人化がありました。国立大学の法人化の結果どういうことが進んでいったのかというと、大学の常勤教員の人件費が減って非常勤教員や任期付きの教員が急増しました。それから人文・社会系で国立大学の教員数はだいぶ減り、同じぐらいのボリュームで私立大学の文系の教員数が増えました。つまり、文系の重点が国立から私立にだいぶシフトしていったわけです。そして共同研究や競争資金の獲得はずいぶん増えました。一生懸命外部資金を獲得するため、新しい研究プロジェクトを立てるようになりました。その結果教授とか准教授とか比較的地位が確立している先生方の研究時間が大幅に減って、基礎研究力は劣化しました。これがこの10年間に起こったことです。ですから、問題はすでに2000年ごろから始まっていて、2015年に文部科学省が突然思いつきで通知を出したというわけではないのです。
2000年ごろにすでに学術会議のなかで人文・社会系科学の役割を見直さなければいけないという声明が出されています。要するに自然科学と人文科学を全然別のものと考えるのはやめて、人文・社会科学の根本的な有用性、自然科学的な生命科学、環境などの価値や方向性、限界を定める上での、有用性を正面から認め、きちんとそちらにも予算がまわる仕組みに変えていかなくてはいけない、ということです。しかしながら、これは色々な政治的理由でそのあとは進みませんでした。
この文系学部騒動で分かってきたことがあります。それは、一般社会にも「理系は役に立ち文系は役に立たない」という通念が蔓延しているということです。
2. 大学の現在
日本の、特に国立大学は、90年代以降いくつかの制度改革を経験してきました。まず、教養部は解体する——ここで大学の教養教育がたいへん弱体化しました。二番目に大学院生の定員数の大幅な増加——そのことによって大学院に入るハードルがすごく低くなりましたが、大学院で修士号や博士号を取得しても良い就職先が見つかるとはならなかった。つまり高学歴者の雇用が広がらなかったゆえに、大学院に行っても結局何にもならないと若者たちが気づき、大学院に入ること自体のインセンティブがすごく低くなってしまった。そして国立大学の法人化——外部から研究費を獲得する理系の先生たちと、困窮化していく文系の研究室の貧富の格差がすごく広がりました。しかし、いま大学が直面している困難は、もっと大きなものがあります。それは、人口が持続的に減少していく社会のなかで大学の数が増えすぎているということです。戦争が終わった1945年、48校しかなかった日本の大学は、現在、約20倍にもなる800校近くまで増えました。1970年代までは日本の人口そのものが増えていましたから大学の数が増えるのはそれなりに理由がありますが、80年代後半以降18歳人口は減りつづけていますね。にもかかわらず大学は増え続けました。そうなると、当然ながら大学に入学するハードルを低くしていかないと定員が埋まりません。大学の側が定員を埋めるために一生懸命志願者をマーケティングしていくような状況です。
これがなにに現れているか、それは大学の学部名称です。私はこれを「学部名称のカンブリア紀的大爆発」と呼んでいます。日本の大学の国立・私立を合わせて学部の名称は1990年ごろまでは97種類、つまり100もありませんでした。法学部、文学部、理学部、工学部に加え国際環境情報学部、国際文化科学部といったものもありましたが、1995年には145種類、2000年には235種類、2005年には360種類、2010年には435種類、まるで商品のラベルみたいに学部名称が増えるという現象が90年代以降の日本に起こったのです。「学生定員を埋めなければならないからかっこいい名前をつける」という商品のマーケティングと同じ論理なんですね。なにか根本的に間違っているのではないかという気がします。
80年代ぐらいまでは、大学の先生は研究に時間をかけることができましたが、90年代末ぐらいから日本の大学の環境は一変しました。研究をしてアウトプットを出しなさい、これは当然ですね。そして教育もしてください——授業もきちんと15回、学生の指導、成績とか審査も間違いなく。考え方として、これは正しいですね。さらに、大学は自治ですから管理者として、PDCAサークルはちゃんと回す、一つひとつのアドミニストレーションも責任をもって行ってください……一人三役です。人がいい人間であればあるほどこれが一気に降ってくるんですね。そうすると先生たちは二極化します。言われていることは全部正しいですから、なかなか時間がないけれども睡眠を削って頑張る、頑張る分だけ底無し沼のように仕事が増えていく。そして最後は体を壊していく。
一方では、「もう自分にはとてもできないからそっとしておいてください。予算もポストもいらない、余計なことも言いません。私は研究を静かに地道にやります」という人も増えています。その場合、負担が大きい国立大学よりも、もう少し楽な大学に移っていくということも起こってくる。これが現状なんです。
3. 大学の死、大学の再生
いまお話しした大学の困難な現状を歴史のなかで見直してみたいと思います。「大学の死と再生」ということです。世界で一番古い大学はどこでしょうか。世界で一番古い大学はイタリアのボローニャ大学ですね。ボローニャ大学が創立されたのは1158年。東京大学とか慶應義塾大学など日本で一番伝統がある大学でも創立140年〜150年ぐらい。自分たちとしてはそれなりに伝統はあると思っているのですが、ヨーロッパには創立400年とか500年を迎える大学はざらにありますので、ヨーロッパに行くと日本の大学はまったくの新参者です。
1158年頃、日本では保元・平治の乱とかが起こっていた平安末期の時代に、ヨーロッパではもう大学があったんです。ただ、それがそのままいまの大学に発展したわけではありません。中世の大学と、その後もう一回復活してくる近代の大学は相当違います。
中世の大学は基本的には旅人たちの協同組合です。10世紀以降中世のヨーロッパでは都市が復活して商業都市のネットワークができてきます。例えば商人とか職人とか聖職者、それから芸人といった色々な人が都市と都市の間を渡り歩くという社会が成立します。そのなかには知識人もいたわけです。たいへんな学識者がどこかの都市に滞在すると、その先生の教えを請おうと学生たちが長い道のり、時間をかけてその先生の元に集まり、そこに一つの学びの場ができます。これをユニバーシティと呼ぶようになりました。ユニバーシティの元の意味は協同組合、だから生協と同じです。つまり生協が元々大学だった、大学が元々生協だった。そんな感じですね。協同組合から出発するんです。なぜ協同組合をつくる必要があったのかというと、迫害される危険が常にあったからです。
言うまでもなくそれぞれの都市には領主、支配層がいました。都市の支配層は学問を高めようとは思っていませんから、そこに集まっている人たちからどうやって税金をとろうかと考え、色々ちょっかいを出そうとするわけですね。それに対して大学側が、「私たちはローマ教皇の、あるいは神聖ローマ帝国の特許状を持っている。直接ローマ教皇や神聖ローマ帝国の皇帝とつながっている特別な存在である。だから私たちはあなたに税金を払う理由はないし、あなたの干渉を受ける必要がない。」と言い張る必要があったのです。これが大学の自治の原点です。ローマ教皇とか神聖ローマ帝国皇帝の絶対的な権威があるから領主層と対抗できるわけです。このユニバーシティは13、14世紀のヨーロッパではたいへん発展します。例えばオックスフォード、あるいはケンブリッジ、プラハ、ウィーン、色々なところに大学が広がってヨーロッパじゅうで大学が学問の中心となり、ヨーロッパ全土でのカリキュラムの統一性とか、ある大学の教授の資格を持つ人は別の大学でも教授資格を持っていると、そういう状況が成立していきます。
しかし、16世紀以降、ヨーロッパじゅうの大学は力を失い、大学は時代遅れになります。デカルトとかパスカルといった教科書に出てくる近代の大思想家、大科学者のなかで大学の教授だった人は本当に僅かです。16 〜18世紀のヨーロッパでは大学教授であることに価値はありませんでした。彼らは自分の権威を大学教授ではなくアカデミーの会員であること、それから古典的な本の著者であることによって証明したのです。つまり、大学の時代からアカデミーと出版の時代に移ってくるわけです。
16世紀以降のヨーロッパの歴史の最大のモーメントの一つと言ってもいいと思うものは、実は出版です。
15世紀の半ばにグーテンベルクは活版印刷を発明します。それまでは筆写ですから、せいぜい何十部しか副本をつくれなかったものが、活版印刷が発明されたことによって一挙にまったく同じ内容の本が何千、何万と刷れるようになってきます。爆発的に知識が複製されていったわけですね。知識に対するアクセシビリティのあり方が全く変わってしまった。そして16世紀のヨーロッパにはそういう出版物があふれていきます。そうすると、それまで学識のある先生の回りに集まってきた旅人たちが、長い旅に時間をかけるぐらいなら印刷されたものを買い集めて自分の書庫をつくった方が手っとり早いということになるわけです。コペルニクスの人生が非常にこれをよくあらわしています。
コペルニクスはポーランドの人ですが、彼の前半生は、ボローニャ大学とかパドヴァ大学とか、イタリアまで来て大学を渡り歩いているんですね。そこで彼は医学、法学や神学を勉強して学位をとっています。でも彼の後半生はポーランドのクラクフにこもって地動説を発見します。なぜそれができたのかというと、出版があったからです。出版のおかげで天文学的なデータをたくさん集めることができた。印刷物を比較参照していくと、どうもどう考えても天動説が間違っていて地動説という結論にいきつかざるをえないということを彼は発見してしまうんですね。ですからコペルニクス的転回というのは、大学の時代から出版の時代への大転換でもあったわけです。
そして19世紀の初頭、時代遅れの大学の状況をフンボルトがひっくり返していきます。フンボルトは「これまでの大学はすでにある知識を教授が学生に伝授するだけの場になっている、それではだめだ」と。そして“研究と教育の一致"ということを考えます。つまり「大学という場は、単に確立している知識を学生たちが学ぶということではなく、先生と学生が一緒になって知識を生み出す場にならなければいけない。そのためには文系は先生と学生が議論するゼミ、それから理系はラボ(実験室)、そのゼミとラボが大学の中核にならなくてはいけない」とドイツのベルリン大学で改革を行います。これが大成功して、その後19世紀を通じてドイツは大学のトップに立つんですね。アメリカのハーバードとかイェールとかプリンストンを出た学生たちも、高度な知識を身につけるならドイツへ留学しなければならないと考えていました。ここからフンボルト型のドイツの大学が、ヨーロッパ全体からアメリカまで広まっていきます。
なぜこれが可能になったのかというと、新しい権力の枠組みをベースにした新しい知の体制が抬頭していたからです。19世紀の新しい枠組みとは、いわゆる国民国家です。ドイツとかフランスとかイギリスとか日本が、ベルリン大学とかパリ大学とか、日本の場合は東京帝国大学とか京都帝国大学とかを国家が支援するという体制ができ、非常に高いレベルの学識が出てきました。
さて、21世紀以降、私たちはどういう時代に立ち至っているのでしょうか。社会はグローバルな、またデジタル的な知識で情報爆発を迎えています。知識にアクセスするのはグーグルとかウィキペディアで十分となると、もはや本もいらなければ大学もいらないということになりかねない。もう一回大学は死ぬのでしょうか。
4.出版の爆発 出版の危機
すでにお話ししたように出版の一度目の革命はグーテンベルクによる印刷革命です。日本もそうですが、それ以前は基本的に知識は秘伝されるものでした。秘伝というのは訓練を受けた特別な人だけに伝えられていくという仕方です。このあり方を活版印刷、つまり出版というメディアは変えたんですね。同じ情報を何千何万と刷れるわけですから、秘伝の時代から知識を公開することによって正確な知識を後の世に伝えようという時代に変わっていったわけです。これは16世紀のことです。そしてそれを前提に宗教改革とか科学革命とか、国語(フランス語、日本語、ドイツ語など)の成立など色々なことが起こります。したがって印刷、出版は近代という時代をつくる基盤となったのです。
そしてこれは、20世紀まで続きました。16 〜18世紀にかけては出版産業が発展します。出版が発展することによって、読者市場というものができます。19世紀になるとさらに新聞産業が発展します。そして20世紀になると新聞に加えてラジオとかテレビといった放送産業が発展していきます。同じ情報を莫大な人々に向けて伝えていきました。ところが、20世紀末あるいは21世紀初頭、私たちはこうしたマスメディア社会からネット社会に変化しようとしています。いわゆるマスメディアの時代が終わりつつあって、携帯モバイルで情報に接し、誰もが情報を発信するようなネット社会です。
では、それによって私たちは賢くなっているのでしょうか。10年ぐらい前までなら多くの人が、「ネット社会の方が賢くなる」という意見を持っていたと思います。しかし昨年の色々な出来事を見ると、そうも言えません。ネット社会になって、ポスト真実、嘘か本当か分からないような情報がたくさん流布して、私たちは賢くなっているとは言えないのではないか、ということにようやく気づきはじめてきました。メディアの誕生によって15 〜16世紀に印刷革命がおこり、いま、情報爆発が起こってデジタル革命。このデジタル革命のなかで私たちはどうすれば賢くなるのかということがいまだに分かっていない、これがいまの状況です。
ここで大学と出版の関係が問題になってきます。賢くなるためにはなにが必要かというと、どうやっても巨人の肩にまず乗らないと無理です。よく、「私のやっているテーマは先行研究がありませんから、自分で考えます」と言う学生がいます。でも、「それは君が不勉強なだけだ」と忠告します。「どんなにユニークなテーマでも必ず先行研究があって、先人の学びから吸収してそれを乗り越えるというスタイルをとらないかぎり学びはない」のです。
▲ Profile
1. 「文系学部の廃止」報道の虚実
2. 大学の現在
3. 大学の死、大学の再生
4. 出版の爆発 出版の危機
5. 「文系」は、役に立つ
6. 大学のゆくえ 本のゆくえ— 脱甲殻類社会への指針


