講演録
「大学のゆくえ 本のゆくえ 〜長く広い歴史のなかで文系知の未来を見通す〜」東京大学教授・ハーバード大学客員教授 吉見俊哉先生 P2
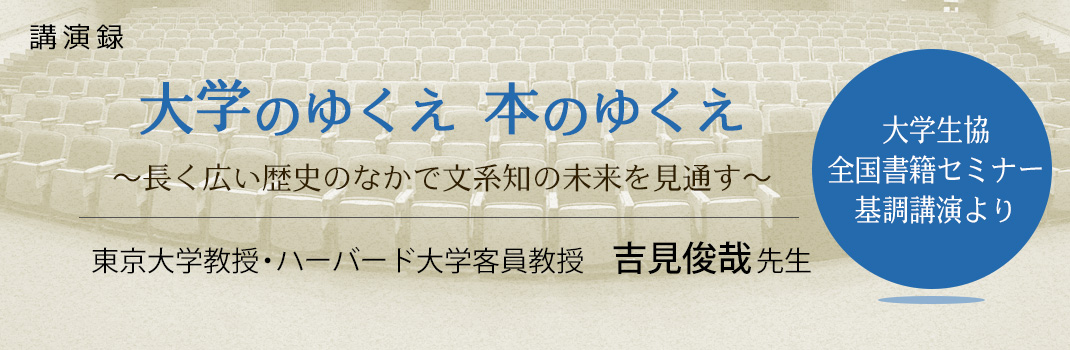
▼ Profile
1. 「文系学部の廃止」報道の虚実
2. 大学の現在
3. 大学の死、大学の再生
4. 出版の爆発 出版の危機
5. 「文系」は、役に立つ
6. 大学のゆくえ 本のゆくえ— 脱甲殻類社会への指針
5.「文系」は、役に立つ
2年前に文系学部廃止の報道で世の中が大騒ぎになったとき、文系の先生方のなかには「自分がやっている学問なんか役に立たない、だけど大切なんだ」とおっしゃる方が結構いらっしゃいました。この論理は、私には非常に違和感がありました。そうではなく、「文系は役に立つ」と言いきる必要があると私は思っています。「役に立つ」とはどういうことか、それは、二種類の意味があります。一つは目的に対する手段として「役に立つ」ということです。東京から大阪に行くまでにどの手段が一番速いかとか、高さ何メートルの建物を建てるのにどういう工法が一番良いかとか、その目的を遂行するのに一番「役に立つ」……これを「目的遂行的」(あるいは「手段的有用性」)と言っておきましょう。しかし、役に立つということにはもう一つの意味があります。それは目的・価値を創出することによって「役に立つ」という「価値創造的」な役立ちです。手段的有用性は当然ながら与えられた目的に対してしか「役に立つ」ことができません。ところが社会が一番大切だと思う価値や目的が変わってしまうと、それは途端に役に立たなくなるわけです。そして実際に過去の歴史を振り返ってみると、社会の価値尺度がドラスティックに変わってきたということを確認することができます。
例えば1960年代と2010年代のみなさんが持っている価値の軸は違います。ちょっと話が飛ぶかもしれませんが、2020年の東京オリンピックが決定したときには多くの人が喜びました。東北の震災復興と連動すれば、オリンピックを日本で開催するのはいいことなのではないかと世界中が思った。でも、そのあと全然うまくいっていません。
どうしてうまくいかないのか、それは1964年の東京オリンピックの成功体験を引きずりすぎていて、そこからの価値転換ができていないからです。
1960年代というのは日本の経済が右肩上がりでどんどんどんどん成長していった時代です。ですから1964年のオリンピックのスローガンは「より速く、より高く、より強く」でした。この言葉をみんなが求めていたんです。でもいまの時代、それが社会全体の合意にはなりえないですよね。そこから脱却して違う価値を考えていかなければいけないのに、それができていないということが問題なのです。
2010年代の社会でいえば「より愉しく、よりしなやかに、より末永く」。「愉しく」というクオリティーの問題、「しなやかに」はレジリエンス、「末永く」というのはもちろんサステナビリティの問題です。社会の価値は50年も経つと大きく変わっているんですね。手段的な有用性だけではやっぱりだめなんですね。それでは常に後追いしかできない。もうひとつの「役に立つ」は価値的創造、この力が日本はすごく弱いです。
なぜかというと、新しい価値をつくるのはどういうことかをみなさんが分かっていないケースが多いからです。新しい価値がつくられていくためには、多くの人々があたりまえだと思っている前提が否定されなければ不可能です。基本的に違う価値を生むためには、違う価値の世界があることを知っていないといけないのです、知識として。これまでお話ししたように歴史を30年50年100年200年という単位で見ていけば社会の価値が確実に変化していますから、その時代の人たちが生きていた世界というのはいまの私たちが生きている世界とは違う、その違いを認識するためには歴史を学ばなければなりません。
世界を広く見ても、日本と中国、イスラム圏、アフリカ、社会が違えば価値が違いますよね。文化的なバックグラウンドとか社会的な価値の軸の違いというものに敏感であるためには、相手を知っていなくてはいけない。だから文化人類学とか社会学とか色々な文系の学問を通して世の中に違う価値がどう存在して、コミュニケーションをとったり一緒に色々なことをやったりするとき、なにが必要なのかという認識がないといけない。これこそまさに文系の「知」がやってきたことなんですね。
概して、理工系的な学問は目的がすでに与えられて、比較的短い期間で役に立つという成果を得るのには非常に優れているのですが、もっと長く価値の転換を導いたり、価値の転換を理解したりするためには文系の知のほうがより長く役に立つのです。
私たちがあたりまえと思っている文系と理系という区別は、当然のことですが中世の大学のなかにはありません。中世の大学では、一方では「神学」「法学」「医学」他方では「リベラルアーツ」がありました。中世の学問のなかで最も役に立つと思っていた学問は「神学」「法学」「医学」のなかで「神学」です。「医学」は人のために、「法学」は国家のために役に立ちますが、「神学」は神様のために役に立つのです。神様と王様と個人、誰が一番偉いかというと当然神様が一番偉いわけで、神様のために役に立つ「神学」が最も役に立つと思われていたわけです。でもそれとは別に「リベラルアーツ」というものがありました。
このリベラルアーツは「文法学・修辞学・論理学」、それから「代数学・幾何学・天文学・音楽」です。「文法学・論理学・修辞学」はいまで言えば文系に近いですね。しかし「代数学・幾何学・天文学」は明らかに理系ですね。つまり理系と文系両方合わせてリベラルアーツなんです。中世では、このリベラルアーツと神学は区別されていたわけですね。
リベラルアーツはやがて「哲学」という概念になります。哲学って私たちは文系だと思っていますが、理系でもあるんですね。例えばデカルトは立派な哲学者であると同時に数学者でもあります。ライプニッツもそうです。ライプニッツは哲学者であり、同時に微分・積分を考え始めました。ですから彼らのなかには数学と哲学の区別はない、そういう時代でした。
では、いつから文系と理系の区別ができたのでしょうか。それは18世紀末ぐらいからです。産業革命の発展がきっかけでした。産業革命によってエンジニアリング(工学系)がどんどん大きくなっていきました。
それに対して人文・社会科学は一体何ができるのか。19世紀末のマックス・ウェーバーを含めて色々な人が考えました。彼らが出した結論は我々がいまも学ぶに値するもので、要するに人間にとっての価値を考える学問として人文・社会科学はあるのだということを言っています。つまり、単に短期間で役に立つという程度の有用性ならば文系の知が役に立つと言うのは相当苦しい。役に立つということには異なる時間的な尺度があります。比較的短い時間(1年、3年、5年)ならばそう簡単に目的とか価値の基準は変わりませんから、目的遂行的な有用性がいいのかもしれません。しかしもっと長いスパンで価値意識が、あるいは人々の価値の軸の意識が変化するということまで踏み込んで考えようとすると、社会科学とか、人文学といった学問が必要だということです。
6.大学のゆくえ 本のゆくえ— 脱甲殻類社会への指針
いま日本の大学、あるいは出版はどういう困難に直面しているのでしょうか。大学が直面している危機は3つあります。一つは18歳人口の激減です。2017年現在において日本の18歳人口は毎年約120万人です。それが2040年には90万人まで減ると言われています。つまり大量の移民を受け入れない限り、日本の大学の規模も若者たちの規模ももっともっとシュリンクしていきます。これはもう動かせません。そしてグローバルな競争がどんどん激しくなり、新しいネット型の知識産業が色々出てくると、大学のあり方が根本から問われてきます。そして大学が直面している困難のなかで根本的な大きな問題は壁だらけであるということです。縦割りで、流動性が少なすぎる。各分野の壁を越えることを可能にする仕組みが弱すぎるのです。だから壁のなかに学生も教員も多くの社会人も籠ってしまう。入試の壁、就活の壁、学年の壁、学部の壁、言語の壁、私たちの社会はいっぱい色々な壁が取り巻いています。この壁を壊していくにはどうしたらいいのでしょうか。
日本の社会も日本の大学もどちらかというと甲殻類、カニとかエビのように殻で身を守っているんですね。そのような社会はしかし、もう持ちません。なぜならば、グローバル化にせよデジタル社会化にせよ、いまの社会は殻を壊していく力が強く働いている社会です。ではどうしたらいいのでしょう。脊索動物は人類の祖先みたいですが、脊椎という神経組織が通っているんですね。神経系が通ってやがて背骨になっていく。つまり、ここから皮膚は柔らかくして殻を着けずに、しかし骨のある種が産まれてくるんですね。そうして人類の進化まで進んだわけです。実際には甲殻類が脊索動物に進化するわけではありませんが、こういうことを未来の大学においても、未来の出版においても、未来の知識的な世界において私は考えていく必要があると思います。
いくつかの例をお話しします。教育に関して私はずっと「21世紀の宮本武蔵」を養成する必要があると言いつづけています。つまり二刀流ということです。一つの専門だけではなく大学は二つの専門を組み合わせて学ばせる仕組みに変わらなければいけないということです。例えば、コンピュータサイエンスを学ぶ学生が、同時に法学部で知的財産権の勉強をする。あるいは農学部で環境科学を学ぶ学生が、同時に文学部で中国の歴史について勉強する。あるいは、医学部で医学の勉強をしている学生が文学部で哲学とか文学とかそういう勉強をする。これはいずれも非常に意味があると思います。ちなみにこれを一般的には主専攻・副専攻とかダブルメジャーと呼んでいて、国際基督教大学などではすでにこれを実践しています。でも本来、この仕組みは東京大学とか京都大学とか早稲田大学といった大規模総合大学でこそ効果があるのです。
これが進まないのは、教育が学生目線ではなくて教員目線で構成されているからです。でも学生目線で考えたら、あきらかにその方がフレキシビリティーがあり将来のキャリアにつながるわけです。なおかつ、こういう仕組みを導入したら文学部は絶対大人気になると思います。だって、賢い学生だったら哲学も文学もやりたいのですね。歴史も好きな子がいっぱいいます。だから医学とか工学を専攻しながら、もう一つ選ぶことができたら、文学部は大人気ですよ。
もう一つ、日本の大学の問題は18歳ばかり集めていることです。18歳、19歳ばかり集めているから非常に同質的で、しかもこの18歳人口がますます減っていきます。それを変えるためには多様な年齢の人々が大学に入れる仕組みをつくるということです。
私は人々が人生で3回大学に入る社会をつくるべきだと言っています。3回というのは18 〜21歳、30代、そして60歳前後です。30代は人生の半ばで、ひととおりキャリアを修めて次のステップに移ろうというとき。このときに同じ会社で昇進を目指す人がいてもいいのですが、全然違うキャリアにチェンジしようという人がいてもいいと思います。その媒介路として大学が役に立つものにならなくてはいけない。さらに60歳前後は定年を迎えますが、まだまだ15年、20年は仕事ができます。あらたにビジネスを始めてもいいかもしれないし、専門職になってもいいかもしれない。そういう人生を歩むための媒介路に大学がなっていけるということです。
もう一つの可能性として出版との関係が出てきます。大学と同じように21世紀は出版のあり方もすごく変容しています。本のあり方、図書館のあり方、ミュージアムのあり方、教室のあり方、大学のあり方、全部同時並行的に変容しているわけで、これは相互に連関しているわけですね。なにがここで重要なのかというと、ツイッター、フェイスブック、ラインといった色々流れてくる集合知に対して、過去との対話——記録知を重ねるということが必要です。これまで単に本が収蔵されるだけだった図書館は、それだけではなくて様々な記録がアーカイビング可能になってきているということです。そしてそのアーカイブにしている知識は単にまとまった作品が入るというだけではなくて、そのプロセス全体がアーカイブされるようになっています。
そして最後に、出版の行方です。というのは、いま大学に起こっている困難と同じことが出版にも起こってきていると感じるからです。かつての大学は一旦、出版の情報爆発でアクセシビリティが非常に簡単になったときに衰退しました。でももう一回知識を生み出す場として大学は復活してきました。そして今日に至っている。一方で出版も16、17世紀以降は発展してきたという話をこれまでしてきました。でも21世紀では、デジタル技術によってふたたび情報爆発が起こっています。
そしていまや出版も大学もスマホで検索すればすぐに情報がアクセスできるような社会、それどころか最近はネット書店が私に対してしょっちゅう私の本を推薦してきます。私の注文傾向から私に必要な本をネット書店のAIは判断するわけですね。そこまで進んでいる。だから大学でも同じことが起こりますね。勉強の傾向から必要な授業を提案してくれる、こういうeラーニングとかムークを受けてみたらどうですか、と。そうすると実際の大学はいらないのではないかということになりますよね。そうなったときに、いったい大学はなにができるのか、ということです。答えはありませんが、一つだけ言えることは、いま大学に必要なのは研究と教育だけではだめだということです。それに社会的な実践——教員と学生が、例えばゼミとか実験室に閉じこもるのではなくて、社会の現場に出ていって社会的な実践をしながら考えていくということがますます必要になってきているのだと思います。
本も同じことです。いままでだったら図書館にあったり、先生が推薦した本を一生懸命買ってきたりして本を読みました。だけどいまはどんどんAIが顧客の動きを分析して、それぞれに合った情報を提供する。しかもスマホを通してコンテンツを提供するような仕組みになってしまったら、いったい本の存在価値はどこにあるのかと問われてきます。本の場合も、完成品をつくってそれが流通していったらそれでおしまいという時代が終わりつつあるのだと思います。むしろ本をつくるプロセス、本が買われていくプロセス、本を読んで学んでいくプロセスを、一つのプロセスとしてどうオーガナイズしていくのか。そしてそのプロセス全体がどういうふうに商売につながっていくのか、というそのプロセス全体のマネージメントとかオーガニゼーション、組織化ということ全体が未来のその知識産業・教育産業の一つの鍵なのではないかと感じています。
吉見俊哉先生の本
 『大学とは何か』
『大学とは何か』岩波新書/本体860円+税
いま、大学はかつてない困難な時代にある。その危機は何に起因しているのか。これから大学はどの方向へ踏み出すべきなのか。知のメディアとしての大学を、中世ヨーロッパにおける誕生から、近代国家による再生、明治日本への移植と戦後の再編という歴史のなかで捉え直し、大学の理念を再定義する画期的論考。
 『「文系学部廃止」の衝撃』
『「文系学部廃止」の衝撃』集英社新書/本体760円+税
大学は、何に奉仕すべきか? 大学論、メディア論、カルチュラル・スタディーズを牽引してきた著者が、錯綜する議論を整理しつつ、社会の歴史的変化に対応するためには、短期的な答えを出す「理系的な知」より、目的や価値の新たな軸を発見・創造する「文系的な知」こそが役に立つ論拠を提示。実効的な大学改革への道筋を提言する。
 『大予言「歴史の尺度」が示す未来』
『大予言「歴史の尺度」が示す未来』集英社新書/本体840円+税
復興と成長の時代、豊かさと安定の時代、衰退と不安の時代、次は何の時代? 本書では、二五年単位を核として、一五〇年、五〇〇年といった長期の尺度も用いながら、歴史を構造的に捉えていく。この三つの尺度を駆使すれば、今後、世界が辿る道筋が見えてくる。知的興奮に満ちた刺激的な論考!世代史と世界史を架橋する壮大な試み!
P r o f i l e
吉見 俊哉 (よしみ・しゅんや)一九五七年、東京都生まれ。東京大学大学院情報学環教授。同大学副学長、大学総合教育研究センター長などを歴任。社会学、都市論、メディア論、文化研究を主な専門としつつ、日本におけるカルチュラル・スタディーズの発展で中心的な役割を果たす。著書に、『都市のドラマトゥルギー』『博覧会の政治学』『親米と反米』『ポスト戦後社会』『万博と戦後日本』『夢の原子力』『「文系学部廃止」の衝撃』など。
▲ Profile
1. 「文系学部の廃止」報道の虚実
2. 大学の現在
3. 大学の死、大学の再生
4. 出版の爆発 出版の危機
5. 「文系」は、役に立つ
6. 大学のゆくえ 本のゆくえ— 脱甲殻類社会への指針


