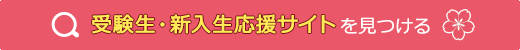- HOME
- 保護者の方へ
- 保護者座談会一覧
- 近畿地区組合員保護者座談会(2024年開催)
- 大学生活には保障も大事
近畿地区組合員保護者座談会(2024年開催)
子どもの意思を尊重しながら進める、受験と大学生活

大学生活には保障も大事
大学生になり、いろんなことが変わっていく中で、どのような備えをされているのかお聞きしたいです。
増田一実さん:
学生総合共済に加入しています。合格後に送られてきた書類の中に案内が入っていて、内容を見て入っておいたほうがいいと思い、早々に加入しました。
稲嶺正一さん:
うちは、私が勤めている会社の組合でファミリーを対象にした共済に加入しています。保障内容を比較した上で、病気・ケガ・自転車の事故など賠償責任もカバーできていて十分だと感じました。
南部美穂さん:
大学生協ではなく、宅配のほうの生協でコープ共済のたすけあいジュニアコースにすでに加入していて、子どもが小さいときから入れています。保障内容も問題なく、大学入学の際に見直して手続きをしました。
学生総合共済に関しては、大学生協が主催する説明会の中で紹介していますが、お聞きになったことはありますか。

増田一実さん:
立命館大学では「プレ・エントランスデー」というイベントがあり、子どもと保護者と別々の会場での説明のときに聞いたと思います。
稲嶺正一さん:
2年半ほど前の話ですが、Zoom説明会の中で説明されていたと思います。
南部美穂さん:
息子が学生を対象とした大学生協のZoom説明会を受けるということで、リビングで視聴している際に耳にしました。
CO・OP学生総合共済とは?
授業のデジタル活用状況とパソコンの購入の仕方
増田実玖さん:
私は先輩とのつながりがあったので、大学に行ったらパソコンを使ったり、iPadでメモを取ったりするという認識はありました。高校ではiPadが生徒一人ひとりに支給されていたので、それを使って勉強するんじゃないかなと思っていました。
稲嶺一廉さん:
メモや資料作成もすべてパソコンで終わらせてしまうのが、大学の授業の受け方なのかなとイメージしていました。
南部悠樹さん:
うちは3歳上の姉がいて、大学でiPadを使ってノートを取ったり、レポートの作成もiPadを使用していると聞いていました。自分も高校のときからiPadに触れる機会が多く、パソコンはあまり得意ではないので、大学に入ってもiPadを有効活用していくのかなと思っていました。
増田実玖さん:
高校の情報の授業では、Word・Excel・PowerPointを事細かくやっていました。ルーラーの出し方やExcelの関数の使い方、PowerPointのアニメーションや図形、オブジェクト作成など、手厚い授業です。全員ではないですが、早期合格者の人がPowerPointで「これから大学に入るにあたって、どういう学びをしていくか」をまとめてオンライン発表という機会もありました。
大学に進学してから「パソコンスキル講座」があったのですが、「高校で習った範囲だな」と思うぐらい、大学で使える知識を教えてもらいました。
稲嶺一廉さん:
うちの高校の情報の授業は、半分が座学で半分が実習でした。座学は、「ギガバイト、テラバイトとは?」や情報リテラシーなど、教科書の導入的な内容です。実習はPowerPointだけですが、基本操作を教わり実際にスライドを作って発表も行いました。
南部悠樹さん:
高校2年生のときに、情報の授業が週に1~2時間程度ありました。ただ、パソコンを与えられた男子高校生がゲームをやっているだけの時間という感じで…。授業で得られたものはあまりありません。
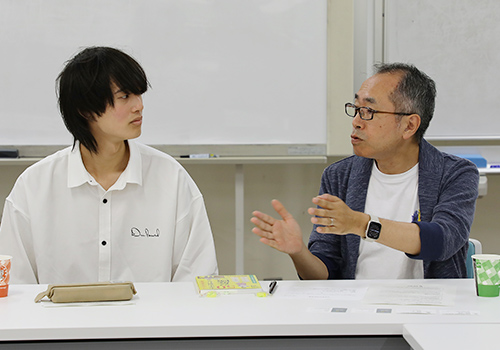
稲嶺一廉さん:
同志社大学では、1年生後期にMOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)でやるような内容の授業があり、そこでやっとスキルが身に付きました。その授業を受けていない1回生前期では、Word・Excel・PowerPointの使い方を知らない状態だったので、レポートや資料作成は苦労しました。
南部悠樹さん:
入学したばかりなので、一つひとつ調べながら何とかやっている状況です。もう少し高校のときにやっておけば良かったなと思っています。
南部悠樹さん:
パソコンとiPadの両方を使っています。自分はiPadのほうが慣れていて、だいたいのことはiPadでやり、課題や文章をたくさん書くようなときはパソコンを使っています。周りも8割方はiPadとパソコンのどちらも使っている印象で、ノートを取るのはiPad、課題はパソコンが多いですね。授業中に資料を見ながら何か書きたいときは、パソコンで資料を見てiPadで書く、という使い方もしています。
増田実玖さん:
私が所属している立命館大学 産業社会学部では、1年生の春だけ必修で「情報リテラシー」という授業がありました。パソコンルームで一人1台パソコンを使い、課題は家で自分のパソコンを使って行います。
それ以降で情報リテラシーやWord・Excelなどについて学びたい人は、「情報リテラシーⅡ」を選択することになります。
稲嶺一廉さん:
自分は同志社大学 経済学部なのですが、商学部と一緒にパソコンの使い方、特にWord・Excel・PowerPointを中心に教わる授業が1年生の秋か2年生の春に取れるようになっていました。あくまでも選択で必修ではなかったです。
南部悠樹さん:
京都大学 総合人間学部では必修の情報の科目はなく、選択で「情報基礎」がありました。私は選択していないのですが、Word・Excel・プログラミングなどについて扱っているようです。
増田実玖さん:
私の学年では、高校1年生のときから一人1台iPadが支給されました。私が中学3年生だったとき、中学1年生は入学と同時にiPadが支給され、学年によってiPadを渡されるタイミングが違いました。
増田一実さん:
タイミングの違いは、おそらくコロナ禍で学校に行けなくなったのが理由だと思います。本来は高校生からの支給のところ、中高一貫校ということで全員に支給して自宅で授業が受けられるように、という学校側の配慮だったと思います。
増田実玖さん:
はい。「Google Classroom」や「Classi」という2つのアプリで、国語や数学など授業単位の連絡はGoogle Classroomから、学校全体の学年便りや生徒会便りはClassiから来ていました。iPadが導入されてから、紙媒体の配布物は圧倒的に少なくなったと思います。
増田実玖さん:
担当の先生によります。紙での提出の先生もいれば、iPadを使いこなしている先生は「Google Classroomにファイル添付して提出してね」という提出の仕方でした。
稲嶺一廉さん:
自分の学校では端末の提供はなく、ずっと紙媒体で連絡は行われていました。
南部悠樹さん:
自分の学校では、情報の授業の間だけ一人1台パソコンが貸し出されていました。iPadは高校3年生のときに一つ下の学年から貸し出されることになり、自分は学校から貸し出されたことはありません。
中学3年生の1学期にコロナ禍で休校になっていたのですが、そのときは授業や課題提出がGoogle Classroomで行われていました。そのときも「各自用意してください」と言われ、学校から貸し出されることはなかったです。
増田一実さん:
家電量販店で購入しました。大学生協のサポートは手厚くすごく迷いましたが、家族全員で引っ越すので「困ったことがあっても家電量販店に行けばいいよね」ということで。子どもだけでなら大学内で完結したほうがいいのですが、うちは特殊なケースだと思います。
稲嶺正一さん:
ネット通販で購入しました。私自身パソコンが好きで、海外メーカーのスペックや、いただいたパンフレットに記載のパソコンのスペック、学部指定のスペックを見ながら、通販で選びました。大学生協は故障時の保障が特徴的で、パソコン選びに慣れていない場合はそちらで購入したかもしれません。
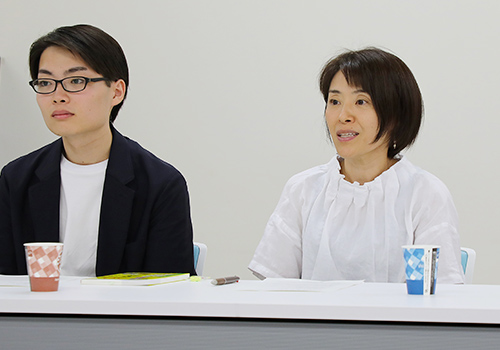
南部美穂さん:
うちは、もともと持っていたパソコンを大学に入ってからも使っていたのですが、どうにも使いにくく、本人から「購入したい」と言われ大学生協で購入しました。大学で使うものは大学仕様になっていたほうがいいですし、パソコントラブルは私では対応できないので、それも含めて任せられる大学生協を選びました。
南部悠樹さん:
大学が始まる前はパソコンをどれぐらい使うかも分からないので、入学のときに買うか少し迷っていました。実際に入ってみて、学校以外でもパソコンを使うことがあったり、バイトでもパソコンを使うこともあったので。パソコンは得意ではなかったので、大学生協で買ったほうが安心かなと思い購入しました。