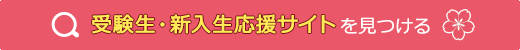- HOME
- 保護者の方へ
- 保護者座談会一覧
- 近畿地区組合員保護者座談会(2024年開催)
- 外国語学習の近況と学習ツール
近畿地区組合員保護者座談会(2024年開催)
子どもの意思を尊重しながら進める、受験と大学生活

外国語学習の近況と学習ツール
増田実玖さん:
私はAO入試でしたが、「英語の習熟度分けのテストがある」という話を先輩から聞いていたので、そのために少しずつ英語を勉強していました。大学に実際に入ってみると本当に習熟度分けで、産業社会学部は5段階で分けられ、個々のレベルに合った学習が行われています。私の聞いた限りの話では、一番上のクラスは英語でディスカッションをしたり、ディベート大会などをしているようで、下のほうのクラスでは基礎的な英語の文法などをやっているようです。
私のクラスは、先生によって授業のやり方が違うのですが、週2日あるうちの一人の先生は「Wordを使って英語で文章を書く」という授業で、レポート作成がメインでした。もう一人の先生は「英語のCMを作ってみよう」と動画編集ソフトなどを使い制作して、こだわったところを発表するという授業でした。高校の授業に比べてすごく楽しかったです。
稲嶺一廉さん:
同志社大学は、単位数は一緒ですがレベルで4段階に分かれます。一番上はかなり難しいと聞くのですが、自分は上から二番目で、受験の英語と比べてそこまで差異がない内容です。授業は2種類に分かれていて、週1回ずつあります。一つは筆記で教科書を中心に、高校でやってきたような授業です。もう一つは英会話を中心にしたリスニング・スピーキングで、先生にもよりますが高校でやってきた授業とあまり変わらない授業も多いです。
南部悠樹さん:
京都大学は、リーディングの授業が週に1コマ、ライティング・リスニングの授業が週に1コマあります。リーディングは日本人の先生が選んだ英語のテキストをみんなで読む形式で、いわゆる受験英語の知識で十分かなという印象です。ライティング・リスニングは、リーディングが40人のクラスなのに対して20人のクラスで、ネイティブの先生が担当をしています。リスニングは授業外での課題になっていて、自分で学習していきます。リスニングも受験の知識で何とかなるレベルで、ライティングに関しても英作文を受験で十分にやったので、今のところ困っていません。
1回生前期の時点では、学力によるクラス分けはなくて、さらに英語を学びたい人は「E2」という授業を選択します。すべて英語で行われる授業で、TOEFLの点数によって1回生の後期から履修資格が取れ、2回生の後期からは誰でも履修できる授業もあります。

増田実玖さん:
私の学部では、英語の授業は1回生だけでした。そのときは、高校のときに配られた『Vintage』という英語の参考書と、スマホアプリ「Duolingo」という英語に限らず外国語を学べるアプリを使って勉強していました。
増田実玖さん:
分からない単語を調べるときに、大学ではスマホで検索をするようになりました。ただ、いろんな英語の翻訳サイトを見ていると少しずつ意味が違っていて、結局どれが正解なのか分からないことがあり、電子辞書を使って意味を調べるほうが良かったのかなと思います。実際、大学に入ってからも電子辞書を使っている友達は「すごく便利だ」と言っていました。
稲嶺一廉さん:
授業の課題として学内サイトから出るものや、外部アプリを使う指定があったため、パソコンやスマホでそのアプリを使って復習することが一番多かったです。アプリも特に問題なく、苦労はあまりありませんでした。
南部悠樹さん:
リーディングに関しては受験期からずっと紙と電子辞書で、紙に書き込みながら読んでいくのに慣れています。iPadでやろうとも考えましたが、慣れたものでやるのがいいと思い、紙と高校で購入した電子辞書を継続しています。電子辞書は、余計な機能がないのがいいところです。スマホでは別のものを見てしまうこともあり、勉強する点においては電子辞書のほうがいいと思い使っています。
リスニングは、京都大学に「GORILLA」というサイトがあり、そこで出された課題を最低限こなす程度です。ライティングは、受験期から英作文の添削にAIを使っていて、「おかしなところを直してください」と指示を出せばすぐに直してくれます。そういう面ではAIやスマホを有効活用していました。
増田実玖さん:
立命館大学はどの学部も共通で第二外国語は6単位分取得する必要があり、学部・学域にもより選べる範囲が違います。産業社会学部は[朝鮮語、中国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語]から選べ、私は朝鮮語を選択しました。
学習する上で、朝鮮語の紙の辞書を買ったり、電子辞書で調べたりはしていません。学校で配布された教科書に掲載された二次元コードから、学校が用意したサイトにログインして、そこで検索していました。
稲嶺一廉さん:
私は中国語を選択しました。同志社大学 経済学部は、基本的に8単位で、2年生の後期までに取る必要があります。学部によっては4単位を1年生までに取り終えるところもあるようです。初めて見るような単語は、教科書の巻末に書いてあったり、教科書内で完結していることが多かったです。それでも分からない部分は、インターネットで検索していました。
南部悠樹さん:
私は中国語を選択しています。他の学部は分かりませんが、京都大学 総合人間学部は英語が必修ではなく、入学時点で[英語、中国語、ロシア語、アラビア語…]と7言語ほどから2~3言語を選びます。ほとんどの人は英語を第一外国語にしていますが、英語を取らず「ロシア語とアラビア語を取る」という人もいました。中国語は、基本的に教科書で完結しています。どうしても分からないときは、図書館に行って辞書を使ったり、スマホで調べたりもするのですが、今のところはそれで困ったことはありません。
大学生活、就活など悩みは尽きない
増田一実さん:
すごく困ったのは入学初日です。入学式で初めて登校する日の朝に、いきなり娘から電話がかかってきて「バスに乗れない!」と言うんです。すぐ車でバス停まで行き、そこから私が送りました。京都は観光客が多くて長蛇の列だったそうで、「これが毎日続くのかな」と不安になりました。今は一つ手前のバス停にずらしたり、図太くなりコツを覚えて問題なく行っています。

稲嶺正一さん:
私が覚えているのは二つです。
一つは通学です。淡路島は電車が走っていないので、息子は電車通学をしたことがありませんでした。事前に下見で電車に乗りましたが、やはり実際の通学時間とは違いがありました。幸い、同志社大学は地下鉄の駅と直結しているのですが、阪急京都線は混むこともあります。
もう一つは授業です。新型コロナの関係もあり、リモートとリアルの授業が交互にありました。大学でリモートの授業となったときに学内のWi-Fi環境が悪く「つながらなくて授業を受けられない」となり、慌ててモバイル回線でつないで授業を受けることもあったようです。最初の1~2カ月ぐらいは、授業を受けるのに少し支障が出ることもありました。
南部美穂さん:
うちは一人暮らしを始めてから、学校が始まるまでに時間がなさすぎて。日々こなすことで精いっぱいで、余裕がありませんでした。
増田一実さん:
心配はいろいろありますが、大学から保護者に向けて就職の説明会や、保護者としてどういうふうに見ていてあげたらいいかという講座がありまして、夫と行ってきました。
「今の就職事情は、本当に大変だな」と思っていた矢先に受けた講座でしたが、それでも「親は口出しをせずに見守ってあげてください」という内容で、その通りにしようと考えています。もちろん相談があれば乗りますが、大学受験と同様、本人に任せてみようと思います。
稲嶺正一さん:
うちは3年生になるので、もう就活の時期です。大学進学のときもそうですが、口を出さずに、本人に「やりたいことは何?」と聞いています。公務員試験を受けるということなので、大学生協の学内講習などを利用しています。やはり受験に不安はありますが、見守るしかないと思っています。
南部美穂さん:
うちは1年生で受験が終わったばかりなので、まだ考えられないですね。
増田実玖さん:
来年の3年生の春からはインターンが始まるんだろうなと頭にあるのですが、今までは小学校の教員免許を取っていたこともあり、「自分が今、何に力を入れたいのか」を考える夏休みにしようと思っています。教職以外に幅広く教育関係について見ていくのか、大学生協の学生委員会でやっている広報に力を入れていくのか、悩んでいます。今年の夏休みでそこをしっかり見極めて、3回生から就活に力を入れていこうと考えています。
稲嶺一廉さん:
自分は、市役所職員の行政職として働ければと考えています。街のプロジェクトや問題解決ができるような職員になりたいと思っています。
南部悠樹さん:
自分は、「何か興味を持ってやれることを見つけたい」という思いもあって総合人間学部を選んだので、決めつけずにいろんなものに触れてみて、一つでも何か面白いと思えることが見つかればいいと考えています。
何かあったときに頼れる「大学生協」への安心感
増田一実さん:
娘と一緒に住んでいるので、そこまで求めることはないのですが、もし下宿だったらと考えると、寄り添ってもらえる本当にありがたい機関なんだなと感じました。
稲嶺正一さん:
もう30年も前のことですが、私が大学生だった頃に比べ、大学生協の役割も時代に応じて少しずつ変わってきていると思います。その中でも、やはり「安心感」というのでしょうか。インターネットなどを使って自分たちで選べるようになる一方で、「詐欺じゃないのか?」「ちゃんとしたものが提供されるのか?」という不安がある部分を、「大学生協を通じてだったら安心して提供していただける」という安心感があります。パソコンや、公務員試験の学内講習、自動車教習所の斡旋など、安心感をベースにしっかり寄り添っていただけるのは、期待しているところであり、実現していただいているところだと思っています。
南部美穂さん:
私が通っていた大学の生協に比べると、守備範囲がだいぶ広くなったなと感じます。私の頃は、教科書の割引や資格試験の学校の割引、免許の斡旋程度でした。今回、息子が一人暮らしをする上で、インターネットではあまりにも情報が多すぎて、何を信じて何をしたらいいのかわからないところ、「これさえやっておけば」「こっちに行けばいいんだ」という道しるべとなる情報を提供してくださって本当に助かりました。
期待したいのは受験時の宿です。息子の受験のときは満室で泊まれず、ホテル選びには本当に困りました。ホテルから受験に向かう人は多かったので、事前にどういうところに泊まればという情報をもう少し充実していただけると、皆さん嬉しいと思います。
増田実玖さん:
組合員の一人として、共済にせよ、パソコンや保障にせよ、手厚い活動をしている大学生協が自分の通う大学にあることが本当にありがたいと日々、実感しています。食堂でおいしいご飯を食べられるのも、栄養を摂れるのも、パソコンが壊れてもすぐにメンテナンスに出せるのも大学生協があるからで。ケガや病気など、もしもの時に共済金を受け取ることができる保障制度がある大学生協は、本当にありがたいと思います。
大学生協の学生委員会として思うのは、ありがたい制度があるのに、あまり知られていないということです。自分の大学でも、「そんなのあるんだ」と言われることが結構あります。この間、委員会の中で共済の給付事例の報告書に目を通したとき、「『指を切った』でも通院すれば保障される事例があるんだ」ということを知り、まだまだ知らないことがたくさんあります。今回、皆さんから大学生協に対する思いや期待の声を聞き、私たち自身の手で反映していけたらなと思いました。
稲嶺一廉さん:
自分も普段から食堂やコンビニ、学内講座など大学生協の様々なサービスを利用していて、すごくありがたいと思っています。その反面、知らない人もまだまだいると思うので、より多くの人が利用するようになったら嬉しいなと、学生委員会の視点からもすごく感じました。食堂で「人が混雑しすぎて使えない」という声も聞いたりするので、より使いやすくなるといいなと思っています。

南部悠樹さん:
自分は18年間、東京に住んでいたのが、大学進学をきっかけにいきなり京都で一人暮らしでした。右も左も分からない中、大学生協という「何かあったときに頼れる存在」があるのは心の余裕にもなりますし、何かがあったときに頼れればと思っています。食堂やショップはあまり利用しないのですが、京都大学生協の本の品揃えは充実していると思います。授業で先生が言っていた本で、一般的な書店には置いていなくても、大学生協に置いてあることがありました。そこはいつもお世話になっています。
ご参加いただきましてありがとうございました。
2024年8月4日大学生協大阪会館にて開催