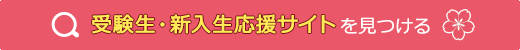全国区組合員保護者座談会(2024年開催)
受験において子どもに任せることと「親のサポート」とは……。
高校生も親も受験で手いっぱいで、合格後に何をすべきかが見落とされがちです。受験方式によっては、合格後から入学までの期間が非常に短い場合も。少しでも不安をなくすためには、早めの準備が必要になります。今回は現役大学生の保護者の方々にお集まりいただき座談会を実施。受験期から入学準備、入学後の生活について振り返っていただきました。

〈参加者〉
- 古川 さつきさん(長男が東京大学1年生)
- 𡈽田 麗さん(長男が早稲田大学1年生)
- 小林 絵美さん(長女が早稲田大学2年生)
受験や進学における親としての不安
古川さつきさん(以下、古川さん):
古川さつきと申します。長男が東京大学の1年生です。
𡈽田麗さん(以下、𡈽田さん):
𡈽田麗と申します。長男が早稲田大学の1年生です。
小林絵美さん(以下、小林さん):
小林絵美と申します。長女が早稲田大学の2年生です。

古川さつきさん
古川さん:
高校が遠方だったので下宿していて、自室で受験勉強をしていました。
𡈽田さん:
高校生のときはすごく自由で、寝っ転がって勉強したり、場所も関係なくやっていました。しかも、「分かっていることをもう一度書きたくない」という理由で、小学校から高校まで課題を一切出さない子どもでした。
親の手続きミスもあり1年間浪人してしまったのですが、浪人時代は予備校に通い、自習室で勉強していました。
小林さん:
娘は福岡の公立高校に通っていたのですが、高校の方針で3年の9月半ばまで行事の運営で忙しく、1学期はほとんど勉強ができない状況でした。このままだと「浪人するだろうな」と覚悟はしていました。
また、高校が国公立中心の指導で、基本的には「私立対策は自分でする」というスタンスでした。
本格的に受験勉強を始めたのは3年の9月頃からで、塾に頼るしかありませんでした。15時半頃に学校が終わり、そこから塾で22時半頃まで勉強して、家に帰ってからは勉強していなかったです。
古川さん:
東京大学だけに絞り、「私立大学も、後期試験も受けない」と言っていて、落ちたら浪人決定なので心配でした。
𡈽田さん:
一度目の入学手続きは夫と息子だけでやるということで、私はノータッチでした。実際に始まってみると二人の間で会話が少なすぎて細かいやりとりができておらず、手続きミスが起きました。入学金は払ったのにその先の手続きを夫がやっていなかったんです。それで浪人することになりました。
予備校では知り合いが一人もいない中、誰とも話さないまま1年間を過ごしたようです。「今年はどうするの?」と問いただすとますます話さなくなってしまうので、こちらで大学の資料を取り寄せ、さりげなく出して「今年は共通テスト利用でどこを受けるの?」などと聞いていました。「地方だっていいのよ」と言ったりもしましたが、「東京から離れたくない」ということで、都内で大学選びをすることになりました。
小林さん:
高校は福岡でしたが、小学校6年までは東京にいたので、娘は「また東京に戻ってきたい」「東京以外は受ける気がない」という強い思いがありました。最初は国立も考えたのですが、学力や勉強時間を考え、「私立大学に絞ろう」と早めに結論が出ました。
高校からの情報も少なく、私立にはどんな受験方式があるのかなど、詳しいことが分からない不安はありました。さらに、コロナ禍だったのでオープンキャンパスがなくなり、実際に見たり、対面で相談ができない不安も。受験期間のホテル予約や長期間一人で過ごせるのか、ホテルから学校までの電車を間違わないかなど、いろいろな不安を抱えていました。
大学の情報の集め方
古川さん:
離れて暮らしていたこともあり、本人に任せていました。高校の先生や友達に聞いたり、大学のパンフレットなどを見ながら情報を集めていたようです。

𡈽田麗さん
𡈽田さん:
受験は、様々な種類、出願の仕方があり難しいです。長男のときは、「親と子がしっかりコミュニケーションを取り、ミスしないようにしましょう」と何度も保護者会で案内がありましたが、夫はそこに参加できていないので一度目のミスが起こりました。
今、受験生の下の子は音楽系志望なのですが、東京の国立は東京藝術大学しかなく、地方の国公立の音大は愛知・沖縄・京都などです。地方の音大の情報が少ない中、東京に集結するフェアに参加したのですが、来ている方が教授で下宿などの入学準備の相談はできませんでした。
小林さん:
うちは東京の私立大学が福岡に集まるフェアに行きました。各大学の職員が来ていて、全体の説明会と個別相談があり、興味がある大学は個別相談もしました。早稲田大学の職員はすごく若いOBだったので生の声を聞くことができ、「どのような受験方式がありますか?」「どこに住むといいですか?」という質問にも答えてくれたので、娘自身もイメージが湧いたようで、行って本当によかったと思っています。
あとは河合塾の「Kei-Net」というサイトに各大学の学部・偏差値・入試情報などが載っていて、サイトを見ながらどの大学・学部を受けるかを調べ、夫とチェックしながら出願スケジュールを立てました。
大学選びに関する親としてのアドバイス
古川さん:
本人に任せていたので、アドバイスはしていません。息子から「こうします」という決定事項の報告があるのみでした。医学部志望から東京大学に変わったのですが、一番上を目指すことだけを決めていたようです。
𡈽田さん:
長男には「国立しかないよ」と言っていて、東京大学を目指していました。結果落ちてしまい、後期で筑波大学を受けて合格したのですが、早稲田大学とすごく悩んでいました。国立後期の発表後1~2日で手続きをすべて行う必要があるのですが、締め切り2時間前ぐらいまで悩んでいました。周りに聞くとみんな「早稲田がいいよ」「理工学部がいいよ」という意見で、長男からは「弟は好きな道を選べて、なんで自分はだめなの?」と言われ、「確かに不公平だな」「もう国立じゃなくてもいいか、親が頑張るか」と腹をくくりました。
小林さん:
うちも特にアドバイスはなく、本人が「行きたい」と言ったところを応援するスタンスでした。
ただ、「一度は実際にキャンパスを見てほしい」と思っていました。
高校2年のときに、コロナ禍で制限がありましたが早稲田大学の予約制の文化祭に奇跡的に直前予約ができたので、娘と二人で行くことにしました。
行く日に都内の私立大学を5~6校を見て回る弾丸ツアーでした。早稲田大学以外はイベントをしていないので、キャンパスを自分たちで回っただけですが、立地やキャンパスの雰囲気を感じ取ることができました。そこで、「やっぱり早稲田に行きたい!」「私はこの大学に来るんだ!」と気持ちが高まったようです。
最初は全然勉強をしていなかったので「無理かな」と感じていましたが、本人が「行きたい!」と言うので否定せず、判定が悪くても「高い目標を持ってもらおう」と思っていたら、最後まで折れずに頑張り切れて合格することができました。子どもに任せていたことと、実際に大学を見に行ってモチベーションが上がったことが良かったのだと思います。

小林絵美さん
小林さん:
周りの友達は「先生になりたい」「医者になりたい」という目標から学部を選んでいたようですが、うちの子は「なんとなくメディア系に興味がある」「社会学が面白そう」とぼんやりしていました。その中で、選択肢が広そうな学部を選ぼうとしていました。今のところ将来もメディア系に進みたいと思っているようです。まだ定まってはいませんが、「勉強は楽しい」と言っているので良い選択だったと思います。
𡈽田さん:
周りには「これをやるためにはこの学部」と決まっている方もいましたが、うちはまったく決まっていなかったです。ただ、「この科目しかやりたくない」という気持ちはあったので、「これができる学部はここしかないよね」「通える範囲だと偏差値的にここだね」と絞っていきました。
下の子は、音楽家として生きていけるかどうか、オーディションで受からないと発表の場がないなど、厳しい社会の縮図の中で生きていくことになります。「音楽家にならなくても、自分は何をしても生きていけるから」と考えているようで、親が応援してくれる大学までは「好きなことをやらせてもらおう」と思っているのかもしれません。
合格が決まってから入学までの不安
古川さん:
一人暮らしが一番心配でした。まずは部屋を決めて、必要な物を購入して。引っ越しまで期間が短く、さらに下の子が二人とも受験生だったので大変でした。
𡈽田さん:
早稲田大学は奨学金の種類がたくさんあるのですが、入学手続きの際に奨学金も申し込む必要があります。提出書類を高校に取りに行く必要があるのですが、締め切りまで残り2時間で「絶対に間に合わない」という状況でした。本来1週間かかる書類を、高校に電話してお願いして、何とか間に合いました。
3月25日頃までバタバタしていて、入学まで残り1週間で必要な物を揃えたり、ガイダンスを確認し始めたり、とにかく時間がありませんでした。
小林さん:
うちは部屋探しが一番不安で、まず大学生協に頼りました。合格発表が遅かったこともあり希望条件に合う部屋は埋まっていたのですが、「1軒おすすめがあります」とZoomでつないでいただけて。ただ、悩んでいる間に他の方に決まってしまいました。あとはもう現地で探すしかなかったのですが、不動産屋と娘が1対1になるのは不安なので夫が休みの日に東京へ行き、娘と二人で回って何とか見つかりました。不安な部屋探しでしたが、大学生協がすごく親切に対応していただいて、成約できれば何万円キャッシュバックなどもあったので、大学生協で本当は決めたかったです。