座・対談
「良い作品は、豊かな時間を与えてくれる」
島田潤一郎さん(夏葉社 代表)P2
島田潤一郎さん プロフィール 著書紹介 サイン本プレゼント
3.「はたらく」ということ
齊藤「はたらく」ということについてもお聞きしたいです。本の中で、自分の仕事をとても好きだと書いてらっしゃったのが印象的でした。抽象的な質問になってしまいますが、島田さんにとって「はたらく」ということはどういうことなのかを教えてください。

島田
僕には小学2年生の娘がいるのですが、彼女はあまり学校行きたがらなくて、よく付き添いで学校に行っているんです。
教室のうしろから観察していると、30人くらいのクラスの中には、当たり前ですが、色々な分野でそれぞれに得意な子がいるんです。走るのが得意な子もいるし、しゃべるのが得意な子、その場を和ませるのが得意な子、いろんな子がいます。一方で、僕の娘のように人としゃべるのがそもそも苦手な子もいる。
そこでどういうことを思うかというと、「得意な人が得意なことをやるのが良い」ということです。みんながみんな同じことをするのではなくて、得意な人が得意なことでまわりの人を助けるというのが、世の中の理想ですね。「やりたいこと」ではなく、何か得意なことで世の中の役に立つのが、良い気がします。
「はたらく」ということは、そういうことであってほしいです。お金儲けや経済を回すということではなくて、得意なことで誰かのサポートをするような。それが仕事になっていてほしいですね。そういう考え方をするようになってから、すごくやる気が出ました。僕は苦手なこともありますが、得意なこともあるので、それで誰かの役に立てたらと思っています。
齊藤
ありがとうございます。自分の仕事のことを幸せそうに語ってくださる大人の方がいると、自分にとっても希望になります。すごくいいですね。
4.力をくれた哲学書
齊藤社会に出る前の5年間、22歳から27歳までの間に色々な本とか出会ってこられたと思いますが、その中で思い出深いものはありますか。
島田
たくさんありすぎるくらいあります。どんな話がいいですか?(笑)
齊藤
辛いときの自分を救ってくれた本があったら、教えていただきたいです。
島田
僕は文学も好きですが、当時読んでいた哲学書が自分の中で大切なものになっていますね。特に、カントの『純粋理性批判』とフーコーの『言葉と物』です。その二作品が、力を与えてくれた気がします。
どんな内容かというと、人間は言葉を通して物事を考えますが、言葉を通して考えられることもあれば、言葉を通して考えられないこともある、ということを言っていると理解しています。
若いときはやはり、「言葉ですべてのものを語れる」と思うわけです。自分のことも、見てきたことも、社会のことも、他国のことも、すべて言葉を通して考えて相手とコミュニケーションできると思っていた。けれども、哲学者たちの著作を読んで「実はそうではないようだ」と学びました。言葉で考えられる範囲は、実はそんなに広くはない、ということを教えてくれて、それは何か逆接的に、すごく力を与えてくれました。
言葉には限界がありますが、限界のあるものを使って、どういう風に考え、どういう風に話して、どういう風にコミュニケーションするのかということになる気がします。
齊藤
夏葉社さんから刊行されている『昔日の客』(関口良雄)と『誕生日のアップルパイ』は、言葉ではないというか、「もの」としての本の部分に、こだわられていると感じましたし、言葉だけではなく、余白をすごく大事にしてくれていると思いました。
島田
そう言ってもらえると嬉しいです。
5.長くて難しい本

島田さんにとって、「学生の頃に読んでおいてよかった」と思う本はありますか。また、『読書のいずみ』の読者である大学生におすすめしたいと思う本がありましたら、ぜひ教えてください。
島田
人生経験が増えていくと、その人生経験の方に重きが置かれるんです。そうすると、その経験が邪魔をして、作者の書いていることが、素直に入ってこなくなります。対照的に、若い時はそれほど経験というものがないから、頭にスッと入ってくる。
そんな時期に読むべきものは、長編作品、それから、難解な作品だと思います。簡単な作品を読むのもいいのですが、長いものや難しいものにどんどんどんどんチャレンジするといいと思います。そういう本は、これから経験が増えていくと読みやすくなるどころか読めなくなるんです。経験がないときの方が素直に読めたりします─専門書はまたちょっと違いますが。
ですから、少し骨のあるもの、たとえば、『失われた時を求めて』や『戦争と平和』、カフカの『城』や『言葉と物』などは、若いときでないと読めないですね。どうして外国文学ばかり挙げるかというと、外国文学の方が読みにくいからです。夏休みのような長期の休みに読むと、忘れられない読書体験になりますよ。
重要なのは、20代の時に読んだ過去の自分が、年を重ねたときの自分を支えるということです。良い小説は、その中に何かメッセージがあるということよりも、何か豊かな時間を与えてくれるものだと思っています。
齊藤
読書が未来の自分を支えるというのは、本当にそうだと思っています。私は未来の自分をあまり想像できないのですが、本を読んでいると、人生はきちんと続いていくんだなと思えます。時間の流れを本で補っている感じがします。
島田
僕も未来のことはよくわからないです。でも最近思うのは、何か未来を語ろうとすると、言葉というものはすごく貧しくなるということです。未来を語る言葉というのは、そんなに選択肢がありません。でも過去を語る言葉というのはすごくたくさんあります。これまで生きてきた自分の過去を、なるべく丁寧な、より良い言葉で語ることが、何か今に繋がるのではないかと思います。
齊藤
本を読むとき、文章を心の中や頭の中で、自分の声で読んでいる気がします。人が過去に書いたものを自分の声で読み直すというのが、結構大事なのかなと思っているのですが。
島田
そうですね、その通りだと思います。重要なのは、自分が作家になったような気持ちで、主体的にその物語を読み直すことですよね。そうすることによって何が変わるかというと、「私」という主体が強く影響を受けるわけです。すると、より良い本を読んだ時に知識が増えるのではなくて、「私」が変わる。
「私」が変わることによってしか理解できないことというのは、たくさんあります。本を読むことは、主体の「私」は変わらず知識だけが増えていくというものではなくて、「私」が強く影響を受けて、かつての「私」では理解できなかったことが分かるようになることだと思います。それは、賢くなったということとは、また少し違う気がします。考えられる範囲が増えたということになるのかもしれませんが、主体が変わらないと、その当事者のことはわかりません。
他国の人たちのことを学ぼうと思ったときに、それを知識として学ぶのか、あたかも自分もその国の人の気持ちになって学ぶのか。それは演技ということではなく、実際に自分がその国の人になったような気持ちになって本を読み、歴史を学んだり、過去の出来事に直面したりするわけです。それはバーチャルというよりは、もう少し根源的なことになりますね。
齊藤
何なら本の内容を覚えていなくても、その本が自分の糧になっていると思います。
島田
そうですね、自分の糧になる本というのは、何か自分という主体に影響を与えるものだと思います。
(取材日:2024年7月18日)
サイン本プレゼント!
.png) 文藝春秋/定価(各)1,980円(税込)
文藝春秋/定価(各)1,980円(税込)
島田さんの著書『長い読書』(みすず書房)のサイン本を5名の方にプレゼントします。
下記Webサイトから感想と必要事項をご記入の上、ご応募ください。
プレゼントの応募は2024年11月5日まで。
当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
プレゼント応募はこちら
対談を終えて
.png)
齊藤ゆずか
ご著書を読んだときから、誠実な言葉の紡ぎ方に惹かれていました。お会いして、島田さんご自身が、自分が大切にしたいものはなにかを意識しながらお仕事をされてきたのだろうと感じました。だからこそ、誰かのために仕事をしたい、とまっすぐに言うことができるのだと思い、そんな気持ちで働けるようになりたいと思いました。夏葉社の本が信頼され、読み手に愛されている理由がわかるインタビューでした。ありがとうございました。
P r o f i l e
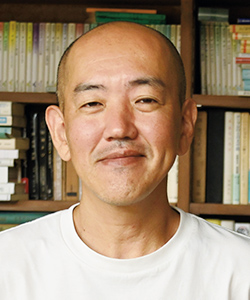
1976年高知県生まれ、東京育ち。日本大学商学部会計学科卒業。アルバイトや派遣社員をしながら小説家を目指す。2009年、出版社「夏葉社」をひとりで設立。「何度も、読み返される本を。」という理念のもと、文学を中心とした出版活動を行う。
●
著書に『あしたから出版社』(ちくま文庫2022)、『古くてあたらしい仕事』(新潮文庫2024)、『90年代の若者たち』(岬書店2019)、『本屋さんしか行きたいとこがない』(同2020)、『父と子の絆』(アルテスパブリッシング2020)、『電車のなかで本を読む』(青春出版社2023)、『長い読書』(みすず書房 2024)がある。島田潤一郎さん プロフィール 著書紹介 サイン本プレゼント


