Report
「オール讀物」(文藝春秋)×「izumi」企画
文芸編集者と語る会
.jpg)

イベントは各日2時間。
- 編集者とはどんな仕事?
- 編集者、出版社に入るために何をしておけばいいか?
- 作家を志す、小説を書く人が聞きたいこと
Zoomのチャット機能も最大限に活用して、話題にあがった本やインタビュー記事などのサイト情報がイベント中に提供されました。
1日目は2年生、2日目は1年生の参加者が多く、両日ともに出版社関係への就職を考えている方が半数を占めていました。また、参加者の中には日頃小説を書かれている方も予想以上に多いことがわかりました。
川田さんと川村さんには2日間でたくさんの質問に答えていただきましたが、誌面の都合ですべてをご紹介することができませんので、印象的だったトピックを抜粋してご紹介していきましょう。

編集者ってどんな仕事?
編集者というと、どうしても多忙な仕事というイメージがあるようですが、「入社してから徹夜は片手で数えるくらい」(川村さん)、「入社一年目で配属された『週刊文春』では初日にいきなり深夜まで働きましたし、『Number』時代は仮眠室を利用しながら三週間くらいぶっ通しで仕事をしていたこともありました。『オール讀物』では、以前は原稿がファックスで送られてくるのを深夜まで待つこともありましたけど、今は技術の進歩でパソコンにデータを転送できるようになったので、ファックスの前で待つ必要もなくなりました。ゲラもPDFでやりとりができるようになったので、徹夜をしてまで仕事をするということは、昔に比べるとないような気がします」(川田さん)。現在「オール讀物」編集部では、前編集長の時代から普通の時間帯に人間らしい生活をするというスタンスでみなさん仕事をするよう心がけているそうです。それでは、みなさんどんな1日を過ごしているのでしょうか。気になりますね。
「今日は取材の立ち会いをして、その後人と会ったり、原稿を読んだり。週末は昨日映画を観に行きましたけれども、次の直木賞に向けた選考作選びももう始まっているので、その本を必死で読んだり、先生方にお手紙を書いたり。人に会っていることが多いですね。10時〜19時のコアタイムのなかでバタバタしています」(川田さん)、「毎日違います。打ち合わせが続いてずっと外にいることもあれば、一日中文学賞の下読みをしていることもあります。一番時間をかけるのはゲラの作業(原稿をいただいて、活字になったゲラに赤字を書きこんでいく)です。コロナ前は、夜いろんな業種の人と会ったりとか同世代と飲んだりとかもしていました」(川村さん)。コロナになって変わったことはたくさんあるようです。作家さん、特に遠方にいる作家さんと会えなくなったこと。また、オンラインのやりとりでは新連載を立ち上げるのが難しく、川田さんが昨年9月に編集長になってからなかなか連載を始められない状態だと言います(3月時点)。「コロナで思うのは雑談の大切さです。原稿を依頼するときも、いろいろな話題を織り交ぜながらじわじわと決まっていくことが多いので、普段作家さんの何気ない雑談に助けられていたなと感じます」(川村さん)
作品づくりにどのくらい関わっているのですかという質問には、「作家さんによります。例えばデビュー間もない方だとあらすじの段階から一緒に詰めていくケースが多いですが、直木賞を受賞されたような、キャリアのある作家さんレベルになると、原稿をお願いしたらあとはほぼ100%の状態のものが届くことが多いので、余程のことがない限り大改稿をお願いすることは、私の経験上まだありません。もちろん『ここは書き足してください』とか、『ここの辻褄が合わないので見直してください』とか、そういう細かいお話はしますが」(川村さん)。
どの作家さんを担当するかは、作家さんのキャリアもあるし、編集者のキャリアもあるので、双方の相性を考慮しながら決まっていくそうです。新人でいきなり大御所の作家さんを担当することもありますが、そこは、「鍛えていただいています」と、川村さん。急ぎの調べ物を頼まれることが多く、「国会図書館に足を運び、ご希望される資料を集め、ということを繰り返していくうちに自然とその作家さんが何を書きたいのか、その方の世界観にだんだんなじんでいきます」。そうやって作家さんと信頼関係を築いていくうちに、編集者が作品の中の登場人物に姿を変えて現れることも実際にあるのです。
作家さんに気持ちよく仕事をしてもらうために、常に気を配ることも大切な仕事です。取材にももちろん同行します。「一緒に編集者が頑張っていかないと原稿が来ないということもあります。同じものの知識を共有したり同じものを取材したりして小説ができていく例はたくさんあります」と、川田さん。直木賞を獲られた大島真寿美さんの『渦』は文楽の話ですが、大島さんと一緒に文楽について初歩的なところから専門家に話を聞き、体験取材をしたりしていくうちに二人とも文楽の沼にハマってしまったといいます。(※1)
「オール讀物」の対談記事や作家インタビュー記事の多くは、編集部員が自分で原稿をまとめているという点にも注目です。インタビューは原稿用紙3枚くらいですが、対談記事は20枚、多いものだと100枚を超えることもあります。他社ではライターがまとめることが多いそうですが、文藝春秋の伝統として社員自らが原稿を書くというのが社風だとか。そう聞くと、「オール讀物」のインタビュー記事もこれまでとは違った視点で読むことができそうですね。
 川村由莉⼦さん
川村由莉⼦さん
編集者への道のり
さて、お二人の話はやがて就活の話題に移っていきます。そもそもお二人が本に関わる仕事を選んだのはなぜでしょう。「文字を扱う仕事がしたかった」とは、川田さん。人にインタビューをして記事を作る仕事がしたかったと話す川田さんは、学生時代バスケットボールに打ち込みプロを目指していましたが、3年生のときに進路変更、マスコミ、ジャーナリズム系を目指します。「ジャーナリズムはテレビもありますが、テレビは画があり音があり、ストーリーが作られています。文字の場合は、読者が過去に経験したことによって読んだときの感じ方が随分変わってくる。それだけ文字は自由度の高いメディアなのではないかと思ったんです。活字離れと言われているけど、文字の可能性はまだまだあるのではないかということで、志望しました」。一方、川村さんは、「大学時代、ゼミを5つハシゴするくらい授業が好きでした。教授と会話できるのがとても楽しかったし、知的好奇心を刺激されていたので、そこから仕事に繋がって新書とか本がつくれたらいいなと思ったのが志望のきっかけです」。入社後、川村さんは最初に「Number」編集部に配属されました。スポーツに全く興味のない川村さんにとっては「つらかった」と言いますが、「編集者は自分の興味に引き寄せることのできる職業です」との言葉の通り、「スポーツ小説は好きです」と言い続けて、「Number」にはスポーツ小説を紹介する連載欄が誕生しました。置かれた場所で自ら花を咲かせるという、素敵なエピソードですね。 川⽥未穂さん
川⽥未穂さん
作家を志している人、小説を書く人に
さて、2日間とも小説を書かれている参加者がとても多く、事前に寄せられた質問だけでなく、当日の直接質問でも、小説を書くことに関しての問いが非常に目立ちました。そのなかで「創作をする人が、自分の書きたいものを書くべきか、あるいは読者のために自分の意思を曲げても書くべきか」という問いに、「自分が書きたいものを書くのが一番いいと思いますが、読者を欲しいか欲しくないかによると思います。商業出版に乗りたいか否かで、ただ自分が書くことを満足させるのであれば書きたいものを書けばいいし、読者が欲しい、或いは商業出版に載せたければ、読者にどういうものが読まれるかということを研究しなければいけないと思っています。読者に届けたいと思っているなら何らかの努力が必要で、それがもしかしたら取材することなのかもしれないし勉強することなのかもしれない、そういう努力をどんな作家さんでもされているという印象があります」(川田さん)。では、文章力をあげるためにはどうしたらいいか……「それは書いて書いて書くしかないし、読んで読んで読むしかないと思います。いいものを読めばいいものを書く力になると思うし、何回も書いていれば、自分の文章のリズムが出てくると思います」。加えて、「原稿をパソコンで書くと文章の入れ替えや上書きが楽にできてしまいますが、すぐに直せてしまうことより正しい文章を書くにはどうしたらいいかということを突き詰めていくことのほうが大事なんじゃないかなと思います」とアドバイスしていただきました。
参加者自身が書いた小説の内容について具体的な相談もいくつかありました。繰り返し2人が伝えたのは、「編集者でなくても、友達とかに読んでもらって、意見をもらうと作品のいいところや欠点が見えてくると思います」と。
作家としてデビューするにはいろいろな方法がありますが、公募新人賞について見てみましょう。
文藝春秋が関わる新人賞には「オール讀物」新人賞(エンタメ)(※2)、「文學界」新人賞(純文学)(※3)、松本清張賞(※4)という3つの新人賞があります。新人賞受賞者には編集者が付き、自分の作品について今後の指針を一緒に考えてくれるというメリットがあります。新人賞を逃したものの、今後絶対に書いて欲しいということも往々にあるとか。応募作を本当に読んでいるのか? という疑問も少なからずあるようですが、川田さんによると、「編集者にとって新人賞は宝の山なので、応募作品は一生懸命読んでいます。ただ、どんなに応募しても引っかからない場合はカテゴリーエラーの場合もあるので、賞を研究して応募されることをおすすめします」。
ちなみに、新人賞に応募されるときに内容以外に次のことにお気をつけください。 ①文字立て——推奨されている形式で提出してほしい。 ②あらすじにも気を配ってください。→「自分で書いた小説なのに、きちんと要約されず文章として成立していないものが頻繁にあるので、それはとても残念です。結末が書いてあっても構いません」(川村さん)。
文藝春秋では、新人賞に応募する人のために次のようなサイトを作っています。どの新人賞にも通用するので、ぜひご覧ください。
お二人の今後の目標も語っていただきました。
「作家の皆さまにもいろいろ目標があって、文学賞をとりたいとか、『オール讀物』に作品を載せたいという人もいるので、作家さんそれぞれの希望や夢を叶えるにあたって、自分が最大限伴走できればいいなと思います。
その先に売れたり、世の中で話題になったりとか、そういうふうになれば一番うれしい」(川村さん)
「会社員として部員をあずかる立場でもあるので、編集者を育てるということにかかわっていきたい。また、今回のようにイベントを開くことで若い人たちに編集者の仕事や本に興味を持ってもらい、また、読者を育てていくということも仕事ではないかと考えています。そんな中で、高校生直木賞(※5)を開催したり、大学生や高校生が作家の方の話を聞けるイベントもやったりしたいなと思っています。ほかにも書店に働きかけて、読書をする人を増やしていきたいです」(川田さん)
このほか直木賞選考会にも関わる「オール讀物」編集部のみなさんの、直木賞の最終候補作を6作品に絞るまでの過程や選考会エピソード、編集者の本音なども飛び出し、参加者にとっては有意義な時間となりました。
参加者からは、「編集者のことだけではなく、文章を書くとはどういうことなのかということや、本を読むとはどういうことなのかを改めて考える良い機会となりました」(2年生)、「作家さんを第一に考えて二人三脚で作りあげているのだなと改めて思いました」(3年生)などたくさんの感想が寄せられました。
今回ご参加いただいたみなさん、文藝春秋の川田さん、川村さん、「オール讀物」編集部の皆様、開催にあたってご協力いただいた皆様、どうもありがとうございました。

● 編集者プロフィール ●
川田未穂(かわた・みほ)
早稲田大学人間科学部スポーツ学科卒。
1995年入社、「週刊文春」「Number」などを経て現在「オール讀物」編集長。
馳星周『少年と犬』、川越宗一『熱源』、大島真寿美『渦』などの直木賞受賞作ほか担当多数。
早稲田大学人間科学部スポーツ学科卒。
1995年入社、「週刊文春」「Number」などを経て現在「オール讀物」編集長。
馳星周『少年と犬』、川越宗一『熱源』、大島真寿美『渦』などの直木賞受賞作ほか担当多数。
川村由莉子(かわむら・ゆりこ)
早稲田大学文学部仏文学科卒。
2017年入社、「Number」を経て「オール讀物」編集部。
阿部智里、北村薫、今野敏、堂場瞬一らを現在担当。
早稲田大学文学部仏文学科卒。
2017年入社、「Number」を経て「オール讀物」編集部。
阿部智里、北村薫、今野敏、堂場瞬一らを現在担当。
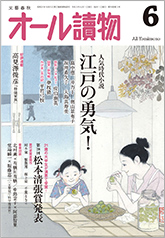
昭和5年の創刊以来90年の歴史を数え、新人賞では西村京太郎氏、赤川次郎氏、宮部みゆき氏、門井慶喜氏、木下昌輝氏、柚木麻子氏ら数多くのベストセラー作家を輩出してきた。また『陰陽師』『探偵ガリレオ』『池袋ウエストゲートパーク』など、話題の映像化作品の原作も掲載してきた日本一のエンターティメント総合誌。
「オール讀物」バックナンバー
「オール讀物」バックナンバー


