2021年のマイベスト
『読書のいずみ』委員・読者スタッフ
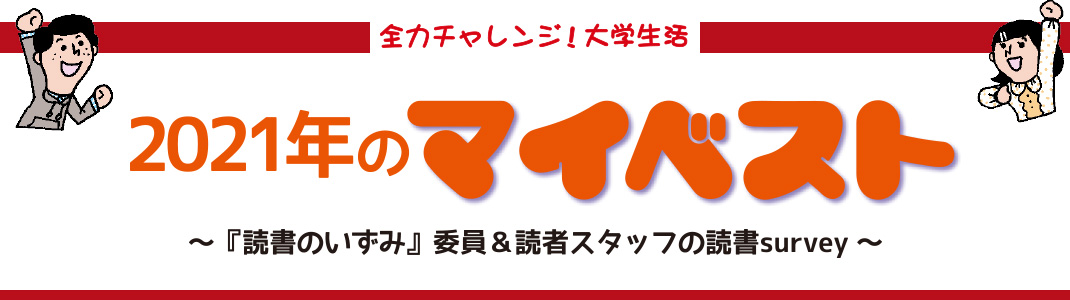
A…2021年に読んだ本ベスト3
B…2021年に読んだ本の冊数
C…お気に入りの読書スペース
D…今年挑戦してみたいこと
-
北海道大学 沼崎麻子/読者スタッフ
A
①新川和江
『新川和江詩集』(思潮社 現代詩文庫) 大人の恋愛や海外の風景など、教科書や子ども向けの詩の本のイメージとはまた違った作品が味わえる。印象的なのは「扉」。子育てと仕事の両立に追いつめられる母親の心境の表現に、ホラーのような恐怖と(自分は親の立場でなくても)共感を覚える。
②ジョン・T.カシオポ,ウィリアム・パトリック〈柴田裕之=訳〉
『孤独の科学』(河出文庫) (厳密にいえば年明けてから読了……)孤独は確かに自由であり、自分と向き合える大切な時間。しかし、孤独には美化できない側面が多々あるという現実を、科学的見地から突きつける本書。自粛生活の孤独・孤立は、想像以上に人々を蝕んでいるのではないか。今からでも真剣に向き合い、支援を届けるべき課題なのだと強く感じた。
③鹿目将至〈鳥居りんこ=取材・文〉
『1日誰とも話さなくても大丈夫』(双葉社) 孤独関連でもう一冊。自粛期間中のメンタル不調対策にお世話になった。人とのコミュニケーションの機会がなくてもどう孤独をのりきるか、自身も孤独に悩んだ精神科医が語るからこそ説得力がある。人と関わるのが苦手だけれど孤独・孤立感も辛い、という方への心の応急処置にも。
B 25冊(多読は74冊くらい)/ C 今年の冬(今のところ前半)は寒かったので、温かい場所ならどこでも最高の場所になっていました(もちろん暖房器具は安全に使いましょう)。/ D 部屋を散らかさない。
-
大阪府立大学 福田望琴/読者スタッフ
A
①山本文緒
『プラナリア』(文春文庫) 自分の心情と主人公の心情がまじりあって区別がつかなくなるほど物語に没頭でき、「自分ではない誰かになれる」という読書の楽しさをしみじみ感じられた。
②池澤夏樹
『スティル・ライフ』(中公文庫) 文章がとても美しく、言葉の味わいを楽しむことができた。静謐という言葉がぴったりとあてはまる、静かで穏やかな物語だった。
③TBSラジオ「相談は踊る」編
『ジェーン・スー 相談は踊る』(ポプラ文庫) ラジオ番組から派生した本なので、読みながらラジオを聞いているような不思議な読書体験ができた。番組に寄せられたいろいろな相談が載っているので、悩み事がある時はこの本を読み返して脳内でジェーン・スーさんに相談している。
B 30冊/ C 自宅の座椅子の上/ D ZINEを出版する!
-
京都大学 畠中美雨/読者スタッフ
A
①フリオ・リャマサーレス〈木村栄一=訳〉
『黄色い雨』(河出文庫) 読書日記でも紹介した、崩壊や死を独特の腐敗の甘さに載せて描き切った一冊。スペインの山奥に住む男性の死が近づくにつれ、時間感覚がなくなり、思考が黄色に埋め尽くされるような読書体験が新鮮だった。
②多和田葉子
『かかとを失くして/三人関係/文字移植』(講談社文芸文庫) 現実上の異世界に誘われる感覚に陥った一冊。導かれるままに読み進めて、ふと見渡すと知らないところへ連れてこられている。中編3編なのに、長編を読み終わったような充足感がある。
③萩尾望都
『トーマの心臓』(小学館文庫) 愛を証明するときに死は如何程の価値をもつだろう? そんな問いへのひとつの答えが本作品。愛を示すために命を投げ出したトーマ、そして命を投げ出されたユーリ。彼らギムナジウムの少年たちを通して愛と生死を繋いで問う一冊。
B 32冊/ C 下宿先の座卓、移動中の電車やバス車内/ D ボルダリング
-
京都大学 徳岡柚月/読者スタッフ
A
①森見登美彦
『熱帯』(文春文庫) 読んでいて、今自分がいる世界とはなんなんだろう、と考えずにはいられませんでした。『千一夜物語』が好きな人、不思議な物語が好きな人、旅好きな人に特におすすめしたいです。
②J.K.ローリング〈松岡佑子=訳〉
『ハリー・ポッターシリーズ』(静山社ハリー・ポッター文庫) 心躍る魔法の世界。重厚な世界観。緻密に張られた伏線。そして儚くも堅い仲間たちの絆。いくつで読んでも楽しくて、何度読み返しても新たな気づきや感情に出会える作品だと思います。
③絹田村子
『数字であそぼ。1〜7』(小学館フラワーコミックスα フラワーズ) 絹田ワールド、大好きです! とにかく楽しい! マイペースな登場人物たちがかわいい! 絹田さんの作品を読んでいると、時間の流れがゆったりして、すごく癒やされるし元気をもらえます。『数字であそぼ。』は最新シリーズで、京都の名門・吉田大学を舞台に濃いメンツが繰り広げるドタバタコメディです。数学の楽しさや奥深さも描かれているので、数学が苦手な方も、読んでいくうちに数学好きになっているかも!
B 105冊/ C 自分の部屋/ D 俳句や小説執筆、絵や写真、音楽活動など趣味を深めていきたいです! 状況が落ち着けば、一人旅をしたいです!
-
お茶の水女子大学 木村真央/読者スタッフ
A
①外山滋比古
『思考の整理学』(ちくま文庫) 不朽の名作だな!と思って論文イヤーだった去年は毎日カバンに入れていました。
②珈琲
『ワンダンス』(講談社アフタヌーンKC) ダンス大好き! きっといつか映画化すると思ってます!
③谷川俊太郎
『自選 谷川俊太郎詩集』(岩波文庫) 映画館の帰り、急に詩集が欲しくなって買いました。人生初。自選というのもなんだか良い。
B 20冊/ C 寝る前、布団の中/ D イラストレーターをいじって作品を作ります!
-
津田塾大学 北田あみ/読者スタッフ
A
①山崎ナオコーラ
『美しい距離』(文春文庫) 私もがんで祖父を亡くしたので、共感するところが多かった。特に「近いことが素晴らしく、遠いことは悲しいなんて、思い込みかもしれない」というフレーズが心に残った。
②俵万智
『未来のサイズ』(角川文化振興財団) 俵万智展に行ったことがきっかけで、初めて、歌集というものを買った。たった三十一文字、されど三十一文字。短歌ビギナーでもすんなり入っていけるのが俵万智さんの短歌だと思う。
③ブレイディみかこ
『他者の靴を履く』(文藝春秋) 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』で話題になった「エンパシー」について深掘りしていて、私自身の思い込みや、ものの見方に対する気づきを与えてくれた本だった。
B 15冊/ C 移動中の電車内/ D 自分の思いを何らかの形にして発信できたらいいな、と思っています。
-
横浜国立大学 田中 匠/読者スタッフ
A
①道尾秀介
『いけない』(文藝春秋) 読んでいて背筋がゾッとするような不気味な感覚に襲われた。ミステリーとホラーのバランスが非常に優れた作品。
②奥田英朗
『空中ブランコ』(文春文庫) 「伊良部一郎」というキャラクターが強烈に印象に残った。彼のもとを訪れる患者たちと織りなす物語が抱腹絶倒で、読んでいて嫌なことを忘れることができた。
③宇佐見りん
『推し、燃ゆ』(河出書房新社) 芥川賞受賞作の中でも読みやすく、すっと頭に入ってきた。自分にも「推し」がいたら、と想像しながら読むとさらに楽しく読むことができた。
B 51冊/ C 自分のベッドの上/ D 本を読むばかりでなく、書く方にも挑戦したいです。
-
金沢大学 光野康平/読者スタッフ
A
①姫野カオルコ
『彼女は頭が悪いから』(文春文庫) 2021年、内容を思い出しては考え込むことの回数が一番多かった作品。
②佐藤学、上野千鶴子、内田樹
『学問の自由が危ない』(晶文社) 多数決の原理で運営される政治。多数派の声や権力によっても揺るがない物事の真理を追求する学問。文明発展のためには欠かせない両者が一定の距離感を保つことの重要性を知ることができました。
③『ユリイカ11号 2021(第53巻第13号)』(青土社) 小説家、評論家、研究者らによる小説家・綿矢りさの作家性や作品群についての論説がまとめられた一冊です。大学一年で出会い、今も大好きな綿矢りささん。本作を読み終わったときに「四年間ずっと好きでいてよかった〜」と心の底から思いました。
B 50冊/ C バスや電車の中/ D 小説やエッセイといった文章関連の賞に応募する。
-
お茶の水女子大学 川柳琴美/読者スタッフ
A
①阿部智里
『追憶の烏』(文藝春秋) 楽しみと恐怖で、1ヵ月ほど寝かせてようやく読めました。いつかの阿部先生の宣言通り、既刊の意味が全く変わってしまった……。
②よしもとばなな
『TUGUMI』(中公文庫) 『izumi』の企画がきっかけで読み返したら、一つひとつの言葉がとても染みました。2回目だけど、素敵な本に新しく巡り合えた気分です。
③宇佐見りん
『推し、燃ゆ』(河出書房新社) 普段とはちょっと違う、初めて感じる類の共感ができた本でした。身体が重い、あの感じがすごく伝わってきます。
B 25冊/ C 寝る前のベッドの中/ D 物語を巡る旅を友達とする。
-
東京経済大学 内田充俊/読者スタッフ
A
①岡野大嗣
『たやすみなさい』(書肆侃侃房) 反転フラップ式案内表示機と航空障害灯をこよなく愛する現代歌人の短歌集。心が疲れた時に飲むホットココアみたいに、じわりと染み渡る。読む心の滋養。
②ツチヤタカユキ
『前夜』(小学館) 「結果を出せなかった真夜中。自分を責め続けて朝が来る。」そんな帯に視線が吸い寄せられて、気がついたらレジに向かっていた。共感できたから。何か成し遂げたいのに失敗続きの自分がいる。つらいとき、泣き出したくなるとき、読みたくなる本だ。
③F
『真夜中乙女戦争』(角川文庫) この小説の主人公は、誰よりも真剣に生き、誰よりも真摯に正気を保ったまま発狂する。しかしその狂気は「四月に一つの物語をも期待しないほど、私はまだ完全に人生を諦められてはいなかった。」という言葉に集約できる。
B 365冊/ C 人をダメにするクッションの上/ D 落ち着いた雰囲気がある大人か、さもなくば猫になりたいです。
-
奈良女子大学 高木美沙/読者スタッフ
A
①青木祐子
『これは経費で落ちません! 8』(集英社オレンジ文庫) シリーズの最新刊。ドラマが好きで読み始めたが、小説だとドラマ以降のストーリーも楽しめるので嬉しい!
②朝井リョウ
『ままならないから私とあなた』(文春文庫) 自分に刺さる言葉が多く、価値観を見直すきっかけになった。極端な考えに走らないように気を付けようと思った。
③西加奈子
『夜が明ける』(新潮社) 色々な感情がこんこんと湧き出て、読後もその世界観に浸ってしまうような本だった。
B 40冊/ C ベッド/ D 凝った料理を作る。
-
名古屋大学 瀬野日向子/読者スタッフ
A
①川添愛
『聖者のかけら』(新潮社) 読み始めてすぐ、一気に話に引き込まれました。落ち込んだり、何かに悩んだりしたときに読み返したくなる本です。
②いしいしんじ
『プラネタリウムのふたご』(講談社文庫) 優しく、美しい言葉たちが印象に残っています。童話のように温かい世界観が大好きです。
③アミの会(仮)
『毒殺協奏曲』(PHP文芸文庫) 毒殺がテーマのアンソロジーですが、耽美だったり、少しコミカルだったり、色んなタイプのお話が楽しめます。
B 72冊/ C 自室の窓際/ D 月に10冊本を読む、きのこの野外観察会に参加する。
-
京都大学 齊藤ゆずか/読者スタッフ
A
①阿部智里
『追憶の烏』(文藝春秋) 大好きなシリーズの最新作で、人の姿をとれる烏たちが暮らす「山内」を舞台にした物語。もともと大きかった期待をさらに上回る面白さでした。予想を裏切る展開も、文体の美しさも、描かれる心理描写も私の心をつかんで離さず、大きく揺さぶりました。寄り添うことの難しさ、通じ合えない思いなど、共感できる自分にはっとさせられ、自分の内面を覗かせるような小説だったことも、ベストに選んだ大きな理由です。
②いとうせいこう
『想像ラジオ』(河出文庫) ずっと読みたいと思っていた本。震災で津波にさらわれ、木にひっかかった状態でラジオを届けるDJの軽妙な語り口と、その声が届く人々が抱える思いを描き出します。死者の姿を見つめることで、生きているとはどういうことかが少しずつわかってくる、そんな物語でした。失われたものを忘れようとする必要はなくて、むしろ想像して思い出していけばよいという、これからも大切にしていきたいと思えるメッセージをくれた本でした。
③森達也
『私たちはどこから来て、どこへ行くのか』(ちくま文庫) 映画監督の著者が、人間の進化などを研究する一線の科学者たちと対談していく本。人間はどこから来て、これからどこへ向かうのかという問いは、これから本格的に学問の世界に飛び込んでいこうとするわたしにとってあまりに深淵で、かつ心惹かれる問いでした。ドキュメンタリーを撮ってきた著者は、文章でも自分の思いを率直に吐露していきますが、それこそが、単なるインタビュー本とは呼ばせない奥行きをこの本にもたらしたのだと思います。
B 34冊/ C 自室のベッドの上/ D ファンタジー小説を書きたいです。また、読書の冊数を増やしたくて、1年間で今年の倍の60冊は読みたいなと思います。
-
信州大学 小古井遥香/読者スタッフ
A
①西加奈子
『i』(ポプラ文庫) 世界中のニュースが瞬時に見られる現代において作者が感じていることや伝えたいこと、「愛は存在する」ということに共感できるストーリーになっている。地理的な制約を超えて世界に対する葛藤や希望を伝える小説の力強さを知り、小説に対する愛情を改めて感じられた作品だった。
②宮部みゆき
『荒神』(新潮文庫) 今まで時代小説は読まず嫌いだったのだが、『荒神』を読んで時代小説への偏見が払拭できた。化け物に対峙した時の人々の言動を通じ、登場人物の懸命に生きる姿はもちろんのこと、現代にも通じる葛藤や矜持も汲み取ることができて、大変読み応えがあった。
③岸見一郎、古賀史健
『嫌われる勇気』(ダイヤモンド社) 「すべての悩みは対人関係から来ている」ということや、「トラウマは存在しない」という内容から、自明とされていることを振り返られる内容が刺激的だった。「アドラー心理学」という新しい考え方も、対談形式で書かれているため分かりやすくなっている。
B 30冊/ C 自宅/ D 新人賞への応募
-
早稲田大学 力武麗子/読者スタッフ
A
①有川浩
『塩の街』(角川文庫) 塩害という災害のせいで変わり果てた世界で、普通なら出会わなかったであろう人たちが出会っていくお話です。物語の世界に引き込まれて読後も余韻に浸ってしまいました。
②青山美智子
『木曜日にはココアを』(宝島社文庫) とにかく心があたたかくなるお話でした。小さなことでも、一つひとつの出来事はつながっているのかもしれないと思える作品です。
③飯間浩明
『気持ちを表すことばの辞典』(ナツメ社) 感情や行動に関する言葉がカテゴリごとに紹介されている本です。何となく読んだり使ったりしている言葉の意味を知ることができておもしろいです。
B 21冊/ C 自室、電車/ D 一人旅に行く。
-
京都大学 三好美咲/読者スタッフ
A
①宮野真生子、磯野真穂
『急に具合が悪くなる』(晶文社) 生死について考えずにはいられなくなります。
②ミラン・クンデラ〈千野栄一=訳〉
『存在の耐えられない軽さ』(集英社文庫) 誰かと感想を共有してみたくなります。
③堀辰雄
『風立ちぬ/美しい村』(新潮文庫) 恋人や友人と過ごす時間が愛おしくてたまらなくなります。
B 20冊/ C 理学部のピロティ(風通しが良い)、寮の屋上(日当たりが良い)/ D 早起き
-
東京大学 任 冬桜/いずみ委員
A
①松岡正剛
『17歳のための世界と日本の見方』(春秋社) 世界の宗教や文化の見方をセイゴオ先生が教えてくれる。点と線がつながっていく快感!
②カルミネ・アバーテ〈関口英子=訳〉
『海と山のオムレツ』(新潮クレスト・ブックス) アルバニア系イタリア人作家が思い出深い食べ物と辿る自伝的小説。絶品料理に釣られて読んで、物語を味わって。
③よこみぞゆり
『すみっコぐらし このままでいいんです』(主婦と生活社) ただただ優しさが詰まっている。欠点・弱点があってもそれでいいんです。
B 15冊/ C リビングの日の当たるところ。/ D 中南米文学
-
奈良女子大学 北岸靖子/いずみ委員
A
①一穂ミチ
『スモールワールズ』(講談社) 連作短編集。世の中にはいろんな人がいて、みんなそれぞれ悩みや苦しみを抱えながら懸命に生きているんだな、と痛感しました。
②養老孟司
『「自分」の壁』(新潮新書) 目から鱗がぼろぼろ落ちました。7年以上前に刊行された新書ですが、今でも充分通用すると思います。
③砂原糖子
『心を半分残したままでいる(全3巻)』(新書館ディアプラス文庫) 記憶喪失もののBL小説。フィクションにありがちなご都合主義的展開はなく、しっかり設定から作りこまれていて、はらはらしながら一気に全巻読みました。
B 120冊/ C 布団の中/ D 料理
-
名古屋大学 岩田恵実/いずみ委員
A
①トルストイ〈望月哲男=訳〉
『アンナ・カレーニナ(全4巻)』(光文社古典新訳文庫) アンナの悲劇、リョービン青年の成長、周りの人々の笑えるやりとり、など諸要素のバランスが素晴らしく、一気に読み切れました。
②リルケ〈高安国世=訳〉
『若き詩人への手紙/若き女性への手紙』(新潮文庫) 「孤独」から「愛」が生まれ、創作の原動力になる。いつかドイツ語原文でリルケの流麗な文を読めるようになりたいです。
③ドストエフスキー〈原卓也=訳〉
『賭博者』(新潮文庫) 賭博に狂わされてゆく一族と、愛する人のために賭けに挑む青年の姿に切なくも熱くなる。カジノに行ってみたいなあと思いました(笑)。
B 120冊/ C 電車の中と寝床/ D 長距離ドライブ(他県まで旅行にいきたいです!)
-
慶應義塾大学 戸松立希/いずみ委員
A
①純猥談編集部
『純猥談』(河出書房新社) 1話あたり数頁というショートストーリーなのに、ここまで心を揺さぶられる体験は久しぶりだった……。
②村上春樹
『一人称単数』(文藝春秋) 「謝肉祭」がオススメ。これを読むと、あなたもシューマンの《謝肉祭》が聞きたくなってしまうはず……!
③垣根涼介
『君たちに明日はない』(新潮文庫) 社会人になったらまた読んでみたい。主人公はリストラ面接官という異色の小説だが、ページを繰る手が止まらない。
B 40冊/ C ベッドの上/ D ベンチプレス80kgを持ち上げる!
-
愛媛大学 千羽孝幸/いずみ委員
A
①佐伯梅友・鈴木康之=監修
『文学のための日本語文法 国語教育叢書』(三省堂) 古本を探していた時、ふとタイトルが気になって買った本ですが、大いに衝撃を受けました。国語の授業で学ぶ「文法」は、あまり役にたたないモノと思われがちですが、この本を読むと思いっきり見方が変わると思います。文法は、役に立つ!!
②下村湖人
『論語物語』(講談社学術文庫) 小難しいイメージを持たれがちな論語ですが、この論語物語は全く違った形で論語に出会わせてくれます。何より、下村湖人の論語に対する体系的な理解の深さに、脱帽させられます。古典とはこのような出会い方もあるのだと教わった作品でした。
③長尾真
『「わかる」とは何か』(岩波新書) 初めてこの本を読んだ時、自分があまりに無意識に「わかった」ということばを使っているのだと痛感しました。教育学部に所属しているということもあって、教えるためにも「わかる」とは何かをもっと具体的に掴まなければならないと思わされた本です。
B 約120冊/ C 布団の中/ D フランス語をもう一度勉強し直したいと思っています。


