いずみ委員・スタッフの 読書日記 156号
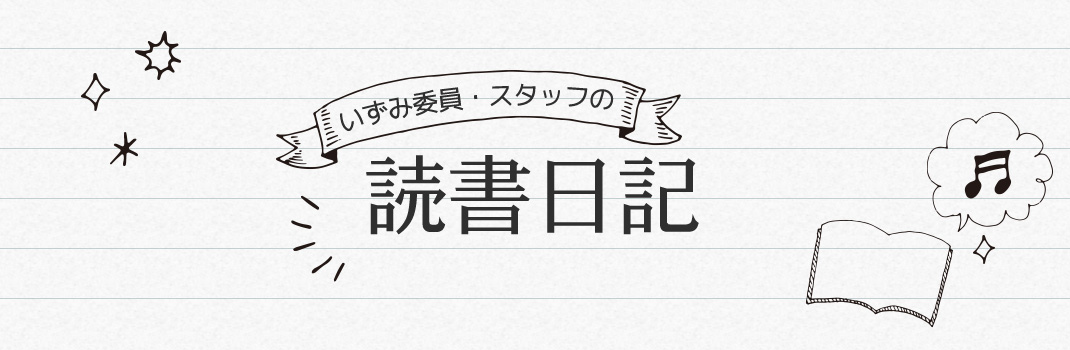
レギュラー企画『読書のいずみ』委員・スタッフの読書エッセイ。本と過ごす日々を綴ります。
筑波大学3年 甲斐いづみ
7月28日
.jpg) 大学生のほとんどがテスト期間であろう7月下旬。テスト勉強からの現実逃避には幾つかの型があるが、私は断然読書派である。それも一度読んだ本をじっくりじっくり味わい返すという流派を誇っている。今日読んだのは谷川俊太郎さんのエッセイ『ひとり暮らし』(新潮文庫)だ。元々は、夏の風物詩「新潮文庫の100冊」キャンペーンの特典であるキュンタしおり欲しさになんとなく買ったものであるが、読み始めるとこれが非常に面白かった。今一度読み返してもやはり素晴らしい。谷川さんは詩人であるが彼の詩は柔らかいと同時に鋭い。エッセイも同じように、淡々と軽妙でありながらハッとさせられる。世界からほんの少し遠いところに身を置いている詩人というものは、日頃からこんなに思索が深いのかと驚くばかりだ。谷川さん独特のちょっとブラックでクスッと笑えるユーモアもいくつも散りばめてあり、久しぶりに「読み終わるのが惜しい」と感じる本であった。
大学生のほとんどがテスト期間であろう7月下旬。テスト勉強からの現実逃避には幾つかの型があるが、私は断然読書派である。それも一度読んだ本をじっくりじっくり味わい返すという流派を誇っている。今日読んだのは谷川俊太郎さんのエッセイ『ひとり暮らし』(新潮文庫)だ。元々は、夏の風物詩「新潮文庫の100冊」キャンペーンの特典であるキュンタしおり欲しさになんとなく買ったものであるが、読み始めるとこれが非常に面白かった。今一度読み返してもやはり素晴らしい。谷川さんは詩人であるが彼の詩は柔らかいと同時に鋭い。エッセイも同じように、淡々と軽妙でありながらハッとさせられる。世界からほんの少し遠いところに身を置いている詩人というものは、日頃からこんなに思索が深いのかと驚くばかりだ。谷川さん独特のちょっとブラックでクスッと笑えるユーモアもいくつも散りばめてあり、久しぶりに「読み終わるのが惜しい」と感じる本であった。
7月30日
 今日は私の21歳のお誕生日である。ハッピーバースデイ to 私というわけだ。友人によると、21歳はとうとう本当に自分で自分の人生を切り盛りしていく重要な年齢らしい。そんな記念すべき日には記念すべき1冊を読むべしとワクワクしながら本屋へ行った。そうして手に取ったのが穂村弘さんの『はじめての短歌』(河出文庫)である。棚の前でパラパラっとめくって「あ、面白い」と思った。最近直感で良いと感じる本に出会えていなかったので即購入し、ケーキもきっちり2つ買って(モンブランとショートケーキにした)ホクホク顔で帰宅した。読んでみるとこの本、短歌の本だが実は短歌の本じゃない。何を言ってるんだと思われるだろう。しかしそうとしか言いようがない。内容としては、一般から集まった良い短歌に対して「改悪例」をつけることで元の短歌の良さを解説するというものだ。この解説も大変面白く、言葉の一文字にこだわることやそこから生まれる絶妙な心の機微を愛したくなる。そしてなんといっても本全体を通して語られる「生きる」と「生き延びる」の違いには考えさせられた。社会で生きていくことは「生き延びる」ことに大変近い。これから私は社会に出ていくだろう。「生きる」こととその楽しみを忘れたくないなと純粋に思った。
今日は私の21歳のお誕生日である。ハッピーバースデイ to 私というわけだ。友人によると、21歳はとうとう本当に自分で自分の人生を切り盛りしていく重要な年齢らしい。そんな記念すべき日には記念すべき1冊を読むべしとワクワクしながら本屋へ行った。そうして手に取ったのが穂村弘さんの『はじめての短歌』(河出文庫)である。棚の前でパラパラっとめくって「あ、面白い」と思った。最近直感で良いと感じる本に出会えていなかったので即購入し、ケーキもきっちり2つ買って(モンブランとショートケーキにした)ホクホク顔で帰宅した。読んでみるとこの本、短歌の本だが実は短歌の本じゃない。何を言ってるんだと思われるだろう。しかしそうとしか言いようがない。内容としては、一般から集まった良い短歌に対して「改悪例」をつけることで元の短歌の良さを解説するというものだ。この解説も大変面白く、言葉の一文字にこだわることやそこから生まれる絶妙な心の機微を愛したくなる。そしてなんといっても本全体を通して語られる「生きる」と「生き延びる」の違いには考えさせられた。社会で生きていくことは「生き延びる」ことに大変近い。これから私は社会に出ていくだろう。「生きる」こととその楽しみを忘れたくないなと純粋に思った。
愛媛大学2回 河本捷太
2015年4月X日
今は、高2の春。たくさん本を読むほうではないが、春なので新たな本と出会いたいと思い図書室で借りた森博嗣さんの『すべてがFになる』(講談社文庫)。久しぶりに本を読んで衝撃を受けた。こんなに面白い本があるのか。数学や物理が好きで理系に進んだが、この本は理系心をくすぐる。主人公が工学部の教授に学生。おまけにほぼ全ての登場人物が理系の人間だ。さらにはミステリィであるこの本のトリックまでもが理系に関するものなのだ。
だがこの本を読んで最も衝撃的だったことは、「天才」の存在に初めて触れたことだった。重要人物である「真賀田四季」は作中で何度も「天才」と称され、彼女の思想は常人には理解しがたいものだった。また、これを書いた森博嗣さんも同様に「天才」だと思った。トリックを知ったときには思わずゾッとした。これまでトリックを知ったときこのような感情になったことがあるだろうか。この本はこれからの人生に大きな影響を及ぼす1冊になる予感がした。

2018年6月Y日
.jpg) 今日なんとなく昔の日記を読み返していた。やはり予感は的中していた。『すべてがFになる』のおかげで読書が趣味となった。またこれにより理系から文転、今は大学生となり文系学部に進学した。高校時代が懐かしい。
今日なんとなく昔の日記を読み返していた。やはり予感は的中していた。『すべてがFになる』のおかげで読書が趣味となった。またこれにより理系から文転、今は大学生となり文系学部に進学した。高校時代が懐かしい。今日読み終わったのはアルベール・カミュの『ペスト』(新潮文庫)。今はこのような文学作品に加え、新書に岩波と難しい本も読むようになったが、高2の春には考えられないことだった。すごい変わったと思う。文学作品が面白いと思えるということは成長したということだろうか。
『ペスト』はカミュの「不条理の哲学」を知ることができる作品で、伝染病であるペストに立ち向かう人々を描いたものだ。登場人物達が討論するシーンが出てくるが、カミュは戦争や死刑制度を例に、死に関わる社会からの不条理に対する考え方や信念を彼らの言葉として語らせており、そこからカミュの思想がうかがえる。カミュの思想は興味深いのでこれからいろいろ調べてみよう。
僕にとって本は自身を成長させてくれるものだ。知識を与えてくれたり、感情を豊かにしてくれたりするからだ。そのことに気づかせてくれたのは高2の春に読んだあの1冊の本であり、それからの生活に本は欠かせないものになった。だから僕はこれからも本を読み続けるだろう。明日はどんな本に出会えるだろうか。

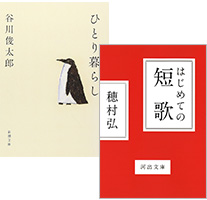 筑波大学3年
筑波大学3年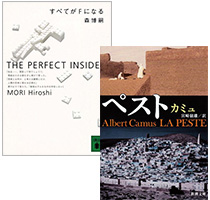 愛媛大学2回
愛媛大学2回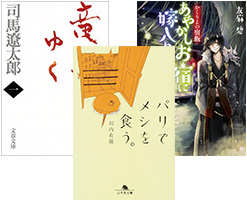 東京外国語大学4年
東京外国語大学4年 埼玉大学3年
埼玉大学3年
