《触》「読んで、触れて、たのしむ本」

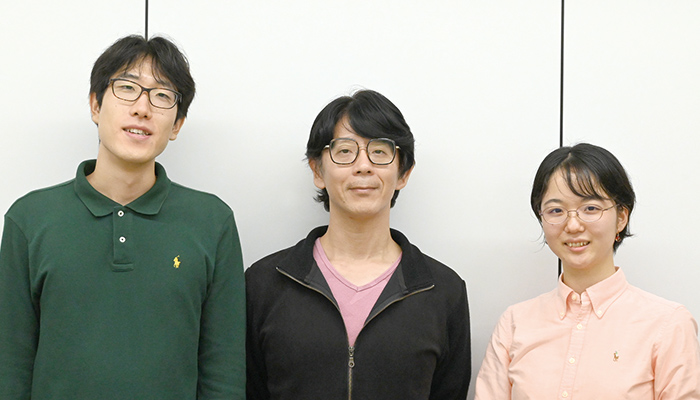
『スピン/Spin』編集長 尾形 龍太郎さん × 高津咲希・木村壮一
新しい雑誌 『スピン/spin』
.jpg) 『スピン/Spin』
『スピン/Spin』
(季刊誌)定価330円(税込) 購入はこちら >2026年に創業140周年を迎える河出書房新社が、そのカウントダウン企画として22年9月に創刊されたオールジャンルの雑誌。ジャンルを超えた執筆陣と、紙の専門商社・株式会社竹尾とのコラボレーションにより毎号表紙と目次の資材(紙)を変えているのが特徴。
高津
『スピン/spin』はどのような雑誌ですか。
尾形
河出書房新社(以下、河出書房)には『文藝』という純文学雑誌があります。でも、エンタメやエッセイなどその他のジャンルのものはなかったんです。河出書房が2026年で140周年を迎えるにあたって、もう一回紙の原点に戻り、どんなジャンルでも入れ込めるような雑誌が出来ないだろうか、と生まれたのが『スピン/spin』(以下『スピン』)という雑誌です。
木村
雑誌の連載や企画はどのように考えていますか。
尾形
連載陣に関しては純文学出身の作家からエンタメ誌で活躍されている作家、さらにはミュージシャンや声優、脚本家など別の肩書をお持ちの書き手まで、ジャンルに偏らないでさまざまな方々に連載をいただいているというのが特徴として面白いと思って決めています。
また、連載だと毎号追っていかないといけないけれど、一号毎に楽しめるページもほしいなと。例えば連載でも「絶版本書店」みたいに、絶版本について色んな人が熱く語るなど、毎号新しい顔で入れ替わりやっていこうというコンセプトで決めています。
高津
〔絶版本書店〕は、「手に入りにくい本だけど、手に入れて読みたい」という、書き手の本への思いが伝わってきます。
尾形
このコーナーから絶版した本が復刊するということがあれば、なお面白いですね。
高津
私は最果タヒさんが色んな方を宝塚歌劇団の公演へ招待するという〔連載往復書簡〕が好きです。この連載はどのように生まれたのですか。
尾形
最果さんに「『スピン』で何かご一緒できませんか?」とご相談したとき、最果さんは宝塚に夢中でいらしたんですね。それで宝塚が大好きな同僚の編集者と何か出来そうだと、最果さんご自身が考えて往復書簡という形になりました。
高津
公演に誘って終わりではなく、観劇後の感想も交わしていて面白いと思いました。
尾形
『スピン』には最果さんの詩の連載もあるのだけど(〔連載詩〕)、連載を始めたきっかけは、ある朝僕がSNSを見ていたら、最果さんが「アニメのキャラクターに捧げるような詩の連載、どこかでやらせてくれないかなー」とつぶやいていて。その瞬間にぜひ『スピン』でやらせていただきたいですとご依頼して実現したんです。
高津
何がきっかけになるかわからないですね。
紙にこだわる

高津
『スピン』は、「紙の過去・現在・未来を考える」プロジェクトを兼ねているということですが、毎号、異なる紙を使用しようと思ったきっかけは何ですか。
尾形
僕は『スピン』を担当する前に『文藝』の編集を20年くらいやっていたのですが、当時は紙を変えるなんて発想はありませんでした。
単行本も担当していたので、デザイナーから「こんな紙を使いたいです」と相談されて製作部に聞くと、「もうその紙は廃版です」ということがよくあった。それでふと『スピン』の製作担当に「毎号、紙って変えちゃダメかな」と聞いたら、「できますよ」となったわけです。もちろん営業部にも確認しました。それで毎号、表紙と目次の紙を全部変えています。例えば、9号の表紙はもう二度と生産されない紙で、目次の紙は新製品なんです。スピンは全部で16号出版されるので、全部で32種類の紙が楽しめる。手触り、あとは匂いもちょっと違うんじゃないかな。せっかく「もの」として雑誌を届けるなら、紙の本を手にする読者に楽しんでもらいたいなと。
木村
僕は雑誌の後ろにある〔紙のなまえ〕というコーナーが好きです。こんな紙があるんだなと。9号の表紙も「クロコダイルの皮革」をイメージした紙と書いてあって、「確かにそういう手ざわりだな」とすごく感動しました。
尾形
全ての紙に名前がある。名付けるということは、それに対しての思いがある。それを知るとちょっとだけ世界が広がるような感じがして。そういう細部にもこだわりたいなと思っています。
高津
〔紙の話〕や〔本の話〕など、本が作られていく過程や技術についての連載もありますよね。
尾形
〔本の話〕では毎回、ブックデザイナーの方々に話を聞くのですが、紙マニアの人が多い。デザインと言っても、ブックデザインはちょっと特殊。彼らが一冊の本をどういう思いで作っているのかを残したいと思っています。
〔紙の話〕は紙の専門商社である竹尾とのコラボ企画で、紙の生産から流通、紙の可能性まで幅広く取り上げています。
高津
私は7号の「箔押し」の話が印象に残っています。記事を読んでから箔押しされたスピンのタイトルを見て、感動しました。
尾形
竹尾さんから箔屋さんに取材をしようと提案いただいたんです。その箔屋さんが帰り際に、「次の号で箔を使ってみませんか」と、その場で言ってくださって。箔見本でもありますよね。箔ってこんな効果があるんだっていう。すごい贅沢な使い方をさせてもらったなと思います。
日常に言葉の栞を

木村
『スピン』のカラフルな表紙が好きなのですが、表紙の絵と言葉は毎号テーマがあるのですか。
尾形
絵と言葉の組み合わせはバラバラです。絵はポール・コックスさんというフランスに住んでいる画家に毎号、描き下ろしていただいています。表紙にはあえて絵のシルエットを、表紙の裏側のページには完成された絵を載せているんです。具体的な絵で惹きつけるのではなく、読者が表紙に描かれたシルエットの絵を見て自由に想像し、表紙の裏の絵と、その絵をなぜ描いたのかという言葉を読むことですべてがわかる。
表紙の言葉は、「日常に言葉の栞を」というこの雑誌の一つのコンセプトとして、雑誌が机の上にあったときに、著者名やタイトルより「言葉」が目に入ってほしいなと思って。
だから「栞」は、いわゆる本に挟み込む栞というよりは、日常の慌ただしい生活の中でふと言葉が入ってきたら、その瞬間、もしかしたら少しだけ、別のことを考えられるかなとか。そういう夢みたいなことを考えながら、色んなジャンルの人に書いてもらいたいと思っています。
木村
確かに。僕は理論系の研究室に所属しているのであまり机から動かないけど、こうやってちょっと言葉があると、ふとした時に休憩したり、現実から逃れたりできるのですごくいいなと思います。
尾形
カバンの中に本が一冊入っていれば、1ページ読むだけでも全然構わない。ネットだとどうしても自分がいつも読んでいるものや知っているものを選びがちじゃないですか。紙の雑誌だったら、たとえば斉藤壮馬のファンの人が皆川博子の文章を読むなど、ふだんは繋がらないような人やものに繋がるのが面白いかな。
紙の本のこれから
高津
紙の本の魅力を知るだけでなく、ウェブの良さや使い方も考えさせられます。
尾形
それはもちろん。だって、絶対にウェブに移行していきますもんね。とりわけ情報という意味では。
紙の原点を考えることは、媒体がウェブに変わっていくこの時代においてウェブの未来も考えることになると思います。ウェブにはない紙の良さがあるけれども、一方でウェブにしかない良さもそこで見えてくる。
高津
今後、紙の本ならではの挑戦や試みで何かできそうなことはありますか。
尾形
『スピン』は330円だけど、やっぱり2000円の単行本ってハードルが高いじゃないですか。でもその2000円で「特別な時間」や「自分だけの一冊」を感じられるようなものを考えていかなくちゃいけないですよね。
高津
私はカバンに本が入っていたり、本棚に本がある空間にいたりするだけでも、本のあたたかさを感じて落ち着く気がします。
尾形
僕も紙の本がすごく好きですが、値段が高くて、スペースをとるのもわかる。でもやっぱり、紙の本って所有している感じや「もの」としてプレゼントする/される喜びがあると思います。「もの」としての本の魅力を皆に伝えて、広げたいですね。
(取材日:2024年10月8日、文=高津咲希)

1975年生まれ。98年河出書房新社入社、営業部に配属。99年6月に編集部に異動し「文藝」編集部に配属。以後2018年まで同部署で雑誌・書籍の編集に携わる(14年~18年は編集長)。2022年9月、オールジャンルの雑誌『スピン/spin』を創刊。
取材を終えて

千葉大学4年生 高津咲希
本の「もの」としての魅力を伝えたい、読者に「特別な時間」を届けたいという尾形さんの思いが印象的でした。『スピン/spin』は私たちの生活にそっと寄り添い、ふとした瞬間に思いがけない作品との出会いを届けてくれるあたたかい雑誌だと感じます。インタビューを通して本作りに携わる方たちの仕事や熱意について知り、紙の本の常識を覆すようなアイディアが紙の可能性や読書の楽しみ方の幅を広げているのだなと感じました。

電気通信大学大学院 木村壮一
取材を通して、紙の本の魅力を再認識しました。見て触れられる本は、デジタルにはない存在感があります。ふと手に取りたくなる質感とオールジャンルの作品は、まさに「紙と物語が並列にある雑誌」だと思いました。『スピン』やこれからの雑誌の在り方について語る尾形さんの眼差しが、優しくも熱意に満ちており印象的でした。キャリアを含め多くの質問にご回答いただき、思わぬ出会いも大切なのだと分かりました。ありがとうございました。


