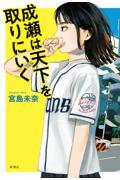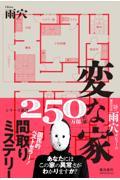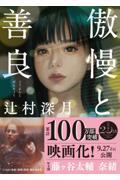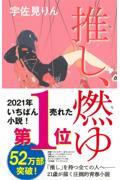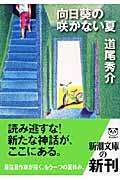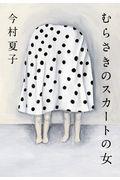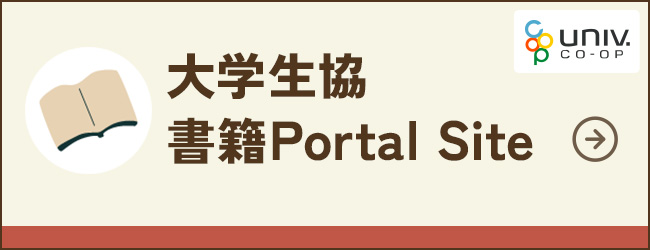アナタにぴったりの一冊に出合うヒントになるかも…
「読書マラソン」(Web版)
2024年4月~2025年3月のコメントで、10以上の投稿があった本をご紹介。
-
投稿数:19『コンビニ人間』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント あ お茶の水女子大学 1年 主人公が何故かとても気持ち悪く感じた。それこそが私は”こちら側”だと思ってしまっているに他ならない証拠のように思えた。言葉の端は少しは理解できるけれど、言っていることが理解できなくて、そう思ってしまう自分が悔しい。
「普通の人間っていうのはね、普通じゃない人間を裁判するのが趣味なんですよ。」藤宮 月子 奈良女子大学 1年 異質感。それを感じた時、どんなにあがいても、自分は所詮人間だと思った。なんの悪気もなく、一方的に主人公を解釈し、物語を膨らませ、価値観をおしつけるこの本の中の人たちと同じ人間だと思った。正常じゃないものを排除しようとする人間の一面がじわじわと抉り出され、視界に付きまとう。そんな奇妙な感覚を覚えさせられる作品だと思った。 ムー 名古屋大学 1年 人間は普通を好む。このことについてこんなにストレートに書かれた本はないと思います。普通とは、働いたり結婚したりして社会を動かす歯車となること。そこで私は社会の歯車から離れたらどうなるのか考えてみました。他者から批判されると同時に、多くの責任から逃れる事が出来ます。自分自身とは何者かをゆっくり考えられそうな気がします。しかしやはり人間は完全にそのように生きることは難しいと思いました。普通と歯車から逃れた状態の行ったり来たりで生きることも一つの方法なのではないかと思いました。 san 東京都立大学 1年 初めて見る人物だった。人と違うこと、普通の人生から外れること、というのはこの社会に生きる上で何かしら壁になるという経験は誰にせよあると思う。直面したときに不服を感じつつも直したり、逆に断固として変わらずにいる様子は容易く想像つくが、この主人公は純粋にそれを見つめていた。コンビニ店員としての普通であるために努め、誰かのお節介も疑問にはなれど嫌という感情を抱きはしないのだ。それだけでなく、普通であることを求められたからと行動はするものの、何処が主体的な、感情的な判断に欠けている様子は奇妙だが面白い。 月 広島大学 2年 多様性が叫ばれる現代だが、社会にとって理解のできないものはいつの時代も排除される対象である。本作の主人公は特に生きづらさを感じていなかったが、周囲の人間が彼女をマイノリティの枠に当てはめようとしたのがその証左だ。この結末をどう捉えるかで人生の価値観は大きく変わると思う。文章が生々しいうえに終始主人公の感情が読み取れず不気味な印象を抱いた。賛否両論ある作品だと思うが、「人生に『普通』な生き方などない」と思っている人にこそ読んでほしい。 おかず 同志社大学 1年 多様性が尊重される時代、私を含め、人々は「差別なんてしませんよ」「多様性を受け入れますよ」という顔をして日々を過ごしている。そんな日々をこの本は揺るがせてくる。
コンビニでずっと、バイトをしている?
・・・そんなの個人の自由だしいいじゃん
死んだ小鳥を食べようと言う?
・・・・・まあ、そういう子もいるよね
男性を部屋に入れて”エサ”をやる?
・・・・・・・・・・・・・・
何が普通で、何が異常か。多様性の時代でどのような判断がなされるのか、するのか。
問いかけられている気がした。サクラモチ 桜美林大学 1年 主人公の古倉さんがコンビニを通じて、現代社会を理解していく話。
古倉さんのコンビニという場所に対する意識が独特で読んでいて面白く、それでいて、その理屈には不思議とどこか共感できるところがあってそれも含めて面白かったです。
この本は150ページ程あり、本の中では薄めの部類だと思うのですが、内容がとても濃く読書が苦手な方でも楽しく読むことができると思います。デイジー 東京農業大学 1年 この本は終始不気味な感じがした。どのようであるかといわれても全く説明のできない不気味さで、この本を読んだことのある人にならきっと理解してもらえるだろう。一見コンビニアルバイトの日常のような感じもするが、読み進めていくうちに人間と人間の生暖かい部分が見えてくる。普通とは何か、そんなことを問うような衝撃的な本であった。 にこ 岡山大学 1年 私もコンビニでアルバイトをしているため、コンビニでの仕事内容には共感して読み進めることができました。
またコンビニでのアルバイトにやりがいを感じている主人公にもどこか自分と似ているところがあるなと思いました。
世の中にある「普通の人」の枠に囚われながらも、当てはまることができないと折り合いをつけて生きる生き方もあるんだなと新たな視点を得られた本でした。丸犬 名古屋大学 3年 数年前にこの本を読んだ時、「今の私を形成しているのはほとんど私のそばにいる人たちだ」という文に感銘を受けたのを覚えている。当時は、自分の人生は一人で成り立つものでなく色々な人との出会いによって作られるものだ、という意味に解釈をしていた。
だが今読み返すと、この文章はただ単純に普通や常識というものの曖昧さについて指摘した文章なのだろうと思う。コンビニでの普通、友達との会話での普通、などそれぞれ違う普通があり、その普通に皆が自然と適応している。意味は違えど、改めて鋭い小説だと感じた。もろっこ 大阪大学 1年 いらっしゃいませ-
今後コンビニに入ってこのセリフを聞くたび、「コンビニ人間」について思い出すであろう。
主人公の古倉恵子は、アルバイトでコンビニ店員として働いているときにしか、自分が「普通」であるとは感じられないという。それでは「普通」とは何で「異常者」とはどのような人のことなのだろうか。本を読み終えても未だに私には分からない。
アルバイトを始めたばかりの私には、違う視点においても刺さる描写が多かった一冊だった。みっきーーー 大阪大学 1年 ある1人の女性は、その彼女自身の独特な性格によって周りから少し変わった目で見られていました。母も妹も友人も、みんな仲良くはしてくれるけれど何か違う世界にいるように感じてしまう、そんな中唯一自分のことを大切な存在だと認めてくれるのが、20年ほど働き続けているあるコンビニです。コンビニに関することしか人生で重要だと思えず、コンビニに依存している彼女の姿はまさに「コンビニ人間」。そんな彼女の悩みや葛藤を細かく描写しているこの本は、読者にこの世界で生きることの根本の意味を考えさせる内容になっています、 3rd 広島大学 4年 本当の多様性とは何か。
どきどきさせられる本は苦手で、この本も手に取るのを躊躇っていた。しかし、この本はざわざわであった。
いつから”みんな”がしていることを自分もできたときに安心を感じるようになったのか。世間に定義された”普通”に囚われてはいないか。コンビニ人間に考えさせられた。
コンビニ人間として生きることが幸せなら、私はコンビニ人間に寄り添える側の人間でありたい。
普通や多様性について、新たな視点を貰える本である。冷房レインボー 三重大学 4年 私は、大学生になって初めてアルバイトをしたとき、社会の一部になったような気がした。この本は、そんな私が共感したコンビニエンスストアでアルバイトをすることで世界の中の正常な部品の一つとしてアイデンティティを確立した主人公の話だ。コンビニ店員という身近な職業を通して、普通の生き方とは何か?を考えさせられる一冊だ。 チャーリーブラウン 九州大学 2年 日常生活でみんなと同じ集団に馴染めない、少し自分は変わり者だけど周りにそれを伝えることもできない、という人に読んでほしい一冊。
主人公は、周りとの違いを感じつつも、ある種の擬態をしながらコンビニで18年間働く女性。白羽という男と同居することをきっかけに彼女の周囲が変わり始め、その過程で真の自分を発見していく。主人公同様に、社会の同調圧力や「正しさ」に押しつぶされず、自分の天命だと思えるほど好きなものにのめりこんでみたい。M お茶の水女子大学 4年 36歳非婚、大学時代から同じコンビニでアルバイトをする古倉恵子。彼女は失感情症のようで、悲しみや愛情などの感情や将来への展望を持たない。社会から排除されないよう、他者が望むように振舞うことを身に着け、ルールが明確なコンビニの店員として生きてきた。
恵子が求められる振舞いを汲み取り、「普通」の人間に擬態できたと安心するシーンに共感した。多かれ少なかれ私たちは社会や周囲が望む人間像を内面化して生きているのではと思わされた。恵子と対照的な白羽というキャラによって物語が深みを増しており、結末に圧倒された。ちょび 愛知教育大学 1年 いわゆる”普通”からは外れた主人公の考え方や感じ方で見る世界に引き込まれ、ページをめくる手が止まらない。その考え方や感じ方は私とはまるで違い違和を覚えるのに、共感できる部分もあったり、自分の考えを見直そうと思わせる部分もある。多様な生き方を表面上は受容しつつある現代社会や自分自身に、逃れられない”普通”のレールが存在することに気付かされた。 ぜう 西南学院大学 2年 「普通とは何だろう」という疑問をぼんやりと思い浮かべたことがある人は、この本によってその当時の記憶が引っ張り出されてゆくのを感じるだろう。コンビニバイトにのめり込み18年、身内や周囲の人間からは今後について心配されるも「普通の暮らし」を上手く思い浮かべることのできない主人公。社会に出てからはコンビニ店員以外の自分の姿を知らず、むしろコンビニ店員として社会の歯車に組み込まれ続けることを彼女は望んでいるのだ。本を閉じたとき、改めて普通とは何かという素朴な疑問について自問自答することになる。 かわなぎ 岩手大学 1年 コンビニという存在を人間と同じように循環しているものとした考えが新鮮だった。結婚や出産はおめでたく嬉しいものだとして生きていたが、それがその人にとってムラから孤立しないための仕方ない行動だった場合それはおめでたいのかわからなくなった。今僕自身に結婚願望がなく、もしこの世界が著者のような人で大半を占めていたら一切の強制感を感じずに生きていけたのではないのかと思う。
-
投稿数:18『成瀬は天下を取りにいく』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント ぽりたん 九州大学 3年 夏を感じる最高の本だった。自由奔放に生き、200歳まで生きること、デパートを建てることが将来の夢の成瀬あかり。夏休み全てを西武大津店からの中継に映ることを目標としたり、M-1に挑戦したり...成瀬は周りの人からどう思われようと気にしない。自分がその人を嫌ってないなら普通に接する。そんな彼女の良くも悪くも周りの評価を気にせず自分のやりたいことに熱中できるところがとても好きになった。誰しも周りの目を気にして自分の好きなように振る舞えない経験をしたことがあるはず。そんな人にこそ読んで欲しいと思う。 小梅 立命館 大学院 “普通”ってなんだろう。一番に浮かんだ言葉だ。最近、多様性という言葉も聞き慣れてきた。けれど、自分がその一員になれているかと問われると首を傾げる。そんな時に読んで、ああそうかと手を打った。成瀬は常に突飛な言動で、いとも簡単に痛快に普通をぶち壊す。だがその根底には明確な理由があり、誰も傷つけない。次第に、周りの方がその嵐に飲み込まれて自然と元気になっている。生きる中で知らずしらず根付いた“普通”を抜け出すことに、怯える必要はない。もっと大胆に、自分らしく生きて良い。彼女がその背中を押してくれる。 本好き 龍谷大学 2年 成瀬が近くにいたら私も目が離せなくなるだろうなと思いました。自分にはないものをたくさん持っていて、こんなふうに自分に正直に生きれたら毎日が楽しくなると感じました。 最後の章では、いつものリズムが壊れ、悩みはじめる成瀬。その不器用さや素直さもいいなと思いました。 これから成瀬が成長して社会に出た時、どんな社会人になるんだろう。成瀬の成長、人生をもっとみたいと思いました。 くさだんご 北海道教育大学 1年 とても読みやすく、共感しやすい小説でした。まるで漫画を読んでいるようにページをめくる手が止まりませんでした。周りと比べてちょっと変わった言動をする成瀬ですが、その一個一個が見事に私のツボを刺激してきて、ニヤニヤしながら読んでしまいました。成瀬が周りの人に影響を与える描写がとても丁寧に書かれていて、感情移入を多くしました。友情、勉強、やりたいこと、全てを詰め込んだ青春小説と言いきっていい小説です。私の隣に高校生の時成瀬がいたら、想像するだけで面白いです。 san 東京都立大学 1年 圧倒的存在感に主人公・成瀬がいるけれど、読み進めていくうちに、そのインパクトと面白さが残りつつも、他の登場人物の素敵なところが感じられ、愛おしくなる作品です。成瀬とその周りのみんなのその後が気になるので、続編も読むしかないです! ラッキー 神奈川大学 1年 「成瀬は天下を取りにいく」が本屋さん大賞を受賞したり、とても流行っていて読んでみたいなと思っていました。成瀬はとても成瀬だし、島崎もとても島崎で私が出会ったことのないような人だし、キャラクターで読んでいてとても楽しかったです。特に、階段は走らないでは成瀬は直接出てきてるいるわけではないけれど、人と人を成瀬が繋いでいて、テレビに毎日映ることがどれだけ凄いのか想像もできません。また、実際の地名やお笑い芸人さんのコンビ名が書かれていることでとても身近な話に感じました。ゼゼカラの漫才みてみたいです! カオナシ 名古屋大学 1年 めっちゃ面白かった!自分も主人公成瀬と同じく膳所高校出身で、滋賀県あるあるがいっぱいでできてとても懐かしい気持ちになりました。高校時代の青春を思い出させてくれるような一冊でした。幼い頃から馴染みのある、平和堂が出てきた時は思わず声をあげてしまいました(笑) アサ 名古屋大学 3年 自分に正直でまっすぐかつ才色兼備で成績優秀、そして周りの目を気にしない。自分らしさをこんなにも表向きにしている姿に眩しさを覚える。行動力が頭一つ抜けている成瀬だが、その行動のほとんどは誰にでも始められることであり、いかにやってみることの大切さがわかる。好奇心赴くままにたくさんの種をまいて1つでも咲く花があれば良い。失敗してもそれは肥やしになる。こう考える人がありふれた毎日を変える一歩を押してくれる人なのであろう。かっこよさに惹かれた、といった安直な理由でも始めることは本当にかっこいいのだ。 あの人 龍谷大学 1年 成瀬あかりは驚くほど独特な性格をしている。一度言ったことは可能不可能に関係なく挑戦するような芯を持ちながら自分が納得すれば簡単して辞めるような柔軟性も持ちあわせている、まさに琵琶湖のような円ではない形にすっぽりとはまってしまいそうな人物である。
そして本編ではそんな成瀬あかり史に刻まれる成瀬の突発で奇抜な行動を様々な者たちの視点から描写している。決して綺麗ばかりではない青春が広がっており共感できる場面も多いと思うので是非読んでみてほしい。ふぁくせ 東京農業大学 4年 この夏、成瀬に出会えて良かった。
本を開いた瞬間から、この主人公はとても面白い人だからこの本はきっと面白いと思った。
主人公の成瀬は、とても変わっていて、とても真っ直ぐな人だ。
自分は成瀬のようにはなれないなと思いながら成瀬視点からの世界の見え方が面白くて、どんどん惹き込まれていった。自分との接点なんて無いと思っていたのに、成瀬を知るにつれて自分と成瀬の似ている部分を見つけたりもして。何も諦めなくていいし、自分を信じて全ての事象に真っ直ぐ向き合う強さを成瀬から分けて貰った気がする。本を読む看護学生 新潟大学 1年 もう天下は成瀬のものだ。
主人公の成瀬は自分のやりたいことを貫き、マイペースかつ極端な言動が多い。常に、中心に一本芯が通ったような一貫性がある。それでいて、人間らしい弱さや寂しさを感じさせる一面があって、とにかく帯に書かれている通り「最高の主人公」だ。ものすごい行動力・カリスマ性・溢れるほどの魅力。今や私を含む多くの人間が成瀬に夢中なのだから、彼女は天下を手に入れたと考えて差し支えないだろう。ぱんなこぱんだ 立命館大学 1年 「島崎、わたしはお笑いの頂点を目指そうと思う」成瀬がまた変なことを言い出した。成瀬と島崎は滋賀の膳所に住む幼なじみだ。成瀬は愛を行動で表す。地元の西武百貨店が閉まる最後の1ヶ月間毎日通った。成瀬はなんにでも挑戦する。自ら坊主にし、髪の生えるスピードを測った。成瀬は天下を取りに行く。前人未到の200歳まで生きることやお笑いの頂点を目指している。そんな成瀬が島崎をM-1グランプリの相棒に誘った。島崎は成瀬の奇想天外な行動をそばで見るために承諾した。「膳所から来ましたゼゼカラです、よろしくお願いします」 ぱんなこぱんだ 立命館大学 1年 「島崎、わたしはお笑いの頂点を目指そうと思う」成瀬がまた変なことを言い出した。成瀬と島崎は滋賀の膳所に住む幼なじみだ。成瀬は愛を行動で表す。地元の西武百貨店が閉まる最後の1ヶ月間毎日通った。成瀬はなんにでも挑戦する。自ら坊主にし、髪の生えるスピードを測った。成瀬は天下を取りに行く。前人未到の200歳まで生きることやお笑いの頂点を目指している。そんな成瀬が島崎をM-1グランプリの相棒に誘った。島崎は成瀬の奇想天外な行動をそばで見るために承諾した。「膳所から来ましたゼゼカラです、よろしくお願いします」 鷽秋かおす 東北大学 3年 2024年の本屋大賞大賞受賞作。「わたしはこの夏を西部に捧げようと思う」から始まる本作は、成瀬の圧倒的なバイタリティに万人が気圧される最強のご当地小説である。「大きなことを100個言って、そのうち一つでも叶えれば、凄い人だ」という成瀬のスタイルは、読後の人生に前向きな影響を与えること請け合いだ。短編集の最後、成瀬視点の話が特に愉快だった。「書を持って」町へ繰り出すには最高の一冊である。 しゅん 名古屋大学 4年 私は人を気にしないようにしている。周りと比較しないし、自分を一番信じている。ただ、親友や家族などは信頼しているし、孤独を感じたことはない。
成瀬の生き方はかっこいい。自分の芯を持っている人間にやはり私は惹かれる。なにより、成瀬の人間味はとても美しい。成瀬を見て、私は自分の生き方は変えるべきではないと感じた。
一人の人間は、誰よりも強いと感じる。それは、孤独を恐れないからである。周りを気にしている人間こそ誰よりもおびえている。
ぜひ、成瀬の生き様に勇気をもらってほしい。ポンポコ太郎 龍谷大学 2年 大津、膳所、西武、平和堂、琵琶湖そして西川貴教。これらを聞いて思い浮かぶのは滋賀県だろう。
そこを舞台に繰り広げられる、頭が良くて滋賀への愛が大きい女の子である成瀬の行動は予想できないものばかりだった。
皆さんはどんなに興味を持っていても新しい事に挑戦することを迷ったことはないだろうか。そして、迷っている間に時間が過ぎ去り、出来なかったことはないだろうか。
そんな誰にでもある迷いを感じさせずに成瀬は天下を取りにいく。そんな彼女に挑戦する勇気を貰い、やりたい事・やりたかった事を見つめ直せる本だった。くりごはん 北海道大学 2年 とにかく興味を持ったあらゆる物事をそつなくこなしてしまう成瀬。そんな彼女の周りにいる人の視点から一章ずつ物語は始まっていく。勉強もこなしながら我が道を走る成瀬に最初は人間味をあまり感じれなかった。挫けることがなく、万事がうまくいっているように見えたからだ。ただ、成瀬自身の目線から描かれた最終章では、彼女の胸中にある悩みや葛藤を知り、親しみが持てた。破天荒で自分軸を持つ成瀬に、周囲の人々は一歩を踏み出す勇気をもらう。青春の甘酸っぱさを味わえた。 ふぁくせ 東京農業大学 4年 この本の主人公「成瀬」に私は定期的に会いたくなる。成瀬に会うために、本を開いている。読んでもらうときっと分かると思うのだが、成瀬は人として魅力的で目が離せない不思議な人だ。最初は突拍子もない人だと思うけれど、読み進めるほどに成瀬のファンになってしまっていた。それくらい成瀬は魅力的だし、前に進む力強さがあって、気分が落ち込んでいる時に勇気をもらえる…私にとっては、そんな存在だ。
この本に出会えたこと、成瀬に出会えたことに感謝したい。
-
投稿数:17『正欲』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント あ お茶の水女子大学 1年 自分の視野はなんて狭いんだろうと思わされた。今まで街中で見る挙動がおかしい人を「頭のおかしい人だ」と断定してしまっていた自分がみっともなく感じた。いかにも「正しい人」である啓喜の振る舞いに苛立ちを覚えたけれど、自分もずっとそんな態度を取ってしまっていたんだろうなと自責の念に駆られた。
「”恋愛感情によって結ばれた男女二人組”を最小単位として世界が構築されていることへの巨大な不安が、そっと足のつま先に触れるのだ。」西山 関西学院大学 1年 正しい欲とは何だろう。言葉にすることは主張であるから、難しい。自分が思い込んでいる「正しさ」だから。読者に対して「あなたはどうなんだ。」と問いかける本は、つい筆者の流れに乗りたくなってしまう。情けなく思っていても、力ずくで理由を作って思考を合わせるのだ。ひとたび目線を変えられると、こんなにも捉え方が変わるのかと驚くかもしれない。私たちは他者を求めるのに、理解し得ない矛盾の中を生きている。だからかまだあまり死にたくないし、佳道と夏月も死ななかったのかもしれない。 M お茶の水女子大学 4年 多様性を叫びながらしかし「多様」とはマジョリティ側から見た「多様」にしかとどまらず、結局旧態依然とした構造を温存し、異物を排除しようとしこちら側に介入し迫害してくる。繋がりを、対話を、と言われるけど、こちらの意見をいくら話したってあなたたちには通じない、それならこちらは黙って陰でやりたいようにやりますよ、という彼らの気持ちを非常に理解できてしまった。社会に対するある種の諦念、侮蔑が私にもある。だが、見方を変えれば私も誰かを迫害しているかもしれない。視点の移り変わりが非常に面白い作品だった。 にょーん 名古屋大学 1年 読む前の自分には戻れない、というキャッチコピーにつられて読んでみました!
その通りで読む前の自分が知らなかった世界、考えもしなかったことを知ることができました。
いい意味でも悪い意味でも新しい自分になれた、そんな気がする一冊ですshu 帯広畜産大学 3年 あなたは「多様性」を本当の意味で理解していますか。
LGBTQが話題となり、多様性に触れる機会が増えた今日。詳しくはないけれど、なんとなく理解しているつもりだった。この本を読むまでは。
水に性的興奮をする登場人物。多様性が叫ばれる社会で彼らの多様性は初めから社会に認識されていない。当たり前のように糾弾される。社会から認められることを諦め、自分たちだけの世界で生きていこうとする。
彼らにとっての障害は社会が作った「多様性」なのではないか。私たちは「多様性」の押し売りをしているだけなのではないか。1ch 富山大学 1年 とても考えさせられる小説であろう。「多様性」という盾(その人が勝手に線引きした範囲内の)の元で、無意識的に、そうでないものを排除する。「メジャー」と「マイノリティ」は単なる二項対立(作中で対岸に例えられる)ではなく、「マイノリティ」に対する「マイノリティ」が存在し、枝葉的に際限なく分散してゆく。結局、己の持つ「正しさ」を常に疑ってかからねば、新たな被害者を生み出し続けるのであろう。 ゆき 東京大学 大学院 映画化もされた話題作。この世に生まれた人は皆読むべき、と申し上げたいところだが、この言葉さえも多様性の強要になる気がして恐ろしい。そしてこの本の感想を誰かと言い合うことも、同じように恐ろしいと思う。もしも、相手が嫌悪感を抱いていたら?
本文中にもあった表現だが、多様性を支えるのは秩序のように思う。自分の欲望を満たすために他人を傷つけない。それが思考する生き物に生まれた運命なのではないだろうか。げっこー 宇都宮大学 3年 「多様性」しかし、その“ものさし”を作るのはあくまでマジョリティの人間である。つまり、そもそも他者が認める「多様性」のフィールドにすら立たされていない人々も存在するのである。「理解する」や「認める」という言葉も、そう気軽に使うものではないのではないか。本当の「多様性」とは何か。「多様性」を尊重する風潮にある現代を生きる私たちだからこそ、直面させられる難題である。読んでみれば、自分の世界が広がったように感じるであろう。 iraka 神戸薬科大学 4年 自分は常にマジョリティ側に居て、マイノリティを受け入れる側、理解する側に居ると思っていたが、本書内の「3分の2を2回で9分の4だから、立派なマイノリティ」という記載にハッとさせられた。最後の大也と八重子の掛け合いのシーンが特にひっ迫しており思わず息を呑んだが、この物語の核がここにあるように思った。
本書冒頭の事件の経緯がどんどん明らかになっていく。最後まで読んだあと、もう一度冒頭に戻って事件記事を読んだが、事件の背景や経緯を知ると、同じ事件なのに感じ方が変化した。とー 東京経済大学 2年 一文一文が重たくて、何度も戻りながら読んでしまった。安易に多様性という言葉を使うことの無遠慮さや、マイノリティを理解した気になる傲慢さを痛烈に批判する内容だったと思う。私たちは絶対に他人を完璧に理解することはできない。そのことを自覚し、自分にとっての普通に該当しないことであっても否定しないことが求められる。しかしそれさえも綺麗事で、社会倫理で許されないこともある。ではどうすればいいのか、分からなくなってしまった。 たま 京都大学 3年 私は今、このコメントを書くのを迷っている。なぜなら、私が発するどんな言葉も正しくなく、誰かを傷つけてしまうという考えに取り憑かれているからだ。こんな時に有用な、なんでも上手くまとめてくれる「多様性」という言葉すら、この小説の読後には使えなくなる。
しかしそれでも私はこの本を薦める。既に名前のついているあなたには、想像もできない世界を知ってほしいから。そして、どんなジャンルにも当てはまらないあなたには、ひとりでいてほしくないから。
誰にもこの世界との繋がりをやめてほしくない。傲慢でも、そう思います。Uka 西南学院大学 2年 「多様性」がおめでたい言葉になっていることに私はイラついていた。同時に、誰も傷つけたくないと思う自分を罪深く感じていた。だって、薄っぺらな多様性を叫ぶ世の中と同じように、私もいつか理解不能な誰かを拒むかもしれないからだ。p439から読む手が止まった。八重子と大也の摩擦は私の中にあったから。2人の対話が始まりそうな予感に薄ら希望を感じた。誰だって抑圧する側とされる側を行き来している。「あってはならない感情なんてこの世にない。」そう言える強さが欲しい。 Uka 西南学院大学 2年 「多様性」がおめでたい言葉になっていることに私はイラついていた。同時に、誰も傷つけたくないと思う自分を罪深く感じていた。だって、薄っぺらな多様性を叫ぶ世の中と同じように、私もいつか理解不能な誰かを拒むかもしれないからだ。p439から読む手が止まった。八重子と大也の摩擦は私の中にあったから。2人の対話が始まりそうな予感に薄ら希望を感じた。誰だって抑圧する側とされる側を行き来している。「あってはならない感情なんてこの世にない。」そう言える強さが欲しい。 冷房レインボー 三重大学 4年 固定概念に囚われたままそれを他人にあてはめようとする愚かさのようなものを感じた。自分が見えている、考えられるものだけを見るのはナイーブだと思えた。ずっと多数派でいるということ自体が立派な少数派になるし、実はみんなが不安を抱えて生きているのではないだろうか。それを確かめ合うために、私たちは言葉を交わす。「多様性」という言葉が飛び交う現代の中で、是非読んで欲しい一冊だ。 アサ 名古屋大学 3年 「多様性」の都合の良さ。どこもかしこも多様性の時代だ、とか言って英語を勉強させられたり、留学を勧められたりするのが当たり前になってきている。でも本当に見るべき個人個人はもっと近くにいるはずなのではないか。出身や見た目、言語なんて分かりやすい違いの多様性ばかり見ていては話にならない。形式的に大きな目標という矢印に組み込まれたようだ。本当の声を欲を、「理解する側」の無意識なマジョリティに挙げるのは無駄なのか。私は普通がゆえの多数派として都合良い言葉で誰かを苦しめていないか心配で胸騒ぎがした。 お茶ごくごく倶楽部 大阪大学 1年 目に入ってくるほとんどの情報のゴールは「明日死なないこと」である。そんな新鮮な視点から始まって私はすぐに引き込まれた。今世間に流行している“多様性”という言葉。自分とは違う存在を認めているようだが、自分が受け入れられるものしか寛容していない。この小説では“受け入れてもらえない”側の諦めと繋がりが描かれている。読んでる中で自分の考え方の未熟さに何度もハッとさせられた。物事は常に見えていたはずなのに私は“見えていなかった”。この本と出合って良かったと心から思う。 ぜう 西南学院大学 2年 ちょっと待ってくれ、と思い本を置いて目をつむり、そして再び手に取る。読み進める過程でこれが何度あったか分からない。「ここまで書いても良いのか?」という、僅かな慄きと興奮を伴ってひたすら活字を追い続けた。ちょうど多様性の礼賛にゲンナリしていた身としては、現代社会で声高に叫ばれる多様性の内部に存在する不都合な部分にスポットライトが当たるような感覚となり、清々しさも感じられた。傑作とも問題作とも評価されうると思うが、私はこの作品を現代に生きる人々にとって突き刺さる強力なアンチテーゼであると解釈した。
-
投稿数:17『アルジャーノンに花束を』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント あ お茶の水女子大学 1年 情緒的成長を伴わない知性の発達がいかに無意味であるかがよく伝わった。知性を失っていくチャーリイの姿はとても切なく、温かみと友だちを取り戻していく温かさがあった。母親と対面したときのチャーリイの「マア…」としか言うことができないというシーンは思わず涙ぐんでしまった。
「ぼくの家族のことやぼくのことがよくわかたのもうれしいです。みんなのことをおもいだしてあうまでわ家族なんかいないのとおんなじでしたけれどもいまわ家族もあることがわかっているしぼくもみんなみたいな人間だとわかっているのです。」あ 九州大学 1年 タイトルのアルジャーノンは、主人公ではありません。知能指数をあげる手術を施されたネズミなのです。この物語は、ネズミと同じ手術を受けた主人公の経過報告を通して進んでいきます。読み書きもままならなかった状態から、誰も達しなかった知能レベルにまで到達し、再び退行していきます。報告を通して主人公の戸惑いや苦悩を肌で感じることが出来ます。 お茶ごくごく倶楽部 大阪大学 1年 今や言わずと知れた名作。幼児の知能しかもたないチャーリーは手術により天才と言われるほど賢くなる。見ていなかったものが見えるようになった世界で苦悩するチャーリーの姿は現在の私たちの苦しみを改めて描いており、ハッとさせられる。恥ずかしながら、知的障害者に対して漠然とかわいそうだと思っていたが、自分の「幸せ」と他人の「幸せ」、何がヒトにとって幸せなのかを考えさせられた。ラストはチャーリーの感情が直に伝わり、読み終わりの余韻は凄かった。一日ごとにチャーリーの日記を読むとリアルで面白いかもしれない。
月 広島大学 2年 この作品を一言で表すにはあまりにも人生経験が足りない。知能があれば幸せになれるわけではなく、結局何が人生において大切なのか深く考えさせられた。中学生の頃の自分が読んでいれば、その後の人生は大きく変わっていたのではないかと思う。最後の一文は切なく、泣きたくなるくらい美しいものだった。人生で一度は必ず読むべき名作。 樋口師匠 広島大学 1年 精神遅滞の主人公チャーリーゴードンが手術により天才的な知能を得るSF小説。知性と感情の関係性の対比構造をとりつつ進む展開が読みどころだ。知性溢れるものは豊かな心や、思いやりを持ち合わせているのだろうか。また、チャーリーと同じく知能を高める手術を施される、本のタイトルにもなっているマウスのアルジャーノン、彼とチャーリーの関係性も物語の肝である。彼らは初めて迷路のテストで出会い、知能という点である意味対等な存在として関係を気づき始めるが、、。彼らのラストシーンを喜劇と読むか悲劇と読むかはあなた次第だ。 ぷにタン 釧路公立大学 2年 手術によって知能を大幅に発達させた知的障害を持つチャーリィが、今まで見えていた社会、友人だと思っていた人たちの真実の姿が見えていくというお話。どこまでも純粋で優しい手術前のチャーリィを知っているからこそ、知能が発達した彼が傷つく姿は読んでいて胸が締め付けられる思いでした。しかし、知能が伸びたことによって得られた喜びももちろんあり、彼が愛を知ったり、今まで彼を潜在意識の中で縛り付けていた母親との対話を試み、苦悩の末解放される姿はとても感動的で、この本に出会えてよかったと強く思いました。 スライム 龍谷大学 1年 話題作を初めて読んだ。
様々なSNSや広告で紹介されていたのでとても興味を持った。
また自分が今まで触れたことのないジャンルだったので読み進められるか不安も多少あった。
読み進めていくと人間の精神的な不完全さが克明に描写されているのが分かり、元々は弱者であった人間がいつしか写真を忘れてしまい傲慢になっていく姿が見られた。不可逆的な、しかしまるで円を周回するかのように一方通行な、経験はその前後で人をどう変えるのだろう。みかん子 奈良女子大学 4年 人生を通じて何度も読みたい。読む度、発見がある。私にとってこの本は、そんな本だ。
主人公は、知的障害を持つ青年。彼には頭が良くなりたいという強い想いがあった。彼は実験の被験者として選ばれ、手術を受けて高い知能を得る。しかしその効果は、期間の限られたものだった
チャーリーの変化に応じて目覚ましく変化する文体が天才の所業。そこに現される知への執着、知能を得て得たもの、失ったもの、一転して衰えていく焦り。そこには人生が詰まっている。
この小説を、10年後、30年後の自分はどう読むだろう。柊 帯広畜産大学 3年 ぼくにわともだちがいる。
知的障害を持つチャーリイには友達がいる。チャーリイは友達に好かれたくて、母親に褒められたくて頭の手術を受ける。徐々にIQが上昇し、チャーリイは天才とよばれるようになる。今まで難しいと思っていたことがあっという間に分かってしまう。
しかし、同時に友達を失った。
ともだちわいいものだ。と、思い出すのはいつなのか。ぜう 西南学院大学 2年 賢くありたい。受験などの競争を経験した人なら、誰しもがそう感じたことがあるでしょう。
32歳でありながら幼児並みの知能しか持たない主人公は、脳外科医の手術によって知能を向上させるプロジェクトに参加することを決めます。その過程で先行的な実験として手術が施されていた白ネズミ・アルジャーノンを競争相手とした検査を受けます。その後主人公のIQは飛躍的に向上してゆきますが、そんな中で愛や憎しみ、喜びや孤独といった感情をを初めて目の当たりにすることになります。読者は賢さを追求する中で、心の真実が見えてきます。ねいろ 愛知教育大学 3年 知的障害を持ったチャーリイ・ゴードンの壮絶な半生を描いたSF作品である。約8ヶ月ほどの出来事が書かれているが、読み終わったとき、私は彼の一生を追ったような感覚になった。目まぐるしい彼の成長と退行、喜び、愛、孤独。すべてが流れ込んでくるようだった。
様々なサイトで「最後の一行がとても良い」といったような感想を目にしていたが、まさに彼の半生を描いたこの本のラストにふさわしい一行だったと思う。読んだ瞬間に体がビリビリと震えるほど鳥肌がたった。彼の半生を見届け、ぜひ最後の一行を目にしてほしい。Arare 中京大学 1年 日記口調で語られるチャーリーの日常がゆっくりと変化していくのを感じ、毎日を一生懸命に生きる姿がとても綺麗だった。ある日から今まで分からなかったことがだんだん分かるようになると人は集まってくるし、知識も増えて豊かになるけれど、元の自分に戻ると人がいなくなっていくという不条理がとても苦しかった。しかし、どんな時も変わらないチャーリーの優しさやあたたかさが私はとても好きになった。多くのことを考えさせられる感動作だった。 鷽秋かおす 東北大学 3年 物語の道筋は、ほぼ全て作中で示唆されている。そういう意味で、意外な結末が待っているわけではない。しかし、この本が突出して面白いこともまた、疑いようがない。本書はチャーリイの人生そのものの追体験であり、誰もがチャーリイの中に自分を見ることになる。確かに序盤はひどく読みにくいけれど、これはこれでなければいけないのだ。我々が本文に感じる感情は、そのままチャーリイに対する他者の視線の投影である。チャーリイが置かれている状況を想像し、そのことが私とチャーリイを更に重ねるのだ。紛れもない良書である。 カンザキ 龍谷大学 4年 ネット上で話題になっていたので、手に取ってみました。あらすじはすでに知っていたのですが、実際に読んでみると非常に切なく、まとまった内容で読みやすく、感動しました。作中のチャーリイの、大人の身体でありながら子供の精神を抱え、苦悶を重ねて順応していく様子は、今まで触れたことのない画期的な感心をもたらしてくれました。あとがきでも触れられていましたが、原書は半世紀以上前の刊行物でありながら全く古さを感じさせない素敵な作品でした。読み終えて、世代を超えて愛される本とは、この本ではないかと思います。 DB好き 名古屋大学 3年 知性と人情は反比例するのか。著者はこの前提を元に作品を書き、人々は感動を得る。だが、私はこの前提が半信半疑に思った。確かに知性が無いほど親しみやすいイメージはあるが、同時に蔑まれやすい。知性が人々との間に楔を打ち込む。言わば、ゴードンはドーピングしたようなものだから、その代償を受けてしまった。著者は、進歩のための実験体に感謝の意を伝えたかった。同時に、我々は障害者と住む世界を分けるべきか否かという議題を投げかけている。基本的人権を尊重するなら分けた方が合理的かと作品を通じて思った。 えび天天 京都大学 4年 最初とても読みにくく、しんどい小説だなと思っていたが、どんどん知能が上がっていくにつれて展開に引き込まれていく。かなり読んでいてしんどい事件もあるが、チャーリィの周りの人がとても優しく、ほっこりする。終盤、退行期は序盤とは違って読みにくくはなるが、チャーリィがどんどん心が優しくなっていくのを感じ、手が止まらなかった。優しさとは何か考えさせられる一作だったと思う。 とー 東京経済大学 2年 あらすじなど調べずに読んだため、最初は文章ともいえない文章が続いて戸惑った。チャーリイはばかにされているのも理解できずに笑ってしまうような知的障害だった。天才となったチャーリイはまたしても周囲との壁を感じ、結局ほとんどの人とほとんどの時間心を通わせることはできなかった。人は同程度の知能を持つ人としか自然体では接することはできず、ずれると憐憫や苛立ちで関係がままならなくなる。そんな場面が多くてやりきれなかった。
-
投稿数:16『変な家』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント 本を読む看護学生 新潟大学 1年 「変な家」待望の続編。前作よりも気持ち悪さ倍増。
前作と同じように、著者・雨穴のもとにおかしな間取り図が届く。それらは一見すると関係のないように見えるが、これまた奇妙な共通点が見えてくる。
ずっと同じ視点で物事を見ていると、大切なことを見落としてしまうということを痛烈に感じさせられた。
なぜわざと歪な形の家を建てたのか、それらの家は何の関連があるのか、著者・雨穴と伴走するような気持ちで読み進め、最高の気持ち悪さを味わえる一冊。namba 富山大学 3年 最初は奇妙な間取りの謎ときの短編が11編あるのかと思ったら、ふたを開ければ、実はすべての話がつながっている。人々の間取りを取材した(という形式の)記事を読んでいると、まるで実話のような感じがしてくる。タブーを知ってしまったような気がして。本当は読んではいけないような、でも気になる。そんな興奮状態だった。
また、「筆者」(語り手)や、筆者の知り合い、取材の対象の人々がいろいろ推理をするが、本当のところはどうなのか、読了後もまだ謎なところがある。真実は何なのか、それを自分なりに考えるのも面白かった。iraka 神戸薬科大学 4年 今回は11軒の家に関する資料が提示され、そのどれもに奇妙な箇所があるのだが、驚愕なのは11軒の間取りが最後に綺麗に繋がることだ。今回はカルト宗教絡みの内容だが、本当にこのような宗教があるのではないかというリアリティさが少し怖かった。巧妙に隠された扉や部屋を探すシーンや、提示される資料が取材記録だけでなく書籍や雑誌記事などさまざまなツールであるところが面白かった。家の間取りと絡ませたミステリーは雨穴さんならではだと思うので、家シリーズの続編を期待している。 らか 早稲田大学 1年 変な家無印の時もそうだったが、話が進むごとに何回もどんでん返しがあり飽きない。作者はよくこの展開を思いつくなーと思う。確かにおばあちゃんは家の中で阻害されていたのかもしれない。老人ホームで働くことでその罪悪感が少しは晴れるのだろうか。お金持ちのお嬢様という一面しか同級生から見られていなかったが内面はもっと奥深いのかもしれない。 ねむねむ 奈良女子大学 1年 続きが気になり、一気読みしました!ミステリの中では比較的読みやすいと思います。映画化されたこともあり、普段読書をしない人にとっても手に取りやすい本だと思うのでぜひ読んでください! 中嶋隼人 金沢大学 1年 不可解な間取り図を巡った不動産ミステリー小説です。ページをめくるごとにドキドキが止まらないのですが、それと同時に話の繋がりがどんどん見えてきて、最後にはストーリーの精巧さに圧倒されます。 本を読む看護学生 新潟大学 1年 「ネット上で話題」では収まりきらない名作ミステリ。
著者・雨穴のもとに届く、どこかが変な間取り図を中心として話題が転換していく。魅力的な助っ人も加わり、いくつかの間取りを見ていくうちに、バラバラであるはずのそれらの家に、不気味な共通点があることに気がついてしまう。その共通点が指し示すものは何か、何のためにその家は「変な家」になってしまったのか、それらを解き明かしたときに、人間の闇に突き当たってしまう。誰を責めることも出来ない感情に苛まれたい人におすすめ。melonpan87 神奈川大学 1年 最初間取りを見た時は、おかしな所がどこかわからなかったけれど読み進めていくうちにこの家の恐ろしさを痛感しました。
表紙にもなっている間取りが、子供に殺人を起こさせるために作られていると知った時は、背筋がゾクッとして、夜寝るのも怖かったです。
実際にこんな事件があって、子供に殺人をさせるしきたりのある家があったということが恐ろしく感じました。まっきー 立命館大学 1年 「変な家」は謎の覆面作家雨穴のデビュー作です。この本はとある家の間取り図から始まるミステリー小説で、窓の無い子供部屋、それを囲うように作られた廊下、二重に作られたドア、左手の無い男性の遺体、男性の妻を名乗る謎の女性、などなどの複雑な要素の詰まった本となっています。
また、ホラーミステリー小説で、暑い夏にはピッタリとなっています。猫武将 近畿大学 4年 「謎の空間がある。」
友人の引っ越し先の相談にのった筆者。間取り図を見ればたしかに謎の空間があった。それだけではなく、その間取り図には奇妙な点が複数存在していた。すべての謎が解けたとき、筆者はひどく不気味で悲しい歴史へと辿り着く。
映画化され話題の一作。一見してなんの変哲もない間取り図がここまでミステリーになるのかと驚いた。物語を読んでいて漂う不気味な雰囲気。話が進むごとにその不気味さはさらに濃いものとなっていき真実へと辿り着くのだが、その真実もとても悲しいものだった。ちー 福岡女子大学 4年 読み始めたときは、些細な間取りへの違和感がここまで大事になるとは思いもしませんでした。推理しながら読み進めますが、その予想を上回ってくる展開でとても読みごたえがあります。ミステリー、推理小説が好きな人、間取りや家に興味がある人におすすめです!『変な家』が面白かったため、『変な家2』と『変な絵』も読みましたが全ておもしろかったです。 アサ 名古屋大学 3年 一見普通の家に見えるがよくよく考えてみるとどこかおかしい。ミステリー小説として新たな切り口となるようなこの作品は、奇妙さと不気味さが折り合いつつも少しずつ謎が解明していき核心に迫っていく。「家」からつながる先祖のしがらみや隠された秘密、人との関わりが不思議な雨月はんの世界観に没入させてくれる。もし家を借りる、買うことがあればぜひ間取りを確認してからにしよう。 桐田 龍谷大学 3年 パッと見何もないような家の間取り図が実は一族を巻き込むような問題をはらんでいた家の間取り図だった話。
オモコロ記事版の「変な家」を読んでいた自分にとってこの本は”めちゃくちゃ広がった話”に見えた。記事として書かれていた内容はこの本の超序盤にすぎなかったからである。そんな一族の秘密に迫るものだったんだ……。
謎が残るのが雨穴氏らしかった。真の黒幕は誰?namba 富山大学 3年 家の間取りにはその家の住人の価値観が色濃く反映されるものだ。子供部屋の位置、キッチンの広さ、和室を設けるかどうか、etc。
しかし、この本に出てくる家の間取りには、その家の住人の異常な因習が関わっていた。最初から最後まで、語り手の語り口が面白く、ページを捲る手が止まらなかった。また、からくりがわかった後も、エピローグで真犯人は別の人物なのではないかという可能性が残されており、考察しがいのある作品であると思った。あいうえお 宮城学院 3年 ホラー作家のYouTuberが送る、不動産ミステリー。
「ほら、ここがおかしくない?」と読者に問いかけながら進んでいく長編ミステリー。最後に全ての謎が解き明かされたとき、その伏線に驚愕し、思わず読み返してしまう。事故物件に行かずとも事故物件特有の不気味さを体験できる一冊。あなたもページを開いて事故物件に足を踏み入れませんか?どせい 東京大学 1年 映画化されて話題になったホラーミステリー。淡々とした語り口なので、ケータイ小説を読むようにすらすらと読める。ある物件の見取り図一枚から、荒唐無稽ともいえる推理が導き出され、そこから息を呑む結論まであっという間に連れていかれる。ふと本から顔を上げた瞬間に、この現実離れしたストーリーが、この世のどこかで本当に起こっているのではないかと思ってしまう。そんな感覚を、人工的な装飾が極限までそぎ落とされた文体が催させる。
-
投稿数:15『六人の嘘つきな大学生』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント 本を読む看護学生 新潟大学 1年 人間の裏側は、月の裏側よりも暗くて見えづらくて歪なのかもしれない。
人間の裏側と聞くと、「この善人ヅラの人間は実は極悪人でした」なんてのが想像し易いだろう。でも、実際はそんなわかりやすいものでは無いことの方が多い。
この小説を読んでいる間、登場人物たちへの印象が何度も変わった。読めば読むほどに、知らない一面がボロボロ出てくる。それって、現実に相対する相手にも同じことが言えるんじゃなかろうか。今、極悪人に見えているその人も、1時間後には聖人に見えるかも。人間は多面立体であると痛感させられた一冊。Mal 愛知教育大学 1年 人は嘘をつく生き物である。その人とどれだけ親しいと思ってもその人の本当の顔は誰にもわからない。六人が塗り重ねた嘘が一つ一つ剥がされ、また一つ一つ嘘が積み重ねられていく。終盤の伏線回収は鮮やかで心惹かれる展開だった。まるで自分もその場にいるのではないかという手に汗握る展開、人間の先入観をうまく利用する伏線、就活の疑問や人間の醜い部分を曝け出すようなストーリー。すべてが六人の大学生たちを輝かせていた。 みかん 神奈川大学 1年 物語は、仲間だと思っていた人の裏の顔が徐々に明らかになり、互いに疑心暗鬼する展開が非常にリアルでした。そしてこの本を通して、人間は良くも悪くも裏の顔を持っている、そう強く思いました。しかしだからと言ってその人が見せる顔がすべてだと思ってはいけないことも、この本から学びました。結局その人の全てを知ることは難しいけど、少なくとも人を見た目や一部の情報から簡単に「こういう人だ」と判断することは止めよう、と周りの人に対する見方を大きく変える一冊となりました。 マズルカ 東京大学 4年 人と深い付き合いをするのが苦手だ。気を許されたがために、信じていた人の裏の顔に出くわすのなんて真っ平御免。陰口だって嫌なのに、裏の顔が「人殺し」である嘘つき就活生の話と聞き、躊躇いを覚えないではなかった。
物語を現実に持ち込むまい。事前の決意はどこへやら、見事に周りへの不信感に押し潰された。怯え苛立ち、距離をとり……読み終わるまでの私は、さながら手負いの獣も同然だっただろう。それでも。結末を迎え、とめどなく溢れたのは優しい涙だった。
明日が、他人が、怖いあなたに読んでほしい。
大事なのはそれからだよ。ぽんた 甲南大学 3年 就活中の6人の大学生が最終選考で心理戦を繰り広げるミステリー。最初は皆仲良く就活を頑張る仲間として協力し合っていたが、最終選考でそれぞれの過去の”罪”が明らかになっていく。その部分が人間の闇や裏の顔を表しているようで面白かった。また、予想していた犯人とは違う人物で驚いた。現在、私自身就活中なので登場人物らが感じていた不安や恐怖にとても共感できた。 ぽりたん 九州大学 3年 私たちは、ある人の一面だけを見てその人の全てを分かったような気になってはいないだろうか。学生同士が話し合って内定者を決める、特異な就職面接の中でスキャンダルや詐欺商法への加担などが匿名で告発される中で、各人への評価は激しく移り変わる。これを告発した犯人は誰なのか。その動機は何なのか。終盤、犯人が明らかになった後もどんでん返しは続く。スキャンダルや詐欺商法への加担は事実であったが、その背景が明らかとなり、更に彼らへの評価は移り変わる。私たちは他人を正しく評価することなんてできないと分からされた。 丸犬 名古屋大学 3年 嘘をついたことのない人、というのはいるだろうか?多分、いないだろう。
では、嘘をついた人はみな悪人となるのだろうか?
そんなことはないはずだ。嘘をついたからといってその人全部が悪とは限らない。あるいは、その嘘は優しい嘘だったのかもしれない。
嘘をついた人の全てが悪である訳ではないように、私たちが人と触れ合う部分は表層の一部で、それら全てで人を規定することなどできるはずがない。人と付き合っていく上で、その事実は諦めでもあるし、救いでもあると思う。この本を読み、そんなことを感じた。もろっこ 大阪大学 1年 何度も読みたくなる就活ミステリーだ。伏線回収が綺麗で圧巻だった。
読み終わってからもずっと「いい人・悪い人とは何か」や「人を信じるとはどれだけ難しいことか」について考えさせられた。「おそらく完全にいい人も、完全に悪い人もこの世にはいない。(中略) 一面だけを見て人を判断することほど、愚かなことはきっとないのだ。」という言葉には戦慄した。
ミステリーとして面白いだけでなく、就活についての知識や採用側の人の状況も知ることができ、読んでみて損はない作品だと思うので、ぜひ大学生は手に取ってみてほしいです!さくたん 札幌大学 1年 一気読み間違いなし!!
成長著しいIT企業「スピラリンクス」が初めて行う新卒採用の内定一枠を賭けた六人の就活生の物語。内定を賭けた議論が進む中、六通の封筒が発見され、個人名が書かれた封筒を開けると「◯◯は人殺し」だという告発文が入っていて…。
伏線回収が素晴らしく、何度予想しても裏切られる展開に読み進める手が止まらない。最後の最後まで面白いので、是非読んでみてほしい。猫武将 近畿大学 4年 新進気鋭のIT企業「スピラリンクス」。5000人を超えるエントリー者のなかから最終選考に残ったのはたったの6人だった。そして最終選考は「6人が話し合い、最も相応しい内定者を決める」という異例の選考だった。選考が始まり話し合いが進むなか、1つの封筒が目に付いた。中には6人への告発文が入っていた。この封筒を用意した犯人がこの中にいる…というお話し。映画化で話題の一作。就活を終えた今この本を読むと、当時の記憶が蘇ってきた。この本から学んだのは「人事は人を選ぶプロではない」ということ。就活を控えた人にオススメ。 アサ 名古屋大学 3年 就職が目前に迫る私たちの学年でその活動とは一体なんなのかと見つめ直すきっかけになった。誰しも猫を被るということがあるように就活生はもちろん、会社側だって都合のいいことを述べ合っていると思ったら本当にいい人を見極めるなど難しいのだと感じだ。誰しも表向きの顔はあり裏側の顔など見せる機会などない。月の話にあるように私達は表面上でしかみたいなのかとも思う。それでもその裏側もやっぱり自分であって、本質の見極めというか根本の魂を知りたいと感じた。さぁ私はこれから始まる面接で何を話そうか。 みっきーーー 大阪大学 1年 今から就活を始めようとしている大学生である私にとって、この小説が与える影響は大変大きいものでした。就活の厳しさ、現実味はわかっているつもりではいました。けれどこの本と出会って、本当の仕事社会への入り口とはそんな簡単なものではないんだなと改めて実感しました。この小説では六人の大学生が他の五人を陥れあってそれぞれの内定に近づこうとしています。一つの会社への入社のためにそこまでしなくてもと思いますが、実際私が就活していたら少し共感できる部分もあったと思います。読者に共感と恐怖をもたらす1冊です。 らな 東京経済大学 2年 この本は就職活動を軸にした小説であり、大学2年生の就活を目の前にした今、就活は最後は運である、人事でも嘘は見抜けない、企業側も嘘をついているといった本性を知ることになり少し怖かったが実際その通りであると思った。前半では全員が悪人に見えるが、伏線が回収され、後半には一周まわって登場人物の別の一面が見えてきて読み応えがあった。
誰にでも表向きの自分と裏向きの自分がいる。自分が今見えている世界だけで考えるのではなく、広い視野を持って全てを知らないと分かりきらないんだと感じた。おもちのろん 滋賀大学 1年 題名の通り嘘つきの大学生が登場し、就活に挑む話です。しかし、その六人は様々な人間性を持っていました。読み終えた今なら、登場人物の初めの印象とかなり変わった印象を持つ人もいます。読者にとっても、登場人物にとっても、その人の印象が大きく変わる出来事があり、読者として推理していた私も、印象が変わりました。この小説は最後に大きなどんでん返しがある小説では無く、ずっとどんでん返しの小説です。読者が思考を休める暇などありません。ただ私には、嘘を見抜く力などないと思いました。きっと誰もがそう思える小説です。 なとり 北海道大学 3年 非常に面白かった。騙し合いのコンゲームのような作品かと最初に想像したが、非常に心温まる話だった。まずそもそもの状況設定にぐいと引き込むものがあり、告発シーンはグイグイと読み進まる。随所に挿入される現在のシーンとのギャップも面白い。各所の伏線を回収しながら綺麗に締めるところがミステリとしてもよくできており、結末の後味もよかった。推理のロジカルさも好印象。
-
投稿数:15『傲慢と善良』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント うなこ 広島修道大学 3年 自分の恋愛と重ねてしまった。
相手に自己評価をつけて判断している。
自分より下に点数をつけた人は恋愛対象として外している。相応しくないと思う。これは自分だ、と思った。
更に自己評価が高いことも自分だと思った。
世間知らずに育て上げられた真実のように育たなかったのは、ある程度都会で育ったおかげだろう。
でもやっぱり、この作品の真実は都合いいな、運がいいなと思ってしまった。
最後まで傲慢さが捨てきれてないし、勿論それは架もだけど。
最後に駆け抜ける感じは無理矢理感が少しあって苦手だった。二人が結局結婚する所も。mint 東京農業大学 1年 この本では他人に対する様々な欲望がリアルに書かれている。他人に対する欲望は何もせず相手に伝わることはない。だから、伝えるために言葉で行動で示さなければならない。しかし、必死に相手に伝えていても伝わらないことや「傲慢だ。迷惑だ。」と相手に拒絶されることもある。拒絶されることが怖くて動けないこともたくさんある。でも、たった1度の人生だ。欲望のまま生きるのもいいなと思った。 みどり 早稲田大学 1年 人間の持つ、自己の相対価値を傲慢に見積もってしまうところや、人から尊重されたくてよく見られようと装ってしまうところをただただ痛いほど突きつけてくる1冊。「結婚だけがすべてじゃない」というような最近の論調に則るのではなく、「結婚をしなくちゃ負け組」というような既存の社会の価値観に則らざるを得ず、どうしても人と比べて高い社会的地位を得ることに囚われてしまう私たちを的確に描写している。いつか、私も主人公の婚約者のようにその締め付けを緩められる時が来るのだろうか。 鷽秋かおす 東北大学 3年 これはある男とある女を主軸にした物語である。この本を読む前に、是非タイトルを注視して欲しい。「傲慢と善良」何が想像できるだろうか。その想像を裏切ることと、そして読後には納得することを保証する。これは特別な誰かの物語ではなく、これといった奇跡も起こらないけれど、だからこそ「刺さる」小説である。男女問わず、普段小説を全く読まないという方にこそ強く勧めたい。男の何気ない(悪意のない)発言が、物語の鍵になるのだが、この「取り返しのつかなさ」が、男に共感していると、かなり痛いはずだ。面白かった。 西山 関西学院大学 1年 自分は傲慢か、はたまた善良か。傲慢な魚、善良なゴキブリなんて聞いたことはないけれど、想像は不可能でない。一方で、そのイメージが人格的であるのは、このような形容が人間に特有だからではないだろうか。さて、この話の主人公、架と真実は婚活を通してそれぞれの境遇、心情の中で出会い、結婚を約束するものの、ある日真実は姿を消してしまう。彼女を探す中で架は、自身の、彼女の、そして社会の傲慢さ、善良さを認識していく。架が探していたのは真実(まみ)であり、真実(しんじつ)であったかもしれないことを、振り返って思う。 アサ 名古屋大学 3年 小さな世界ではある点と点が全てだと思い、たとえ歪だとしても無理やり線で結んで辻褄を合わせようとしてしまう。一見浅い知識ゆえの仕方ない行動に思えるが、もっと周りを知ろうとしていないのであればそれは傲慢だ。スマホやゲームなどの娯楽の発展で恋愛にのめり込む現代人は少ないが、いつかはそれなりに恋をしてびびっとくるいい人と結婚して子供を産みたいと高望みしている。自分という形に完璧に合わせてくれる人は絶対にいないのに。寄り添うだとか支え合うだとか妥協でものを言う資格は自分にあるのか。その答えを教えてくれる。 てとらぽっど 横浜市立大学 1年 タイトルにもある、「傲慢と善良」という言葉が当てはまる登場人物が多く出でくる。それ故の、彼らを取り巻く問題、人生に同情したり不思議に思ったりする。また、彼らと重なる部分で、痛いくらいに現実を知らされる、目をそらしたくなる部分で目をそらさせない筆者の語りかける力が強いと思う。特に、「自分がない」という人はぜひ読んでみてほしい。私自身も、登場人物と重なるところがあり、今、自分を変えたいという気持ちで溢れている。 みっきーーー 大阪大学 1年 婚活で知り合った2人の男女がそれぞれ家庭の事情を抱えながら大恋愛をする物語です。大恋愛をすると言ってもただ愛し合うだけの関係ではないのです。ストーカー事件や失踪事件が起こりながらもつながり続ける2人。私はこの本を読んで、恋愛というのはほんとうに人間の数だけあるものなんだなと感じました。私だったらこんなことはできないと思う場面があったり、一方でそんな気持ちになるのも理解できるという場面がいくつもあります。最後の最後までどのやうな結末になるのか分からないので一気に読み進めてしまいます。 らな 東京経済大学 2年 第一章の最後でこの本の最大の謎が分かり、二章への展開にゾッとした。私は物語に出てくる真実に非常に共感した。小さい頃からいい子に育ってきて、容量が悪く、大人しい性格である真実は私とどこか似ていた。そんな真実が遠くの地で1人、自分を変える行動をしたことは、非常に凄いことだと思った。私もやりたいことに挑戦して、自分の今見える世界を変えたいと思った。 猫武将 近畿大学 4年 長い婚活期間を経て、ようやく婚約者と巡り会えた西澤架。ある日、彼の婚約者である坂庭真実が失踪した。以前からストーカーによる被害を訴えていた彼女だったが、架は真剣に取り合わなかった。真実の失踪を機に、架は本当の彼女を知る…。
映画化で話題の一冊。大人の恋愛が描かれた恋愛小説だが、恋愛要素だけでなく「自分らしさ」とは何かが描かれていると思う。この本のタイトルにもなっている「傲慢」そして「善良」。
この本を読めば無意識の「傲慢」と「善良」であるがゆえに被る不遇を自らの人生と照らし合わせることができるはず。チカパシ 立命館 3年 30代の結婚観についての話だが、私たちのような大学生にも当てはまるような、胸が痛い物語だった。過去の出来事を引きずっていたり、そのせいで目の前の相手に全く向き合うことができていない自己中心的な考え。知らぬところで人に行動を縛られてしまっていることが、自分かわいさゆえに中々気づくことができない主人公の心情がリアルに描かれていた。 にょーん 名古屋大学 1年 どこの書店に行っても入り口など目につきやすいところに大量におかれているのをみてずっと気になっていた作品です。読み始めると止まらなくなるくらい物語の世界に入り込めて満足できた。主人公の婚約者の失踪の理由は以外だったけれど、その理由がわかってからはミステリーよりも人間ドラマのようになりそのあと2章の展開が変わるのも意外で楽しかった。自分より少し年上のおとなに読んでもらいたい作品です あかね 岡山大学 4年 映画化もされていたので、タイトルは知っている人もいるかもしれません。婚活についてのお話。主人公西澤の婚約者・坂庭真実がある日突然姿を消し、その居場所を探すため、彼女の「過去」と向き合っていきます。
「恋愛だけでなく生きていくうえでのあらゆる悩みに答えてくれる物語」です!読み終わった後ちょっと人間不信になるかも?ぜひこの世界を体感してみてください。たま 京都大学 3年 現代人が婚活をうまく進められない理由は、傲慢さと善良さにある…これは、結婚相談所の仲人の言葉である。傲慢さはなんとなく分かるけれど、善良さも仇となるのか? 婚約までしていた彼女が失踪し、その足取りを過去に遡って追いかけるアラフォー男性・西澤架。彼女の人生を追っていくうちに、傲慢さと善良さの謎が明らかになっていく。婚活なんて大学生にはまだ早いと思うかも知れない。しかし婚活というひとつの事象から炙り出されるのは、現代人みんなに共通の心の中。彼女の行方にも注目しながら、人間性を考えさせられる一冊。 ぴょん 名古屋大学 1年 世間でも多くの人が利用している婚活アプリで出会った男女についての話でした。
昔は結婚って憧れていたはずなのに、いつしかしなければならないという義務感ばかり…。
本当の好きってなんだろうと考えさせられるお話でした。
-
投稿数:15『推し、燃ゆ』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント Mal 愛知教育大学 1年 推しと言う言葉が身近になった現代において、推しの炎上、推しが推しでなくなる瞬間。“推し”がいる人ならば直面するであろう問題からどう逃げるか、あるいは立ち向かうか。自分も“推し”がいるので、自分自身に問いかけられたような気がした。推しがいればなんともなかった問題も推しがいないだけでこうも拗れていくのかと、恐ろしくもなった。“人”になってしまった“推し”を私は応援できるのか。“推し”がいなくなった私はどうなってしまうのか。考えさせられる作品だった。 ぽてじゃが 滋賀大学 3年 推しは偉大だ。私にも推しがいる。主人公ほどの熱意を持っているとは言えなが少なからず生きる一つの目的になっていることは事実であり、そのような推しを「背骨」と表現したこの物語を忘れることはないだろう。背骨という表現はとてもしっくりくる。誰しも日常を送るためには背骨が必要であり、これが推しの人もいれば仕事の人もいるだろう。背骨を大切に生きていこう。 緑内障予備軍 桜美林大学 1年 授業中にところどころ抜粋され、全体的な内容が気になったため読んでみました。この物語の主人公は推し活に励む女の子です。冒頭は読みやすいと思いながら読み進めていましたが、途中で主人公の推し活への熱意に狂気を感じ、戸惑いを感じました。また、病気設定が明らかになってから話に入り込めなくなってしまい、純粋に楽しむことができませんでした。主人公に共感できる人にはおすすめの作品だと思いました。 月 広島大学 2年 推しがいる人、特に人生を捧げて好きだと言える推しがいる人は絶対に見てほしい。推しは単純に好きという気持ちではなく、人生そのものを形成する存在なのだ。人生を豊かにするコンテンツの一つのはずだったのに、気づけば推しなしでは生活できないほど依存していて、それが良くないことだと分かっていてもやめられない自分の気持ちが少し昇華された気がした。リアルを犠牲にして推しにつぎ込んでいる今、推しがいなくなったらどうなってしまうのか皆目見当もつかない。本作主人公の気持ちが痛いほどわかってやるせない。 ぜう 西南学院大学 2年 みなさんは「推し」はいますか? 私にはいません。そんな私でもこの本から推しという存在に対する解像度がとても高くなりました。この本を読み始めた当初、熱烈に推しを応援する主人公のことを少々オーバーに感じていましたが、うまくいかない日常の中で推しの沼にはまるその姿はあまりにもリアルに描かれていました。そして自身の全てを注ぎ込んできた推しが突然炎上したとき、人はどのような反応を示し、その後どういった行動に出るのか。私の知らなかった「推し」という存在がいる世界をこの本は教えてくれました。 カステラ 弘前大学 1年 「推しが燃えた。」という印象的な1文から始まるこの本は、推しがいる私にとって、自分だったら…と想像を掻き立てられるものだった。五感による表現が豊かで、自分が普段何気なく目にしているものも、生々しく表現されている。推しに初めて出会ったときの衝撃、推しに支配されていく生活、偶然目にしたネット上の言葉がまとわりつく1日、推しに関わることは夢中になれるのに日常生活は器用にこなせない居心地の悪さなど、普段心の中に留めておいている感情が綴られていて、共感でき、心に残ったストーリーだった。 1ch 富山大学 1年 芥川賞を受賞した本作品は、主人公が突然推しを失った失望感がありありと描かれていた。現代っ子の推しという存在が私たちにどれだけ影響を与えているかが、象徴的に描かれている。私自身の推しも、私自身の生活の一部と化しているが、推しがいなくなったら、、、ということは考えたくないものである。言葉の文が巧みで、読み応えがあった。 ふぁくせ 東京農業大学 4年 あなたには「推し」がいますか?
私にはいます。同じ次元にも、別の次元にも、愛おしい「推し」が私を支えてくれています。いつもありがとう。
多くの人が「推し」という存在に支えられている今、この物語はまるで自分と同じ世界を生きている誰かの日常を盗み見ているような気持ちになります。
この物語の推しポイントは、『誰もが通った、あるいは通るであろう身近な存在「推し」を取り扱っていて物語に入りやすい』『「大きめの文字」「短めの文章」で、普段本を読まない人も読みやすい』所です!ラッキー 神奈川大学 1年 推しが炎上した。私にその経験はない。推しはいるが、炎上したこともないし、炎上するほど人気でも有名でもない。しかし、私の生活の中心でライブに行って配信を見て、2500円でチェキを撮ってお話する。そのために働くし大学生なってやっと沢山会える様になった。あかりとは少し違うが、推しのグループももうすぐ解散する。推しが炎上しても応援し続けているあかり、しかしいきなり自分の前からいなくなったら、引退したらファンの力ではどうすることもできない。それでも生きてみようするあかりはとても強いと思う。 がうっちぃ 静岡大学 2年 アニメーション映画を見ているような細かい描写だった。色は抑えめで淡々と進む。けれどラストは静的なのにダイナミックで。文体は読みやすいのに、手足を後ろで縛られて、ピンクと紫を混ぜたような色の毒を飲まされているようだった。絵の具のようにドロドロとしたそれは、わたしの腹の中で重くのしかかっているような気がした。 ぴにょー 弘前大学 3年 貴方にとって「推し」とはどのような存在でしょうか。
「推し」を推すことは、主人公のあかりにとって「背骨」であり、「推し」がいない生活では、あかりは普通の生活さえもできなくなってしまいます。
この本を読む以前、私にも「推し」がいました。私の推し方は、遠くから「推し」を見つめ、「推し」の幸せを願うというものでした。
「推し」の文化には、本当の意味で〈心〉を奪われ、いつかは終わってしまうことだってある〈推し活〉に身を捧げる人がいる。それは果たして幸せなことなのか。そんなことを考えさせられる本でした。鷽秋かおす 東北大学 3年 推しは神だ。思考回路と行動原理がひとつづつ推しへと向いていき、全ての事柄が推しに始まり推しに繋がると考え、最終的には推しを推すためだけに明日があればいいとさえ思う。これはとある作家を熱烈に推していた過去の私である。主人公と私の「推し方」はかなり近い。当時の私にとって、大学の受験勉強すら推し活の一環でしかなかった。私にとってこの小説は、あり得た世界線の自分である。彼女にもう少しの器用さがあったならと歯がゆい気持ちになる。しかしどうすることもできないのだ。それは自分がよく分かっている。 あおりんご 名古屋大学 2年 愛しい人にもう二度と会えないかもしれないと知って失恋のような痛みをおぼえたとき、ふとこの本を手に取りたくなった。主人公の推しへの熱意や絶望、うまく生きていけない痛みなどが生々しく描かれていた。さまざまな描写において肉体についての表現が数多くあるのが印象的で、主人公の苦しさが読んでいる身にも伝わってくるようだった。現代特有の「推し」文化について鮮明に感じられるだけでなく、文学としても愛すべき作品だ。 チャーリーブラウン 九州大学 2年 推しを追う10代の主人公のリアルを鮮明に映し出した小説だと感じた。主人公にとって推しは自分の”背骨”であり、つらい学校生活や家庭の状況、勉強からの逃げ場となっていた。主人公ほど過激ではないが、私自身も推しを心のよりどころにしているところがあり、その態度に共感できた。推しに自分のすべてを投影するのではなく、生きていく中で一種の指標になればいいと学んだ。 ブルーハワイ 名古屋大学 2年 主人公の感情を様々な表現で鮮明に書かれていて、他人である自分がまるで主人公になったような感覚になれました。内容は全体的に暗く落ち着いていて、夜に自分の心情全てを預けて読むのにちょうど良いものでした。
また、特筆した「好きなもの」がない自分にとって、今までは「推し」という感覚があまり身近ではなく、さらに言えばその手の話は少し取っ付きにくいとも思っていたのですが、この本を読んで「好きなもの」、「推し」の存在がこんなにも生活を支えることが出来るのかと考えさせられ、羨ましくも感じました。
-
投稿数:14『博士の愛した数式』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント あ お茶の水女子大学 1年 読み終えて、とても温かくて優しい気持ちになった。誰よりも博士の数学への愛を理解できるし、感覚を共有できることをとても幸福に感じた。博士のルートへの愛情は寛く尊いもので、こんなに真摯に曇りなき愛情を注ぐことができることは幸せだろうなと思った。
「私たちはただの広告の紙に、いつまでも視線を落としていた。瞬く星を結んで夜空に星座を描くように、博士の書いた数字と、私の書いた数字が、淀みない一つの流れとなって巡っている様を目で追い掛けていた。」デイジー 東京農業大学 1年 私がこの本を読もうとおもったのは裏表紙にあるあらすじに「ぼくの記憶は80分しかもたない」と書かれていたからである。記憶障害を題材にする小説はいくつかあるが、数学者×記憶障害は見たことがなかったので新鮮だった。読んでみると博士は人生の途中までの記憶は完全にあるがこれからの記憶は80分しかもたないという病気らしい。1番心に残ったのは家政婦の子供「ルート」を思う気持で、その分ルートも家政婦も博士を愛していた。血の繋がりがなくても、記憶がなくてもここまで他人を想い行動することができることがとても素敵だった。 おまつ 名古屋大学 1年 心温まる物語でした。博士の子供を愛する心や、ルートの成長、「私」の人を思いやる性格が読んでいて嬉しくさせました。三人で出かけるシーンや、お祝いをするシーンにはほっこりするエピソードと共に、ふとしたことがきっかけで不安が現れる危うさもありました。ハートフルな場面が続きながらも、博士の病気により常に切なさが付きまとっている雰囲気が独特でした。 月 広島大学 2年 人の温かさやぬくもりを感じられる、現代に生きる人にこそ読んでほしい作品。物語で主に登場する人物はたった三人だが、三者三様に思いやりをもってお互いを尊敬した行動をとっている姿に胸を打たれた。私は数学が嫌いだが、数字を博士や家政婦のように捉えることができればもっと視野が広がり楽しい人生を歩めるのだろうなと思った。数学がほんの少しだけ、面白いと思えた。 にょーん 名古屋大学 1年 数学と記憶障害と阪神タイガース。この結びつけようにも結びつかないようなキーワードが、家政婦の「私」と「私」の息子のるーとと記憶が80分しかもたない博士によって美しく織り成されます。優しいひとびとによる優しい物語です。3つのキーワードのうちどれか1つでも興味がある人にはぜひ読んでいただきたいハートフルな内容です。 くさだんご 北海道教育大学 1年 これは、事故によって記憶を80分しか保つことのできない博士と、そこに奉公している家政婦、そしてその息子であるルートによって紡がれる愛の物語である。もちろん、「数式」と題名にあることから、この本には数学がかなり登場する。数学を高校で一通り学んだと思っていた私でさえ知らなかったことが多く綴られており、数学の美しさを再認識した。この数学が3人を繋げていく描写が繊細だった。80分しかもたない博士の記憶の中で家政婦とその息子の2人はどういう関係を築こうとしているのか、儚くも心にずっしり響く物語であった。 くりごはん 北海道大学 2年 なんて穏やかで柔らかな物語なんだろう。80分しか記憶がもたない博士、博士の家で働く家政婦とその息子の会話の節々に、互いを大切に思いやる気持ちが表れていた。次に博士と会う時は、初めましてになってしまう。けれど、神秘的な数字の関係を介して、心の奥深くで繋がっていける。そう信じて彼と僅かな時間を共にする彼女らの姿に、胸を打たれた。この本を読んで、今まで無味乾燥なものだと思っていた数字に味わいを持てた。何かを伝える時、博士はいつもそっと数字を持ち出す。彼のその柔和でさりげない優しさが私は大好きだ。 ぜう 西南学院大学 2年 文系で、数学に対する苦手意識が未だに抜けない身でありながら、この本には引き込まれるものがあった。数学の「博士」が出てくるからには、ある程度の知識が必要なのではないかと身構えて本を開いたところ、それは杞憂に終わった。博士の口から語られる数式は小学生でも理解できるようなものではあるが、その数式自体に存在する宇宙のような広がりや、数学の授業では感じたことも無かった温かみに触れることが出来るとは思ってもいなかった。文系にこそ届いてほしいし、この本が初代本屋大賞受賞の作品ということも頷けるはずだ。 もろっこ 大阪大学 1年 80分しか記憶が続かない数学者と、その担当家政婦、そして彼女の息子の日常を描いた物語。
細かな描写や、小川洋子さんの紡ぐ綺麗な文章が心に染みる作品だった。
なんの繋がりもなさそうに見えて、3人は絶妙に互いを頼りにしている。物語としてまとまりがよく、ラストには思わず息が漏れた。
数式もよく作中に出てくる。私には理解できないものもあったが、それらを自分で調べてみるのも楽しい時間だった。鳥博士 東洋大学 3年 「これ、社会に出て何の役に立つの?」数学を嫌っていた私が読んでみた。
220と284は友愛数である。記憶が80分しか保てない博士はそうやって相手との関係を築いていく。今、友愛数と聞いて、ダメだと思ったそこのあなた。ぜひとも読んでほしい。私と同じように、友愛数で通じ合う登場人物達の姿を見て心を打たれるから。
この本を読んでも、難しい数式が解けるようになるわけではない。しかし、数字がただそこに無機質に存在しているということ。無意味なものとは決して思わなくなるだろう。とー 東京経済大学 2年 自分は数学が苦手で好きでもなかったが、この本の博士が語る数学は、素晴らしく興味深いもののように思わされた。老人と家政婦、子どもという類似性のない人たちが、ときに数学をコミュニケーションの手段としながら交流していく様子は、とりとめのない日常の愛しさを教えてくれる。互いが互いを大切に思い合う様子に心打たれた。 DB好き 名古屋大学 3年 世の中には数字が溢れている。私たちは基本的に日々生活していく中で、その数字の意味を深くは考えない。この本では、その数字の運命的な、神秘的な美しさを教わった。普通の数字でも博士の言葉によって鮮やかになり、全く異なる場所にいるような気分であった。同時に、主人公が次々と数字に魅了されていき、導かれていく描写も素敵であった。分からないことは恥ではなく、新たな真理への道標。自分も日々分からない壁に当たるが、主人公との違いはそこに美しさを感じるかであった。数字に関わらず、純粋な探究心を思い出させてもらった。 詩暢 京都大学 1年 本を開けば、博士の部屋の埃っぽい空気感が立ち上がってくる。
博士を喜ばせようと奔走する家政婦の「私」とその息子、ルート。
幼いルートに向ける、博士のまなざし。
彼らの心の交流に、忘れかけていた大切なものを思い出させてもらった気がする。劇的な出来事が起こるわけではないけれど、物語は穏やかな幸せに満ちている。
いつか、終わりを迎える。そううっすらと予感しながらも、彼らの日常がずっと続いてほしいと願わずにいられなかった。ぷにタン 釧路公立大学 2年 文体がとても整然かつ美しく、読み終わった後は浜辺の引き波を眺めているような気分でした。友愛数によって結ばれた博士と家政婦、そこに加わる息子のルートとの絆の、言葉にできない尊さと温もりに読んでいて惚れ惚れとします。主人公が母親なので、この本をまた歳を重ねてから読んだら今とは違う新しい発見ができそうだなと感じました。
-
投稿数:14『世界でいちばん透きとおった物語』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント san 東京都立大学 1年 この本をおすすめしようにも、なんと伝えればいいかとても悩んでしまう。きっと、ただ本そのものを差し出し、「亡き父の小説を探すお話だよ、”体験”してみて。」と伝えることしかできないと思う。
帯に書かれた「電子書籍化絶対不可能!?」に誘われ、読み進めれば進めるほど増える謎にページを捲る手は止まらず結末をむかえてしまったが、ラストには確かに『透きとおっていた』。ちゅね 名古屋市立大学 2年 物語を読み終わったあと、本当にもう一度読み返した。
SNSでバズってたから読んだ1冊。初めは表紙の絵柄から恋愛小説なのかな?と思ってたけど、読み進めていくうちにどうやら違うなと分かった。恋愛要素もあるけど、それ以上に家族の愛情を感じる話。終盤の謎が明かされるシーンが感動的すぎて、ロッテリアで読みはじめたことを超後悔した。
あと、帯に「この物語を読んだ後、きっともう一度読み返したくなる。」って書いてあって大袈裟だなーと思っていたけれど、マジで読み直しました。齊藤 宇都宮大学 2年 話にどんどん引き込まれた。最後の2章は目を見開くほどの展開だった。伏線回収はさることながら、組版のトリックがとても素晴らしい。途中から「世界でいちばん透きとおった物語」の真実については薄々勘づいてはいたが、その勘を上回るほどの事実に胸を踊らされた。今までに体感したことのない感動と、ピッタリとハマる感覚を賞賛したい。 でんでん虫 名古屋大学 1年 この本に仕掛けられたある工夫に気づかされた時、とてつもなく衝撃を受けました。気づけばページを何度もめくり返していました。言葉のひとつひとつに施された工夫に、感動を覚えました。普段あまり本を読まないあなたにも、もちろん読書好きなあなたにもおすすめしたい1冊です。
-大御所ミステリ作家宮内彰吾は死亡した。宮内の不倫相手の子供である「僕」は遺稿探しを始める。-
電子書籍化絶対不可能!?、紙の本でしか体験できない感動を是非、体験してみてください!本を読む看護学生 新潟大学 1年 この本は紙書籍に宛てられた盛大なラブレターだ。
殊更に感動を強調する内容ではないし、涙を誘う要素は少なかったはずだった。でも私は読後、号泣した。事件を追いかけているわけではないのに、散りばめられたヒントがクライマックスで一つの像を結んだ。いや、「像を結んだ」というよりは「透き通っていた」という表現が適切だろうか。その時に、なんだかどうしても泣きたいような感傷で胸がいっぱいになった。とても凸凹していて奇妙な形の「愛」を目にしたからだと思う。電子書籍の時代にむしろ、これは紙で読むべきだ。おむらいす 名古屋大学 1年 ミステリー作家の宮内彰吾が死去した。彼は死の間際まで「世界でいちばん透き通った物語」を書いていたという。その原稿を探すため宮内の息子から捜索を依頼され、宮内の隠し子である主人公は遺稿探しを始める。
この物語を読み終わったとき、トリックに「まさか!」と思い、前のページに遡ってしまった。正直に言って何を言ってもネタバレになってしまう。「強烈な読書体験」と著者が言う通り、この本の仕掛けはきっと一生忘れることができない。バースデーケーキ お茶の水女子大学 3年 タイトルや「電子書籍化不可能」というキャッチコピーから、大体の仕掛けは予想できていたものの、著者が成し遂げたことは予想をはるかに超えた偉業だと感じた。主人公自身の作品とする設定はもちろん、京極夏彦や谷崎潤一郎の「春琴抄」など、現実世界と物語世界の交わり方もシンプルであると同時に幻想的なのが印象に残る作品だった。 りゅ 弘前大学 1年 結末に近づくにつれて、「これも伏線!?こっちも!?」と驚くことばかりの物語。この小説を完成させたこと自体天才だと思う。藤崎翔の「逆転美人」と同じように、絶対に電子書籍化はできない小説。紙の本でないとこの小説の感動や衝撃を味わうことはできない。とりあえず読んでみてほしい。今までにない本の美しさを感じることができ、この小説以外に「世界でいちばん透きとおった物語」というタイトルをつけることができないと感じられる。 げっこー 宇都宮大学 3年 ある一文を読んだ瞬間、ゾッとした。自分自身も、この本に隠された仕掛けを当に体験していたからである。小説は物語そのものを楽しむもの。今までそう思っていた。しかしこの本は私のそんな思い込みを、一瞬で消し去ってしまった。物語そのものだけではなく、作者のトリックにも本当に驚いたし、このような形でも読者を楽しませてくれる本があるのだと感動した。電子書籍が普及する現代だからこそ、紙の本の魅力を再確認できる一冊である。読み終わった際にはきっと、心が「透きとお」ったように感じるであろう。 すい 富山大学 4年 「…そういうことか」
電子書籍では味わえない感動。電子書籍派の人もこれだけは紙で読んで欲しいと思った。読み終わり、とあることに気付いた時に衝撃を受けた。そして、次の瞬間もう一度最初から読み始めた。
何を書いてもネタバレになってしまう。この作品はどんな状況であってもネタバレ厳禁。でも、誰かに話したくなってしまう。同じ本を読んだ人と感想を話し合いたいと感じた。y 滋賀大学 2年 全体的な話としては普通だけど、タイトルの意味が最後まで読むことでわかったときは、これまでのページ全部を見返したくなるほどびっくりした。帯にも書いてあったようにこれは、電子書籍では絶対に味わえない感動だと思う。話の構成上、小説を出版するまでの過程や小説家たちの仕事が学べるところもよかった。絶対にネタバレされる前に読むべき。 かなあみ 金沢大学 4年 紙のページを捲って、真実に気付いた時、私はゾッとした。人って、こんなことができるんだ、と。やろうと思ってできるものではないし、やってみようとも思えない。でも、この本は私の手元に存在している。その事実からは、絶対にこの仕掛けを完成させてやるのだという執念すら感じた、そんな本でした。
この読書体験は、人生で一度しか味わえないと思うので、皆にも読んでほしいです。電子書籍化が不可能故に、紙の本しかないので、書店まで買いに行くことをお薦めします。大春車菊 名古屋市立大学 1年 すごい。本当にすごい。それしか出てこなかった。
この物語はミステリである。そして謎が解けたとき、私たちは主人公と同じ感情を抱くことになる。それは驚愕、動揺といったものであるが、その感情は小説の内容のみに向けられたものではない。このような本が存在しているという事実を、私は受け入れることができない。本当にすごいのである。
紙の本でしか味わうことのできない感動を、ぜひ体感してほしい。お茶ごくごく倶楽部 大阪大学 1年 どういう結末になるのだろうと考えながら読んでいたが、全く予想もしなかったところを突かれた。そこがあったか!!と作者の発想に脱帽です。いろんな伏線が緻密に張られていて、それらが最後に見事に回収されていくのは読んでいて気持ちがいい。ストーリーでしっかりと魅せてきた。何を言ってもネタバレにないそうなのでまだ読んだことのない人はすぐに読んでみて欲しい。もちろん紙で。この本はきっと“言葉で心臓を刺す”だろう。
-
投稿数:13『方舟』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント dusk 名古屋大学 2年 とある理由から巨大な地下施設で一晩を過ごすことになった10人。翌朝に地震が起こり、扉が岩で塞がれ、閉じ込められてしまった。さらに地下からは水が溢れ出してきてこのままでは1週間で水没してしまう。1人を犠牲にすればここから脱出できる。そんな時に、殺人が起こった。さて、犯人は誰だ?見つけ出して犠牲になってもらうしかない。
ミステリとしての完成度はさることながら、その裏テーマとして存在するトロッコ問題のようなものに、とても考えさせられる作品だった。しっかり騙されました!ゆき 東京大学 大学院 ある地下施設に閉じ込められた。一人犠牲にすればその人以外は全員助かる。犠牲にするのは殺人犯だ。良心は痛まない。たとえその犠牲となる人が、過去に愛した人であっても。
選択を迫られたときに、その人と共に残る、その人の代わりに犠牲になるという決断ができる人はある意味で狂っていると思う。
わたしはこの『方舟』の中で死んだ。ごきりん 東北大学 4年 誰かを犠牲にしないと出られない、そんな空間で起こる殺人事件。地下空間の浸水は時間の問題、出口はただ一つ。犠牲になるべきは誰か?そんなの犯人に決まっている。生きて脱出するために犯人を捜せ!
これから読む探偵の諸君は、次のホワイダニット(動機)を考えてほしい。ハウダニット(犯行手段)なんて作中の探偵にでも任せておけ、トリックなんてこの作品ではおまけだ。
なぜ犯人はバレたら殺される中、殺人を行ったのか?
なぜ犯人は3人も殺す必要があったのか?
なぜ犯人は犠牲になることをすんなり受け入れたのか?きくけこ 北海道大学大学院 大学院 日本ミステリの歴史は『方舟』以前/以後に分けられるーそう思わせてくれる圧倒的インパクトを有する衝撃作。読み終わった後ここまで放心状態が長く続いた本は初めてだった。それほどまでに鮮やかで恐ろしい結末。作中の些細な違和感はすべて回収され、一つにつながっていく。「後期クイーン問題」への見事な解答や、名探偵という存在への皮肉など、コアなミステリファンも満足すること間違いなし。歴史の当事者になりたいあなたは今すぐ読むべし。未経験の衝撃を約束する。 みかん 神奈川大学 1年 残り1週間で殺人犯を見つけ出し、水没してしまう地下から脱出する、という非常に息の詰まりそうな展開が面白かった。読んでいる間はずっと苦しく、まるで自分もそこに閉じ込められているかのような緊張を感じていた。そして、予想もしていなかった結末には言葉が出ず、読み終わった後は呆然としてしまった。トリックも巧みで驚きがあり、非常に読み応えのある作品。 はると 東京大学 3年 久しぶりに震えたミステリー。素早い展開で読みやすいながら、漂う雰囲気は非常に重く、常に息苦しさが付きまとう。明らかにされた真相に驚き、その残酷な真相に絶望を覚える。非常に素晴らしい作品だと思うし、推理物好きの人にはぜひ一度は読んでみて欲しい。ただし、自分はもう一度読めと言われても読みたくはない作品である。 くろのすけ 横浜市立大学 1年 正直、何を言ってもネタバレになる。最後まで読み切ってほしいとしか言えないが、とにかく面白かったのだ。騙されたと思って読んでほしい。
主人公は大学時代の友人と行った謎の地下施設に閉じ込められてしまう。地下施設に浸水が始まりタイムリミットもある中、脱出するには誰か1人を犠牲にし装置を起動させるしかない。そんな状況で起こった殺人事件、装置を起動させ死ぬのは犯人であるべきだ……。
大体こんな舞台設定である。これだけで言えばよくあるストーリーなのだが、読めばわかる。唯一無二の衝撃をもたらすだろう。バースデーケーキ お茶の水女子大学 3年 地下建築に閉じ込められ、かつ1人づつ殺されていくというシチュエーションのなかで、想像していたよりもそこにいる人たちの混乱や狂乱が描かれていなかったのが、よりいっそう不気味で、極限状態を描かずに極限状態を表現するということに長けているように感じた。最後の展開は予想できないもので、これまで読んだ本の中でもトップクラスで不安が読了後に襲いかかるものだった。 さゆ 京都大学 2年 昔からアニメや漫画で好きになるキャラクターといえば、もっぱら悪役だった。今作は密室殺人、殺人に次ぐ殺人、人とは思えない殺人が起こる異常な空間に、自分がいる体でストーリーが進んでいく。良質な推理小説は登場人物が少ないとはよく言ったもので、どんどん容疑者が絞られていく一方でなかなか真実に辿り着けない。最後には「完璧な」推理と「思い通りの」展開に頭を殴られ、操られるように冒頭から読み返した。犯人のことを、もっと知りたいと思った。こんな小説、最初で最後かもしれない。 たま 京都大学 3年 地下建築に迷い込んだ10人。暗い中で山道を下りるのは危険なため朝まで過ごすことにする。すると不運な災害により出口が塞がってしまった!建物をよくよく調べると、1人が犠牲になれば他の人は助かる仕組みだと分かるが、そこで事件が起こる。その犯人が犠牲になるべきだと誰もが思い、推理が始まった。
最後まで読んだ時、犯人の恐ろしさに背筋が冷たくなりました。仲間のなかに絶対に犯人がいるという状況で互いに疑い合い、さらに「犯人だからといって犠牲にして良いのか?」と問いかける人間の姿。人間の狡猾さも窺えるミステリです。みさき 桜美林学園 1年 エピローグで衝撃のあまり頭が真っ白になった。文字通り180度ひっくり返された。
地震により9人が地下構築に閉じ込められた中で殺人が起こる。タイムリミットまでに犯人を見つけ出し、犯人を身代わりにして8人で脱出するのが最善だと思われたが、そもそも何もかもが真逆だった。最後、主人公が誤った二分の一の選択には言葉が見つからない。ラストの6人、特に翔太郎の絶望は計り知れない。私にとってはどんなに怖いホラー小説よりも恐ろしい結末だった。フレミッシュ 京都大学 大学院 地震で封鎖された地下施設〈方舟〉に閉じ込められた十人。脱出するには誰か一人が犠牲にならなければならない。そんな非常事態時に発生した殺人。犯人こそ犠牲になるべきだという合意のもとで犯人探しが始まるが――。
特殊なクローズドサークル内で発生した事件を明快なロジックで解き明かす見事なフーダニット小説。最後の数ページで明かされる真相に驚愕することは必須。ミステリーマニア 福井大学 3年 本書は洞窟という閉ざされた空間で起こる殺人、いわゆるクローズドサークルミステリーである。地震により男女10名が洞窟に閉じ込められるのだが、一人が犠牲になれば全員が助かるという状況に陥る。そんなとき、無惨にも殺人が起きてしまい…という内容なのだが、この作品の素晴らしいところはエピローグまで目が離せないというところである。きっとこの本を詠んだ人は最後の数ページを何度も読み返し、愕然とすることだろう。是非とも読後のなんとも言えぬ感情を味わって頂きたい。
-
投稿数:12『告白』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント こおり 三重大学 1年 友達にずっとおすすめされていてやっと読みました。1つの出来事に対して複数人の、視点からや日記形式、ブログ形式で書かれており様々な捉え方ができて色々考えさせられました。また、人間のリアルな感情も忠実に描き出されていてのめりこんで読み進めることができました。 花京院典明(本物) 名古屋大学 3年 少年犯罪が起きたとき、話題になるのは大抵事件を起こした少年少女の動機だった。
その根底にあるのは「純粋なはずの子供に何があったんだろう」という好奇心だと思う。
そして彼らの人生をストーリーとして消化して飽きたら忘れる。
そんな誰しもが持ってる醜い心を、作品の少年と同時に断罪していると感じた。黄色いキャバリア 徳島大学 1年 登場人物ほとんど全員の視点から書かれていた。それぞれの言い分考え方価値観があって、1人のエピソードを読む度何重にも物語が更新されていく。
森口先生はやはり復讐に静かながらも人生をかけていた。
渡辺修哉が生きる糧としていた母親を復讐の的にした。
最終的な復讐か完了され、後味がすっきりした話だった。予想もしないような結末で、夫が妻の復讐を阻止したにも関わらず、やはり森口先生は誰よりも上手だった。それぞれの考えていることや立場が明確化されている分、出来事一つ一つに引き込まれていく。面白かった。ラッキー 神奈川大学 1年 イヤミスの女王、湊かなえのデビュー作あらすじだけは知っていたが初めて全編読んで衝撃を受けた。結末も衝撃だったが被害者、加害者それぞれの家庭で様々な悩みや関係性があり家族の形も様々で私が知っているのはごくわずかなのだと思った。特に、修哉は母親も新しい母親もどちらにも新しい子供ができて元の子供は捨てられてはいないが存在を否定されている感じが、私に想像出来ることではないがすごく怖いことだなと思った。 月 広島大学 2年 将来、教員を目指す人こそ読むべき作品。倫理観とは、復讐とはなんなのか考えさせられた。思春期の若者の未完成な倫理観や愛情の不足が引き起こした事件がさまざまな視点から語られ、その人間臭さや愚かしさがリアルに綴られている。私は教員志望の学生だが、この作品を読んだ後は自分の中の決意が揺らぎ、途方に暮れてしまった。 shu 帯広畜産大学 3年 私は作中で描かれる犯人の感情に出会ったことがある。
「愛美はこのクラスの生徒に殺されました。」ホームルームで担任の悠子先生が話し出す。先生の復讐によって少しずつ犯人の少年たちの素顔が明らかになっていく。
どうして少年たちは殺人を犯してしまったのか。その理由はあまりにも思春期の中学生らしい。
誰か少年たちを止めてくれる人はいなかったのか。少年たちが真っ当に思春期の悩みを抱えて生きていく術はなかったのか。鷽秋かおす 東北大学 3年 「イヤミスの女王」湊かなえによる珠玉の一冊。この世の悪意が網羅されているのではないかと錯覚する。この手の小説に馴染みがないので、結末を消化するのに時間を要した。最終的に、消化できないという結論に達した。物語の筋はむしろ分かりやすい。しかしいくら感情に重なる部分があっても、主人公含め誰一人として行動に共感ができなかった感がある。うんざりしながらも読み進めてしまう作者の腕が恐ろしい。 TBK 龍谷大学 1年 この本の登場人物は私にとって共感できるようで共感しにくく、共感しにくいようでどこか共感できるような感情が生まれそれに応じて行動していると感じる。それゆえ罪の意識は人それぞれ異なっており被害者にも加害者にもなる側面を全登場人物が持っていると思う。大きな物事というのは本当に色んなタイミングの巡り合わせで起きるものだと実感した。一人一人の視点から話しが章ごとにすすめられるためひとりまたひとりと思惑や状態を知っていくことで読者の中で繋がっていくのが大変読みやすく面白かった。 1ch 富山大学 1年 最初は各登場人物の主観的視点から始まっていった。事件に対して、各々の心情や言動を回想した。やがてそれは歪みを産んだ。各人の軌跡の交点に矛盾が生じた。そこには、事件の真相が隠されていた。憎しみは憎しみを呼び、復讐を呼び、また、憎しみと復讐を呼んでいった。一言で言うなれば、「グロデスク」ではあるが、その一言に尽きない、各人物の感情の交錯が生々しく感じられた。「告白」というたった二文字の題名にも関わらず、大きな余韻を残して、この物語は、はたと終わってしまった。 アサ 名古屋大学 3年 不朽の名作であるこの1冊。この作品は推理小説ですが珍しく犯人は分かったうえで物語が進んでいきます。変わりゆく視点に思いもよらぬあの時の発言が思い起こされて、ひとりひとりがもつ感情の細やかさが際立っていました。「異様でした」事件後の空気の歪みを犯人、先生、クラスメイト全員から感じるので次々と新たな告白に絶望してしまいます。人への裁きやいじめ、不登校児への対応、一見平凡な家庭。この世界線はリアルでどこか気味悪くて、描かれる最後の復讐はこの世で最も残酷でした。つい口調が小説に影響を受けてしまいましたね ごきりん 東北大学 4年 悪人ならどれだけ虐めも良いのか?
犯人への復讐を自らの手で行わず,世論に任せるとどうなるのかが描かれていた.
今のSNSの私刑的なものに近い.そして,登場人物たちがどのように私刑に向き合うのか.
私刑に疑問を持ちつつも無垢な悪意にあこがれるもの,罰に苦しみ堕ちるもの,罰など気にせず自身の快楽を求めるもの.三者三様の感性を味わう作品.かわなぎ 岩手大学 1年 章を追うごとに登場人物の人間像が変わっていき、人間の口から出る言葉には事実以外にも自分の都合や保身が混ぜられていることがあるという考えればわかるがふとした時に忘れてしまうような感覚をつかれた気がした。僕自身、本音のような感じを出しながら自分の考えを自分がよく見えるように脚色してしまっているなと感じることがある。告白というのはその人の全てをさらけ出すのではなく、その人の譲歩できる限りを出しているに過ぎないのだなと思った。
-
投稿数:10『殺戮にいたる病』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント 黄色いキャバリア 徳島大学 1年 最後の衝撃が今まで見てきた作品の中で桁違いに強かった。あまりの強さに状況を理解するのにかなりかかった。
読んでいる時は”雅子”の視点はいらないんじゃないかと思ってた。しかしこの視点があることがより最後の最後まで結末が分からない話を作り出していたと感じた。
3人の登場人物の視点の時系列が最初はあっていなかったように感じたが、それも含め樋口さん達がどうやって犯人までたどり着くかを辿っていて本当に面白かった。丸犬 名古屋大学 3年 東京の繁華街で起こった連続殺人を中心に物語は進んでいく。その中でも頻繁に登場する犯人の描写はとても精密に描かれており、あまりの残酷さに目を離す事ができなかった。殺人の方法、犯人の心理、情景描写など、どれを取っても凄まじく犯人の一貫した哲学には美しいとさえ思ってしまった。
またこの物語には凄惨な描写の裏に、様々な影が巧妙に隠されている。この本を読み終わったのなら、その影を暴くため間違いなくもう一度最初から本を読み始めるはずだ。ももた 大阪大学 1年 開始早々から衝撃的なシーンですぐに引き込まれた。女性の死体でしか愛を感じず殺害を繰り返す稔と稔を怪しむ母親、元警部の樋口の視点から描かれるストーリーは悲惨な内容でありながらどこか現実味を帯びている。次第に真相に近づいていく母親と樋口、そして殺戮を繰り返した果てにある真実に気づいた稔のラストへ続く緊張感に読む手が止められない。
予想もしなかったラスト一行には鳥肌がたち、読み直すといくつもの伏線があったことに驚かされる。作者による巧妙なトリックにあなたはきっと騙される。本を読む看護学生 新潟大学 1年 これは自分の隣の家で起こっていることだと思った。
普通の家庭、普通の親子、普通の夫婦に見える。けれど、夫婦仲のちょっとしたすれ違いや子供への対応の違いが、殺人鬼を生み出すことがあると納得し、隣家や自分の家さえもそうなるかもしれないと戦慄した。
読みながら「気持ち悪い」と思っていたはずなのに、ラストシーンに至った直後、もう一度読み直した。それくらい理解し難く胸の悪くなる内容だし、人によってはトラウマかもしれない。
でもこの病魔は、誰しもが持ち得るものだ。内容より、その事実が一番怖い。バースデーケーキ お茶の水女子大学 3年 2度読み不可避、最終段落までのすべての章が伏線であり、どんでん返しに全てをかけたエンタメ性が高い作品だった。であると同時に、母性への執着や、人間が本質的に本能的に抱く死への関心を、殺人という刺激的な方法で鮮やかに描かれている点は、芸術的だなと感じた。
違和感を感じた一方で、それを見逃してしまったことに悔しさも感じる作品だった。ごきりん 東北大学 4年 探偵の皆様に依頼だ。
犯人は蒲生稔。彼を暴いてほしい。
君たちに与えられるのは、蒲生稔(犯人)、蒲生雅子(家族)、樋口武雄(元警察)の3人の視点からの情報。犯人の視点があるんだ、楽勝だろ?
私は見事に騙されたけどな!この作者に全力でアレをやられたら無理だって。
最初にエピローグ持ってくるとか、わかってんねぇ。
あれをやられたら、絶対もう一周したくなるって。スライム 龍谷大学 1年 見事なトリックを用いた物語の展開に鳥肌がたった。
書店でまず全面帯を見たときに心を惹かれたのであるが内容もそれに全く負けていないほど洗練されており、初めての試みである2周目を読んだ。
なるほど小説が小説である理由、文字から話を読み取るということの難しさと大切さを改めて感じたように思う。
過激な描写が含まれるものの、誰が読んでも面白いと感じられる。なとり 北海道大学 3年 主人公と母親の視点が交互に繰り広げられ、前者ではグロテスクなサイコサスペンス劇を、後者では過干渉の毒親日記を見せられ、違う方向から同時に攻められてしんどかった。どちらも妙に生々しく、サスペンスの肉感がすごいのが特に印象に残るが、母親が息子の性の部分まで管理しようとしているのもおぞましかった。これらの描写に気を取られて、道中の伏線には全く気付かず、衝撃的な結末に驚いた。 しょまる 名古屋大学 4年 まず、怖いのが苦手な人は読まない方がいいです。骨の髄まで恐怖したい欲望を抱えている人や、私のように品性のひん曲がった人には強くおすすめします。この本には小説という媒体でしか表現できない技巧や、細部まで緻密に設計された伏線がちりばめられています。中身を置いておいても、まず小説そのものの完成度が高いのです。そして内容においても人間性の本質、つまり頭では納得できないけど共感はできる描写が心地よいです。読者を選ぶ本ですが、読み終わった後の衝撃と、この本が脳みそに刻み込まれることはお約束します。 みさき 桜美林学園 1年 巷で話題になっており、私好みの匂いがしたので拝読。結末が気になってページを捲る手が止まらなかった。ラストはよくありがちな手法ではあるものの、かなりの衝撃で面白かった。私が読んできた小説の中でも群を抜いたグロ描写で度々顔をしかめた。この衝撃はぜひ味わってほしいが、勧めるには人を選ぶ。この手のサイコパスな殺人鬼が登場する作品は、フィクションとして見る分には楽しめるが、実際にこういった趣向を持った人が存在すると思うと恐ろしくてたまらない。樋口とかおるが助かったことが本当に不幸中の幸いだった。
-
投稿数:10『向日葵の咲かない夏』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント デイジー 東京農業大学 1年 「違和感」
本を読んでいる中でずっとどこか違和感を感じていた。物語が想像もできない方向へ次々と進み、そのあとを必死に追っていくと最後には違和感の霧がはれ、まったく予想していなかった結末が目の前に広がった。齊藤 宇都宮大学 2年 小学生が主人公で、軽く読みやすい文体とは裏腹に、設定や話の展開に重みがあります。最後のどんでん返しには、想像もつきません。読後感はなんだか不思議な感覚でした。私個人としては、おもしろいというよりも興味深い一冊だと感じました。私はこの本を四回程読んでいますが、読むごとに新しい発見や隠された描写に驚かされます。ミステリーを楽しみたい方、いい意味での裏切られた感を味わいたい方に、特におすすめです! ゆき 東京大学 大学院 叙述トリックが気持ちいい。内容は気持悪い(人を選ぶ)。
わたしの周りでこの本を読んだ人は、みな「なんか気持ち悪かった」と述べていた。
その原因は物語の内容によるものか、それとも夏の嫌なところ、例えばジメジメとした空気だとか野菜が腐った匂いだとかを詰め込んだような空気感からくるものかは分からない。
少なくともわたしは最後まで読んで「気持ちがいい」と感じたし、彼の物語を見届けることができてよかったと思う。shu 帯広畜産大学 3年 S君が首を吊って死んでいた。1週間後、S君は蜘蛛になって僕の前に現れた。「殺されたんだ。」と訴えながら。僕は妹のミカと事件を追い始める。ゴミが散らばった家。僕を毛嫌いする母。見て見ぬふりをする父。口が達者すぎる3歳のミカ。ほんの少しの違和感が読み進めるにつれて積み重なっていく。「僕」の生きている現実は恐ろしく残酷だ。それでも生きていくために。「僕」は自分の作った世界の中に閉じこもっている。 くさだんご 北海道教育大学 1年 「最後がよくわからないけど、全体的になんとも言えない、夏にぴったりな本」そんなことを友達から言われてこの本を読み始めた。小学4年生のミチオが主人公でこの物語は進められていく。同級生であるS君の死、死体の消失、S君の生まれ変わり、ミチオの妹の存在、、そこから思いもよらぬ方向へ話は進んでいく。推理小説だと思って読んで行くが、最終的には「登場人物がみんな狂っていたんだ」という感想に収束してしまった。最後の章は私なりに理解したが、少々気味悪く感じた。これから夏本番だが、向日葵は当分見たくない。 バースデーケーキ お茶の水女子大学 3年 S君の事件を通して描かれる、1人の人物の「オカシイ」様子が徐々に明らかになっていくのは、ミステリとは少し違ったスリリングさがあった。物語の表層で事件は起こっているものの、ミチオの視点からみる世界はファンタジー性にも溢れているように感じた。ここまで大きなものではないかもしれないが、私たち一人一人が見る世界は微妙に異なっていることを改めて認識できた作品。 てとらぽっど 横浜市立大学 1年 人間が怖くなった。みな、普通の顔で生活して、同じ世界に生きているように思えるけど、見えている世界はそれぞれ違う。この物語は特に、登場人物が、それぞれ自分自身を守るために、独自の物語をつくって、独自の世界に住んでいる。
読んでいくうちに、彼らの世界を知ることが出来るが、残酷で、悲しくて、とても理解は出来ない。げっこー 宇都宮大学 3年 読み終わってまず、ゾッとした。そして再読後にまた、ゾッとした。「誰だって、自分の物語の中にいるじゃないか。自分だけの物語の中に。その物語はいつだって、何かを隠そうとしてるし、何かを忘れようとしてるじゃないか。」複雑に絡み合ってしまった事件の背景には、登場人物たちの苦しみがあるのではないかと思った。全てが一気に明らかとなるラストは目が離せず、読む手が止まらなかった。そして、一つの“物語”に終止符を打った主人公の今後の“物語”がとても気になった。 さゆ 愛知大学 4年 友人が首をつって死んでいた。そして姿を消してしまった。僕の体を見つけて欲しいんだ。そんな風に生まれ変わった友人に言われる。私は早く真実を知りたくてページをめくった。しかし、読み進めていく先にあるのは混乱。読み終えたはずなのに戻り、そしてインターネットに本のタイトルを入力した。読了後きっと意味が分からなくなる、おもわずどういう意味が調べたくなってしまう、そんな一冊です。 お茶ごくごく倶楽部 大阪大学 1年 クラスメイトのS君が首を吊って死んでいるのを発見するが、目を離した束の間に死体が消えてしまう。一週間後、S君は生まれ変わって“ある姿”で自分の死体を探すように頼んできた。奇妙なことの連続の中にある日常。だがその日常でさえもどこか違和感がある。読んでいく中で感じた違和感はぜひ大事に持っておいてほしい。最後に全てが腑に落ちるだろう。僕とS君と妹のミカの三人のひと夏の物語。
「誰だって、自分の物語の中にいるじゃないか。その物語はいつだって、何かを隠そうとしてるし、何かを忘れようとしてるじゃないか」
-
投稿数:10『むらさきのスカートの女』
ペンネーム 所属大学 学年 感想コメント あお 愛知教育大学 1年 芥川賞を受賞したこの本は、「わたし」の語りによって、「むらさきのスカートの女」と呼ばれる女性を観察した様子が書かれています。
話の展開にスピード感があり、一度読み始めるとページをめくる手を止められなくなります。また、読み終えた後、すぐにもう一度読み直したくなりました。登場人物についての情報が非常に少なく、考察が面白い一冊だと感じます。丸犬 名古屋大学 3年 少し異質な姿と行動で街の名物人物となっている、「むらさきのスカートの女」。そんな彼女が気になる主人公は、あの手この手を使って友達になろうと裏で画策する。いかに自然に友達になれるか。その主人公の狂気的なまでの行動力があまりにもぶっ飛んでいるのだが、主人公の語り口がとても冷静なため、まるで狂気が日常へとすり替わっていくような奇妙な感覚であった。また衝撃的なラストも必見である。主人公が本当に見ていたのは一体誰だったのだろうか。 鷽秋かおす 東北大学 3年 実は変人を見つけるのは容易い。ちょっと街中を注意深く観察していれば見つかる。しかし、変人だと分かっていながら、進んでその人に話しかけようとする人は珍しいし、ましてや友達になりたいだなどと思うひとは稀だ。そのレアケースが今作の主人公「黄色いガーディガンの女」である。むらさきのスカートの女と自然と友達になるために、あくまで裏から多くの計を巡らせる様は、偏執的であり、かといって本人が特段情に厚いわけでもない。自己完結した好意を、ここまで平坦におぞましく描いた作品が他にあろうか。 黄色いキャバリア 徳島大学 1年 「むらさきのスカートの女」と言われていた最初、不気味な雰囲気が彼女にはあったが話が進んでいくにつれ、その女の人間味ある性格と行動がどんどん分かるようになってきた。主人公の方が不気味なのではとも思ってきた。
しかし結局逃がしてあげた主人公も逃げた女も誰もどうなったか分からない結末だった。
また逃げた先でも「むらさきのスカートの女」と呼ばれ、話が繰り返されるのではないかと考えた。本を読む看護学生 新潟大学 1年 とにかくこの作品は、「妙」なのである。
どの地域にも、決まった格好で決まったルーティンを生きる「ちょっと変わった人」はいるだろう。私の地元にもいる。仮に、「黒いリュックの女」としよう。私は彼女が毎日大きな黒いリュックを背負って徘徊しているのを知っていて、きっと周りの住人たちも彼女を認識していると思っている。しかしどうだろう、その人がいつも黒いリュックを背負っているなんて知っているのは私だけで、むしろ私のほうが「ちょっと変な人」なのかも。そんな気味の悪い感覚になる、とにかく「妙」な小説である。サクラモチ 桜美林学園 1年 私は、この著書を読んで、冒頭から中盤にかけて説明が多く、何か一つ、大きな出来事が起こるということはなかったが、それはつまらないわけではなくリアルが追及されていて唯一無二の面白さだと思う。終盤にかけて、転がるように物語が進んでいくのは、読んでいて面白く、最後の締めの文章も、今まで読んだ意味を読者に与える文章だったので、読んでよかったと思いました。 ひろと 名古屋大学 2年 初めから終わりまで、「わたし」がひたすらどうかしていて、まるでコントを見せられているみたいで、ノンストップで面白かった。ネタバレをしたくないので、印象に残ったところを多くは書けないのだけれども、「わたし」が初めてむらさきのスカートの女とまともにコンタクトを取るシーンが、あまりにもおかしくて、読みながら吹き出してしまった。他にも思わず笑ってしまうシーンが散りばめられていて、本を読んでニヤニヤしているところを人に見られるとひとたまりもないので、家で一人で読んで正解だった。 かわなぎ 岩手大学 1年 SNSで炎上している人だけでなく、それを過剰にに攻撃したり、嫌がらせをする人にも違和感の目を向けるべきで、注目を浴びる人が一番風変わりかというとそうでない。大衆の中に、異常な思考を持って注目する人間がいる可能性もあるなと思った。むらさきのスカートの女を追っていく描写が、次第に主人公の異常さを表していく描写へと変わって行く様子が不気味で面白かった。また、自分から見る自分と他の人から見る自分の人物像の違いを改めて考えるきっかけになる作品だと思った。 あかね 岡山大学 4年 日常の些細な話に見えますが、後半に行くにつれホラー感が増してきます。今村夏子さんの本だなという感じです!
語り手に感情移入しているとどんどん気味が悪くなってくるかも!?今村夏子さんの本を読んでいると、この気味の悪さがどんどん中毒になってくるかもしれません。ぜひ読んでみてください。芥川賞を受賞した作品です!ふぁくせ 東京農業大学 4年 なんなんだろう、この薄気味悪さクセになる。
「わたし」の近所に住む「むらさきのスカートの女」が「わたし」と同じように気になって仕方がなかった。「むらさきのスカートの女」が気になって仕方がなかったはずなのに、いつの間にか「わたし」が気になって仕方がなくなっていた。
なんだろう、この何とも言えない奇妙な感じは…妙に頭に残って、不思議な読書体験になった。